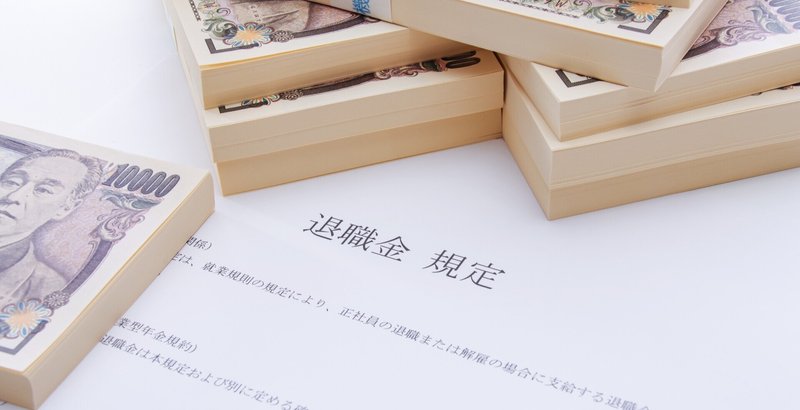
役員退職金の支給額はどう計算するのか?[2022.3月号]
役員退職金とは?
どんな経営者もいつかは経営から勇退する事を考えます。
その時に法人にあるキャッシュを
法人から役員に支給する方法が役員退職金です。
法人から個人に役員退職金を支給すると
法人と役員個人、双方にメリットがあります。
法人のメリット
役員退職金は不相当に高額でない事を前提に限度額まで
退職金という大きな経費を作り出す事が出来ます。
経営者個人のメリット
退職所得として税制面での恩恵を受けれる事
役員報酬や役員賞与とは比べ物にならないぐらい
税務面で優遇されています。
計画的に退職金を支給する事で
引退後の資産の中に
効率的に現金を作り出す事が出来ます。
法人オーナーは
この退職金支給における税務メリットが
法人側と個人側の二つ存在します。
その為、困惑する部分があります。
今回の記事では
主に法人側でのメリットをご説明します。
役員退職金、幾らまで経費計上可能なのか?
前述で不相当に高額でない事を前提に
役員退職金は経費計上可能ですが
支給額には根拠が必要です。
その支給額は一般的には
勇退時の役員報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 = 役員退職金
とされています。
功績倍率には、係数が用いられ
会長/2.8、創業社長/3.2、
専務2.6、常務2.3、取締役2.0、監査役1.6
等、該当の役員が法人において
どれだけの重責を担っているか
また、資本金・従業員数・職種によって変動します
例えば、直近での
役員報酬月額100万円の社長が40年勤めた後
勇退をするとなった場合
勇退時の役員報酬月額 × 在任年数 × 功績倍率 = 役員退職金
月額100万円 × 40年 × 3.2 = 12,800万円
上の計算結果では
役員退職金としては1億2800万円が相当額となり
この全額が経費計上可能となります。
役員退職金を支給する上で注意したい所
例えば、役員退職金を支給すると
とある年度の決算書において
上記の1億2800万円が
いきなり特別損失として記載される訳です。
当然、税務的にこの金額は何だ?となる訳なのですが
その時に、支給根拠とされるのが
役員退職金規定の有無
そして取締役会や株主総会での決議が
必要とされています。
役員退職金規定と議事録について
規定、議事録は
法人の運営上の決定事項を表すものです。
これらの決定事項をいつの時点で規定したのか
規定に基づき、いつの時点で支給を決めたのか
というのが根拠として必要です。
特に規定においては、いつ定められたのか
公証人役場で日付の確証を取る事で初めて活きます。
以前、とある士業の先生とお話しの機会があった際に
顧問先での以下の様な経験を大変悔やまれておりました。
とある創業社長が
会社に役員退職金規定を備えていない状態
でお亡くなりになってしまった。
創業社長と縁故の無い取締役が
会社の後を見る事になったのだが
創業社長の配偶者様への
死亡退職金支給額の決定について
大変揉めた挙句、その配偶者様に
会社から数字的根拠のある死亡退職金
が届けられなかった。
税務上の根拠として以外にも
自身とご家族様の為にも
役員退職金規定は備えましょう。
退職とは必ずしも会社から退かなくても良い
例えば
・常勤役員が非常勤役員へ
・取締役が監査役へ
といった変更によるものでも
「みなし退職」が成立します。
しかし注意点としては
・退任後も実質的な経営権を持っている等
経営上主要な地位を占めていない事
・そして、退任前の役員報酬より
概ね50%以上の報酬が減少している事
等の要素から実質的に退職したと認められた場合は
会社から完全に退任しなくても
役員退職金の受け取りは可能です。
役員退職金支給により狙うべき事業承継
・特別損失の計上による自社株評価の引き下げ
例えば、非上場株式の原則的な評価は
下記の2つの方法があります。
・類似業種比準方式
業績が良いと、評価が高くなるとされる
・純資産価額方式
保有純資産が大きいほど評価が高くなるとされる
この株式の評価額が高ければ高い程
株式そのものを取得する為の費用
相続・贈与を受ける為の税金
が相関的に高くなります。
よって、自社株評価が高い会社は
後継者が社長の椅子に座るだけで
高額のお金が必要になる
といった事が発生し得るのです。
これらを戦略的に対策する為には
利益を圧縮する(赤字を作る)、含み損を計上する
等といった手段が有効です。
そこで役員退職金の支給によって
特別損失を計上する事は
自社株評価を下げる為の
王道的な有効手段となります。
役員退職金を会社に準備するには
役員退職金を会社から支給するには
結局の所、キャッシュが無ければ支給する事は出来ません。
その為に取るべき方法は、お金に色を付けて
時間を味方につけて貯めていくにほかなりません。
そこで
社長の健康上における不測の事態
場合によっては突然の退職への対策をしながら
・退職金の準備
・利益の繰延べ
を図ることができる
生命保険は役員退職金の捻出に役立ちます
事業承継、相続対策というのは
早く動けば動くほど取れる手段というのは豊富です。
また、老後資産としての退職金に関しても
早く動けば動くほど、ある目標の金額に対して
同額の積立でも
掛かる年数は少なく、金額は最大化できます。
そういった法人の将来に関しての
入口から出口までを
今から考えていくのも
創業社長の役目かもしれませんね。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
