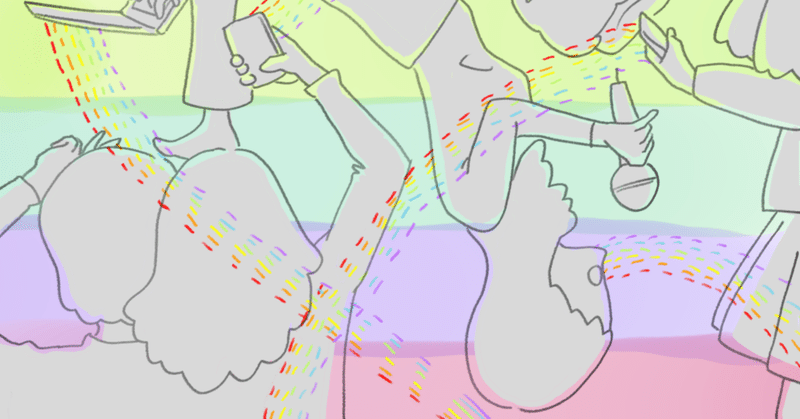
村上春樹「ねじまき鳥クロニクル」(新潮文庫)を読む② ー退屈さとセクシュアリティ
「ねじまき鳥は実在する鳥なんだ。どんな恰好をしているかは、僕も知らない。僕も実際にその姿を見たことはないからね。声だけしか聞いたことがない。ねじまき鳥はその辺の木の枝にとまってちょっとずつ世界のねじを巻くんだ。ぎりぎりという音を立ててねじを巻くんだよ。ねじまき鳥がねじを巻かないと、世界が動かないんだ。でも誰もそんなことは知らない。世の中の人々はみんなもっと立派で複雑で巨大な装置がしっかりと世界を動かしていると思っている。でもそんなことはない。本当はねじまき鳥がいろんな場所に行って、行く先々でちょっとずつ小さなねじを巻いて世界を動かしているんだよ。それはぜんまい式のおもちゃについているような、簡単なねじなんだ。ただそのねじを巻けばいい。でもそのねじはねじまき鳥にしか見えない」
小説を読むということ、読まれるということ
村上春樹は、以下のように話している。私の大好きな文章だ。
いつも言っていることなんですが、小説には意味なんてそんなにありません。というか、意味という座標軸でとらえることができないからこそ、小説が有効に機能するのです。意味という座標軸でとらえてしまうと、小説は味気ないつまらないものになってしまいます。「意味はようわからんけど、なんかおもしろいし、読んだあと腹にたまるんや」(なぜか関西弁になる)というのが僕の考える小説の理想のかたちです。大事なことは固定の中にではなく、推移の中にあります。それが僕の考える「村上春樹の読み方」です。
小説を読むうえで「大事なことは固定の中にではなく、推移の中に」あるというのは、非常に示唆的な言葉であると思う。
小説の構造を言語化し、様々な視点から位置づけを行うのが文学研究であり、私自身も過去に研究に携わっていた身ではあるため、その意義や有用性を否定するわけではない。
しかしながら、村上春樹の言うように、小説(あるいは読者)というものは推移していくものであり、読み手の状態や世界の状況によって、容易に変化する可能性を孕んでいる。
イタリア文学の翻訳者であり、ふくよかで流れるようなエッセイを書く須賀敦子の読書日記に『本に読まれて』というものがある。
このタイトルを初めて見た際にはっとさせられたのだが、あらためて、本は読むものでありながら、読まれるものーーそのときの読者を映す鏡になりうるのだと感じる。
以上のことから、ここで私が書きたいのは(村上春樹は存命の作家のため、研究対象になりえないというのもあるが)どう読まれるべきか、というものではなく、「ねじまき鳥クロニクル」という物語を今現在の私がどう引き付け、どう受け止め、どう感じたのかということである。
そしてこの記録を通して、今後私にとってこの物語が、どう推移してゆくのかを知ることができるのではないか、と思うのだ。
「ねじまき鳥クロニクル」の構成について
村上春樹の作品においてよく感じるのは、その物語がもつ生々しいエネルギーだ。
つまり、彼の作品には堅牢なプロットの存在を感じることはできず、代わりに、生物が生長してゆくような(それはいささかグロテスクでも、セクシャルでもある)湿ったあたたかさがある。
この物語は三部構成になっている。
「泥棒かささぎ編」「予言する鳥編」「鳥刺し男編」の三つだ。
「ねじまき鳥クロニクル」は、全編を通してそれぞれの人物のモノローグがあり、主人公の回想があり、それ自体が複数の章にまたがっていることもある。マトリョーシカのように、物語が入れ子式になっているということだ。そのため、物語はジグザクと複雑な軌道を描き、時代も先の戦争中の満州まで遡ったりする。「クロニクル(年代記)」とは称されているものの、必ずしも直線的な運動によって物語られているというわけではない。
そのなかで第三部「鳥刺し男編」だけ、私は異なる印象を受けた。
この第三部の位置づけとしては、いわば第一部、第二部で提示された謎の回答編なのだが、これまでの物語の組み立て方とは、また違った進行方法を採る。
すなわち、これまでは主人公(岡田亨)の目線で進められた物語が、様々な人物の視点あるいはメディアから語られるようになる。
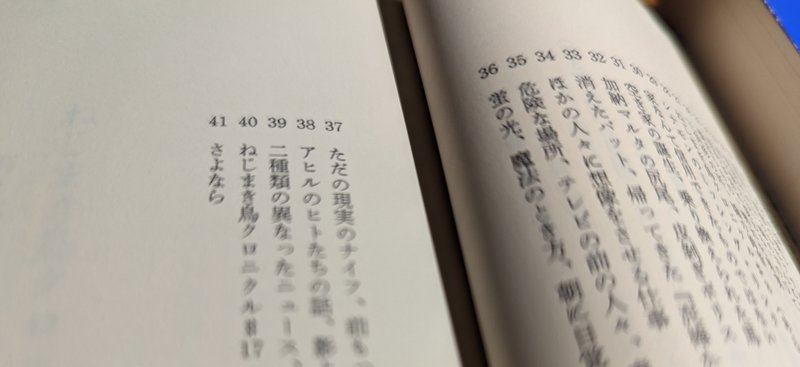
週刊誌の記事、赤坂シナモンの記憶や”物語”(それは「ねじまき鳥クロニクル#○○」というファイル名でパソコンに保存されたテクストだったりする)、笠原メイの手紙など……。
ブリコラージュの様相でもって、さながらミステリ小説のように、ある種の事実が読者の眼前にのみ、浮かび上がってくるような構成になっている。
(最後に明かされる、笠原メイの手紙が主人公の岡田亨に届いていなかったという事実は、人間存在のかなしみとうつくさを感じさせる。又、すべての事実を余すことなく知れるのは読者のみで、まさに物語というものが持つきらめき、愉しみを存分に味わえるのが第三部なのではないだろうか。)
第三部がないと謎が中空に放り投げられたままになってしまうとはいえ、その存在がやや色気がないように感じるし、第二部「予言する鳥編」における、市民プールの水中で月蝕(のようなもの)を幻視するフィナーレが狂おしいほどに好きなので、この記事では主に第一部、第二部に焦点を絞って感想を書いていきたいと思う。
ある種の”退屈さ”について
村上春樹の中長編を読んでいていつも感心するのは、作中で大きな事件が起きるわけでもなく、むしろ単調な日常が繰り返されてゆくという、一見退屈そうな場面に多く筆が割かれているということだ。
ただ街を歩きまわったり、なにもない高原の山小屋にひとり立てこもったり……。
「ねじまき鳥クロニクル」においても、主人公がただベンチに座って眼前を通り過ぎる人々を観察する場面だったり、物語を読むうえで大きな鍵となる、或る空き家の井戸の底で座ったまま過ごす場面が出てくる。
(回想や空想、夢を通じて別の空間に出入りするため、読むのには意外と苦痛を感じなかったとはいえ、岡田亨が井戸に入り出てくるまで、新潮文庫版でなんと約百ページ!)
「ねじまき鳥クロニクル」は特に、物語のすぐそばに”退屈さ”が横たわっているように思える。
そして、”退屈さ”は笠原メイの場合は死への考察につながり、主人公の岡田亨の場合は、猫や妻クミコの失踪を経て、自分を省みる機会へとつながっていく。
名声や地位を獲得してゆく綿谷ノボルの世界(それは村上春樹のいう「悪い物語」のメタファーでもある)と対置されるように、岡田亨は有形無形のものを一つずつ手放してゆくのである。
セクシュアリティについて (序)
退屈さを退屈さとしてそのまま描いてしまうと、読み手が飽きて、読むのを止めてしまうのは自明のことだ。
村上春樹の情景描写はすばらしく、細部にまで彼のよく言う「親切心」によって目が配られているのは間違いないだろうし、それが飽きさせない理由でもあるだろうが、それ以外の”エンジン”もあるように思われる。
その一つがセクシュアリティ。
特にこの「ねじまき鳥クロニクル」においては、セクシュアリティが大きな役割を果たしているのではないか。
物語は、主人公がスパゲティーをゆでている際、得体の知れない女から電話がかかってくる場面から始まる。
「じゃあ教えてあげるわ」と女は言った。「私は今ベットの中にいるのよ。さっきシャワーを浴びたばかりで何もつけていないの」
僕は黙って首を振った。これじゃまるでポルノ・テープじゃないか。
「何か下着をつけた方がいいかしら? それともストッキングの方がいい? その方が感じる?」
女は「十分だけでいいから時間が欲しいの。そうすればお互いよくわかりあうことができるわ」と言う。気持ちが分かり合えると言うのだ。しかしながら、実際に耳を傾けていると、話される内容は「ポルノ・テープ」のような内容だった……。
そして、この女あるいは女が話す内容には、実は意味があるということが、第三部で次第に明らかになっていく。
また、先に言及しておくと、村上春樹自身はセクシュアリティについて、以下のように話している。
[……]僕がセクシュアルなシーンを書くのは、それが人間の心のある種の領域を立ち上げていくからです。そういうことがときとして物語にとって必要になります。暴力や血なまぐささもそれと同じです。非現実的なできごともそうです。それらが物語を有効に起動させていきます。[……]
性欲や性のとらえ方に関しては、個人によって大きな差があります。性欲がとても強い方もいれば、弱いというか、淡泊な方もおられます。僕は小説家として性というものを、魂と魂を結びつける通路のひとつとして捉え、そのように描いています。しかしもちろん性だけがその通路ではありません。ほかにいろんな通路があります。というか、性はその通路のひとつのメタファーに過ぎないのかもしれません。[……]
この言は、そのまま「ねじまき鳥クロニクル」にも当てはまる。
なかでも特に注目したい作中人物が「加納クレタ」である。
次回に向けて
まだまだ作品におけるセクシュアリティの話は続くが、腕が疲れてしまったので、今回はこの辺で一度筆を擱きたい。
次回の更新では、この村上春樹の言を補助線にしつつ、加納クレタを話の中心に据えて自由気ままに喋っていきたいと思う。
まだまだ表層の部分で、中身の詳しい話まで進めることができていないが、少しでも面白い!と思っていただけたのあれば、幸いである。
なお、セクシュアリティといえば、私が初めに村上作品を読んだのは中学三年生の頃で、手に取ったのは学級文庫として置かれていた「海辺のカフカ」だった。
そのときも(当時は中学生だったので……)矢鱈にエロい!!と思ったのを覚えている。というより、下巻の途中で読むのを投げ出してしまったためか、今となってはその印象しか残っていない……。
(つづく)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
