
コンパス・ポイント・スタジオ~アイランド・レコード周辺(2)
コンパス・ポイントの特集2回めはスライ&ロビーと彼らと関わりの深かったアーティストが中心です。
(「CPAS」は「コンパス・ポイント・オール・スターズ」の略です。詳しくはパート1をごらんください。)
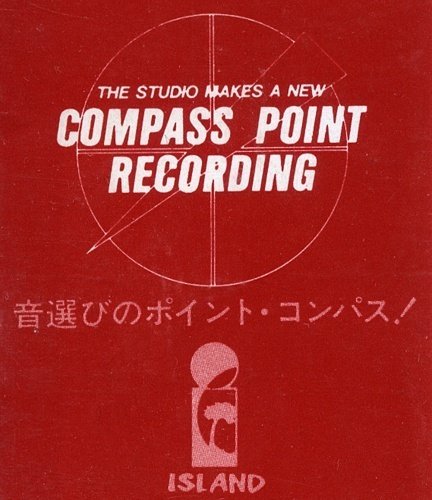
<ブラック・ウフル>

'72年ごろにキングストンで男性3人組のヴォーカル・グループとして結成。幾度かのメンバー・チェンジを経て、'77年ごろにはリード・シンガーのマイケル・ローズ、バック・ヴォーカルに女性のピューマ・ジョーンズと唯一のオリジナル・メンバーであるダッキー・シンプソンの3人編成に落ち着くことになる。アイランド・レコードからのリリースは'80年のサード・アルバム"Sinsemilla"から。ボブ・マーリーの没後はアイランドのレゲエ部門のトップ・プライオリティ・アーティストになり、音作り、ライブ活動の両面で海外マーケットを意識した展開を行っていた。
アイランド時代のスタジオ・アルバムは全てスライ&ロビーのプロデュース。スライ&ロビーはこの頃多数のレコーディングに関わっていたが、レーベル側の意図もあって彼らが最も「攻めた」音作りをしているのがブラック・ウフルのアルバムだ。コンパス・ポイントでの録音が含まれているのは"Red"以降の4枚だが、"The Dub Factor"は"Red"と"Chill Out"の曲を元にダブを施した、ミキサーのポール・"グルーチョ"・スマイクルの作品とすべきものなのでここではジャケ写のみで。




この頃の彼らのアルバムはキングストンのチャンネル・ワン・スタジオでソルジーらのエンジニアの元で主要なトラックを録音し、その後オーバーダブがある際はコンパス・ポイントで追加の録音を行って、最終的なミックスは同じくナッソーでスティーブン・スタンリーが行う、というのが定番のスタイルのようだが、コンパス・ポイントの「音の良さ」が表れているのが"Red"。スライのドラムの鳴り、ロビーのベースのウネリがクリアでダイミックなミックスに映える。前作ではオカズ的に入れられるシン・ドラムのピュンピュンという音が目立っていたが、今作ではそれも抑えめでシンプルで力強いアレンジ、それでいてジャマイカ・ミックスのアルバムにはないモダンな仕上がりになっている。
次の"Chill Out"ではアレンジ面で凝った音作りが見られる。これまではあくまで飾り的な使用に留まっていたシン・ドラムがスネア音として常時聞こえるようになり、水が滴るような不思議な音色のウォーリー・バダルーのキーボード、常時鳴るパーカッション、随所に入るダブ処理…など、ウフルのメンバーの独特なヴォーカル&コーラスを生かしつつ新しい音にトライしている。おそらくグレイス・ジョーンズのレコーディングで得たノウハウをこちらにも応用してみたということなのだろうが、レゲエ以外のリスナーにもアピールしたいという狙いにはピッタリ。私が初めて買ったレゲエのアルバムもコレなのでした…
ライブ盤とダブ・アルバムをはさんでリリースされたのが問題作"Anthem"。スライが全編でシモンズ・ドラムを使用し、そのメタリックな音色が全体を支配している。ベースやギター、キーボード等ももちろん入っているのだが、聴き終えて印象に残るのはビンビン鳴っているシモンズとコーラス、それとダブ処理。なお、このアルバムはナッソーとロンドン、またUS向けに再度ナッソーで行ったものの3種類のミックスが存在するが、ここでの感想はロンドンでポール・"グルーチョ"・スマイクルがミックスしたアルバムについてのものです。


シングルは"The Dub Factor"には入っていないダブが2ヴァージョン入りの"Darkness"とフランソワ・ケヴォーキアンがリミックスした"What Is Life?"を。"What Is~"はイントロや間奏部の音の抜き方、エフェクト類を控えた生っぽい鳴りにハウス畑のフランソワ独特のセンスを感じる。
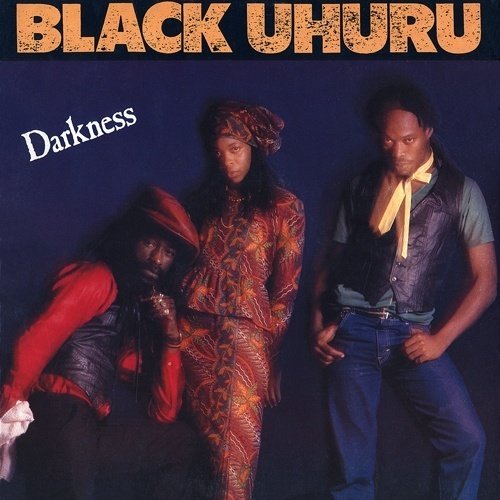

アイランドが力を入れていたグループゆえベスト盤/編集盤も数多く出ているのだが、こちらでは'93年に出た2CDのアンソロジーを。これまで未発表だったフル・レングス・ヴァージョン(正直あまり違いがわからないですが)が数曲、シングル・オンリー曲やヴァージョン違いも含まれている。


<グウェン・ガスリー>

'50年、ニュー・ジャージー州ニュー・アーク生まれの女性シンガー。'70年代半ばから教師として働きつつ、セッション・シンガーとして数多くのレコーディングに参加。アレサ・フランクリン、クインシー・ジョーンズ、ロバータ・フラック等の曲でバック・ヴォーカリストをつとめる一方で、キャメオのラリー・ブラックモンのプロジェクトのイースト・コーストにも参加。また作曲家としてもシスター・スレッジやベン・E.・キング等に曲を提供していた。ピーター・トッシュ'79年の"Mystic Man"のレコーディングで一緒だったスライ&ロビーと意気投合し(特にロビー・シェイクスピアのお気に入りだったとか)、コンパス・ポイントでスライ&ロビーのプロデュースのもと、デビュー・アルバムを録音することになる。スライ&ロビーとの2枚のアルバムの後はNY制作に戻り、'86年には"Ain't Nothin' Goin' on But the Rent"のNo.1ヒットを放った。
スライ&ロビーの二人が遊び程度に録音したビッツ&ピーシズのシングル(スライ&ロビーの項で取り上げます)で(レゲエではなく)アメリカのR&Bにも対応した音が作れることに気づいたクリス・ブラックウェルは、二人に進言してアメリカのR&B/ディスコ・マーケットを意識した作品を作ることを提案。そこにタイミング良く知り合ったのがガスリーで、彼女は曲作り/レコーディングのため一時的にジャマイカに移り住んで制作が進められることになる。


第一弾となる"Gwen Guthrie"はA面の全曲が切れ目なしに繋がった編集も斬新なディスコ・アルバムで、スライ&ロビーのレゲエ以外のサークルでの力量も示す内容だった。ミキシングにマイケル・ブラウアーが関わったセカンドでは音の抜けが格段に良くなり、完全にUS産R&Bに対応したサウンドへ。ロック~ニュー・ウェイヴ的な尖った感覚のあるグレイス・ジョーンズとは違い、ガスリーの包容力あるヴォーカルを生かしたまろやかなR&Bで、バラードでも優れた曲が収められている。
ガスリーは「パラダイス・ガラージ」のDJラリー・レヴァンもお気に入りで(ドキュメンタリー「MAESTRO」にはパラダイス~が閉店する週のイヴェントに出演したガスリーが観客に謝辞を述べるシーンも収められている)、彼女の曲をプレイする際にはレコードをそのままかけるのではなく、レヴァンが独自のミックスを施した曲をオープン・リールで流していた。その噂を聞きつけたアイランドの副社長ハーブ・コーザックがテープを聴き、商品化することになったのが7曲入りのパドロックのアルバム。

もともとディスコを意識した作品だった曲が、レヴァンの編集/リミックスでよりクラブ・プレイ向きの音へ-アカペラやリズムのみが繰り返されるイントロや間奏部、徐々に音が厚くなっていきサビでピークに達する-まだリミックスという概念が浸透する以前にその価値をアピールした一枚。オリジナルの音源には無かったダブ処理が随所に見られるところも興味深い。"Seventh Heaven"は強力なドラム・ブレイクから始まるオリジナル・ヴァージョンのほうが好きですが…
<スライ&ロビー>

スライ・ダンバー(ドラムス)とロビー・シェイクスピア(ベース)は'70年代半ばから行動を共にするジャマイカきってのリズム・セクション。'78年ごろからはプロデュース業や自身のレーベル運営も行うようになりジャマイカ国内のレゲエ・マーケットで名作を量産するいっぽうで、'80年代半ばからはロック~ポップス系でも多数の作品に客演、ミック・ジャガーから上田正樹まで多様なアーティストと共演している。近年まで精力的に活動していたが、ロビーが2021年末に逝去。スライの芸名はスライ・ストーンに由来するもの。
スライ&ロビーが彼ら自身の名義でコンパス・ポイントで録音したアルバムは少なく、'85年の"Language Barrier"のみ。

このアルバムはナッソーでCPASの面々と録音した音源に、NYでボブ・ディラン、ハービー・ハンコック、アフリカ・バンバータ、バーニー・ウォーレル等の多数のゲストの演奏をオーヴァーダブしたもので、プロデュースしたビル・ラズウェル/マテリアルの過剰なアレンジばかりが目立つ作り。主役のはずの二人も分厚い音に埋もれて「うまいリズム・セクション」というだけに終わってしまっているように感じる。ちょうど彼らが欧米のポップ・フィールドで旬の存在になっていた時期だけに、(当時の)最先端の音で攻めてみるか…といったところか。シャッフルでアルバム中の一曲だけ流れてくるとけっこういい感じに聞こえるのだが、通して聴いてみるとうるさ過ぎで疲れます。
それとは対照的なのがジャマイカ録音、ミックスはコンパス・ポイントのスライのソロ・アルバム。

ロビー・シェイクスピアのほか、元ウェイラーズのタイロン・ダウニー、ディーン・フレイザーらのホーン勢等ジャマイカの顔なじみの面々によるレゲエ・アルバム。インスト・ナンバーが中心だがA-2では珍しくスライがやさしい声で唄っている。ソウル系のカヴァーが3曲あり、マーヴィン・ゲイの"Inner City Blues"ではデルロイ・ウィルソンがヴォーカルを聴かせ、2曲あるウォーのカヴァーでは原曲の雰囲気を生かしつつうまくレゲエ・フレイヴァーに落とし込んでいる。全体にリラックスした雰囲気が伝わる好アルバムだ。
グレイス・ジョーンズのレコーディングで得たアイデアを元にスタジオ内での遊び的にレコーディングされたものと思われるのがビッツ&ピーシズのシングル。グレイスの"Nipple To The Bottle"の原型のようなドラム・ビートをバックに、ヤーブロウ&ピープルスのヒット曲をほぼ原曲のままのアレンジで演奏し、ラップ風のヴォーカルをのせたもの。B面の"(Break 1-5)"ではドラムとパーカッションのみのリズム・トラックからヴォーカルやキーボードが加わって肉付けされていく様子が明かされている。

<イアン・デューリー>

'42年に西ロンドンのハーロウで生まれたシンガー。'70年代半ばにキルバーン&ハイローズ名義でアルバムを2枚発表するがヒットには恵まれず、本格的に売れるのはブロックヘッズと共に活動するようになる'77年ごろから。'80年代後半からは俳優としても活動する。「パブ・ロック」の代表的なアーティストのひとりともされるが、ブロックヘッズによる黒っぽくファンキーな演奏とアクの強いヴォーカル、毒気を含んだ詞は彼独自の持ち味だ。

トム・トム・クラブでのレコーディングが無くなったスライ&ロビーとタイロン・ダウニーが参加して急遽制作されることになったアルバム。チャス・ジャンケルによるとバハマに着く前のイアンはまだ曲が十分に書けておらずふさぎ気味だったそうだが、レコーディングはスティーヴン・スタンリーの好サポートもあって順調に進んだという。スライ&ロビーの強靭なリズムを生かしたファンキーな曲、イアンのもうひとつの持ち味である哀感を帯びたスロー、イギリス人らしい皮肉の効いたナンバーなどもバランス良く収められ、ラストの"Spasticus Autisticus"で爆発する内容。

元々はユニセフからの依頼で'81年の世界障害者年に向けた曲を、ということで作られたもののようだが、出来上がった曲は左半身に障害を持つ彼と健常者との関係をテーマにした、皮肉と自虐が入り混じる強烈な詞の曲。過激すぎるためBBCでは放送禁止になってしまうが、アメリカではヘヴィなベース・ラインを生かしたファンキーなサウンドが好評でダンス・チャートでトップ40入りするヒットに。12インチのB面はスティーブン・スタンリーによるダブで、ベースとリズム・ギターの絡みがシック風の前半から、ダブ処理されたシンセやドラムが激しく鳴り響く中間部等、オリジナルのヴォーカルも生かしつつインスト部分にスポットを当てたミックスになっている。
<チャス・ジャンケル>

'52年ロンドン生まれのキーボード奏者。'70年代前半からスタジオ・ミュージシャンとして活動した後、'77年にイアン・デューリーのグループ、ブロックヘッズに加入し、イアンの相棒として作曲/演奏/プロデュースで活躍。ソロ活動を行うためにブロックヘッズは'78年に脱退するが、イアンとのつかず離れずの関係はその後も続いた。'81年にはファースト・ソロに収められていた「愛のコリーダ」がクインシー・ジョーンズに取り上げられて大ヒット、それ以降しばらくのアルバムではディスコ・ヒットを意識したダンサブルな曲が必ず収録されている。'88年にLAに移住、リリースのペースは落ちたが近年まで新作を発表している。
チャスも同行した上掲"Lord Upminster"のレコーディング時には隣のスタジオでトム・トム・クラブがファースト・アルバムを録音中で、その流れで両アルバム関係者の交流があった。チャスの妹アナベルがトム・トム・クラブ"Genious Of Love"のビデオの監督を手掛けることになり、チャス自身はティナ・ウェイマスの妹ローラと恋に落ちる。

"Chazablanca"はその二人がラブラブな時期にコンパス・ポイントで録音されたもの。ローラは5曲の曲作りに関わったほかバック・ヴォーカルをつとめ、B-1"Whisper"ではチャスとデュエット。裏ジャケの参加ミュージシャンのクレジットでは真っ先に彼女がリスト・アップされているところに愛情を感じる。

音はチャスの過去作とそれほど変わらず、ディスコ・ナンバーとキーボード奏者らしい打ち込み多用のシンセ・ファンクが中心。イアンと共作した"All I Want To Do Is Dance"はスライ・ストーンの影響を感じるリズム・ボックス+生演奏によるファンク。ローラとのデュエット"Whisper"は彼女のちょっと冷めたヴォーカルが入ってくると途端にニュー・ウェーヴ感が増す気がする。
<ギュイ・クェーヴァス>

'45年、キューバのハバナ生まれ。'64年に渡仏してパリでクラブDJとなり、またファッション・ショーの選曲家としても活躍した。役者としても活動しており、プリンスの映画「アンダー・ザ・チェリー・ムーン」にもチョイ役で出演している。DJとしてはドナ・サマーやヴィレッジ・ピープル、ビー・ジーズ等のディスコ・ナンバーから、アングラなファンクやフィラデルフィア・ソウルをミックスした選曲を得意としていた。自身のミュージシャンとしての作品は'80年代に3枚のシングルを残している。2022年にはシングルの音源に未発表曲を追加した編集盤がリリースされた。

彼の作品でコンパス・ポイントと繋がりがあるのが2枚目のシングル"Obsession"。本人以外の演奏者のクレジットが無く、録音はフランスのスタジオで行われているのでCPAS周辺が演奏している可能性は低いが、A面の"ナッソー・ミックス"はその通りナッソーでスティーブン・スタンリーとフランソワ・ケヴォーキアンがリミックスしている。ジャケットのアートワークはグレイス・ジョーンズの作品で知られるジャン・ポール・グードが担当。

3枚のシングルはいずれもファンク度高めの黒っぽい内容で、ゲイ・カルチャーから出てきた人にしては意外だが、特に良いのはやはり"Obsession"。グルーヴィなリズム・ギターのカッティング、ヘヴィなベース・ライン、キャッチーなコーラス等が絡み合うナンバー。ご本人のヴォーカルがオネエ丸出しのナヨナヨしたタイプなのを気にしなければ、ヴォーン・メイソン&クルーの "Bounce, Rock, Skate, Roll"をアップデートしたようにも聴こえるカッコイイ曲だ。アイランド・フランスから出たオリジナルの12インチは現在プレミア化している。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
