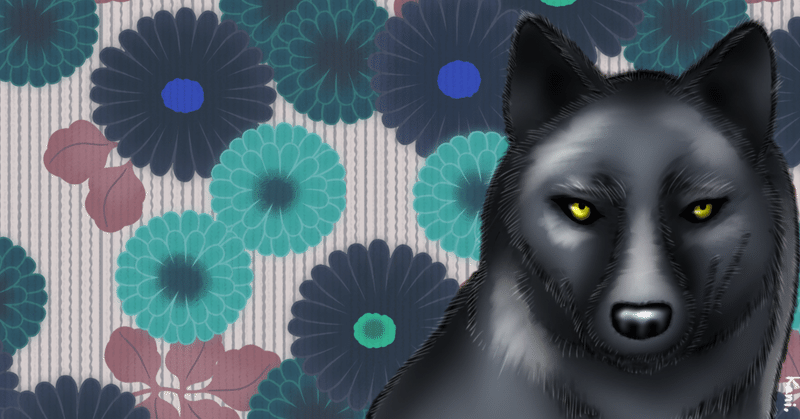
天地伝(てんちでん) 2-17
十七
「お犬さまは、死なのでございますか」
口にくわえていた狸がそんなことを言った。わしは苦笑を浮かべ「死ではないが、生でもあるまい」と、低くつぶやいた。
「死は、それを忘れた者の命を、奪うのでございます」
「それならわしは、とうに生を奪われているはずじゃ」そう言って着地すると、地面にくわえていた狸を転がした。「去れ。どこへなりと行くが良い」
狸は目を瞬かせ、しばらく逡巡したのち、口を開いた。
「でも、お犬さま。どこへ行こうと、同じでございます。人は、山を崩します。あの屍の山も、人が次々と捨てたものです。悪行の果てと、苦しみの果てが、あの死臭なのでございます」
狸の黒い顔を眺めながら、鼻を鳴らした。
「わしの知ったことではない。同情を誘おうとしても無駄じゃ。いま言ったことが本当だろうと、ちいとも可哀想だなどと、思いはせん。貴様があの社の前で、人の腐肉を喰らい、人を騙し、金品を奪っていたのも事実だろう?」
でたらめだった。だが、狸はいくらか思い当たることがあるのか、ぐう、と押し黙り、辺りをうろうろと歩きまわり始めた。それを眺めながら、にやにやと笑う。こいつは阿呆じゃ。
「腹が減っていたから、奴らを喰った。それだけの話じゃ。気が変われば、貴様とて腹に入れるかも知れん」
そう言って、口を大きく開くと同時に、狸は短い悲鳴を上げて森の奥へと、逃げて行った。狸の尻尾が、闇に消える瞬間を見送りようやく、息をついて、力を抜くことができた。ぐったりとして頭を地に伏せる。
脱力しため息をつくと、みずからの行いを恥じた。何が「義」だか。でたらめも良いところだ。笑わせる。確かに、タイマは愛とやらの代わりに義を一にして、行為し語る。だが、わしは欲望を一に思考し、かつそれが絶対的なものだと思ってる。わしに、タイマのような振る舞いなどできるはずがない。
「だからこそ八枯れはんの行動は、心に近いのと違いますの?」
「いつからそこに居た」
草むらから出て来た東堂に、呆れた視線を送った。東堂は茶色い角刈りをかきながら、苦笑を浮かべた。
「ひどいな。ずっと、おりましたよって」
「逃げたんじゃないのか」
「そないへっぴりと違いますよ」
そう言いながら、紺色の上着をはたいている東堂の顔を眺めながら、鼻を鳴らした。「逃して良かったんだな?」と、低くつぶやくと、東堂は不敵な笑みを浮かべて、首をかしげた。
「逃したんは僕と違います。何の関係もあらへん、行きずりの黒犬や」
「半焼したぶんの働きはしたはずだ」
「それはこっちが決めることや」
うんざりした表情を浮かべると、東堂は顎に触れながらにやにやと、笑みを浮かべた。
「よろしおっせ。その代り、一つ良いこと教えたりますわ」
東堂は、風に着流しの袖をひるがえしながら、灰色の双眸を細めた。どこから取り出したのか知れない、黒い帽子を目深にかぶり、微笑を浮かべた。
「義とは、道徳を務めるものであり、あるいはその行いや。つまり、愛とは違う、徳を行う義務なんや。でも欲望は渇望であり、みずからの望みを信じ、行う。それは頭で考えてやるんと違う。心の求めで動くさかい。存外、恭一郎はんより、八枯れはんのが、愛とか心とやらの法には、近いのかもしれん。まあ、必ずしもそれが善とは限らん言うこっちゃ」
東堂は闇の中を歩きだすと、枯草を踏みながらのど奥で笑った。その笑い声は風に乗って、わしの鼓膜を微かに震わせた。
「ほな、さいなら」
うしろ姿が消えると同時につぶやいたその言葉は、えらく儚い響きを内に含んでいた。からころ転がる下駄の音が、じょじょに遠ざかり、聞こえなくなる。
そうか、とため息をついた。尻尾を振って踵を返す。夜のつめたい風を受けながら、牙を見せて笑った。藪と木々の間を駆け抜ける。闇と光のはざまを飛び越える。追い風に毛を逆立てて、タイマと由紀の待つ、あの古ぼけた家屋へと足を急かした。
サポートいただいた、お金はクリエイター費用として、使用させていただきます。 いつも、ありがとうございます。
