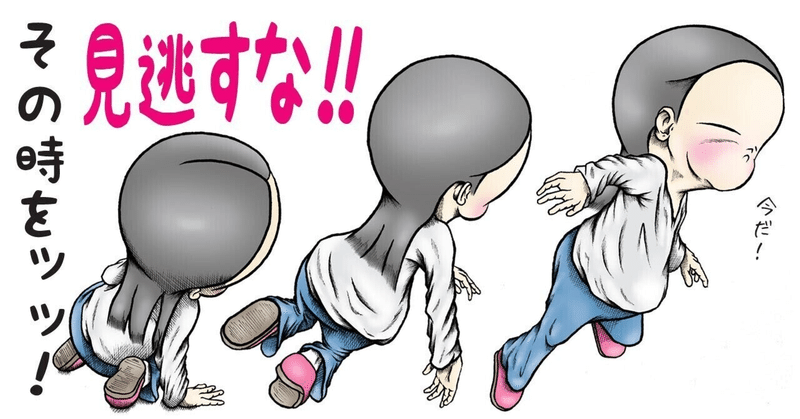
【株】6/27〜7/1振り返りと来週の展望
今週の注目決済指標
・米国 05月 中古住宅販売成約指数
全米不動産業者協会(NAR)が発表した5月中古住宅販売成約指数は前月比+0.7%となった。予想外に昨年10月来のプラスに改善。前年比では-12%。6カ月連続のマイナス。在庫が少ないなかで価格は上がり続けており、ローン金利の上昇と合わせて住宅を購入しにくい状況は継続している。
・米国 06月 製造業景気指数
6月の製造業景気指数は53.0と、前月の56.1から低下し、2020年6月以来の低水準を付けた。市場予想の54.9も下回った。新規受注指数が約2年ぶりに拡大と縮小の節目である50を下回り、連邦準備理事会(FRB)の積極的な金融引き締めで景気が冷え込みつつあることが改めて確認された。消費の対象がモノからサービスに回帰していることが減速の一部要因になっていると見られるが、このところの経済指標で金利上昇による需要減退が示されている。
原油価格の動向
・結果
今週1週間で価格は1ドル上昇。週明けは2日連続陽線だったが、その後2日連続陰線。週末は陽線で引けている。
・テクニカル
4月12日から引けるトレンドラインは割らずに済んだものの、前回高値に達する前に反発。25日移動平均線よりも価格が上に来ることはなかった。

・気になった原油関連記事
[ロンドン 30日 ロイター] - 石油輸出国機構(OPEC)加盟国とロシアなどの非加盟国で構成する「OPECプラス」は30日の閣僚級会合で、8月も現行の増産ペースを維持することで合意した。9月以降の方針を巡る討議は先送りした。OPECプラスは6月2日の閣僚級会合で、7月と8月の増産枠をそれぞれ日量64万8000バレルに引き上げることで合意。今回の会合でこの増産ペースを維持することを確認した。ロシアによるウクライナ侵攻を受け原油価格は上昇し、北海ブレント先物は3月に1バレル=139ドルを超え、2008年以来の高値を更新。その後は低下したものの、供給逼迫などを背景に現在でも115ドルを上回っている。MUFJのイーサン・ホーマン氏は、OPECプラスの増産能力は乏しいと指摘。「供給不足に対する懸念が景気後退への懸念を上回っている」と述べた。
[ワシントン 28日 ロイター] - 主要7カ国(G7)がロシア産石油価格に上限を設ける計画について、中国およびインドと前向きかつ生産的な議論を行っていたことが関係者の話で28日分かった。大幅な割引価格で石油を購入することができるため、中国とインドには計画を順守するインセンティブがあるという。関係者は匿名で、1バレル当たりの価格の上限はまだ設定されていないが、石油を生産し続けるインセンティブをロシアに与えるのに十分な水準でなければならないと述べた。関係者によるとG7各国政府は、価格上限を超える貨物について石油輸送のどのサービスを禁止するのかをまだ決めておらず、海運サービス、保険、貿易金融、貨物の仲介などを直接的に禁止することを検討しているという。また、西側諸国の制裁逃れが可能な船舶の数が限られていることから、ロシアが単に価格上限での石油販売を拒否した場合、より高い価格で販売する選択肢はほとんどない上、貯蓄能力も限られているため、ロシアは生産の大幅削減を余儀なくされ、キャッシュフローが減少し、エネルギーセクターに一段のダメージを与えることになるとした。
・考察
現状の世界情勢は、物価上昇などを理由に景気後退フェーズに入ろうとしている。景気が後退するということは、石油の需要も減ることになり、結果、原油価格は下落すると考えられる。過去にもFRBが量的緩和政策で金融引き締めを始めると、原油価格は下げはじめ、OPECが減産を見送ると大暴落した事例がある。(需要が減るのに供給量が変わらないから結果的に需給のバランスが崩壊した)
しかし、景気後退も囁かれる中、ロシアの地政学リスクによる原油の供給懸念も同時に起きているため、今週の原油価格は一進一退を辿った。
・メモ
原油は資源ではあるが、金融商品化しているので、価格は市場心理で上下する。基本は需給のバランス。
石油と言う商品は、価格が下落しても生産を減少させるインセンティブが働きにくいため、価格下落が止まらない一方で、逆に価格が上昇しても新規投資を行って生産を増加させるには時間がかかるため、価格上昇が止まらないという性質を有する。
最近の原油高は、3つの要素が重なったことによるものと考えられる。
①世界的に脱炭素化の流れが加速するなか、近年、化石燃料への投資が低迷していたこと
②2020年春先のコロナショックを経て、主要国の景気が持ち直し、原油需要が急増したこと
③ウクライナに侵攻したロシアに対する経済制裁により、ロシア産原油の供給不安が高まったこと
米国債10年利回りの動向
・結果
今週1週間で、米国債10年利回りの金利は0.3%下落。6月28日から4日連続の陰線となった。
・テクニカル
今年3月の安値から引けるトレンドラインを割った形になったが、直近安値の2.7%の抵抗線は割っていない。今までほぼ下回っていなかった25日平均線よりも価格が下がる形に。(米国債10年利回りの動向にテクニカルが効いているかは分からないが)

・気になった金利関連記事
きょうのNY債券市場で10年債利回りは一時2.79%まで急低下した。リセッション(景気後退)への懸念が根強く、市場はリスク回避の雰囲気を強めた。朝方発表した6月のISM製造業景気指数が2年ぶりの低水準を付けたことや、5月の建設支出高も予想に反して減少したのを受け、米連邦準備制度理事会(FRB)の積極的な金融引き締めが景気に及ぼす悪影響が強く意識された。
米ドルの為替動向
今週のドル円相場(USDJPY)は、週初135.12で寄り付いた後、①株式市場の軟調推移や、②原油先物価格の冴えない動き、③上記①②を背景としたリスク回避の円買い圧力が重石となり、週明け早々に、週間安値134.51まで下落しました。しかし、6/24に記録した直近安値134.35をバックに下げ渋ると、④米金利上昇に伴うドル買い圧力や、⑤米5月耐久財受注(結果0.7%、予想0.2%)の良好な結果、⑥中国経済の持ち直し期待(北京市と上海市における新型コロナウイルス新規感染者が2月下旬以来となるゼロを記録→リスク選好の円売り圧力)、⑦ニューヨーク連銀ウィリアムズ総裁による「次回FOMC会合は0.50%か0.75%の利上げが議論される」「景気後退シナリオはない」とのタカ派的な発言、⑧サンフランシスコ連銀デイリー総裁による「経済と労働市場は強くよりソフトなランディングに良い位置」との米経済に楽観的な見解発表、⑨クリーブランド連銀メスター総裁による「米金利は来年4%を上回ることを望む」「米経済のリセッション入りは予想していない」「次回FOMCで75bpの利上げを支持する」とのタカ派的な発言、⑩パウエルFRB議長による「米経済は実際にはかなり強い」「米経済は金融引き締めに十分対応できる状況にある」とのタカ派的な発言、⑪上記⑦⑧⑨⑩を背景とした米FRBによる更なるタカ派傾斜観測、⑫6/22に記録した直近高値136.72を突破したことに伴う仕掛け的なドル買い・円売りが支援材料となり、週央にかけて、1998年9月24日以来、約23年9ヵ月ぶり高値となる137.01まで急伸しました。もっとも、買い一巡後に伸び悩むと、⑬米経済指標の冴えない結果(米5月個人消費支出や米6月シカゴ購買部協会景気指数、米6月ISM製造業景況指数)や、⑭米5月PCEコアデフレータ(結果4.7%、予想4.8%、前回4.9%、※前年同月比)の市場予想を下回る結果、⑮米金利低下に伴うドル売り圧力(米10年債利回りは3.00%の大台を割り込み一時2.79%まで急低下)が重石となり、本稿執筆時点(日本時間7/2午前5時30分現在)では、135.31前後で推移しております。

NYダウの動向
・結果
今週1週間でNYダウは、約400ドルの下落。31097ドルで引けました。週明けから4日連続陰線でしたが、週末は陽線で引けました。
・テクニカル
先週の4日連続陽線の流れを引き継げず、前回高値をブレイクする前に反落。しかし、前回安値の29900円台も割っていないので、まだどちらとも取れないが長期的には下落トレンド継続中。先週の4日連続陽線の流れで25日移動平均線を超えられなかった。

・気になったNYダウ関連記事
【NQNニューヨーク=古江敦子】1日の米株式市場でダウ工業株30種平均は反発し、前日比321ドル83セント(1.0%)高の3万1097ドル26セントで終えた。米長期金利の低下が株式相場を支えた。ハイテク株の一角が買われたほか、景気動向に業績が左右されにくいディフェンシブ株が上昇した。3連休となる週末を前に持ち高調整の買いが入り、取引終了にかけ上げ幅を広げた。
日経平均の動向
・結果
今週1週間で日経平均は約800円下落して、25935円で引けました。週明けは2日連続で上昇したものの、週中から3日連続陰線となりました。
・テクニカル
丁度25日移動平均線で反落。先週は安値ラインで反発したものの、今週は高値をブレイク出来ず。25700円台のラインを抵抗線と出来るか注目。

・気になった日経平均関連記事
[東京 1日 ロイター] - 前場の東京株式市場で日経平均は、前営業日比233円51銭安の2万6159円53銭と、3日続落した。米国などの金融引き締めの加速による世界景気減速懸念が引き続き意識され、積極的な買いは手控えられた。米株先物が軟調に推移したことも相場の重しとなった。日経平均は小高くスタートしたが、上昇の勢いは続かずマイナス圏に沈んだ。その後も徐々に下げ幅が拡大し、一時、約240円安の2万6148円61銭まで下落した。時間外取引で米株先物が軟調に推移したことや、値がさ株の下落が相場の重しとなった。
業種別株価変化率の動向
今週の最も上げた業種は石油石炭で、最も下げた業種はゴム製品となった。
今週のトップワーストの業種は、わかりやすく原油の供給懸念による価格変動が原因と思われます。

来週の注目決済指標
・米国 06月 ISM非製造業景気指数
・米国 06月 FOMC議事録
・米国 05月 貿易収支
・日本 05月 国際収支―貿易収支
・米国 06月 失業率
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
