
大人になっても判らない。それが人生。映画 『わたしは最悪。』(2021)
小さい時、といっても当時はもう中学生だったけれど、ゴダールの『女と男のいる舗道』(63) を初めて観た時の衝撃は忘れられない。文化的素養が乏しかった私にとってありきたりな作劇上の起承転結・序破急を脱構築するゴダールの実験的な試みはどれも新鮮で、眉目秀麗なアンナ・カリーナに惹かれたのは言うまでもないが、彼女の演じる主人公ナナのあまりに素朴な "人生の惑い" が当時の自分に重なって、舗道に冷たく横たわるあの結末はあまりにも唐突で酷に思えた。
翻って2022年の夏、大学に入ったばかりの私は突如として舞い込んできた何事かを成すにはあまりに短く、何事も成さぬにはあまりにも長い、そんなモラトリアムを目前に途方に暮れていた。
人生を抱えきれなくなった時はいつも映画に逃げる。『大人は判ってくれない』(59) で育った自分の処世術だ。ふと立ち寄った最寄りの映画館で私は、あの時に似た衝撃を憶えることになった。
前置きはさておき、『わたしは最悪。』(2021) は『テルマ』(17) や『母の残像』(15) で知られるヨアキム・トリアー監督作。この年のアカデミーで脚本賞と国際長編映画賞にノミネートされ、あの『ドライブ・マイ・カー』(2021) と鎬を削ったことは記憶に新しい。

本作『わたしは最悪。』はオスロの街を舞台に、若さと才能に溢れる20代後半のアラサー女性・ユリヤの人生における「最悪」な選択の数々を、全14章の短編エッセイ形式で魅せる現代版『女と男のいる舗道』とも言える作品。しかし今作が一線を画すのは、ゴダールがナナというヒロインが人生に惑う中で舗道に冷たく横たわるまでの顛末を12編のタブローでもって淡々と、ある意味でリアリスティックに映したのに対し、ヨアキム・トリアーは自分自身の可能性に翻弄されながらも世界を置いてきぼりにしてまで「自分探し」を続けるユリヤを追いかけ続ける、そんな「ドキュメンタリー性」を内包しているところにある。
自身の若さと才能を持て余すあまり途方もない人生の選択肢に囲まれてしまい身動きが取れなくなる。そんな現代人を描いた作品といえば、森見登美彦の小説『四畳半神話大系』、あるいはNetflixオリジナルシリーズ『マスター・オブ・ゼロ』が思い浮かぶところだろう。

CM俳優としてひっそり活躍する主人公デフのNYでの日々をシニカルかつウィットに富む形で「現代人の今」として切り取る『マスター・オブ・ゼロ』。原題は"Master of None"、日本語で「器用貧乏」と主人公デフをそのまま言い表しているのだが、『わたしは最悪。』の主人公ユリヤもまた器用貧乏(=Master of None) な現代人なのだ。
本作『わたしは最悪。』はユリアの大学進学からの「最悪な選択」と共に始まる。成績が良いという理由だけで医学部に進学したユリヤは、膨大な勉強量とインターネットからの情報の応酬というこれまた現代的なストレスから医学を諦め、心理学の道に転向し、それと同時に当時のパートナーと別れる。しかしいざ心理学を学び始めると、すぐに講師と関係を持ち、結局「何かが違う」という理由で今度は写真家の道に転向する。
芸術の道にも何処か納得がいかないままのユリヤは、成り行きで出会った年上の売れっ子グラフィックノベル作家「アクセル」との交際を始めるものの、30歳を目前にして彼から「子供が欲しい」と告げられ、ユリヤは再び決断を迫られる。ここまでが本作冒頭。

私自身は決してユリヤのように優秀でもなければ才能に恵まれていたわけでもないが、少なくとも学生という身分で社会の門前が聳え立つ今だからこそ、「若さ」という有り余る可能性を前に途方に暮れてしまう心持ちにはとても共感できる。
加えて、この作品はユリヤの「女性」としての視点が色濃く反映された、語弊を恐れずにいえば「フェミニズム映画」としての側面が強く、特に30歳を目前に「結婚」や「子供」といった自分の人生の可能性を大いに限定するライフイベントを選択する決断を、自身の生理的な事情と他人からの、社会からの要請に迫られる空気感、つまりは「パターナリズム(家父長制)の呪縛」が映画全体に重くのしかかる。
象徴的なのが、この映画冒頭でユリヤに子供が欲しいと迫るパートナー「アクセル」の存在である。彼はいかにもサブカル臭い性差別的なコミックを描いている作家で、これはオルタナティヴ・コミック界の帝王「ロバート・クラム」がモデルになっている。
(このロバート・クラムのドキュメンタリー『クラム』(94) を監督したテリー・ツワイゴフ監督の『ゴーストワールド』(01) もまた「人生の岐路に立たされる女性」を二人の主人公のすれ違いを通して描いている点も興味深い。)

グラフィックノベル作家として成功している「年上」の男性相手として、言動の端々に典型的なパターナリズムを感じさせるばかりか、まだ若いユリヤの可能性を突如として縛りつける反・フェミニズム的な立ち位置であるアクセルは、ユリヤの若さ故の愚かしい「最悪」な恋人選びの象徴でもある。
今作『わたしは最悪。』は監督の初期作『リプライズ』(06) 、『オスロ、8月31日』(11) から続く「オスロ三部作」の最終作に位置付けられるのと同時に、監督のフィルモグラフィーにおける前作『テルマ』(17) の精神的続編としても見ることができる。『テルマ』も今作同様に主人公の女性がオスロの街で大学に入学する場面から始まる。「パターナリズム (家父長制)の呪縛」を超常現象として扱ったフェミニズム的なテーマ性は『わたしは最悪。』に脈々と受け継がれている。

しかし『テルマ』の主人公が最終的には「パターナリズムからの解放」を成し遂げたのとは異なり、『わたしは最悪。』におけるユリヤは一見すると自由奔放な選択をしているようで、彼女は確実に「パターナリズムの呪縛」に囚われているのだ。

30歳を目前にしてもユリヤにはまだ「自分」というものがわからない。いつかは家庭を持つことも良いのかもしれない。でもそれは確実に「今」ではない。アクセルに子供を、家庭を持つことを迫られたユリヤは、人生を決着させることができず、パートナーとも、そしてこの「規範的な世界」とも溝を深め、孤独を募らせていく。
そうして、通りがかりに見つけたパーティに紛れ込んだ先で同年代の青年・アイヴィンと触れ合うユリヤ。お互いにパートナーがいるスリリングな高揚感の中で、二人は徐々に距離を縮めていき、ついにユリヤはアクセルに別れを告げて、彼の元へと駆けていく。

パートナーとの別れを決心した刹那、ユリヤのいる世界は彼女と浮気相手の「彼」を除いてその一切が静止する。マジックアワーの光景に包まれるオスロの街を置き去りにして彼の元へひた走るこの魔法のようなシーン、恋に愛に溺れる時のあの甘美な無限とも思える時間を盛大な遊び心を持って表現したこの手法には、「雑多でジャジーな形式主義 ("messy, jazzy formalism")」という彼独自の作家性が反映されている。

『わたしは最悪。』の最も愛すべき魅力は、耽美なシネマトグラフィーはもちろんのこと、やはりこの「雑多でジャジーな形式主義」という監督の作家性に基づいた「人生賛美」に尽きると思う。
今作はその形式こそ『女と男のいる舗道』を彷彿とさせるが、映像表現として自分の中で真っ先に結びついたのは、フェリーニの『8 1/2』(63) とイニャリトゥの『バルド、偽りの記録と一握りの真実』(2022) だった。奇しくもある作家(というか監督自身)の半生を切り取ったこの両作品は、カオスと言う他ない奇想天外な映像表現を通じて「混沌とした人生の豊かさ」を礼賛する、そんなテーマを描いていた。
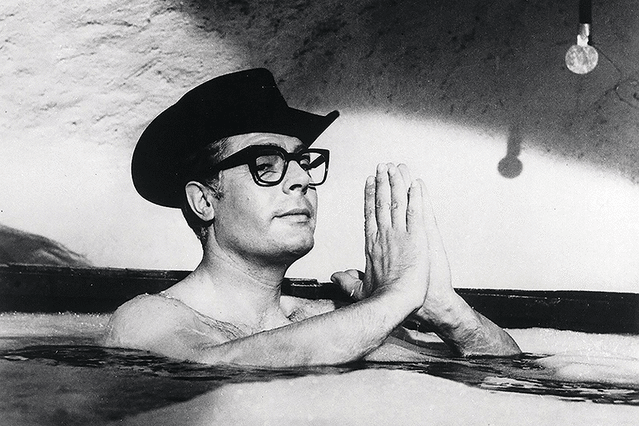
映画的な起承転結を解体した『女と男のいる舗道』と、『8 1/2』的な奇怪な演出、「人生の混沌さ」を表現するための遊び心を余すことなく発揮した"雑多でジャジーな"作品。それこそが『わたしは最悪。』であり、現実の我々のように人生に翻弄されるユリヤの姿に感情移入しないのは無理というものだ。
今作は監督のもう一つの作家性でもあるフェミニズム的なテーマの影響を多分に受けているが、決して観客を選ぶような問題意識で構成されているわけではない。ユリヤが対峙する「最悪」な世界は、彼女以外のキャラクターをも翻弄する。
ユリヤとの子供を欲したアクセルも、その言動にパターナリズムを感じさせる描写こそ多々あれど、それが彼の個人的な問題として処理されることはない。彼もまた規範的な世界に蔓延るパターナリズムの呪縛に囚われている人物として、その社会的な背景が問題提起される。
そんな彼との人生から逃れた先でユリヤが出会ったアイヴィンは、アクセルとは対照的にこれといった社会的地位を持たない非・パターナリズムな同年代の青年だが、その彼との関係もまた、ユリヤの「妊娠」という出来事(インシデント) により亀裂が入ってしまう。「妊娠の不可抗力的な暴力性」という点においては、同年公開の『あのこと』(2021) というフランス映画にも通底する。
妊娠や結婚といったパターナリズムにおける「女性の幸福」、ひいては「幸福な人生」という呪縛に、彼ら彼女らは翻弄されてしまっているのだ。
ユリヤが最も恐ること、それがまたしても「雑多でジャジーな形式主義」により具体的に示される展開がある。マジックマッシュルームでトリップしたユリヤの見る幻覚がアニメーションや特殊メイクを駆使して演出される一連のシークエンスにおいて、「老化により自身の(性的)魅力を失うことの恐れ」と「妊娠と出産という女性であるが故の不可抗力的な苦しみ」から醜い怪物のような姿に映るユリヤは、自分を捨てた家庭を顧みない「父親との確執」を前にして、自身の最も女性的な手段 (筆舌に尽くし難いので是非本編で確認してほしい) で父親に、彼女を縛り付けるこの最悪な世界の呪縛(パターナリズム) に対抗する。

そんな彼女を「最悪」な現実はどこまでも待ち受ける。作中終盤、妊娠が発覚し動揺を隠しきれないユリヤは、時を同じくして元カレのアクセルが末期がんを患い余命がそう長くないことを知らされる。彼の元を訪れ、妊娠を打ち明けたユリヤは、産むかどうか迷っていることを彼と、子供の父親であるアイヴィンに告げる。
かつては子供を欲していたアクセルは自分にもはや未来がないことを恐れ、「君と生きたい」と本音を吐露する。そんな彼を前にして、妊娠に戸惑っていることで様々な罪悪感を暴力的に抱かされてしまうユリヤは、再びオスロの街を背に向け、逃げ出すのだった。朝方、海辺の桟橋にたどり着き佇むユリヤの姿は、トリュフォーの『大人は判ってくれない』(59) のラストにおける世界から、大人たちから逃げ続け、ついに最果ての海岸にまで来てしまったあのアントワーヌ少年を彷彿とさせる。

帰宅したユリヤがシャワーを浴びていると、彼女の身にはもう一つの「最悪」な出来事が降りかかっていた。しかし、それは同時に、この最悪な世界へのユリヤの「勝利」を意味していたのかもしれない。ユリヤもまた、アントワーヌ少年と同じく、世界に立ち向かったのだ。
たしかに「わたし」は、私のいるこの「世界」は、「最悪」かもしれない。
しかしそれでも、理性なんてものではどうにもできない、大人になっても判らない、そんな混沌に満ちたこの「人生」は「最高」で、されど人生は続く。最悪な選択の数々に翻弄されてきたユリヤを映画と共に追いかけた我々が目にする、ついに自分の人生に向き合い出したラストのユリヤの姿は、そんな人生の豊かさを静かながらも力強く肯定してくれる。
ナナの人生が銃声と共に無惨にも唐突な終わりを迎えたあの女と男のいる舗道で足踏みしていた私の背中をそっと押してくれる、そんな素晴らしい作品だった。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
