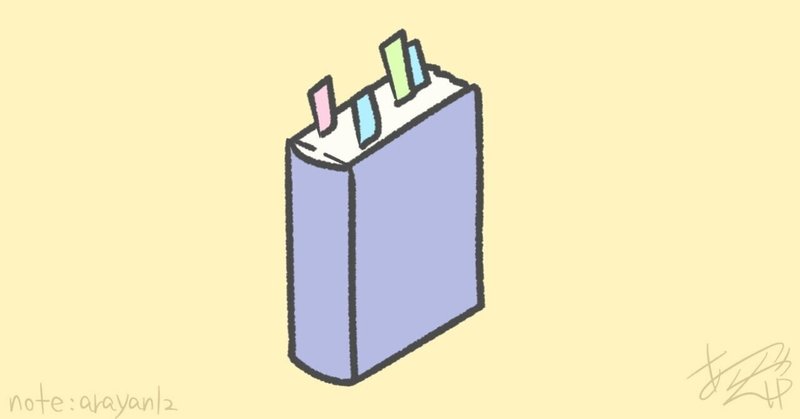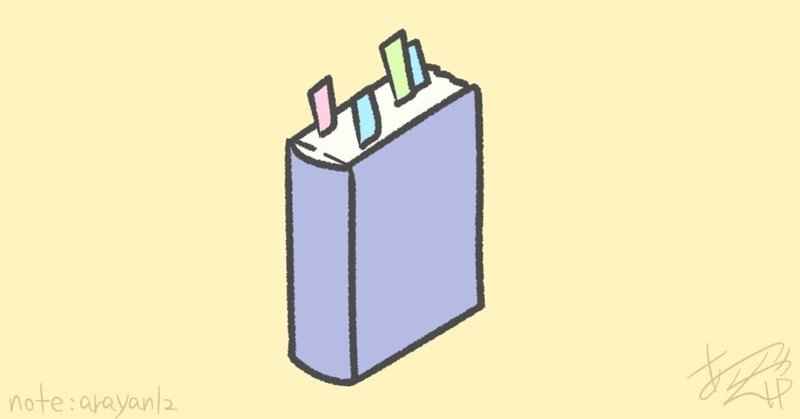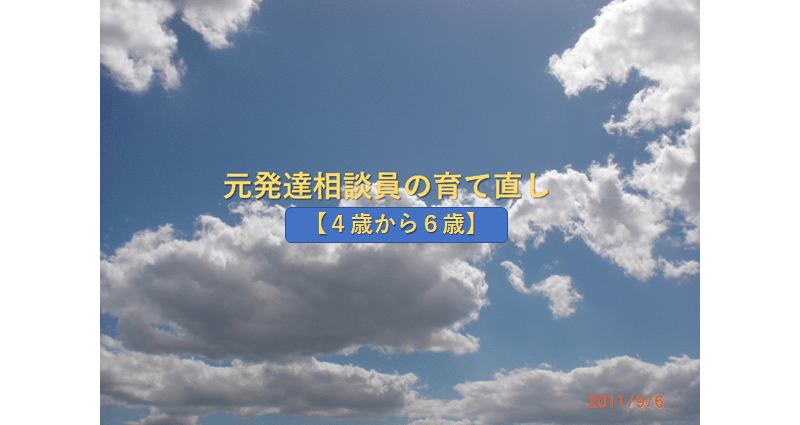
- 運営しているクリエイター
2021年6月の記事一覧
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 その6
3️⃣ 発表するときは、立ってイスを机の中に入れ、みんなの方を向き適切な
声の大きさで話す。 【育て方】
子どもは、声の大きい子はいつも大きい声で話し、声の小さい子どもはいつも小さい声で話す傾向にあります。
だから親が「今は、もう少し大きな声で」とか「ここでは、少しボリュームを下げましょう」とか評価の声かけをして、
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 その7
4️⃣ 成文(文語文)で話す。
5️⃣ だらだら発表しないために、前以てノートに書いてから発表する。
【育て方】
小学校に行く前から、成文で話す経験もしておきましょう。【解説】にもかきましたが「成文で話すことが、考える力やコミュニケーションの基礎になる」からです。小さいときから、取り組んでも損はありません。
普段は口語ですから、どんなときに「成文で話す」ように教えたらい
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 その8
6️⃣ すぐに発表できない時のマナーを身につける。 【育て方】
子どもには、直ぐに返事ないときがあります。狼狽するからです。返事をするのに時間がかかる子どももいます。情報の伝わり方が遅かったり、思っていることを言葉に紡ぐのに時間がかかったりするからです。
だから、すぐ返事できないときのマナーを教えておくと、授業中のマナーに繋がります。
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 19 発表の方法 特別編
Twenty Alcatraz(12万PV達成)さんから、「発表の方法 その7」に
「こんな聞き分けのいい発達障害の子どもなら結構楽ですよねー。実際ひどいと駄々こねて暴れますから。」
というコメントを頂きました。
今は「聞き分けの良くなった凸凹タイプの子どもために、小学1年生に向けて何を育てておけばいいのか」ということを書いています。しかし、4歳になってもまだ「やりとり」が成立していな子
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 20 作文が書けるようになる その1
これには、補助項目がありません。「作文」付いてその1で【解説】します。そして、その2で、幼児期での【育て方】を書きます。
【解説】
学校では「作文を書く」ことを目指します。それには、意味があります。様々な人が、いろいろ言っています。
・貴重な自己表現の場である
・自己肯定の場である
・集中力を高める場である
・将来と向き合う場である
・心が育っていく
一番大事なこと
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 20 作文が書けるようになる その2
4歳から6歳のときに、どうやって「作文を書く力」を育てるのか、その【育て方】を書きます。
「作文を書く力」を育てる方法は、「発表の方法」の【育て方】でも書きましたが、文語で話す機会を設ければいいのです。その時は「頼み事」のときがチャンスだと書きましたが、日常会話でやっても構いません。
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 21 辞書が引けるようになる その1
これにも、補助項目がありません。「辞書」ついて「その1」で【解説】します。そして「その2」で、幼児期での【育て方】を書きます。
学習指導要領上では、3年生のときに国語辞典の引き方を教えることになっています。しかし、それはほんの少しだけです。それだけでは、いけません。なぜなら「辞書を引くこと」には、大きな意味と効果があるからです。
今の小学校は指導要領が変わって、教師が一方的に知識を与え
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 21 辞書が引けるようになる その2
「辞書を引くスキル」の【育て方】を書きます。
4歳から6歳の子どもは、好奇心盛りです。「~は、なぁに?」「これは、なんという~なの?」など、いろんなことを聞いてきます。
そのときが「辞書を引くスキル」育てるチャンスです。知っていたら、ぱっと答えたいところですが、わざと「調べてみようか?」と「調べる」ことに誘ってみましょう。
【解説】でも書いたように、調べて知った内容より調べる過程を知る
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 22 植物や生き物の世話ができる その1
これにも、補助項目がありません。「植物や生き物の世話」ついて「その1」で【解説】します。そして「その2」で、幼児期での【育て方】を書きます。
学校では、動植物を飼育栽培することは、次のような意義があると考えています。
1. 豊かな感情、好奇心、思考力、表現力をはぐくむ
2. 自分以外の相手を思いやる心、他者とのコミュニケーション能力
育てる
3.豊かな人間形成
Ⅱ 低学年で覚えて欲しい学び方スキル 22 植物や生き物の世話ができる その2
「学校に進学すると何らかの動物の世話をしたり、植物を育てたりすることが必ずある」のですから、家庭でも、6歳までに動植物を飼育・栽培する経験をしておきましょう。
学校での意義と同じ様に次の5つが育ちます。特に、凸凹タイプの子どもは、2番と5番のために飼育栽培を経験させた方がいいです。
1. 豊かな感情、好奇心、思考力、表現力をはぐくむ
2. 自分以外の相手を思いやる心、他者とのコミュニ
Ⅲ 低学年で覚えて欲しい対人スキル 23 あいさつができる その1
これの補助項目は、次の2つです。
1️⃣ 先生とクラスメイにあいさつする
2️⃣ 授業の初まりと終わりにあいさつする
一つずつ解説をします。
1️⃣ 先生とクラスメイにあいさつする 【解説】
平均タイプの子どもは、朝の登校時に先生やクラスメイトに会うと気持ちよく「おはよう」と挨拶します。帰るときも「さようなら」と言って帰っていきます。
しかし、凸凹タイプの子どもは、基本あい
Ⅲ 低学年で覚えて欲しい対人スキル 23 あいさつができる その2
2️⃣ 授業の初まりと終わりにあいさつする 【解説】
この「授業のあいさつ」は、学級経営と大きく関係します。1️⃣でも解説しましたように、発達に凸凹がある子どもは「授業のあいさつ」をしない子が多いのです。しかし、「授業のあいさつ」は「先生からの最初の指示」にあたります。だから、あいさつをしない子が一人でもいると、クラスルールが乱れていきます。
その流れは、次のようになります。
Ⅲ 低学年で覚えて欲しい対人スキル 23 あいさつができる その3
1️⃣ 先生とクラスメイにあいさつする
2️⃣ 授業の初まりと終わりにあいさつする
【育て方】
「あいさつすること」を育てていくためには、経験したことに言葉で知識を与えて、「覚えて」で覚えてもらうのがいいでしょう。
つまり、まず親が実際にあいさつしているところを見せて、それに説明を加えましょうということです。そして、常識として覚えてもらうのです。
実際には、散歩などをしているときに「近
Ⅲ 低学年で覚えて欲しい対人スキル 24 学校のルールを覚える その1
補助項目は3つです。
1️⃣ クラスルールは全部覚えて、口で唱えられるようになる。
2️⃣ 学校のルールは全部覚えて、口で唱えれるようになる。
3️⃣ 遊びなどのルールも全部覚えて、口で唱えられるようになる。
ここでは、ルールについて【解説】します。
クラスや学校には、実にたくさんのルールがあります。だいたい常識的考えれば、すぐ分かるようなことでもルール化されています。
例と