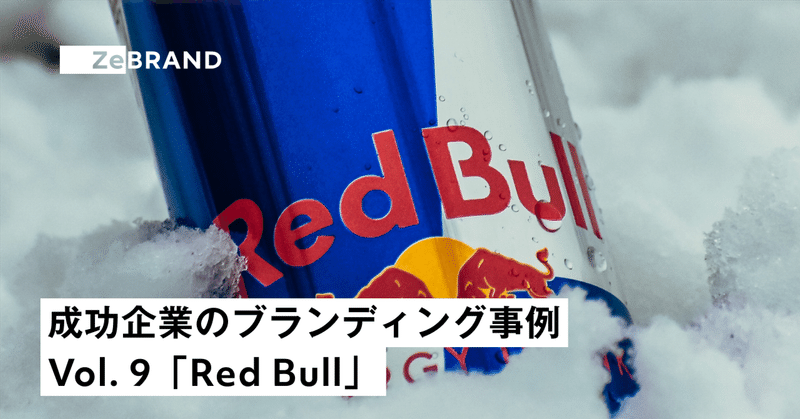
成功企業のブランディング事例 Vol.9 「Red Bull」
成功企業のブランディング事例シリーズのVol.9へようこそ。
Vol.8を見逃した方は、こちらからお読みください!
本シリーズでは、様々な企業をピックアップし、その企業のブランディング手法や、それによって得られた効果についてご紹介します。
ニューヨークでサービスをローンチし、一年で約55,000ユーザーを獲得したZeBrandが、ブランディング初心者にもわかりやすい解説を目指します。グローバルで展開するブランディングサービスで提案している3つのステージに基づいて、体系的に企業を分析し紹介していきます。このシリーズを読みながら、ブランディング知識を蓄えていきましょう。
ブランディングに興味はあるものの、
・ブランディングが企業にどんなメリットをもたらすのか知りたい方
・ブランディングに関する知識を蓄積したい方
に役立ちます。
ブランディングの概要に関しては、こちらの記事をご参照ください。
Define: ブランドの核となる方向性を整理し、定義する
・ブランドDNA
Design: ビジュアルアイデンティティをデザインする
・ブランドストラテジー
・ビジュアルアイデンティティ
Deliver: ブランドを世界中に届ける
・ブランドアセット
Refine: ブランドを見つめ直す
・Define Design Deliverを繰り返しながらフィードバックをする
Red Bullとは
レッドブルは東アジアの機能性飲料にインスピレーションを受けて、1980年代半ばにオーストラリアで創業された企業で、エナジードリンクのレッドブルを販売しています。2022年には年間で115億本が販売され、世界のエナジードリンクの中でトップシェアを誇っています。売上高や収益、営業利益も上昇しており、会社市場最高を記録しているそうです。30年間成長し続ける要因は、極めて効率的なコスト管理や継続的なブランド投資の強化にあると、自社HPにて分析されています。では、具体的にレッドブルがどのようなブランド投資を行ってきているのか、創業から30年ほどの誕生して長くない企業がここまで愛される所以を探っていきます。
レッドブルのDefine
市場開拓とキャッチコピー「翼をさずける」
レッドブルが商品を出す際に、東アジアの機能性飲料にインスピレーションを得たと前述したとおり、レッドブルの商品は、既存の市場の中で作られた製品となります。そのため初めのころは、日本も含め世界中でシェアを伸ばせずにいたそうです。レッドブルは、栄養ドリンク市場の中で戦い抜くためには、判断基準になる栄養素の多さや効用の優劣などで勝つのは難しいと考えたそうです。
つまり、売り上げを伸ばすためには、シンプルに「美味しくて、安くて、栄養素が多く、大量に飲める」ドリンクを作るのでは勝てないと考えたのです。よく考えると、レッドブルを飲むときは「美味しさも、安さも、栄養素の多さも、缶の大きさも」求めてないことに気づきませんか?
レッドブルは、「栄養ドリンク」という市場ではなく、「エナジードリンク」といった新たな市場において、「元気になる」「気分を上げる」ために飲むものと位置づけることによって、先駆者となることに成功しました。疲れたおじさんが飲む「栄養ドリンク」ではなく、気分を上げたい若者がレッドブルを飲むといった価値転換を「Red Bull 翼をさずける」といったキャッチコピーが後押しする形となり、人気ドリンクとして認知されるようになったのです。
レッドブルのDesign
力強いロゴマーク
レッドブルのロゴマークには、ブランド名のレッドブルつまり、赤い牛が起用されています。エナジードリンクの効果を想像させるような、元気のよい雄牛がモチーフにされており、元気で雄々しいイメージを受けるものとなります。

ロゴの印象もあることから、レッドブルといえば、赤い雄牛のシンボルマークや青・銀色のイメージがあるでしょう。これは、レッドブルがスポンサーを務めるスポーツチームにおいても、イメージカラーとしてロゴやユニフォームに使われていたりと、一貫されています。例えば、サッカーチームの例を挙げますが、「FC Red Bull Salzburg」「New York Red Bulls」「Red Bull Bragantino」「RasenBallsport Leipzi」「FC Liefering」のレッドブルがスポンサーをしている、5チームすべてにおいて胸の同じ位置にレッドブルの雄牛のロゴが描かれ、全チームのユニフォームのカラーが赤や白がメインになっています。

レッドブルの愛されるCM
レッドブルといえば、テレビで「レッドブル翼をさずける♪」といった、一言とともに流れるCMを思い浮かべる人もいるのではないでしょうか。手書きで描かれたようなかわいらしくユニークなイラストで作られるアニメーションは、ハンガリーの制作会社で1985年から変わらず、今でも紙に鉛筆と水彩を使って手書きで作成されているそうです。大きくて有名なアニメーション会社などに出資してCMを作るのではなく、小さな制作会社に頼むところもまた、挑戦する人を応援するレッドブルらしさのようにも感じます。レッドブルのアニメーションCMは世界170カ国以上のマーケットにて放送されていて、日本人を含め、多くの人から愛されています。制作者の話によると、2人のキャラクターしか登場しないわずか15~20秒のCMでも、アニメーションの準備に3~4週間、その後ペイントやクリーンアップで1週間を要するため、約5週間もかかるそうで、「Superhero」というタイトルのCMを作るときは9種類ものパターンを用意したこともあったそうです。失望したカエルの王様やずる賢いナポレオン、喉が乾いたドラキュラなど、個性的で魅力的なキャラクターが毎回私たちを魅了していることからもわかるように、1つの広告に対するレッドブルの熱量を感じることができるでしょう。
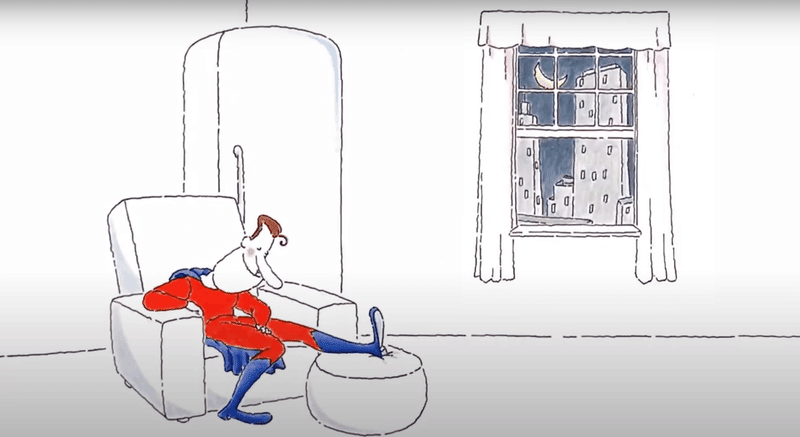
実はレッドブルは所有している航空機やレーシングカーなどのコレクションを展示する「レッドブル・ハンガー7」といういわば近代ミュージアムなるものをドイツに作っています。そちらでは、世界中で人気なアニメーションCMの合計40,000点を超える原画や漫画のコマ、スケッチ、総原稿が期間限定で展示されていました。
レッドブルのDeliver
エクストリームスポーツの協賛
レッドブルが成功した理由として必ず語られるのが「スポーツマーケティング」だと言えるでしょう。スノーボードやサーフィン、BMXなどのエクストリームスポーツにレッドブルは積極的にスポンサー契約を結んでいます。危険さ・華麗さ・過激さを兼ね備えたエクストリームスポーツに、レッドブルはあえて注目て、スポンサー契約をすることでブランド力を高めています。これが、いわゆる大企業が一般的に行うスポーツマーケティングと大きく異なる点です。人気スポーツの有名選手のスポンサーとなることでその選手の知名度や人気から企業側は宣伝効果を狙おうとするのがよくあるスポーツマーケティングなのですが、レッドブルはあえてマニアしか知らないスポーツのスポンサーをメインに行います。スポンサー契約に加え、空のF1と呼ばれる「エアレース」や、28mの断崖から海に飛び込む「クリフダイビング」など新しいエクストリームスポーツの大会も、レッドブルの名を冠し、開催することで、スポーツ自体を広げることにも貢献し、選手や組織に、ただお金を提供するだけではなく、一緒に協力しあうパートナーのような存在となることで、一般の企業とは全く違うイメージを獲得しているのです。そして、リスキーでスリリングだけれど、大きな挑戦をするといった姿がレッドブルの商品イメージと重なり、「レッドブル=先駆者」といったイメージを私たちに根付かせています。逆に、レッドブルのロゴがゆったりとした雰囲気の場所にあることを想像してみると違和感を感じるのではないでしょうか。この違和感を感じさせる力がブランド力の高さとも言えるでしょう。

クラブやバー
レッドブルの宣伝の場はスポーツだけにとどまりません。初めは、エナジードリンクとしてのキャラクターを確立するために、イケてる若者が多くいるクラブやバーでプロモーションを行いました。ダンサーやミュージシャン、DJを発掘するコンテストなどを開催していました。出演者にはパフォーマンスの前などにエナジードリンクを飲んでもらい、その感想をSNSで発信してもらうことで、若者の間に「おじさんが飲む栄養補給ドリンク」と言うイメージから「若者がパワーをチャージしたい時に飲む、いけてるドリンク」と言うイメージをつけることに成功しました。
レッドブルカー
レッドブルは街中でのサンプリング活動も行っています。街中でレッドブルのサンプリングをしているのを見たことがあるのではないでしょうか?レッドブルのサンプリングは、よくある「アルバイトの人が人通りの多い場所で一心不乱に配りまくる」といったサンプリングとは違った工夫や機能があります。ポイントは、量より質を意識しているという点です。まずは、サンプリング用のレッドブルを乗せる車に関してですが、ルーフに巨大な「レッドブル缶」を載せた街中で異彩を放つ車となっています。サンプリングの缶を積むための車であるにもかかわらず、後部座席が削られており(実はレッドブル缶の部分には何も乗っていないので)、とても小さいのです。レッドブルカーと呼ばれるその車のナンバーは必ず「283(つばさ)」となっているなど、レッドブルのこだわりの高さを感じることができます。つまり、単純な配布「量」よりも、記憶に残る体験の「質」を重視しているのです。また、レッドブルカーに乗るのはレッドブルガールと呼ばれる美人女子大学生2名で、サンプリングのチームは「ウィングスチーム」と呼ばれます。このレッドブルガールによるサンプリングの姿勢も非常に印象的です。レッドブルガールは単純にレッドブルを配り回るのではありません。レッドブルガールはその場でレッドブル缶を開けてコミュニケーションを取ります。例えば、「翼を授かったことはありますか?」といった会話をしてくれたり、レッドブル缶を開ける時には「レッドブルリング」といった、リングで缶を開けられる特殊なリングをつけていて、お客さん側から「それはなんですか?」といった会話を引き出す工夫もされているのです。一見お客さんと会話する時間は、新しい顧客獲得のチャンスを逃しているように、もったいなく感じるかもしれませんが、レッドブルはあえて会話することで、レッドブルのコアなファンを増やしているのです。

まとめ
レッドブルが世界でトップの売り上げを誇るエナジードリンクになったのには、他の企業とは一味異なる、さまざまな戦略とその一貫性にあります。ユニークなキャッチコピーと、そのイメージにあった一貫したプロモーション活動が、私たちの心にあるレッドブルのイメージを作っているのです。
成功企業のブランディング事例シリーズでたくさんの事例を知ることで、ブランディングに関する知識やアイディアを蓄えることにつながります。本シリーズの他記事にも興味がある方は、こちらからご覧ください。
ZeBrandはブランディングに関して、戦略構築からアセット作成まで一括で管理することのできるブランディングプラットフォームとなっております。ブランドガイドラインの作成や各種SNS用テンプレートの作成なども可能です。ご興味ありましたら、お問合せください。
