
【かんたん解説!】義務化されたHACCPとは?飲食店がやるべきことを簡潔に解説します!
「最近、食品衛生法が改正されて、HACCPをやらなくちゃいけないって聞いたんだけど、何をすればいいの?」や「そもそもHACCPって何?」といった疑問に今回はお答えしようと思います。
飲食店向けに解説しますので最後までお読みいただくと、難しいと思っていたHACCPが出来るようになれるはずと思います。

HACCPとは?かんたんに解説します。
■食品衛生法が平成30年に改正され、令和3年6月1日より施行されました。これに伴い「HACCPに沿った衛生管理」が、原則として全ての食品関連事業者に義務化されました。
※食品衛生に関する指導員の方が見たらざっくりすぎて怒られるかもしれませんが、まずは大まかなイメージをお伝えしております。


HACCPを実施しなければならない事業者について
小さな飲食店など食品関連事業者はこれまで【一般的な衛生管理】を行ってきました。それに加えて急にHACCPも実施しろって言われても困ります。そこで、事業者の規模や内容に応じてHACCPで取り組むべき内容を区分しております!

【小規模事業者とは?】
「食品の取り扱いに直接従事する者が50人未満の製造・加工等の事業場」
「製造・加工等した食品の全部または大部分を隣接または併設する店舗で小売販売するもの」
「飲食店営業または喫茶店営業を行う者その他食品を調理する営業者」
「食品を分割して容器包装に入れ、または容器包装で包み小売販売する営業者」
「容器包装に入れられ、または容器包装で包まれた食品のみを貯蔵・運搬・販売する営業者」

【HACCP実施の対象外となる業種】
農業および水産業における食品などの採取業
公衆衛生に与える影響が少ない(食品衛生上のリスクが低い)営業
(食品または添加物の輸入業)
(食品または添加物の貯蔵または運搬のみをする営業、ただし冷凍・冷蔵倉庫業は除く)
(常温で長時間保存しても腐敗、変敗その他品質の劣化による食品衛生上の危害の発生のおそれがない包装食品の販売業)
(器具容器包装の輸入または販売業)

上記に該当しなかった食品関連事業者は、一般的な衛生管理と【HACCPに基づく衛生管理】を実施しなければなりません。
HACCPの考え方を取り入れた衛生管理って何するの?

HACCPとは、Plan(計画)Do(実行)Check(評価)Action(改善)を行えば良いのです。



1つ目の社員教育の手間が軽減できるというのは、これまでオーナーや料理長などが当たり前のように行ってきた食品に関する衛生管理は、新しいスタッフが入るたび1人1人にその教えを伝えてきました。
これはとても大切なことなので、一人前の料理人になってもらうにはとても時間がかかります。
しかし、食材ごとの取り扱い方など教えたけれど新しいスタッフも人間なので忘れることもあるでしょう。その時すぐに聞ければ良いですが、常に一緒にいる訳ではありません。結果、わからずに食品を扱い食中毒の事故など起こされた日には、たまったものじゃありません。

2つ目は飲食店を経営していると、お客様から言いがかりのような理不尽なクレームを受けることもあるかもしれません。「ここで食事したら体調がおかしくなった、どうしてくれるんだ?」なんて言われ、もし因果関係がないことの因縁をつけられたときに対処する方法はありますでしょうか?

他にも当然、衛生環境が向上している訳なので自社商品に自身を持って販売することもできるし、食の事故など起きにくく悪評が立つことを防ぐことができます。SNSが発達した現代で食の事故を起こした営業者がかんたんに炎上していることは皆さんご存じだと思います。
衛生管理計画書ってどうやって作るの?
前置きが長くなりましたが、いよいよHACCPでやることの第一歩「計画」の作成です。

以下がそのひな形ですが、項目を埋めていくだけで計画書が作成できます!




次にこちらのひな形ですが、ここにはお店のメニューを大きく3つのグループに分けその管理方法を記入します。


食材や料理を危険温度帯に長く放置しておくと、食中毒の原因となる菌やウイルスが増殖してしまいます。しかし、短時間であれば害を及ぼすまで増殖しないため、速やかに低温(10℃以下)または、高温状態(60℃以上)となるように心がけます。
グループの分け方は、
第1グループ‥「冷蔵品を冷たいまま提供する非加熱のもの」(例:冷ややっこ、刺身など)
第2グループ‥「肉や魚など冷蔵で保管していたものを調理し加熱するもの」(例:ハンバーグ、焼き魚など)
第3グループ‥「調理した後に一時的に保存し、提供する時に再度加熱するもの」(例:カレー、ソース、ポテサラなど)
に分類します。


「第2グループ」に分類されたメニューは比較的に肉や魚などが多くなり、有害生物が付着している可能性があります。しかし加熱殺菌が可能となるため、食材の中心部までしっかりと火を通すことが大切です。
「第3グループ」に分類されたメニューは、一度火を通したからと言って死滅しない有害生物もあるため、危険温度帯に長時間置いておくことは危険です。調理後はできるだけ速やかに冷却し低温で保管、提供時に再び加熱するときはしっかりと火を通しましょう。



計画の実践と記録、改善
計画の実践はスタッフ皆んなで実行しなければ意味がありません。誰か一人が取り残されないように皆んなで共有しましょう!

一気に2枚ともご覧ください。
万が一、その日に何かあったならそのことを特記して記録に残しておきましょう!



まとめ
【HACCPについて】
食品衛生法の改正によりHACCPが義務化された
飲食店は「これまで行ってきた一般的な衛生管理」と「HACCPの考え方を取り入れた衛生管理」を行う
HACCPでやることは主に「計画の策定」「実践」「記録」「改善」
計画書や記録はひな形が用意されていて、その項目を埋めていくだけで作成できる

HACCPのご相談なら、Second.行政書士事務所へ
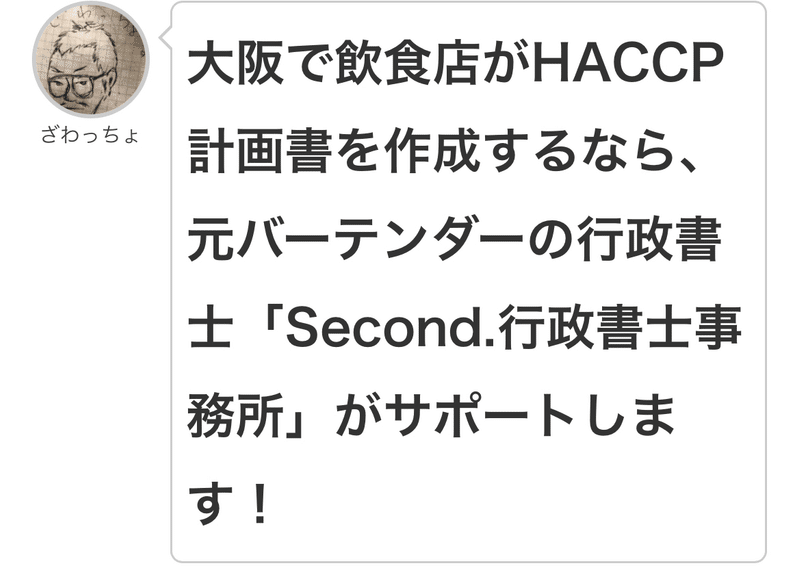
「HACCP計画書の作成サポート 基本料金5500円(税込)~」(準備中)
※メニュー数の多さや調理工程の複雑さに応じて、別途追加料金が発生する場合がございます。
※当事務所スタッフの交通費はお客様にご負担いただくようお願いしておりますので、ご注意ください。

▪️「ZOOM」での全国対応を準備中です。
お問い合わせはメール、またはLINEからでも随時受け付けております。
相談料は無料!まずはお気軽にお問合せください。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
