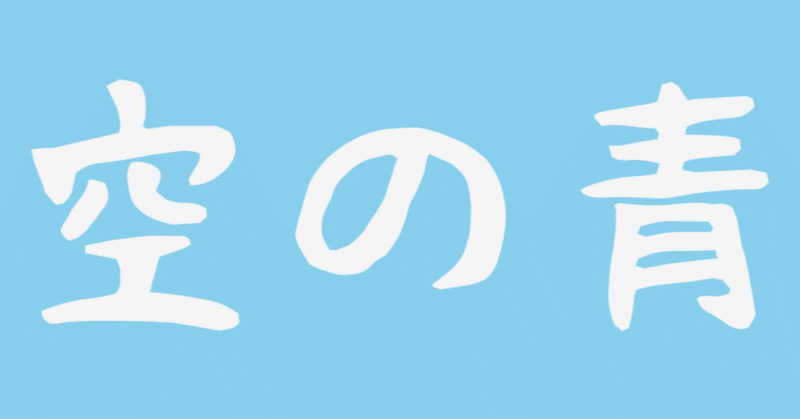
20040709 空の青(2)
空はなぜ青いか$${^{*1}}$$の続き。近くで見ると無色透明な空気がどうして遠くから見ると青く見えるのか。水は青い光以外を吸収し易いので海が青くなる$${^{*2}}$$のと同じように、空気も青い光以外を吸収してしまって青く見えるのだろうか。
水を茶碗や盥に入れて覗いても水には少しも色が付いていない。深い池や海などでは、水がある程度沢山あると青く見えてくる。空気は常に身の回りにあって沢山あるはずだがなかなか青く見えない。青いのは空ばかりである。水よりも更に青色以外を吸収しにくいのだろうか。それとも空気の密度が薄いからだろうか。
水に比べて空気は圧倒的に軽い。800分の1しかない。軽いと言うことは含まれる分子の数が少ないと言うことである。光を吸収するのは分子だから分子の数が少なければ吸収されにくい。
光が吸収されて、その光が人間の目に入るためには、そのものを通過しなければならない。光は何もなければ真っ直ぐ進む。空は太陽の光で青く見えているはずである。夜になると黒くなることを考えれば明らかである。太陽が上空のどの位置にあっても空は青い。ということは太陽の光が空気を通過する内に青い光以外が空気に吸収されるから、空が青く見えるのではないことになる。上空の空気中を通った太陽の光は我々の頭をかすめて宇宙空間に放たれる。
太陽の光は空気の中で散らばっているのである。空気が少ないと散らばる光の量も少ないので殆ど判らないが、空のように空気が沢山あるところでは散らばる量が多くなるのでそれが見えてくる。光の散らばり方は波長によって異なる。波長が短いと空気中で散らばりやすい。即ち太陽の光のうち波長が短い青い色の光が空気中で散らばりやすい。光が散らばれば地上にいる我々の目に入ってくる。それで空は青く見える。
レイリー$${^{*3}}$$(レーリー、レーレー$${^{*4}}$$)散乱という。空気中の分子の数が多いほど散らばりやすい$${^{*5}}$$。
空気のない世界では、太陽から直接降り注ぐ光しかない。青空は見えない$${^{*6}}$$。
*1 20040708 空の青
*2 20040707 海の青
*3 Lord Rayleigh - Biography
*4 『天才バカボン』キャラ紹介 | 赤塚不二夫公認サイトこれでいいのだ!!
*5 レイリー散乱とは - コトバンク
*6 as11_40_5902.jpg
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
