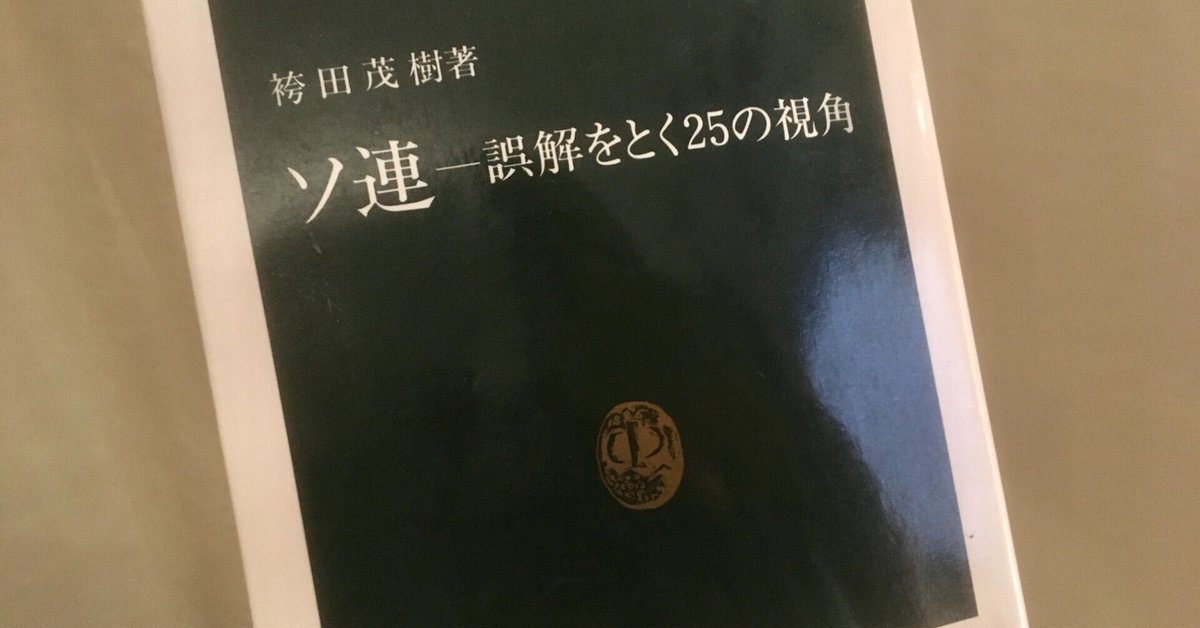
「ソ連ー誤解をとく25の視角」
この本を手にしたのはいつだったのだろう。もしかするとモスクワ行きを決めた2000年だったかもしれないし、モスクワを初めて訪問した後だったのかもしれない。
まさか、この本がこんなに役に立つなんて。
のっけから思い当たる節がたくさんあったのだ。以下、少し引用部分が長いがご紹介してみようと思う。
私は5年余りソ連で暮らしたことがあるが、あちらで生活した経験からいうと、どんな指導者が現れようといかなる改革策が出されようと、あの国が本質的に変わるとはとても信じられないと言うのが正直な実感である。
このように、たしかに上の政策は変わり文化面での変化は顕著なのだが、これから問題になるのは、ではあの巨大な惰性をもったソ連の社会や経済がはたして本当に変わるのかということだ。
ソ連の政治とか社会の性格について、またソ連人の考え方や行動について、われわれ西側の人間がしばしば基本的な部分での認識をかいているのではないかということである。より正確にいうと、ソ連認識が実態から離れたあまりにも表面的で平板な通念や虚像に支配されているということだ。
このように現実とは乖離したソ連認識は、一般国民だけでなく国際問題の専門家の間にさえ見られる。
「ソ連ー誤解をとく25の視角」はじめに、より
もちろん今、「ソ連」という国は存在しないし、冷戦時代でもない。それなのに、今のロシアを見ていると、著者の袴田茂樹氏が当時受けたソ連に対する考えがまだ当てはまるような気がしたのだ。
ロシア人の知人がFacebookに投稿していた1930年台に書かれた詩の意味がわかったような気がした。ロシア人にとっては、今プーチンがやろうとしていることがまるでスターリン時代のように思えるのかもしれないからだ。
ソ連教育理論の柱と見られているマカーレンコ(1888−1939)彼は指導者の権威を絶対化し軍隊的な規律を重視する集団主義教育論を打ち立てた。
「権威の意義そのものは、それが年長者の疑うべからざる風格として、その力、価値として受け取れられるところにあるのだ。・・・時には証拠をあげなくても、あなたが言ったから正しいのだというふうにする必要がある。・・・こうして私たちが無条件に自分の指導者を信じる素質がつくられるのである。・・・年長者や集団の全権委員の論理に対する尊敬、このきわめて大切な価値は伝統によって保たれてゆくのだ」
「スターリン主義の人間学」としてのマカーレンコ。ルソー的な理想主義を嘲笑する徹底したシニカルな人間学がある。
ソ連人には、一般的精神として、全ての人間は、その天性からして卑劣官であり、これを厳しく監督しないと、ネジのように扱わないと、過酷な法律を禁令を適用しないと、ただちに腐敗し、盗みをし、堕落をし、祖国を裏切りはじめるだろうという確信が存在する。(L・レールト)
スターリン時代に生まれた指令経済のシステムそのものが、人間不信を前提としていた。
「ソ連ー誤解をとく25の視角」ソ連共産党と人間性悪説、より
まだ数章しか読み進めていないが、すでに現状況に重なる箇所が多々出てくるのには正直驚いてしまう。本当に現政権が全てをスターリン時代のように後退させたいのかはわからない。当時の先人たちでさえ「人間不信の制度」を批判するようになり、社会や経済の活力を窒息させていたことに気づいたというのに。どうか同じことを繰り返さないで欲しい。
それにしても、「ソ連」を扱っているこの本がこんなふうに役に立つ日が来るとは夢にも思わなかった。
サポートは今後の取材費や本の制作費などに当てさせて頂きたいと思います。よろしくお願いします!
