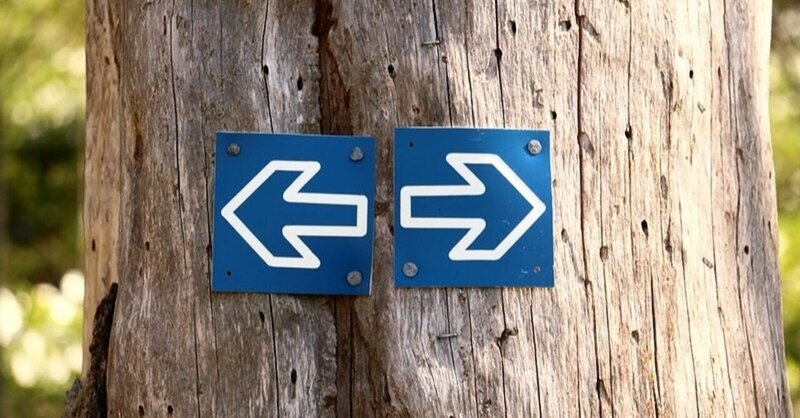
読書記録「漂流日本左翼史 理想なき左派の混迷1972-2022」池上彰・佐藤優著
講談社現代新書
2022
新左翼で終わったイメージのある
それだけではない部分が取り上げられていて興味深かった。
『漂流 日本左翼史』では、一九七二年以降を扱っているが、新左翼が内ゲバとテロリズムに傾斜し、社会的影響力を失うなかで、左翼の主戦場は労働運動になったという見方を私たちはとった。
その労働運動も徐々に大衆の支持を失っていくことになる。
そこにはもちろんソ連崩壊という背景もある。社会党に関しては一部をパージしていった結果ともいえる。
一方でマルクス主義以外で人気を集めたとして少し紹介されていた吉本隆明の説明。さすがにわかりやすかった。
マルクス主義では政治体制のあり方(上部構造)は下部構造である経済体制に規定されるものと通常考えますが、吉本は戦前の日本が、天皇制のような宗教的イデオロギーにあっさりと支配されてしまったことに強い疑問を持っていました。そして国家や法律、企業といった社会の公的な関係、つまりマルクス主義的な上部構造は詩や文学と同じく単なる虚構であり、共同の幻想であると考えた。その幻想の正体を『古事記』や『日本書紀』を紐解きながら考え、「国家とは何か」を本質的に探求することで、国家と個人の関係を見つめ直したのです。
現在の左翼の状況はまさにタイトルにある通り「理想なき左翼」。
人は大きな物語、理想に惹かれてついてゆくもの。その理想を語れない左翼はまさに迷走しているといえる。
ウクライナ情勢もあって、環境問題などで一時は注目を集めた社会運搬も下火になってしまうのだろうか。
目の前のことで手一杯でそんなことなど言っていられないというふうになってしまうのだろうか。
運動を組織していく難しさについても語られていたが、このまま人々が別の方向に流されてしまわないか、心配になった。
あとがきで佐藤氏は超越的価値観を持つことの必要性を述べているが、日本においてはそれは無理なのではないかと加藤周一の愛読者として思ってしまった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
