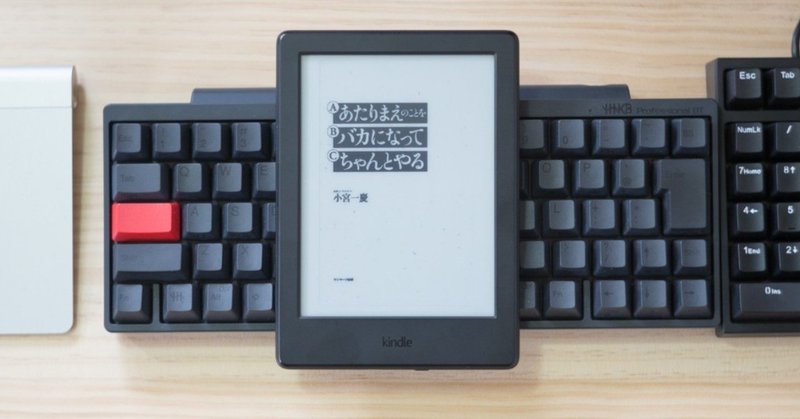
=読書感想文=あたりまえのことを バカになって ちゃんとやる 小宮 一慶
小宮 一慶氏は、数々の著書出している有名な経営コンサルタントです。
人としての基礎、基本、原理原則を中心に、堅いビジネスを提唱する人で、経営以外でも人生訓として大いに役立つことが多い上に、それをわかりやすく書いてくれるので、この方の著書は結構読んでいます。
私も独立してから当たり前のことを当たり前にするのが一番難しいと思いました。今までは、会社が当たり前のことを当たり前にするように縛ってくれていました。しかし、起業すると誰からも管理されません。規制や規則かないということは、自分で、自分を管理、コントロールしないといけないです。結構つらいことです。
でも、大丈夫!この本を頭に叩きんでおけば安泰です。
起業を志す方や、仕事や生活をより良くしたい方におすすめです。
–この読書感想文の読み方–
本の中から、気になった言葉(文章)を引用しています。「 」の部分です。本を純粋に楽しみたい方は、ここを読まずに本を入手されてください。
「→」は、私の感想です。
読んだ人によってそれぞれ心に刺さるポイント、文章が違うと思います。
読んで見たいと思ったら、実際に読んで、再びこの文を読んでいただき、
私の着眼点との相違を楽しんでもらえれば幸いです。
そして、あなたの新しい発見や問題の解決のヒントになったら嬉しいです。
–スタート–
「小さなことさえ、徹底してできない人に、大きなことができるわけがありません。掃除さえきちんとできない者に、ちゃんとした仕事ができるわけがないのです。」
「Aはあたりまえのこと、Bはバカになること、Cはちゃんとやることの頭文字ですよ。」
→大きなことをやっている人は、小さなことが目立たないので、やってなさそうなんですけど、結構小さいことからやっているんですよね。ユニクロの柳井さんは、小売は、リテールだ、だからディテールにこだわるとダジャレみたいな事言いますが、本当に細かいことに気づいてやっていくそうです。
「チューブの中の「幸せな場所」を歩くために大事なこととして、たとえば次のようなことがあげられます。 「何が起きても、前向きにとらえる」 「人間として、正しい考え方を持つ」 「仕事を深めるための勉強をする」 これらはいわば、人生がうまくいくための原理・原則と呼べるものです。」
「ハンドルを右に切れば、車は右に曲がり、左に切れば左に曲がる。それと同じ理屈です。前向きにとらえれば、「命」が自然とチューブの上のほうに運ばれ、後ろ向きにとらえれば、「命」が自動的にチューブの下のほうに運ばれていく。だから「運命」と呼ぶのだと、私は考えています。」
→チューブという考えは、著者独自のものですが、考えてみれば、当たり前なんです。人間は、見た方向に進もうとします。自転車乗っていて、右を見ながら、左に曲がるなんて、ただの曲芸です。人間の体は、目線の先に行こうとします。
「成功や幸せとは、人を幸せにしたご褒美だと私は思います。」
「人生は四つの団子が串に刺さっているというのです。 最初の団子は自分です。二つ目は家族や友人、三つ目は会社、そして四つ目は社会や国家です。 老師はこの四つのどれもはずさない生き方をしなさいというのです。」
「自分の団子をはずしてはダメ。でも、まわりにいる人を幸せにする団子も大切にしなければいけない。そして企業もうまくいくように、社会にも貢献できるように、それぞれの団子の真ん中を突き刺すような生き方が大事」
「それは現実を理想に近づけようという志があるからです。」
「この世は「弱肉強食」の世界ではありません。 「優勝劣敗」の世界です。 つまり、優れた者が勝ち、劣った者が敗れる。ただ、それだけの話です。ライバルを蹴落とすのではなく、自分が優れたことをするよう全力をつくせばいい。優れたことをしているとまわりから評価されて生き残り、そうでなければ生き残らないということです。適者生存なのです。」
「だいたいどんな分野のことでも、三時間もあれば、入門書を一冊読むことができます。 もう少しがんばって、三十時間、バカになって、ちゃんと勉強すれば、基本的な考え方の枠組みを身につけることができます。つまり、これまでとはまったく別のものの見方やものさしを手に入れることができるのです。」
→こういうものを大学の時に気づいたらよかったなと思いました。教授が書いた本を1冊、1年間かけて、つまり大体、30-40時間ほどかけて、読み解いていく。最初に3日くらいで読んでしまったら、もっとその分野に入れるし、合うか合わないかも分かる。
「自分で選んだわけではない仕事こそ、脇目も振らず、バカになって取り組む。自分で選んだわけではない、すなわち、天が与えてくれたチャンスだと思うことが大切です。」
「机の上をふくと、おもしろいことが分かります。 半分きれいにすると、残り半分の汚れがものすごくよく分かるのです。そこを全部きれいにすると、今度は机の表面の汚れやべとつきに気づきます。だから、心をこめてふく。すると、もっと別の汚れに気づくようになる。 そこで何が起こると思いますか? 気づきが深くなるのです。」
→他の本を読んて気づくことに、優秀な経営者は掃除が好きです。綺麗好きとか、潔癖とかそういうのとはちょっと違うのです。掃除が好きなんです。あるお坊さんが言っていました。掃除は心を磨いていると。
「実際に手を使って動かしてみれば、怖いものは何もないということです。頭であれこれ理屈を考えていただけでは、怖くて一歩が踏み出せません。」
「成功した人はみな、ほめ上手です。 なぜかというと、人をほめるのは人の長所が見えているからです。つまり、物事の悪い面ではなく、よい面を見ることができるということです」
「ほめて育てろ」ということで、多くの人が誤解しているのは、ダメなところをほめてしまうことです。それは「ほめる」ではなく「おだてる」です。 長所を見つけ出して、それを生かそうとするのが「ほめる」。だから、ダメなところはダメと指摘しなければいけません。」
「よりよい仕事をしようと考えている人は、もっと仕事の質を高めようとするので、一段ステップアップします。それが生業を超えさせるのです。 そして、仕事を通じてお客さまに喜んでもらえると、仕事を社会貢献と考えるようになっていきます。そしてもっと多くの人に喜んでもらいたくなります。すると結果として、収入も増えていきます。 それはそうです。お客さまは自分を満足させてくれる人が好きですから、その人のところにはどんどん仕事が来ます。 そうなると、その仕事は生業ではありません。」
「一番いいのは、自分にこう問いかけてみることです。「もう一回生まれ変わっても、あなたはこの仕事をやりたいですか?」
「私にとって、自己実現とは、「なれる最高の自分」になること。「なりたい自分」になれるかどうかは分かりませんが、「なれる最高の自分」にはなれるはずです。潜在的に持っているものを全部使いきればいいのですから。」
「人生の師匠である藤本幸邦先生にはこういわれました。 死ぬとは生きることだ。 だから、死を意識することは、目いっぱい生きることだ。」
「愛されるより、愛すること。もらうことより、与えること。 人から何をもらいたいかということより、自分が何を与えるかが大事だということです。人から評価やお金をもらうより、自分ができることを相手に最大限してあげる。そうすると、自分は死んでも相手の中に生き残ります。 そのためには美しく生きたいとも思います。」
→最近書いている本の感想文にことごとく出てきますね。商売の基本は、「ギブアンドギブ」さらに言ったら、「Contribute」貢献です。
「小さな意思決定をどれだけ積み重ね、精度を高めてきたか。それが意思決定力となり、ここぞという大きな意思決定の場で発揮されるのです。」
→父も含めて、私の知っているビジネスで成功している人は、本当に小さな意思決定も迅速に正確に行います。レストランもメニューも即決です。でも、ほぼ失敗しません。長年の勘という一見いい加減そうなものも今までの経験からくる脳の反射です。結局どんなことも日々の積み重ねなんだと感じます。
「たぶんチャンスはみんなに平等にめぐってきているはずです。でも成功するかどうかは、そのときまでに準備がどれだけできているかにかかっています。せっかくチャンスがめぐってきても、準備がないとそのチャンスをつかむことができないのです。」
「チャンスと準備はいっしょなのかもしれません。準備している人にはチャンスがやってくるといってもいいでしょう。「チャンス」と「準備」は成功のための一対の言葉なのです。」
→日々の積み重ねですし、常に準備を怠らないということが大切ですね。最高の被写体が目の前に現れたのに、カメラ持ってないカメラマンとかいう話です。私は、常にカメラ3台持っています(そんなにいらない、、、)
「一期一会で出会った人と最大限、気持ちのよい関係を築きたいと思っています。」
「あたりまえでいることこそが、じつは一番偉いことだということを、私たちはもっと自覚すべきです。」
「あたりまえのことを、バカになって、ちゃんとやる。神さまは私たちにけっして無理なことを求めているわけではありません。 あたりまえのことをちゃんとやりなさい。そういっているだけです。」
–全体の感想–
いいことばっかり言いますよね。でもこういうことって、当たり前にすぐ忘れます。こういうことを当たり前に忘れないように当たり前にするように当たり前のごとく暗唱していかないといけないと思います。
早口言葉みたいで、意味がわからないですね。
まとめます。
当たり前のことを当たり前にするには意識が必要です。このまとめを定期的に読んで、自分にとっての当たり前としてできるようにしていきたいと思います。
それでは、テストです。A、B、C はなんの頭文字でしたか?
忘れてしまった人は、もう一回読んでくださいね^^
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
