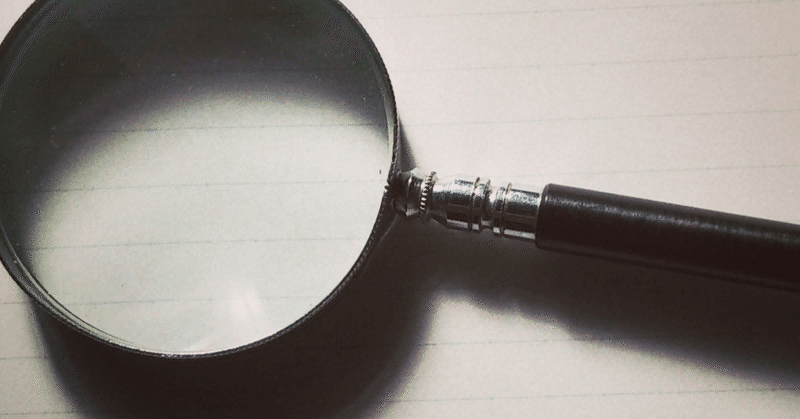
ミステリー小説の魅力
「ミステリー小説」
この言葉を聞いて、浮かべる作品、作家はおそらく人それぞれだ。
古典的なところで海外のコナン・ドイルやアガサ・クリスティ。日本の江戸川乱歩、横溝正史。
四半世紀以上活躍の綾辻行人、赤川次郎、東野圭吾、宮部みゆき。
イヤミスというジャンルもいつしか当たり前になり、反対にコメディ的な要素を含むキャラクター小説の要素を持つものや、日常系の謎を解いていくほっこりした作品、ファンタジー色の強いライトノベル風味のもの。
エンターテイメントとして楽しめるものから、深く世の中を考えさせられる重厚な作品まで。
どれもこれもミステリーであり、枚挙にいとまない。
なぜこんなにミステリー小説は多岐に渡り、そしてそれぞれに魅力的なのだろう。
私自身のことになるが、普段は新書やノンフィクションを読むことが多い。
しかし時々、ミステリーを読み耽ることがある。
小学生の頃の赤川次郎、モーリス・ルブラン、コナン・ドイル(どちらかというとルパンが好き)。
中高校生の頃の横溝正史、江戸川乱歩(わかりやすく厨二病…)。
大学生の頃の東野圭吾、アガサ・クリスティ。
人生停滞期でぐつぐつ煮こごっている頃は奥田英朗、薬丸岳、道尾秀介、久坂部羊、近藤史恵。
再挑戦の学生時代には宮部みゆき、伊坂幸太郎、海堂尊。
仕事を始めてからの柚月裕子、綾辻行人、芦沢央、葉真中顕。
そして今、最も好きな作家と言えるかもしれない松本清張。
もちろん作品全てを読破出来ているわけではない。
以前に読んだ物については、詳細を思い出せない作品の方が多い。
あの面白かった話、どの作品だったか、誰か教えて下さい(涙)という状態。
「フィクションなんて」と、斜に構えて、手に取らない時期すらあった。
それでもミステリーはそばにいてくれた。
小学生の頃の転校したばかりの不安な気持ちに。
中高生の頃の言い知れないもやもやした思いに。
大学生の頃の漠然としたモラトリアムの終わりへの怯えに。
人生停滞期でもミステリー小説を読む間は、色々なしがらみを忘れることができた。
2度目の学生生活は、記憶力低下に苦しみ、毎日のレポートへのダメ出しに凹みながら、寸暇を惜しんでページを繰った。
社会人になってからはさすがにペースが落ちたかと思いきや、ふとミステリーを手にとっている自分がいる。
なぜ私はこうもミステリーに身を委ねたくなるのだろう。
それはきっと自分を取り巻くこの世界そのものが、数えきれないほどの疑問符に満ちているから。
世の中の動き、親しい人の考え、自分の気持ちですら、どうかすると謎だらけで、何ひとつはっきりしたものはない。
ミステリーはいつも、そんな溢れかえる疑問符に惑う気持ちの拠り所となってくれる。
誰もが迷い、悩み、苦しんでいるという共感を。
救われないことがあることへの憤りをぶつける先を。
そして事件や謎が解決される、爽快感と安心を求めて。
たとえそれが物語の中でだけであっても、そこにそれぞれの救いを見出すことができる。
パンドラの匣から溢れ出した災厄と、遺された希望にも例えられそうな「ミステリー小説」。
幸いにして、まだまだ未読の作品が星の数ほどある。
また既読の作品であっても、読み返して新たな発見を得ることも。
先日読み返した『そして誰もいなくなった』は、あまりのことに開いた口が塞がらず、『容疑者Xの献身』では不思議なほどXに共感した。
日々に謎があり、心が迷っている時ほど、ミステリー小説は面白い。
そう思えば、ふと毎日が楽しくなる。
不安が減る。
だからこそ私は惹かれてやまない。
何かしらでも、あなたの琴線に触れることができたのなら、サポートいただければ幸いです。 いただいたサポートはありがたく活動費(つまりは書籍費、笑)にさせていただきますね。
