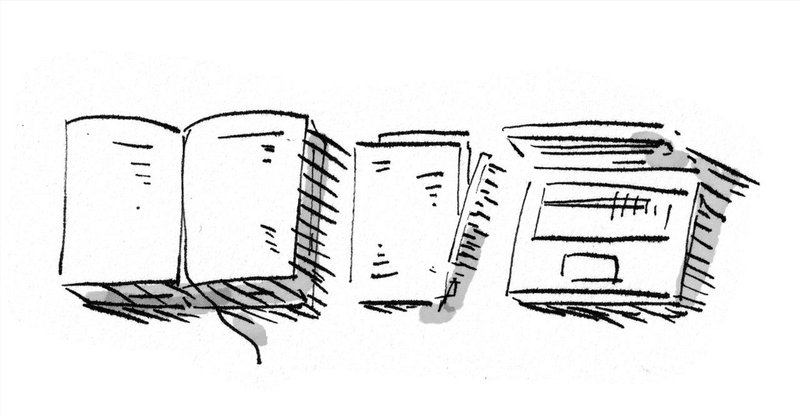
「浅い記事」を脱却し、「深い記事」の制作するための施策について。
日々、様々な記事がタイムラインを流れてきますが、しばしば「ゴミのような記事」が批判の対象となっています。
必要な情報が埋もれて混乱するから素人ブロガーがゴミ記事増やすなよ…。 https://t.co/AV6Cyw7DSu
— チタン (@titanium365) February 23, 2020
しかしこうした記事の何が「批判に値する」のでしょうか?
"浅い記事 "が引き起こす問題
「浅い記事」という表現は、洞察力や独創性、あるいは社会的な価値を欠いたコンテンツを指します。
そのため、浅い記事は新たな洞察や有益な視点を読者に提供することはありません。質より量に重きを置き、低コストで乱造される傾向があります。
多くの場合、このような記事は一般的な知識の再掲や、入手可能な情報の単なる言い換えに過ぎません。
また、浅い記事には、偏向的な意見、根拠の薄い主張、フェイクニュースなども含まれ、こちらは益がないというよりは、むしろ害となります。
これは個人や素人のブロガーだけに見られる傾向ではありません。
例えばかつて、ニューヨーク・タイムズ紙は、ハフィントンポストを名指しで批判し、「低品質コンテンツを垂れ流している」としました。
ウェブサイトが、読者への実質的な見返りを提供することなく、ただクリック数を稼ぐためだけに記事を掲載している
こうした行為の最大の問題の一つは、浅薄な記事が増えれば増えるほど、オンライン上でユーザーが求めている価値ある情報の探索が難しくなってしまう点にあります。
こうした状況は、読者の時間の浪費につながりますから、タイトルだけ扇情的で、中身がない「クリック詐欺」と認識されます。
実際、大手マーケティング・ソフトウェア・プラットフォームであるHubSpotの調査では、読者の42%がブログ記事を流し読みしており、さらにブロガーの 52% は、コンテンツを通じて読者と関わることがますます難しくなっていると述べています。
結局、低品質な記事は、デジタルでの存在感を高めることを目指してコンテンツに依存している企業や個人にとって評判を下げるリスクとなりますから、批判されるのも無理はありません。
"深い記事"を提供するメリットと課題
これらの問題が存在する一方で、あるいは浅い記事が大量生産されることへの反動として、より大きな価値を提供するコンテンツに対する需要は高まっています。
また、2015年のレポートによれば、ブログを行っている企業は、ブログを行っていない企業に比べて、Web サイトの訪問者数が 55% 多くなる、という調査結果すら示されています。
そこで、深い記事の重要性が浮き彫りになります。
深い記事の制作は、リサーチやライティングに多くの時間を費やす必要がありますが、そのメリットは大きいです。
一つは、グーグルが高品質なコンテンツを優先するということです。Googleの公式見解が示すように、質の高い記事は検索エンジンの結果ページで上位に表示されやすく、結果としてトラフィックが増加します。
また、深いコンテンツは読者のエンゲージメントを向上させることができます。Forbesによれば、コンテンツマーケティングで、エンゲージメントを増やすには、読者または顧客に価値を提供することに重点を置く必要があります。どれだけ効率的に次から次へと記事を作成できるかは、あまり重要ではないのです。
特に、競合他社に対して質的に優位性がない限り、検索ランキングの上位を占めることは難しいでしょう。
また、検索エンジンだけではありません。「深い記事」を制作することは、選択したテーマにおける権威を示し、業界でのリーダーシップと、読者から専門家であるとのの認識を作り上げることができます。これは、Entrepreneur Magazineが指摘している通りです。
しかし、深い記事の制作には課題が無いわけではありません。時間とリソース、そして能力が問われます。Content Marketing Instituteによれば、高品質なコンテンツをコンスタントに制作することが、コンテンツ制作者が直面する課題の一つであることが明らかとなりました。
また、オンラインマーケティングの第一人者であるニール・パテルが指摘しているように、最新の情報を常に入手し、それに合わせてコンテンツを適応させるためには、継続的なリサーチと時間が必要です。
"浅い記事 "と "深い記事 "
こうした背景から、我々は「浅い記事」を避け、「深い記事」を書かねばなりません。では、どうすべきでしょうか?
根本的なところとして、まず最初に押さえておきたいのが、「浅い記事」と「深い記事」の正確なちがいです。
これらの言葉は、特にwebライティングの世界で頻繁に使われていますが、その本質的な定義を理解している方はそれほど多くありません。多くの場合それらの定義は「悪い記事」と「いい記事」の同語反復に過ぎないのです。
そこで私たちは「行動」につながる分かりやすい定義が必要であると考えました。それは、次のようなものです。
浅い記事と深い記事の4つのちがい
ここから先は

生成AI時代の「ライターとマーケティング」の、実践的教科書
ビジネスマガジン「Books&Apps」の創設者兼ライターの安達裕哉が、生成AIの利用、webメディア運営、マーケティング、SNS利活用の…
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
