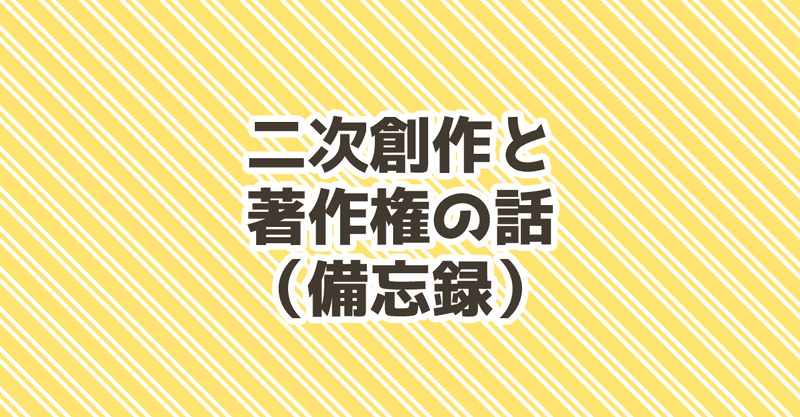
二次創作と著作権(備忘録/2023.6.5更新)
はじめに
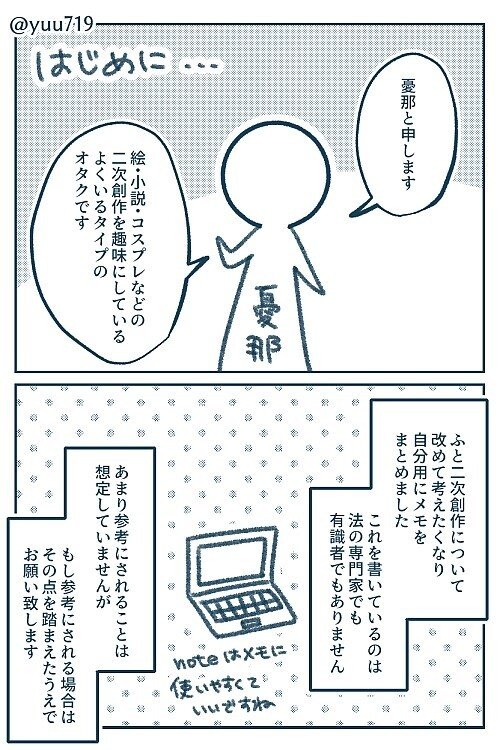
これは人並みに同人活動をしているオタクが、今一度『二次創作と著作権』について考えたくなり作成したメモです。長いです。
決して学級会を開きたいわけではなく、人に二次創作を勧めたいわけでも止めたいわけでもなく、意見を押し付けたいわけでもありません。
もし意見が食い違ったら「こいつとは気が合わない」とお考え下さい。
間違いを見つけたら訂正します。
もしこのメモを何かに使う場合、当方が参考にしたURLの先も確認するようにお願いします。知らない間に更新されている可能性があります。
また、何か情報提供をしてくださる方はコメントもしくはTwitter(@yuu719)にお願いします(趣味アカウントで申し訳ないですが…)。
分かりやすいようにしようと思った結果若干ふざけた表現がありますが、内容は真面目に書いているつもりです( . .)
(追記:2023.6.5)簡易まとめ更新
とりあえずの結論
この記事を書いてからしばらく経った、今現在(2023.6/5)の結論。
公式の言うことが全てである。
以上。
※「公式」とは、「公式関係者」や「公式アカウント」など、”そのジャンルにおけるすべての公式側の人間”を指します
……………………………………………………
短すぎるので補足。たとえば、以下のような事例があるとする。
二次創作のイラストを、報酬1万円もらって描いた(有償依頼)
キャライメージ(特定のキャラを連想させる色、モチーフ、模様など)/キャラのイラストを用いたネイルアートで商売をしている
非公式のコスプレ衣装を作って売っている
キャライメージのアクセサリーを作って売っている
公式の二次創作ガイドラインに「性的な表現はNG」と記載されているにもかかわらず、18禁の同人誌を作っている
二次創作の動画で広告収入を得ている
さて、何番が「二次創作としてNG」なのか?
→ 公式の言うことが全てである。公式にNGと言われたら、それがNGである。
最近は公式の二次創作ガイドラインが設けられる例も出てきたが、正直形だけであって、実際のところはほとんどがファンの善意に委ねられている。もちろん諸々気を付けているファンが多いが、一方で、(わざとでも、わざとじゃなくても)明言されているルールを破っている人も数多く存在する。
そしてそれらを含めて、「どこまで許すか」を決めるのは公式である。
一般人がスマホで簡単に見られる情報を、公式関係者が見付けられないはずがない。つまり上記のような事例が起きていることは間違いなく公式側も把握している。が、放置されているのが現状である。
個人的には1番や6番がめちゃくちゃ嫌いで、二次創作の中でも特に”許されない”行為だと思っている(思っていた)のだが、注意されているのを見たことがないため「公式の人間はさほど気にしてないんだな(=黙認)」と結論付けた。
実際、本当にまずいときはちゃんと公式が動く事例も見てきている。記事内で取り上げた事例もそう、ポケモンの二次創作FPSゲームがすぐ消されたのもそう、とある二次創作の動画が消されたのもそう。
お金が絡んでいてもいなくても、公式が「まずい」と思ったら何かしらのアクションがある。それがないのなら、多分そういうことなんだろうと思う。
当方は割と古いオタク(個人サイト時代~)で、オタクになった当初は「二次創作は著作権侵害だから全て隠せ」くらいの雰囲気があった。
しかし気付けばSNSに二次創作が溢れていて、公式からガイドラインも出てくるようになった。二次創作に対する考え方に相当なアップデートをしないといけなくなった。
また、「自分と公式関係者の考え方にズレがある」場面にも何度か遭遇した。声優さんが明らかな腐向け/夢向けのセリフリクエストに堂々とキャラ本人の声で応えてたり、広告収入を得てそうな二次創作の動画に公式関係者が「いいね!」と言ってたり。直近だと、夢女子拗らせて勝手にソロウエディングしてたら集英社オンラインから取材が来たり。
「○○はやるな」「○○は隠せ」みたいなのは所詮オタクのエゴで、公式関係者は意外と二次創作を受け入れてるんだなというのが今のところの感想。
あくまでもOK/NGの”線引き”を決めるのは公式で、たとえ公式ガイドラインの違反行為でも、公式以外の第三者が「今すぐ消せ!」みたいなことを言う権利はない(”教えてあげる”なら良いと思う)。
第三者ができるのは、せいぜい公式への通報くらい。
ただ、「アクションがない」のを100%「黙認」だと決めつけるのは良くないと思っている。確かに「黙認」の可能性はあるが、「数が多くなったら対処する」「金額が増えたら対処する」(から今は放置)の可能性もある。
「Aさんが1万円で二次創作の有償依頼を受けてた!自分もやってみよう!」とか、「ガイドラインには性的な表現NGって書いてあるけど、みんなエロ絵描いてるから大丈夫!」とか、そういうのは安直で危ないかなと。
ある程度節度を守っていないと同じ作品を好きな別のファンに嫌われるだろうし、そうなると公式への通報もされやすいはず。目に余るほど節度がなかった場合は「全面禁止」にもなりかねない(最近だとpixivFANBOXのAI作品禁止というのがありましたね)。
以下は二次創作をやるにあたって、個人的に気を付けようと思っていること。
①ガイドラインを確認
そのジャンルの二次創作のガイドラインがあればまずは目を通す。話はそれからだ
②非営利前提
他人の作品で勝手に儲けてはいけない。ジャンルによっては細かく決まりがある
③競合に気を付ける
公式で出ているものと同じようなもの、公式だと間違われるものは作らない。場合によっては海賊版や模造品にもなり得る
二次創作でしか得られない栄養があるのは間違いないので、今後も二次創作はやっていくけど、「ファン活動」として認められる範囲で楽しくやっていきたい。
著作権とは
著作権は著作物を保護するための権利です。
著作物とは、思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいいます。
引用元:https://www.jpaa.or.jp/intellectual-property/copyright/
二次創作とは
『二次創作』とは、何らかの下地となる作品・表現があり、それらを元にしている創作物および創作行為を指し、英語圏では『fanfic』や『au』とも呼ばれる。
引用元:https://dic.pixiv.net/a/%E4%BA%8C%E6%AC%A1%E5%89%B5%E4%BD%9C
元ネタ(オリジナル)が別にある創作の総称。ファンアートとも呼ばれる。
なお、二次創作を元にした創作を「三次創作」と呼ぶことがあり、その理論でいくと四次創作、五次創作…と続くが、結局のところは二次創作である。
二次的著作物とは
キャラクターの絵から着ぐるみを作ったり、小説を映画化したり、ある外国の小説を日本語に「翻訳」した場合のように、一つの著作物を「原作」とし、新たな創作性を加えて創られた著作物のこと
引用元:https://pf.bunka.go.jp/chosaku/chosakuken/h22_manga/comment/list_na.html
言葉は似ているが、二次創作とは別物。
模倣品・海賊版とは
模倣品とは特許権、商標権などの知的財産権を侵害した製品のことで、バッグや財布、時計などの偽ブランド品のほか、有名メーカーの電化製品などを模倣した例があります。
海賊版は著作権者の許諾を受けずに複製(コピー)された製品のことで、書籍、音楽・映像・写真やソフトウエアなどを複製した例があります。
引用元:http://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2020_14.html
こちらも二次創作とは別物。二次創作よりもオリジナルに損害を出しやすいため、比較的警察沙汰になりやすい印象がある。
例:「鬼滅の刃」キャラクターを無断使用 男2人を著作権法違反容疑で書類送検
また、○○風アクセサリーなど「“それ”とは言ってないがどう見てもそうだろ」というようなものでも警察沙汰になることがある。
例:「鬼滅の刃」偽グッズで16億円荒稼ぎ業者を逮捕 “キャラ・商標”を直接不使用でも摘発の理由
→業者に対する記事だが、本文に「個人が鬼滅のキャラクターのポスターを複製したり、アクリルキーホルダーを自作したりして、ネットのフリーマーケットサイトで販売し、書類送検された事件は山ほどある」との記載あり

★似たような概念に「トレパク」がある。トレース(写し書き)したのにオリジナルだと偽ったり、利益を得るためにトレース作品を作ったりすると“悪意がある”とみなされこう呼ばれる。大抵は著作者から訴えられたり周囲から叩かれたりする。
★漫画のトレースで忠告が入った例:弊社コミックスのトレース行為(無断複製行為)被害についてのご報告
今回言及したいのは「二次創作」であり、それ以外についてここでは深く触れない。
また、ここで言う「同人誌」「同人グッズ」はすべて二次創作のものを示すこととする。
法律上の話
具体例を挙げる。
まず、著作者「神」が描いた漫画「GOD」があるとする(※ネーミングは適当。また、以降は著作者のことを“神”と表現することがある)。

「GOD」の著作権は著作者の「神」が持っている。譲渡はしない。
「神」が作品「GOD」を発表し、人気が出てファンがついた。
ここで前提として、著作権侵害は親告罪であり、GODの著作権侵害の訴えは神が自ら行うことでしかできないことを示しておく。
翻案権侵害や同一性保持権侵害は、いずれも、被害者などからの告訴がなければ公訴を提起することができない「親告罪」に該当します。したがって、実際に捜査機関が訴追を行うためには、被害者である著作権者・著作者の告訴が必要となるのです(著作権法第123条第1項)。
引用元:https://funabashi.vbest.jp/columns/general_civil/g_others/4434/
※いっとき騒がれたTPPの著作権法改正による「著作権侵害の一部の非親告罪化」(=GODの著作権侵害の訴えを神以外でもできるようになる)だが、同人誌やパロディ作品は海賊版と違って利益を目的としておらず、原作と全く同じものではないものが大半なため基本的に対象外となっている様子。
**********************************
ファンAは、神がネットに上げたGODのイラストを神の許可なくコピー機でプリントアウトし、自分の部屋に飾った。

→著作権法の「私的使用」範囲内になるため、問題ない。
第三十条 著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
※私的使用が目的でも、例外でアウトになる行為があるので注意。
ただし、デジタル方式の録音・録画機器等を用いて著作物を複製する場合には、著作権者に対し補償金の支払いが必要。コピープロテクション等技術的保護手段の回避装置などを使って行う複製については、私的複製でも著作権者の許諾が必要。私的使用目的のための複製であっても、違法著作物であることを知りながら音楽又は映像をインターネット上からダウンロードする行為は、権利制限の対象から除外される。
**********************************
ファンBは、GODに出てくる主人公のイラストを神の許可なく模写してSNSにアップした。

→手元に置いておくだけなら私的使用の範囲だが、ネットに上げた時点で私的使用の範囲から外れるため、神の怒りに触れた場合は訴えられる。また、本物そっくりだった場合は海賊版と間違われる可能性がある。
**********************************
ファンCは、GODに出てくる主人公の二次創作イラストを神の許可なく描いてSNSにアップした。

→ファンBと同じ。手元に置いておくだけなら問題ないが、ネットに上げた時点で私的使用の範囲から外れるため、神の怒りに触れた場合は訴えられる。海賊版と間違われる可能性は模写よりも低いと思われるが、素人目で見分けがつかないこともあるので一概にそうとは言えない。
**********************************
ファンDは、GODの同人誌を神の許可なく作って同人誌即売会で売った。

→ファンBと同じ。手元に置いておくだけなら問題ないが、同人誌を不特定多数へ向けて売ると私的使用の範囲から外れるため、神の怒りに触れた場合は訴えられる。
**********************************
以上のように、二次創作は神本人に許可を取った場合、もしくは私的使用である場合を除いて、すべて著作権法違反に該当する。
もう少し掘り下げておくと、二次創作は法律上の「翻案」という行為にあたり、翻案は著作者にしか認められていないため、GODの二次創作=神に無断で翻案したとして著作権法違反になる。
また同時に、二次創作の内容によっては「同一性保持権」という「GODは神が思った通りにしか改変してはならない権利」も侵害する可能性がある。
二次創作を行うことは、著作権法においては「翻案」という行為に該当します。翻案とは、著作物を編曲・変形・脚色するなど、オリジナルの本質的な特徴を残しながら、具体的な表現に修正・増減・変更などを加えて別の著作物を創作する行為をいいます。著作物の翻案を行う権利は、著作権法第27条において著作権の一つとして規定されており、著作者(原作者)が専有するものとなっています。そのため、著作権者に無断で二次創作(翻案)をする行為は、原則として禁止されているのです。
さらに、著作者に無断で二次創作をする行為は、著作者人格権の一つである「同一性保持権」の侵害にも該当します。同一性保持権とは、著作者の意に反して著作物を改変されない権利をいいます。二次創作を行う場合、オリジナルの著作物を改変することにより制作されることが通常ですので、著作者の同一性保持権の侵害が疑われることは避けられません。
二次創作の実態の話
現在栄えている二次創作はその多くが著作権法違反にあたるが、警察に捕まるような事態に発展することはほとんどない。何故か。神は見て見ぬふりをしてくれているからである。
これはよく“お目こぼし”と呼ばれ、法律で禁止されているにもかかわらず逮捕される人は少ないという現実が存在している。

また、漫画や雑誌に「ファンのイラストコーナー」があるように、著作者が二次創作自体を好意的に捉えている(ので訴えない)ことが多い。
しかし何でも良いわけではなく、
・二次創作により、著作者が大きな損害を被る場合
・二次創作を営利目的で作成し、勝手に利益を出している場合
・二次創作を見た著作者及び第三者を不快にさせた場合(宣伝にならない、売上につながらない、作品に悪いイメージがつく)
…などの場合は、著作権侵害で訴えてやろうと思われても仕方がない。
結局のところ訴えようと思えば訴えられるけどやってないだけで、神がその気になれば全員罪に問える。
神の怒りに触れた例
神の好意や件数が多い点から訴えられにくい二次創作だが、全く訴えられた例がないかと言われるとそんなことはない。また、それに至らなくても忠告やお願いを掲載した例がある。
ミッキーのプール事件
小学生が学校のプールにミッキーの絵を描いたところ、ディズニーから消せと言われた話。ディズニーの二次創作が恐れられる理由のひとつと思われる。
ドラえもん最終話同人誌問題
ファンがドラえもんの最終話をネタにした同人誌を作って売ったところ大ヒットし、本物と勘違いした人が小学館に問い合わせるなどしたため、小学館が同人誌の作者を著作権侵害で訴えた。
ポケモン同人誌事件
性的な表現を含むポケモンの同人誌を作って売っていたファンが、ある日突然任天堂に訴えられて逮捕された。任天堂は子どもに悪影響を及ぼすことを懸念していた様子。
名探偵コナンの同人誌
名探偵コナンの同人誌を出していたサークルが小学館に訴えられた。直接の理由は不明だが、大手でダウンロード販売の売上が多く活動が目立っていたのではないかと推測。
ブロッコリー(うたプリなどの運営)
自分から動くタイプのアクティブな神。ある日突然Twitterで公式から忠告リプライが届く。対象はいろいろあるようだが、同人グッズなどに対しても動いている様子。
ウマ娘公式(Cygames)からの「お願い」
スマホゲームの運営が「イメージを著しく損なう表現は行わないようご配慮いただけますと幸いです」というお知らせを掲載。背景として、このゲームでは実在する馬を擬人化している=馬主さんに迷惑を掛けたらコンテンツが終わるため、ファン活動に言及はしないが馬主さんを怒らせるようなことは控えて欲しい旨を周知しておきたかったことが推測される。なお、ファンの間で「ウマ娘の18禁表現はNG」といった話が出ているようだがそのような記載はない。
(2023/04/06追記)二次創作ガイドラインが制定され、そこに性的描写のある創作は公開NGとの表記がされていた。よって、18禁表現はもちろんそれに至らなくてもNGの可能性がある。
※当方はこのゲームをやっていないが、馬主さんのブログを見る限り同人活動をしている人間としてだいぶ申し訳ない事態になっている。
神の怒りに触れないために
神の怒りに触れるのを防ぐため、二次創作をやる上でよくなされていることを挙げる。
①ひっそりやる
神の怒りに触れないために、神に見つからないようにするという考え。二次創作界隈では以前からこの傾向が見られる。もちろん見つからなければ何をやってもいいというわけではないが、少なくとも見つからなければ訴えられることはない。ただし神本人に見つからなくても第三者によって通報されるケースがあるので、それをなるべく防ぐには、
・ネットに上げない
・見る人を選ぶ作品は鍵アカウントで公開したり、ワンクッションを設けたりする(閲覧者を不快にさせた場合、通報される可能性が上がる)
・Twitterなどでは検索避け(※後述)をしたり、ホームページを検索避けしたりする
…などの方法がある。
②売上(利益)を出さない
同人誌などを作っている人間には暗黙のルールかと思うが、二次創作で利益を出すことは基本的にNG。人様の作品を無断で使っている上に儲けを出すことは許されない。売上を目的として世の中に出回っているアニメグッズなどは当然それを売る側が神から許可をもらっており、大抵の場合はその際にお金(使用料)が掛かる。
したがって、売上が出る行為をしていることが第三者から見て分かる場合、神から訴えられる可能性及び誰かから神へ通報される可能性がある。
後述する各企業の二次創作ガイドラインでも、非営利の二次創作であれば構わないが営利目的の二次創作は認めていないというところがほとんど。同人誌や同人グッズは、印刷費などの材料費の回収を目的に値段がつけられていれば非営利とみなされることが多い。
※後述するが、二次創作でも売上を出して良い場所(ジャンル)は存在する。また、たまに公式が条件付きで二次創作で売上を出しても良い企画をしていることがある。LINEのONE PIECEクリエイターズスタンプ企画など。
③二次創作であることや自分の名前を明記する
公式とは関係ない旨を分かりやすいところに書いたり、自分の名前やIDを載せたりすることで二次創作であることを主張する方法。出所を明らかにすることで神への直接の通報を防ぐ。海賊版と間違われないためにも以前からよくなされている印象。
無断転載や、海賊版グッズに絵が勝手に使われるのを防ぐのにも有効。

二次創作のガイドライン
二次創作はもともとファンが勝手にしているものだが、ついに神の側から二次創作についてのガイドラインが出てくるようになってきた。
これは「二次創作はほとんどが著作権法違反だが、うちではここまでなら許す」という方針を各企業がまとめたもの。「著作物の利用範囲を拡げるPCLとピアプロリンク」という動画が分かりやすい。
複数のガイドラインに目を通したが、特に押さえておきたいと感じたのが以下の3点。
①非営利目的に限る
→うちの作品で勝手に金儲けをするな!やるならちゃんと契約しろ!
②競合が発生しないことを求める
→うちが売ってるものと似たものを出すな!それじゃ海賊版と変わらない!
③二次創作だと分かる創作性を求める
→ほぼコピーしたようなものは二次創作として認めない!それじゃ海賊版と変わらない!
最低限この3点は頭に叩き込んでおこう、というのが当方の見解。
一例としてガイドラインへのリンクをいくつか貼っておく。
VOCALOID(初音ミクなど)
→二次創作に優しい公式として前から有名なところ。ピアプロリンクというシステムで申請することで同人誌の有料頒布などが可能になる。
あんさんぶるスターズ!!
→かなり細かく規約が決まっているのでとても参考になる。更新率も高い。
刀剣乱舞などを手掛けるニトロプラス
→同人グッズの数や許される売上額が具体的に決まっていて、線引きが分かりやすい。
Fateシリーズなどを手掛けるTYPE-MOON(Fate/Grand Order版のガイドラインもある)
→同人グッズは商業目的で作るのはNGとの記載があるが、同人誌にはそれがないのがちょっと気になる。が、同じように考えるのが無難?
ツイステッドワンダーランド
→ディズニーが絡むので嫌煙されている部分があるみたいだが、内容を見る限り他企業と変わらない。
東方Project
→「常識の範囲内で基本的に自由」としているほか、特定のサイトであれば同人誌の電子書籍販売ができたり、同人音楽の販売を行えたりする。
まとめ
ここまでで一旦まとめる。
著作権侵害は親告罪であり、訴えを起こせるのは著作者だけである。
二次創作は本来なら私的使用以外でやってはならないことだが、原作に良い影響が多いことも確かなので、現状は著作者が見て見ぬふりをしてくれている。もしくはガイドラインでやってもいいことを示してくれている。
著作者がその気になれば訴えられるので、二次創作は節度を守ってファン活動として見てもらえる範囲内で楽しむこと。
以上、ここまでが二次創作と著作権について調べてざっくりまとめたもの。これ以降は個人的に気になることをまとめる。
筆者の考えが結構な割合で混ざるので、冒頭に書いた通り、意見が合わない場合は気が合わないと判断してほしい。
個人的に気になること
二次創作の有償依頼およびpixivFANBOXなどのクリエイター支援サービスの利用について
ぶっちゃけ今回著作権を調べてまとめようと思った事の発端。
最近、TwitterやSKIMA(個人が有償依頼を受けられる仕組みを持つサイト)で「二次創作の有償依頼を受け付けます」という人を見掛ける。内容は、依頼主からお金を貰って二次創作をする(絵を描いたり小説を書いたりする)というもの。
これが果たしてファン活動として許されるのか?と疑問に思ったため今回いろいろ調べて回ることになった。
結果、二次創作の有償依頼は営利目的だとみなす(ので許さない)と明記されているジャンルを発見。アプリゲーム「あんさんぶるスターズ!!」のガイドラインより。
Q. 好きなイラストレーターの人にお金を払ってイラストや漫画を描いてもらっても大丈夫でしょうか?
∟ A. 依頼に基づいて有償で行われる二次創作(通常の業務委託のほか、有償のリクエスト、コミッション等が該当しますがこれに限りません)については、金額および当該著作の権利帰属先を問わず、また事後的に同人誌へ再録される予定の作品であっても、営利目的とみなします。同様に、閲覧に際して有償の会員資格等を要する形態での二次創作(クリエイター支援サービス、パトロンサイト、ファンクラブ、クラウドファンディング等を指しますがこれに限りません)についても、金額およびその支払い形態が一時的か継続的かを問わず、営利目的とみなします。
二次創作の有償依頼のみならず、クリエイターの創作活動を応援するためのサービス利用も営利目的とみなす旨が書かれている。pixivFANBOXなどが該当する。
単純に考えて、
・お金を貰って二次創作をする→やり方が「仕事」そのもの。無断で他人の作品を使い、個人的な利益を得ている。
・よくある非営利活動の定義、「材料費の回収」になっていない。
…などの理由から、二次創作の有償依頼およびクリエイター支援サービスの利用を「非営利の二次創作」だと言い張るのは無理があると思う。

また、
・上記のSKIMAでは「著作権、肖像権に違反する商品の出品、または掲載する行為」を禁止しているので、自分が著作権を持たない作品や著作者から許可を貰っていない作品をネタにした出品は規約違反である
・SKIMAと似たようなサービスを行っているSkebというサイトでは、二次創作の有償依頼に対し運営がわざわざそれ専用のシステムを用意している
…ことなどから、一般的にもこの認識で間違っていないように思う。
※ちなみにメルカリは「許諾なくキャラクターなどを使用したハンドメイド品、同人誌など」は出品禁止なので、許諾がない限り二次創作の有償依頼はもちろん同人誌や同人グッズも出品禁止(仮に許諾があってもフリマアプリやオークションへの出品を嫌う人が多いので、出品する前に同人誌の注意書きなどを確認すること)。
有償依頼や支援サービスという形態が流行り始めたのが最近であり、ガイドラインでもまだあまり見掛けることがないが、あんスタが取り入れたのなら他のジャンルでも徐々に普及すると思う。どこのガイドラインでも大抵似たり寄ったりのことが書いてあるので。
個人的には二次創作=ファン活動であり、利益を発生させないことが大前提というのはもちろん、ファンなら原作者に敬意を払うはずなので、自分の利益のために他人の作品を利用する人間はファンではないと思っている。そういうことをする人とは関わりたくない。高額転売ヤーを憎む感情と似ている…。
★参考事例:某絵師の場合
某漫画で二次創作をしている有名な絵師さんがいるのだが、
・二次創作イラストの色紙を他人からの依頼で作成し、明らかに材料費以上の値段で販売(=二次創作の有償依頼。1枚3500円~)
・原作によく似ている絵柄でお絵描き教室を有料で開催
…などの行為を繰り返ししていたところ公式の目についたようで、ある時期を境に原作漫画へのファンレターが全く採用されなくなったそう。
★例外ジャンル:UNDERTALE
当方が唯一知っている、公式で二次創作の有償依頼に許可を出しているジャンル。UNDERTALEというゲーム作品。
ガイドラインを読む限りここの神は全力でファン活動を支援しているらしく、二次創作の有償依頼も許可している。ただし「営利目的で作品を使用されること」は当然懸念しており、商業での販売は禁止、同人誌の電子書籍でオンライン販売するのは禁止…などがルールに盛り込まれている。したがって有償依頼も商売と同じようなノリでやるとお咎めが入ると思われる。
なお、UNDERTALEが許しているなら他も大丈夫なんじゃないかという意見が出てきそうだが、SKIMAやSkebの方針及び各企業のガイドラインの文章からして、UNDERTALEが特殊なだけであると考えるのが無難と思う。
★二次創作の有償依頼を公式ガイドラインで容認している大手のジャンルが他にもあったらぜひ知りたいです!
同人誌や同人グッズの受注販売、オンデマンド販売、委託販売について
即売会などで対面で売る方法(=直接販売)ではなく、注文が入るたびに制作や販売を行う方法(=受注販売、オンデマンド販売)、第三者に委託する形で販売を行う方法(委託販売)での同人誌や同人グッズの販売について。
受注販売やオンデマンド販売を禁止するジャンルは散見される。上記で二次創作の有償依頼を許可しているとしたUNDERTALEでも、オンデマンド販売サービス(pixivFACTORYなど)の利用は禁止されている。
おそらく、売上が出るか出ないか/出るならどの程度出るかの見込みが立てられないことが主な理由。直接販売はあらかじめ生産数が決まっており売上の見込みも立てやすいが、受注生産となるとどのくらい売れるかが分からない。
委託販売についても同様に禁止されているケースがあり、「同人誌の委託販売はOKだが同人グッズはNG」といったように同人誌と同人グッズのルールが異なる場合がある(例:あんスタ)。
記事を書くにあたって複数のジャンルの二次創作ガイドラインに目を通してきたが、ざっくりした印象は
・受注/オンデマンドなどの売上がどうなるか分からない販売方法は禁止
・同人誌の委託販売は良いが、同人グッズはダメ
…といったところ(もちろん各ジャンルのガイドラインに従うのが一番)。
コンビニのネットプリントを使ったイラストなどの配布について
あまり言及されているところを見たことがなかったのだが、あんスタのガイドラインにてそれらしき記述が追加されたためここにメモしておく。
事前にイラスト等の素材を入稿しておき、購入希望者による商品選択に応じて都度、当該素材を用いて商品の印刷や生産がおこなわれるサービスについては、直接販売には含まれない委託販売であり、かつ事実上の受注生産商品でもあるとみなします。したがって、非営利目的とはみなさず、この方式でのグッズ頒布については無償(サービスの利用料は発生するが作者自身には収入が発生しない事実上の無償であるケース、または一切金銭を徴収しないケース)での頒布であっても認めておりません。
Q. 同人誌なら受注生産でも大丈夫でしょうか?
∟ A. 受注生産的な形態をとる印刷物であっても、その内容・形態等が明らかに標準的な同人誌の範疇である紙類の印刷物については、現状は同人誌の一種として扱います。したがって、現状はただちに生産方式に制限を設けることはしません。
ただし、印刷対象が紙またはそれに類するものであっても、同人誌よりもグッズとしての用途・性質が強いもの(ステッカー、シール、カード、しおり、付箋、便箋、封筒、ノート、メモパッド、ポスター、カレンダー等が該当しますがこれに限りません)については、同人誌ではなくグッズとみなします。したがって、受注生産的形態での頒布を行うことはできません。
同人誌の付属物または代替物として頒布される単ページまたは見開き程度の分量の印刷物はグッズとはみなしません。
これを読んだ限り、当方は
ネットプリントはたとえ二次創作の作成者に儲けが出なくてもNGである
同人誌のオマケである場合や、ペラ一枚・見開き程度の同人誌(小説など?)である場合は同人誌の一部とみなして例外的にOKとする
…なのかなと思った。
「営利目的かどうかにかかわらず基本NG」としているので、この場合は既存グッズとの競合を危惧しているのではないかと感じる。特にコンビニの印刷機を使ったグッズは多数のジャンルで主流になってきているので、そこと競合するのではないかと。
他のジャンルでの扱いについては別途調べる必要があるが、ひとつの大きなジャンルで禁止されてる行為であるならなるべく他でもやらない方が無難そう…というのが当方の感想。
二次創作ガイドラインがなければ何をしてもいいのか
よく分からないが、公式のガイドラインがなかったら何をしても良いと解釈する人間が存在するらしい。
ガイドラインは神がファンのために厚意で作ったものであり、すべての神が用意してくださるとは限らない(むしろない方が多い)。ない場合の二次創作は著作権法により私的使用以外は許されないので、100%お目こぼしの世界となる。
ガイドラインがないから何をしてもいいわけではなく、むしろ逆で、ガイドラインがない場合はほぼ何もしちゃいけない(というか、だからこそガイドラインが存在する)。
以下、ガイドラインが存在しないジャンル(※note執筆時)で著作権について触れているページを例として出しておく。
ONE PIECE、NARUTO、銀魂、鬼滅の刃、呪術廻戦などを扱う集英社
→「個人の方に対して、利用許諾は行っておりません」
進撃の巨人、東京卍リベンジャーズなどを扱う講談社
→「著作権法によって権利が守られています」
任天堂
→ゲーム実況について一定の条件下で利益を出しても良い旨が発表され、話題になった任天堂。ただしファンアートは「任天堂の知的財産の利用や創作は、各国の法令上認められる範囲内で行ってください」とのこと
ポケットモンスター
→「個人のユーザー様に個別に許諾を差し上げることは行っておりません」
名探偵コナンなどを扱う小学館
→「著作権は、著作権者に帰属します」
写真を参考にして絵を描く際の著作権
写真をもとにして絵を描く場合、二次創作の観点以外に写真の著作権が絡んでくる。以下のサイトが参考になる。
絵と、写真と、著作権のおはなし
他の絵を参考にして絵を描く場合も同じようなことが言える。両者ともにやり方を間違えるといわゆる“トレパク”問題に発展する。
二次創作の通報の仕方
同人の世界では「公式の人間に二次創作について聞くこと」はタブーとされている。理由は、「二次創作してもいいですか(してる人がいるけどいいんですか)?」と聞いたところで神は「ダメです」以外の回答ができないことは分かりきったことであり、わざわざ“見て見ぬふり”をしてくれているのに余計なことを言わせてしまうことになるから。ガイドラインがある場合、それに載っていないことを聞くことがタブーにあたる(やってもいいなら載せている)。
また、世の中には大量の二次創作があり、いちいち個別に回答していたら大変=神の手を煩わせてしまうという意味でもタブーとされている。
しかし中には悪意を感じたり、やりすぎだと思ったりして神に通報したくなる二次創作もある。その場合、当方は以下のように考えている。
個人の好みや趣味の違いで通報しようとしていないか?
→「自分の好みじゃないから」という理由で通報しない。世界の中心は自分ではないので、嫌いなもの(いわゆる”地雷”)がうっかり目に入って気分を害したとしても見なかったことにする。ガイドラインの違反、もしくはサービスの規約違反に当たらないか?
→①に該当しないもので通報したくなるほどのものは、公式から出ているガイドラインもしくはそれが掲載されているサービス上で規約違反に該当する可能性がある。
前者であれば③に進む。後者であればそのサービスの運営に通報してみる。例えばSKIMAにおける二次創作の有償依頼は許諾がない限り規約違反であるため、SKIMA運営に通報すれば何かしらの措置が行われるかもしれない。二次創作の制作者と連絡が取れるか?
→制作者にメッセージを送れるなら、「○○という行為はガイドラインで禁止されています」のように送ってみる。誰にでも“知らずにやってしまった”ミスは起こり得るので、喧嘩腰にならないこと(余計な事態に発展する可能性がある)。悪気がなければすぐに取り下げてもらえると思う。最終手段(公式に通報)
→悪意を感じる(ファン活動に見えない)、②でサービスの運営が動いてくれない、③で全然返事が来ないなどの場合、最終手段として公式ホームページの問い合わせフォームなどを使って著作者に直接通報する。
ただこれは普段同人活動をしている当方の考えであり、すべてに当てはまるかは分からない。また、マナーなどお構いなしに真っ先に著作者に通報する人もいると思う。二次創作は通報されない範囲でするように心掛けるしかない。
★余談
ディズニーの問い合わせフォームに通報したときは「権利侵害関連はこっちにお願いね」(英語)といった旨の返信が来たので、ちゃんと一通ずつ対応する人がいる様子。(問い合わせは日本語でやった)
怖いのはディズニーと任天堂(ポケモン)?
「ディズニーと任天堂(ポケモン)の二次創作はやばい」みたいなことは以前からよく聞くし、他のジャンルより慎重にやれといった意見を見たこともある。しかし著作権は平等に適用されるので、どこが危険だとか安全だとかはない。また、両者ともに二次創作に特段厳しい事実も見当たらない(ツイステのガイドライン/ポケモン公式関係者のTwitter参照)。
ただ実情として、同人誌や同人グッズを生産している印刷所でも一定のジャンルだけを自主的に禁止しているところは存在する(例:おたクラブ)。おそらく海賊版と間違われる可能性が高いことを懸念しているのだと思う。ピカチュウやミッキーといったキャラクターは、人間のキャラクターよりも本物と見分けがつきにくいのだろう。そういった意味でなら確かに“やばい”かもしれない。
同じ理由で同人誌よりも同人グッズは海賊版と間違われる可能性が高く危険とする意見があり、これも間違っていないと思う。同人誌には注意書きを入れられるがグッズだとなかなか難しい。作る際は海賊版と間違われないように何か工夫をしたいところ。
…話は逸れたが、ジャンルに関係なく著作権は存在するので、○○は危険だけど▼▼は安全!のような考えは持たない方が無難だと思う。
検索避けについて
Twitterなど不特定多数の人が集まっているSNSなどで行う検索避けのことを記述する(ホームページを検索ロボットの対象から外す作業ではない)。
検索避けは前述の“二次創作はひっそりやる”という手段のひとつで、やり方はいくつかある。こちらのページが参考になる。
検索避けをするのは、主に著作者や二次創作に理解のない人(二次創作を見る気がない人)が原作タイトルやキャラ名、ハッシュタグなどで検索をした際に二次創作を見付からないようにするため。
大抵の場合、見付かってほしくない=見る人が不快になるかもしれない、同じ趣味の人にしか見せたくない二次創作に対して行う。
「検索避けをするべき場面」の考え方は人によって様々であり、
二次創作を掲載するときは何であってもするべき
エログロ要素を含むもの、カップリング要素を含むものはするべき
コスプレは見る人を選ぶのでするべき
公式タグ(公式アカウントが使用しているハッシュタグ)を使わなければそれでいい
…など、おそらく人の数だけ答えがある。そして本当の答えを知っているのは著作者のみで、第三者が他人に強要できるものではない。
誰かが二次創作エロ絵を検索避けなしに載せてたところで、サービスの規約違反でもない限り「駄目ですよ」と言う権利は著作者にしかない。
★参考:不快なのでTwitterに18禁の二次創作を公開して欲しくない人たち
そしていくら検索避けをしたところで、見つかるときには見つかる。エゴサの達人として河野大臣が有名だが、どうやって見つけてきたのかよく分からない画像だけのツイートも探されて反応されている。
以上をまとめると、検索避けというのは、
自分でやるべきだと思ったらする
周りの同じ趣味の人がやってて、自分もやるべきと思ったらする
基準は人によって違う。他人に強要しない。できるのは著作者だけ
…というものだと当方は思っている。
★参考事例:ONE PIECEの場合
ONE PIECEは集英社とは別に個別の公式サイトがあるのだが、そのトップページにでかでかとTwitterやインスタの「#ONEPIECE」タグを拾って載せている。「#ONEPIECE でつながろう!イラスト、コスプレ、 フィギュア、名言、なんでもOK!」という説明付きで、どう見ても二次創作大歓迎としか思えない。
「(許諾がない)二次創作は(著作権法違反なので)検索避けをするべき」という意見に当方は概ね同意だが、こういうのを見ると何でもかんでも検索避けをすることが正しいとは言えない。誰も「#ONEPIECE」タグを使わなかったらおそらくONE PIECE関係者は悲しむ。
ただ、FAQには
キャラクター・画像・音楽の使用につきましては、法律により認められた範囲内での使用に留めていただき、それを超える利用につきましては控えていただきますようお願いいたします。
特に、キャラクターのイメージを損なうような画像などをインターネットへアップロードするのはご遠慮ください。
…との記載があるので(“なんでもOK”って言ってたのに)、結局のところ「ファン活動は作品を盛り上げるために必要だが、作品に悪影響が出る活動はやめてほしい」ということだろうと思う。
ONE PIECE以外にも言えるが、“キャラクターのイメージを損なう”がどこからどこまでなのかは著作者にしか分からないので、このあたりの線引きは本当に難しい…。
★余談:検索避けの“逆”
検索避けと似たような考え方で、「検索避けをした上で同じ趣味の人にしか伝わらない特定の単語を入れるべき」というものがある。同人マナーの一種で、著作権とはあまり関係がない。
よく見掛けるのが「カップリング名」。特定のキャラクター同士の恋愛を描いた二次創作で使われる単語であり、キャラクター「AA」と「BB」の場合はそれぞれの頭文字を取って「AB」のように表記する。「AB」の二次創作を載せる際にこの単語を表記することで、「AB」の作品を見たい人は検索で引っ掛けられるようになり、見たくない人はワードミュートできるようになる。pixivにおけるタグと同じような役割を果たす。
当方はこの考え方に賛成だが、キャラ名によっては頭文字を連結させたら一般的な単語になってしまった→全然関係ない単語の検索結果と混ざる場合があるので、やはり絶対にやるべきとは言えないかなと思う。また、ただの“配慮”であり他人への強要もできない。検索避けと同じようなものと思う。
コスプレについて
アニメや漫画のキャラを元にしたコスプレも、もちろん著作者から訴えられる可能性がある。以下、参考サイト。
明確な線引きがない(※2021年現在、コスプレについてルール化がされるらしいとの情報はある)ので専門家の中でも意見が割れるようだが、「完成度が高いほど著作権侵害の可能性が高くなる」様子(元ネタが分かりやすくなるから)。
ただACOSなど公式側からコスプレ衣装が出ているケースがあるので、同人誌などと同じようにコスプレ=ファン活動として認識されていると考えて問題ない。節度を守っていれば訴えられることはおそらくないと思う。特殊な例として、任天堂キャラクターの衣装を着て(=コスプレ)公道をカートで走れるというサービスをした業者が訴えられたことはある。
★公共の場でのコスプレ
ときどき議論されているのでついでに触れておく。ここでのコスプレはオタクが趣味でやるガッツリなコスプレのことを指しており、小さなお子さんがやる微笑ましいコスプレのことではない。
公共の場(街中や公共施設内)でのコスプレは、
不特定多数の人がいる中で著作権法違反に当たるかもしれない格好をする(もしかしたら近くに著作者や関係者がいるかも?)
街中でコスプレをした人に出会うことはまずない=目立つため、通報される可能性がある
イベントか何かと勘違いされて人だかりができた場合、通行の邪魔になる
着替えや化粧を公共トイレなどで行った場合、迷惑になる
…などの理由から良くないものとされることが多いので、「何を着て歩いてても個人の自由!」のように考えている場合は上記の点について少し考えるべきかと思う。
この前は映画館にコスプレイヤーが出現した件を見掛けたが、映画館側は許可を出しておらず、次からはスタッフが声を掛けてやめてもらうとのことなので、迷惑行為とみなされている。
わざわざ時間と場所を限定したコスプレイベントが存在する理由や、各種イベントでわざわざ「コスプレ可能」という表記がある理由も、普段コスプレは許されていないものだからだろう。
“良くないもの”とされることがある以上、公共の場でやった場合は作品自体のイメージダウンにもつながるのでその点も考えたい。
※冒頭にも載せた通り当方はコスプレをするタイプのオタクなので、「個人的にコスプレが嫌いだから公共の場ではしないでほしい」と書いているわけではない。コスプレが趣味の人間からしても、公共の場でのコスプレは良くないものという認識。
キャラクターがプリントされた布などで作ったものはハンドメイド品として販売しても良いのか?
市販されているキャラ物の布やワッペンなどを使って作ったハンドメイド品を、個人が(キャラの著作元の許可なく)お金を貰って売る場合を想定している。
結論から言うとNG。著作権マークや注意書きがない場合はOKな場合もあるみたいだが、おそらく稀なので基本はNGだと思っていた方が無難。
キャラ物の布、ワッペン、お菓子の型、手作りキットなどはその作品のファンが趣味で作ることを想定した商品であり、商売道具として使われることは想定されていないので個人の金儲けには使わないこと。
★参考:キャラクター生地でハンドメイド品を作って販売は違法?調べてみた
YouTubeの広告について
最近は必ずと言っていいほどYouTubeで広告が流れるようになったが、あれには投稿者が(広告収入を得るために)意図的に設定している場合と、投稿者の意思とは関係なく(YouTube側で)設定されている場合がある。
したがって、二次創作の動画に広告が出ていたとしても投稿者が広告収入を得ているとは限らないので注意。
見ている側からは違いが分からないので、投稿する側なら「自分の二次創作動画に広告が出てるけど、広告収入は得てないよ!」とプロフィールにでも載せておくと安心かもしれない。
当方も勘違いしていたところなので、自戒を込めて。
また何か気になることができたら追記します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
