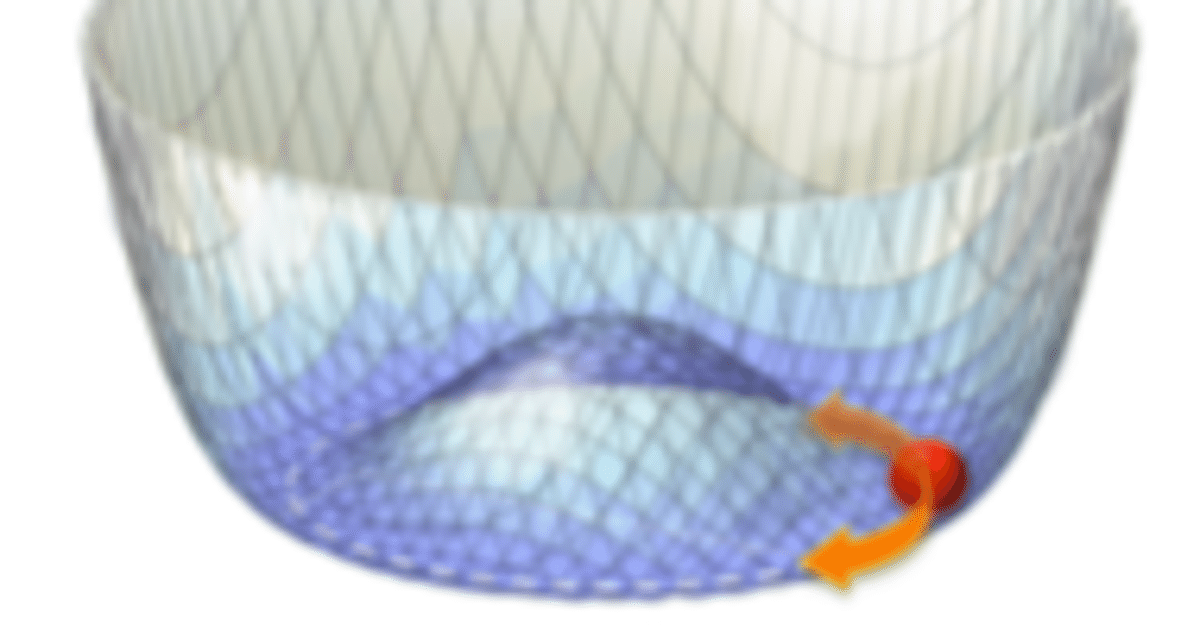
ハドロン物理学のまとめ
超電導についての概要
導体を流れる電流と電圧の関係はオームの法則で表され、
電圧の大きさ = 電気抵抗 × 電流の強さ
となります。つまり、電気抵抗が大きいほど電流が流れにくい事を意味します。これをミクロの視点でみると、電子が固体物質中を移動するときに結晶を作っている正イオンと衝突することで、電気抵抗が発生しています。従って固体物質の温度が高くなると、抵抗が増加します。
絶対零度に近づけた時、正イオンの振動は小さくなる事で電流に対する邪魔がいなくなり、同時に電子も動かなくなるとされます。
つまり、電流が流れなくなることは、抵抗は無限大であることを意味します
このことを確かめるべく1911年にカマーリング・オンネス は水銀を極低温に冷却し、温度に対する電気抵抗の変化を測定しました。すると、水銀の温度を下げながら電気抵抗を測定したとき、絶対零度の手前の4.2 ケルビンで電気抵抗が突然消えることを発見しました。
この現象を超伝導といい、従来の電気抵抗が存在する 電気伝導を常伝導といい、超伝導が現れる温度を転移温度といいます。
この超伝導の理論的な説明はBCS理論で展開され、1957年に完成しました。そのきっかけになったのは、同位体効果です。同位体とは、原子核に含まれる陽子の数(原子番号)は同じだが、陽子と中性子の数の和(質量数)は異なる元素を言います。
同位体効果とは、同位体の量が大きいほど、転移温度が下がるという事です。
この効果が発見されると、超伝導は原子の熱振動と深く関わっていることが推測され、以下のようなことが考えられました。
固体中を伝わる音波を粒子(フォノン)とみなし、それが転移温度以下になると、2個の電子の間でフォノンがやりとりされることで引力が生じる事で、クーパー対と言われるいつまでも離れない電子のペアを作り、クーパー対は集団を組んで固体中を移動をします。
そうなることで電子が正のイオンとぶつかっても周りの電子の強いスクラムで押さえつけられて散らばり乱れることなく、電流が流れ続けるというわけです。これが超伝導の仕組みです。
超伝導になった物質の特徴としてマイスナー効果というものがあり、超伝導体の上に磁石を置くと宙に浮くというものです。この現象を応用したのが、リニアモーターカーであります。
また、常温で超伝導が発生する物質があれば、電気抵抗による送電ロスがない送電線を開発できるようになるが、そのような物質はまだ見つかっていません。
質量の起源とヒッグス粒子
質量とは、「運動状態(静止or動いている)の変わりにくさ」を表します。その事を考慮の上で、以下の記事を書きます。
超伝導状態は、物質を低温にする事で実現します。
その時に物質に光が入ると、光はあたかも質量を持つ状態になります。
その時の電子の状態を明らかにしたがBCS理論です。それによると、物質を極低温にしていく時、ある温度になった途端、各々の電子はペアを作り、そしてペアの集団を組むことで、電子の数が不明になります。つまり、電子の数が保存されないということです。
ネーターの定理によると、電子の数が保存されるならば、それに関連する対称性があると言われます。しかし電子の数が保存されないので、対称性はないと言えます。つまり電子の数がわからなくなると、対称性が破られると言えます。
これは、こちらから意図していないのに自分勝手に対称性が破られていると言え、これを自発的対称性の破れと言います。
この時、南部・ゴールドストーン粒子が発生し、光と混ぜ合わせることで、光が質量を持つのです。
この理論を用いてフェルミ粒子が質量を持つ仕組みを考えたのが南部陽一郎氏です。
まず、カイラル対称性とは、どちらか一方のスピンの粒子だけを入れ替える対称性です。
南部陽一郎氏は、粒子が質量を持つと観測の仕方によってスピンの向きが変わるならばカイラル対称性が破れていると考えました。
(質量を持たない光子は、追いつくことができないので、スピンの向きは常に変わりません。)
そこで、フェルミ粒子が質量を持つとカイラル対称性が破れているならば、カイラル対称性が自発的に破れる理論を作れば、粒子が質量を持つ仕組みを説明できるのではないかと考えられました。その時に導入したのがヒッグス場です。
ヒッグス場が高いエネルギーを持った状態のことをヒッグス粒子と言います。
研究の結果、ヒッグス場があることで質量を少し持ち、カイラル対称性の自発的破れにより、さらに質量が生じることで、真空から物質になるという結論を得ました。つまり質量の起源は、ヒッグス粒子にあるのではなく、ヒッグス場とそれを取り巻くフェルミ粒子の自発的対称性の破れにあります。
質量の起源は、粒子がヒッグス粒子とぶつかり、その摩擦力が質量の起源と紹介している記事がありますが、間違いです。最初に言いましたが質量とは、「運動状態(静止or動いている)の変わりにくさ」を表します。もし摩擦が生じますと、すでに動いているものは止まってしまい、質量とは、「運動状態の変わりやすさ」という全く正反対の定義になります。なので、ご注意ください。
質量を考える時はヒッグス場を考えるのであって、ヒッグス粒子はあくまでもおまけに過ぎないという事です。ヒッグス粒子を発見すると、ヒッグス場がある事を意味するという事です。
この題名では神の粒子:ヒッグス粒子と名ずけましたが、実際はヒッグス粒子をなかな見つけられないことからGoddamn particle(忌々しい粒子)と名ずけられましたが、これでは教育上悪いので、編集者はGod Particle(神の素粒子)と名ずけています。
パイ中間子凝縮について
パイ中間子について
1934年、湯川秀樹は、陽子が正電荷を持つ粒子を放出して中性子になり、それを別の中性子が吸収して陽子になり、その逆過程も起こるという理論を発表しました。これを、中間子論と言い、正電荷を持つ粒子をパイ中間子と言います。ここで、陽子がパイ中間子を放出する反応はエネルギー保存則に反するので、パイ中間子が存在できる時間は、不確定性原理を満足するごく短い時間内になります。この時間内にパイ中間子が他の核子(陽子や中性子)に吸収されることで、核力が発生します。
ここで核子の働く範囲は原子核内のみであることを用いると、パイ中間子の質量がわかり、その結果、パイ中間子は核子の質量より小さく、電子より大きいことを見出したことから、パイ中間子の名前の由来になりました。
以下では、パイ中間子が不確定性原理を満足するごく短い時間内でなくともパイ中間子が存在できるという現象であるパイ中間子凝縮についてこれから説明します。
核物質中のパイ中間子凝縮について
まず、物質とは「量子場の励起状態」であり、真空とは「量子場の基底状態」 であります。その関係は「自発的対称性の破れ」によって説明されます。
その自発的対称性の破れによって、物質は大きく性質や形態を変えています。パイ中間子凝縮はパイ中間子が自発的対称性の破れを起こしてできた現象です。
通常、パイ中間子が存在できる時間は、不確定性原理を満足するごく短い時間内にしか存在できないので生成や消滅を繰りかえしています。つまり全体的に見ると存在していません。これを、真空期待値は 0 であるといいます。
しかし、原子核が高密度に集団を作ると、原子核内のパイ中間子の密度が大きくなり、パイ中間子が存在するようになります。このことをパイ中間子凝縮といいます。
わかりやすくいうと、早く点滅している光は本当に光っているのかはわかりませんが、点滅するタイミングがずれている光をたくさん重ね合わせると、光が見えるようになるのと同じような感じです。
これは、真空期待値が 0 でなくなり、真空期待値が有限の値を持つようになることを意味し、自発的対称性が破れた一例でもあります。
このパイ中間子凝縮は玉垣良三氏が予言したものであります。
このような現象はまだ実験では確認されていませんが、実際に起きているのは中性子星内部であると考えられてます。
参考文献
小山慶太「入門 現代物理学 - 素粒子から宇宙までの不思議に挑む」中央公論新社 (2014/8/22)
伊達 宗行「新しい物性物理―物質の起源からナノ・極限物性まで」講談社 (2005/6/21)
矢口裕之「初歩から学ぶ固体物理学」講談社 (2017/2/21)
大栗博司「強い力と弱い力」幻冬舎 (2013/1/30)
南部陽一郎「クォーク 第2版」講談社 (1998/2/21)
国広 悌二「別冊数理科学 クオーク・ハドロン物理学入門」サイエンス社; 不定版 (2013/8/30)
杉山 忠男「理論物理への道標〈下〉」河合出版; 三訂版 (2014/8/1)
この記事が参加している募集
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
