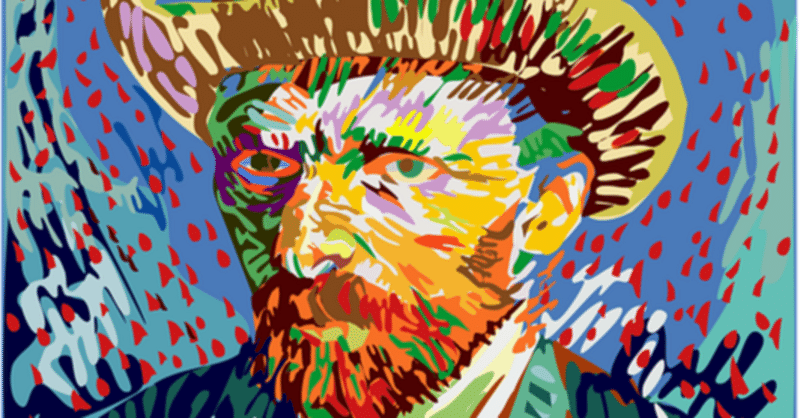
「やさしい」のは良いことではない
ゴッホのやさしさ
ゴッホというと奇人ぶりで有名だ。
耳を切っただの、自殺しただのというグロテスクな話題ばかりが注目されるが、貧しい人やめぐまれない人に対して度を越して同情する人だったことでも知られる。つまり、過度にやさしい人だったわけである。
やさしい、というと良いことに思われがちだが、なにごとも度を超すとよくない。たとえばゴッホは、弟のテオから仕送りしてもらったお金の大半を、身重の娼婦に渡してしまった。
娼婦に同情するのはいいけど、生活を削ってまで慈善活動にはげんではいけないし、そもそも自分で稼いだお金ではなくて仕送りである。
こんな風に彼のやさしさは周囲をふりまわして、混乱させるようなものだったらしい。とはいえ、こう書きながら、ほんのちょっと心が痛いというか、他人とは思えないところもある。
度を越えたやさしさは誰も幸せにしない
ぼくにもちょっと似た気質があり、他人の置かれた状況に度を越して感情移入してしまう。子供の頃からそうで、じぶんで言うのもなんだけど、ゴッホほどではないにせよ、生きていくのが大変だった(笑)。
今でも心の底では
地球のどこかに苦しんでいる人がいる限り、自分は幸せにはなれない
という風に思っているところがある。ただし、こういう考えが誰の幸せにも役立たず、災厄をもたらすだけだということがわかっているので、なるべく表に出てこないようにコントロールしている。
しかし、それが隠し切れずに表に出てきた時に奇人といわれる。または、「やさしい」と評されることもあるけど、ゴッホを見ればわかる通り、
度を越えたやさしさは誰も幸せにしない。
のである。
他人の性格はナゾ
ぼくは、なにごともバランスが大事だと思っているし、そういう風にここでもよく書くのだが、もともとバランスの取れた人間ではない。上記のような性格の反省の上に成り立っているわけで、このように人間の性格というのは複雑に出来上がっている。
自分の性格ですらなかなか理解できないのだから、まして他人の性格などわかるはずもない。そんな他人が78億人も生きている地球上で生きているのだと思うとめまいがしてくるが、こんな風に感情移入してめまいを起こすのが、ゴッホ流のダメなところである。
「千曲川のスケッチ」
さて、最近、寝る前にオーディオブックで、島崎藤村の「千曲川のスケッチ」というのを聞いている。
これは藤村が20代の後半から30代の前半に、長野県の私塾で英語教師をやっていたころの様子をつづったエッセイである。110年前の作品なので、明治維新の記憶も生々しく残っており、なかに「古城の初夏」という一節がある。
彼の勤める私塾に、物理や化学を受け持つ年老いた理学士がいる。藤村が、はじめてこの学士に逢った時は、
ただこんな田舎へ来て隠れている年をとった学者と思っただけで、そう親しく成ろうとは思わなかった
そうだ。しかしそのうち「幾多の辛酸を嘗なめ尽して来たような」学士の人となりに触れ、「これ程何もかも外部へ露出した人を、私もあまり見たことが無い」と感じるようになり、親しくなっていく。
そして、
旧士族には奇人が多い。時世が、彼等を奇人にしてしまった。
と思うのだ。つづけてこう書かれている。
もし君がこのあたりの士族屋敷の跡を通って、荒廃した土塀、いしずえばかり残った桑畠なぞを見、離散した多くの家族のいたましい歴史を聞き、振返って本町、荒町の方に町人の繁昌を望むなら、「時」の歩いた恐るべき足跡を思わずにいられなかろう。
たったこれだけの描写にすぎないが、維新後に士族が舐めた辛酸が垣間見える。
大きな物語は無数の小さな悲惨に支えられている
今の僕らには、旧士族の没落などはるか昔のことであり、ふだんは想像する機会すらない。それでも藤村に「時」の歩いた恐るべき足跡、などと言われると、ぼくはいろいろとはげしく想像してしまって、真夜中に1人で落ち込んで疲れた。入眠のために聞いているのに、眠れなくなっては世話はないのである。
しかし、
時代に大きな動きがあるときには、いつでもこのようなことが起こっているのだ
と改めて思う。○○革命だろうと、○○戦争だろうとみな同じで、「歴史」などと呼ばれてありがたがられているあらゆる「大きな物語」は、無数の小さな悲惨に支えられている。
そして、明治維新だの、戦国武将だの、坂本龍馬だの、織田信長だのと、さも痛快そうに語る人々の無神経さを空恐ろしく感じるとともに、ついていけないとあらためて感じる。
ただし、こんな風にゴッホ流でつきつめてしまうのが、ぼくのよくないところなので、ウクライナ戦争をアツく語る人々の言葉も平気な顔で受け流そう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
