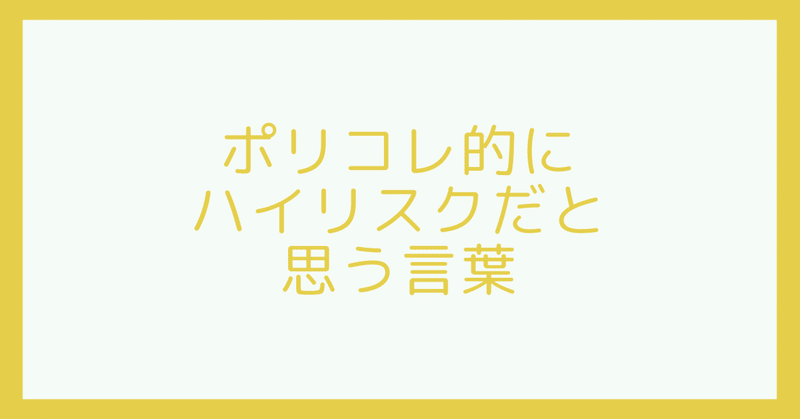
ポリコレ的にハイリスクだと思う言葉
こんにちは、化粧品会社でEC担当をしているユリです。
ここ数年、企業の炎上事例は枚挙に暇がありません。
「そりゃ燃えるでしょ」という内容ではなく、「それで燃えるの?」というような、何気ない言葉選びが一部の消費者を不快にさせている、そんな難しい事例も増えているように思います。
私は広報担当ではないのですが、メルマガやSNS発信、商品説明やキャッチコピーなどを考える業務があるので、その辺のトレンドには鈍感にならないように気をつけています。
自分は全く不快に思わなくても、不快に思う人がいるかもしれない”ハイリスクワード”みたいなものを自分の頭の辞書の中に入れていて、対外的なコミュニケーションを取る際には、「本当にこの言葉が適切か?」と立ち止まります。
この感覚は人それぞれで正解もなく、全ての人に迎合する言葉選びをし続けることは不可能だし、する必要もないと思います。
ただ、世の中の流れやマジョリティの感覚とズレた感覚を気づかず発信し続けると、炎上まではいかなくとも、なんとなく不信感を持つユーザーの割合が増え、結果として静かにファンが離れていく‥という現象も起こり得るので、
「この言葉はハイリスクかも」と認識した上で使うことが大切かなと思うのです。
というわけで、私が使うときに少し慎重になるワードをまとめてみました。
私が”不快に思う言葉”ではなく、私が”ハイリスクだと思う言葉”です。
そして、ハイリスクだから絶対に使うべきじゃない、と思っているわけでもありません。
ブランドによってポジションは違うし、ポジションを取らず当たり障りのないことだけを伝えていると、結局誰からも支持されないブランドになると思うからです。
別の属性の人から見たら、違和感を覚える部分もあるかと思います。
あくまで私(20代後半女性/独身)の感覚であり、正解があるものではないので、イチ意見として読んでいただけると幸いです。
そしてこの感覚は数年後、また大きく変化しているのだろうなと思います。
⒈「男性」「女性」「男の子」「女の子」
ジェンダーについてはここ数年特に過敏になっているので、私は商品やブランドの訴求をする上で、ジェンダーについて明言するようなワードを使うときはかなり慎重になります。
例えば、「美しくなりたい全ての女性に」「女の子らしい香り」「男の子っぽいデザイン」など。言わずもがな、ジェンダーバイアスを助長するという意見をもらう可能性が多いからです。
ただ、ジェンダーではなく、セックス(文化的ではなく生物学的)の文脈での性別について言及するときは、これらのワードを使っても問題ないと、私の中ではラインを引いています。
例えば、「生理痛に悩む女性に」「男性の髭剃りのストレスをゼロに」など、生物学的な性差が明らかな場合です。
そうではなく、比較的男性が多い”イメージ”とか、女性が多い”イメージ”とか、グラデーションを描いている文脈では、あえてゼロヒャクな概念の「性別」を明言しなくてもいいシーンは結構あると思うのです。
⒉「お父さん」「お母さん」
これもジェンダー系ですが、「お母さん」というと、ファミマの「お母さん食堂」騒動を思い出す方が多いかと思います。
サザエさんの世界のような、ステレオタイプ的な「お父さん像」「お母さん像」が崩壊している現代では、「家事をしてくれるお母さん」「仕事を頑張るお父さん」という概念を押し付けるようなコミュニケーションは反発されますよね。
母の日、父の日のプロモーションなど、どうしてもこれらのワードを使わないといけないこともあります。そしてこれらのワードそれ単体は何も問題はないのです。
ただ、「いつも仕事を頑張るお父さんに♪」とか「お母さん、いつもおいしいご飯をありがとう!」とか、なんかそういうのは危ないニオイを感知します。
⒊「モテ」「男ウケ」「女ウケ」
「モテメイク」とか、「男ウケ抜群!」みたいな言葉、昔は雑誌でよく見かけました。
が、ここ最近、特にZ世代には、こういう言葉には冷ややかな目を向けられるような気がします。
美容やファッションは、「異性にモテるために頑張っている」という認識(誤解?)があったと思います。
だけど、実際に綺麗になりたいと思って努力するのは、異性にモテるためではなく、自分のQOLを上げるために他なりません。Twitterで美容垢と呼ばれる人たちのツイートを見るとよく分かります。
なので、「こうするとモテるよ!」と言う訴求の背景には、「モテたいんでしょ?」という偏見が感じられ、反発を招きます。
「いや別に自分のためにやってるだけで、異性の目とかどうでもいいんだけど…」という感情を持つ人が一定数いるということは、理解しておくべきことだと思います。
他人から良く思われたいという承認欲求から、自分がなりたい自分になりたいという自己実現欲求に昇華しているのかもしれません。
もちろん、モテたいというのは三大欲求の一つ(性欲)で、モテたい人が絶滅したわけでは全くないので、モテたい人にターゲティングした商品はどんどんモテを訴求するべきだと思いますが。
⒋「可愛い」「美人」「イケメン」
ルッキズムという言葉が一般的になったのは、一体何年前からでしょうか。
容姿について言及することは、例えそれがポジティブな言葉だとしても、徐々にタブーとなりつつあります。
「美人過ぎる医師」「イケメン議員」というようなコピーは、世代によっては強烈な嫌悪感を感じます。
顔は関係ないだろうと。顔の良し悪しが関係ない場面で、なんであえて顔について言及するのか、と。
もちろん、容姿についてネガティブなコメントはさらにタブーとなります。
容姿のコンプレックスを助長するような下品極まりない広告・広報はまだまだよく見かけますが、これらが批判の対象になり、致命的なブランド毀損になることは明白です。
すでに、2020年にはYouTubeのコンプレックス広告へ抗議する署名活動が起こっているほどです。
私も、どんなに商品自体が良かったとしても、こういうマーケティングをしていたら絶対に買わないです。
⒌「肉」
ワード、というとちょっと違いますが、番外編で。
ヴィーガン人口が爆発的に増えるのと比例し、これから先、肉はきっとどんどん腫れ物のような扱いになっていくんだろうなと感じています。
畜産業は環境負荷がとても高く、動物愛護だけでなく、SDGsの観点からヴィーガンになる人が多いからです。
日本は欧州などに比べると環境問題への意識が低く、「お肉食べほーだい!」「絶品焼き肉」「肉ケーキ」「肉ドレス」などのワードもまだまだキャッチーです。
でも、この景色は10年後にはきっとまるっきり変わっているんだろうなと思います。
肉を過剰に消費するような行為は、「恥ずかしいこと」「みっともないこと」「環境保護に全く意識が向いてない残念な人」というレッテルが貼られる日も、そう遠くはないのではないでしょうか。
今現在でも、例えばSDGsや動物愛護を強調している企業にインフルエンサー社員がいたとして、SNSで「焼き肉食べ放題行ってきました〜!」なんて呟いていたら、その企業の経営姿勢に惚れ込んでいたファンは静かに離れていくはずです。
私自身、肉は大好きでよく食べますが、インスタで肉をジェンガの形にカットした焼肉屋の画像を見たときは、なんだか下品だなぁとかなり引きました。そして、「あぁ、きっとこういう気持ちなのね」となんとなく理解しました。
今この時点では問題がなくても、今後批判される世の中になっていくだろうな、とある程度予想することは重要だと思っています。
なぜなら、企業がネット上で発信した内容は半永久的に残り、時にそれが「この会社、昔こんなことやってた!」と遡及される可能性があるからです。
以上、私が現段階でリスクに感じるワードを一部抜粋してみました。
繰り返しになりますが、これらの言葉を全て避けるべきと言いたいわけではありません。
最近だとスープストックトーキョーのように、あえてノイジーマイノリティに屈せず毅然とした態度を示したことが絶賛され、強く支持された事例もあります。
https://diamond.jp/articles/-/322288
実際、このようなポリコレ忖度には辟易としている人も多いでしょう。
「何も言えなくなった」「尖ったコンテンツが無くなってつまらなくなった」という声も多いです。私もそう思う瞬間はあります。
ポジションを取って、リスクを取って発信をしなければ、誰からも共感されず、支持されることはありません。
しかし、お客さんとのコミュニケーションをするにあたり、やはり世の中のトレンドにはアンテナを張っておくべきだと思うのです。
それが好きであっても、嫌いであっても。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
