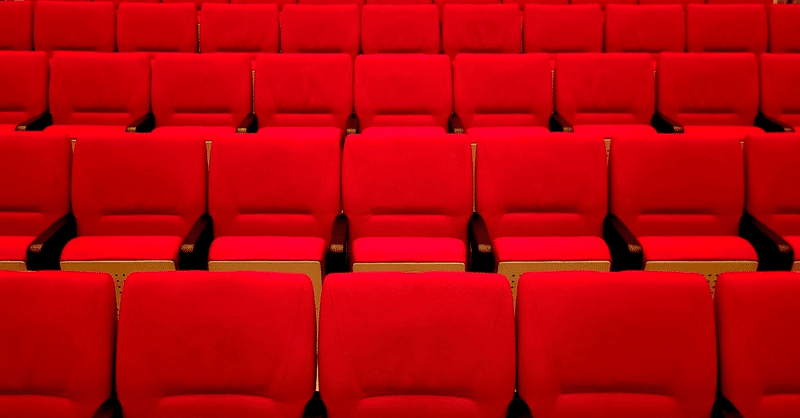
『演劇』は”生活への愛”を思い出す芸術だ。
はじめに(あとがき)
今日、人生で多分初めての『演劇』を観てきた。
そしてそこで感じた『演劇』の特殊性や感想を3,300文字で書いてみた。
私の中で『映画』と『演劇』は近しいイメージがあったので、映画と比較しての感想もあるが、それを通して『演劇』の概念を私なりに解釈した面白い文が書けたと思うので是非読んでほしい。
(*演劇名や会場等は諸事情で伏せさせていただくが、今人気の『演劇』である。)
座席に座った時に感じた『違和感』
開幕前にまず思ったのは「今ここでしかない」感が凄い。
これは目の前で行われるという臨場感も勿論なのだが、どちらかというと「場所の限定」の感じ、つまりメタ視点からの疑問が強かった。
こんな大きめの会議室くらいの舞台で一体何ができるのか、という、若干の期待を持ちながら開幕した。
私は最近、作品のストーリーを追わない。というより、なぜか追えないのだが、今日もそれで全くと言って良いほどその時その時で何をしている場面なのかはよく分からなかった。
なので、演出の迫力と演技の奥深さで刹那的に楽しみ、残りは私の中での『演劇』の捉え方ができたので、ここではそれを書いていこうと思う。
1階席後方で観た『演劇』
劇場は2階席含め1300席くらいのキャパだったのだが、私は1階席後方のそれなりに見やすいところに座った。そこで観ていて感じたのは、やはり映画と違って観づらい。細かい表情や表現が出来ない中でいかに勝負するかが肝のようだ。
だが、その距離が面白くもあった。遠さというモザイクをかけられた中で脳がどうフィルタリングし処理するのか、というのは意外にも小説を読んでいるような感覚に近かったかもしれない。またそこで生まれる一種のつまらなさにも小説のような味がある。
客席と舞台の『境界』
映画の場合:
映画の客席とスクリーンの間にある『境界』は明るいように思える。
きっと、"それらが目の前で行われていない事"と"情報が全てあらわになっている事"から、私たちは映画館で観ていることを忘れ、映像を脳内に間接的に投影していて、つまり滅茶苦茶に没頭しているわけだ。
または、観客と言う実体を席に置き、視点が『境界』と一体化しているとも言えるだろう。
演劇の場合:
それに比べて、客席と舞台の『境界』は私たちが目の前で見ていると言う責任感や座席と舞台との《距離》の問題から、どうしても凄く没頭はできないし、多分それが演劇の楽しみ方なのかもしれない。「演技上手いな〜」とかの映画では上映中はあまり思わない事を平気でやれるのが演劇の良さだ。
そのため必然的にメタさが常に付き纏ってくるわけだが、勿論、演者は私たちに”意識”を向かせることはない。
なので観客側の現実感と舞台上の現実感に大きなギャップが発生していて、これが面白い。
舞台側にも実体があるのでとても《舞台上の現実感》(リアリティ)があり、その中で大道具移動などの《観客側(真)の現実感》が相まって舞台上には複雑性がある。対して観客の私たちはこれを観ているだけだ。
どっちが現実か?と聞かれればこっち側には何もなさすぎて、向こうが現実と言いそうになる。無論そんなわけがないので、それらから逆に客席側の現実感が高まり、そうすると不思議と舞台上にも《舞台上の現実感》が出てくる。
舞台:非現実を現実的な手法で見せる
↓
観客:メタい目で観客側以上の《現実感》を見る
↓
謎の目の前の別世界(現実)感
舞台と客席の目をやると影があるのだが、そのために、そこに小さな「死」を感じるような大きな無限性の暗さを感じた。それは『視界の外の闇』を見ているようだった。
「おお、むしろこの現実から隔離されている向こう側の感じをメタさで作り出すのか〜」と考えていたら、その瞬間、急に観客サイドに敵役が来ちゃって観客側にあからさまなコンタクトを取られてしまい、少し笑ってしまった。これ以上カオスになってどうするんだよ。
音の『しょぼさ』
気のせいかもしれないのだが、1300人キャパでこの音質?みたいな感じだった。
先述した私の『演劇』の楽しみ方から、あえて音質で没頭できないようにしているのかと思うほどだ。
それだとしたら、この時代にそんな余裕な事をしてしまうのカッコ良すぎるが、どんどん便利になるこの時代に商売人たちがそんな事を考えるわけがないのが現実だろう。
もしかすると《距離》の問題で、より正確に発言を聴こえるように全ての音を凄くクッキリさせているのかもしれない。テレビや"らくらくフォン"にあるあの機能をそのまま落とし込んだと言う説だ。そして実際にそう思って聞いたらそんな音質だった。
だが、そう考えると一気につまらない。ここまで『混沌的な舞台』や『暗い境界』を引いといて、それを音質ごときがぴょいとそちら側へ飛び越えさせようとしている運営側の意図を聞いているのに等しいのだ。
と言いつつそう言ったつまらなさも醍醐味ではあったのだが。
メタさの『面白さ』
そんなこんなでずっと割とメタい目で見ていたのだが、これが意外と面白い。
大道具:
天井に着きそうなくらいとても大きい大道具が出てくると、舞台裏の構造も少なくともこれくらいのが入る大きさで、「もしかしたらその形に合わせて作ってるのかも」と考えると舞台裏の形まで想像してしまっていた。舞台より外の空間に”宇宙”を感じることができた。
照明:
ケルベロスが出てくるシーンで、『"ケルベロスの前足"が下半身のマッチョ上裸男』とその1mほど後ろ側にいる『黒子(上半身は真っ黒)のケルベロスの足』だけがただ暗闇の舞台上で光を当てられるのだが、それがまさにケルベロスを表していた。
いわゆる”ケルベロスの胴体”は見えないのだが、メタい目で見ていても本物のケルベロスに見えてしまう時もあって、その時は非常に感心した。
『何を見せないのか』と言う本来の芸術ではあまりない表現が新鮮で、より芸術の感じがした。
人工の太陽:
朝日が昇ってくるシーンがあるのだが、どうやら本物の太陽をスタジオに持ってくるのはできないようなので、観客から見えない舞台袖から暖色の光をぽわ〜っと照射していたのだが、それもまた見事だった。
”太陽”の暖かさが本物の太陽以上に感じとれるほどに暖かい光をしていたからだ。「モノマネは本物を誇張しないとダメ」みたいな風潮はこれかと思いながら、その影が織りなす偽物感と本物感を楽しめた。
この太陽光が差し込む窓の外を想像してみると、『何もないピンクの粘土のような世界』と『太陽光まではビジネスとしていないようなビル群』の両方が脳裏に浮かんできて、正直ここが一番感動した。
閉幕:
人工の太陽光のなんとも言えなさに感動していたらあっけなく舞台は終わった。
役者たちが合計で10回くらいお辞儀を繰り返して最終的にスタンディングオベーションをする(聞いたところ舞台ではこれが”常”らしい。)のだが、ここはかなり”文化”的だった。
これはおそらく演劇特有の文化だし、これは決して日本的じゃないのにも関わらず演劇ではやってしまえるんだという逆に日本の文化っぽさもあった。
私はそういうのが大好きだ。ここまで含めて作品なのかもしれない。
まとめ
ここまで2900文字くらい書いてしまったようだが、『演劇』とは本当に奥が深いようだ。それも、文字にできる奥の深さが多くあって嬉しかった。
音楽や絵画は言葉にできない奥深さなのでそれがちょっともどかしい。もちろん、それが醍醐味なのだが最近はnoteを書くのにハマっているので、今回は非常に良い経験をできた。
それに、ここまで書いてきた通り、『演劇』とは、多くの《制約》のなかで行われている芸術だ。今までの中で一番社会的だった芸術であることは言うまでもないが、それを体感する面白さは、芸術が本来持つ”真実への愛”と言うより”作り物への愛”であって、そういった側面から最近忘れている”生活への愛”を思い出せて素晴らしかった。
芸術の新しい側が知れて良かった。劇団四季とかそういうものも是非見て見たい。そして、そこで演劇の限界を知って酔いしれる喜びは、底知れない面白さがあるだろう。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
