
母子健康手帳を3世代読んでみた。
私の父の母子手帳を祖母から母へ渡されたのをきっかけに、
母子手帳の変化を3世代分読んでみました。
ということで以下の「母子健康手帳」を比較。
□1958年交付の母子手帳(父)
□1983年交付の母子手帳(私)
□1994年交付の母子手帳(妹:10歳年が離れているので参考までに追加)
□2016年交付の母子手帳(娘)
※ちなみに母子手帳は通常母親が妊娠期に交付されるものです。

1.そもそも「母子手帳」とは?
母子手帳は「母子健康手帳」の事で、原形は昭和17年(1942年)から始まった妊産婦手帳にみることができる。また昭和17年か ら昭和20年(1945年)までは、国民体力法に基づく「乳幼児体力手帳」が用いられる。
流産・死産・早産の防止、妊娠や分娩時の母 体死亡を軽減することを主な目的として、敗戦後の混乱の中、妊婦や乳幼児にしっかりと生活物資が配給されるのに役立つ。
昭和22年に児童福祉法が成立、公布され、妊産婦手帳の 本来の目的であった妊産婦自身の健康管理だけでなく、この手帳の対象を小児まで拡大。「母子手帳」とし、昭和23年にその様式が定められる。 昭和40年に制定された母子保健法に基づき、「母子健康手帳」と名称が変更される。妊娠した者が妊娠の届出をすることにより手帳を交付するようにる。
(参考情報:厚生労働省の母子健康手帳の交付・活用の手引きより一部抜粋し編集)
という内容でした。
戦後の妊婦さんがしっかり出産できるようにちゃんと物資を配給しよう、というところからだったんですね。粉ミルクの配給記録などがなされていたそうです。そのあと子供の権利に関する法律ができて「母のため」から「母と子の」という手帳に変わっていったのですね。
2.「母子手帳」は日本だけ?
アメリカ留学時「女性学」の授業で日本の育児についてすこし触れたとき、「母子手帳」を引き合いに出したことがあります。はじめてアメリカにはそんな手帳は存在しないということ、むしろ母子手帳のある国のほうがまだまだ少ないということを知りました。
母子手帳発祥の地は日本だそうです。今では一部の発展途上国や先進国でも日本にならってとりいれられているとのことです。
「母子手帳」ってとても便利ですよね。
□インターネットが普及している現在、どの地域の親も同じ世代で共通の情報がシェアできる。
□子供の発達や予防注射の記録ができる。
□医師と親のコミュニケーションがスムーズになる。
ちょっと小話ですが、アメリカで義母と「日本人はよく血液型の話をする」という話題になり、もちろんアメリカ人夫なので血液型がわからず、その場で30年以上も前の担当小児科医に電話して尋ねた、というエピソードがあります。どうやら「日本で生活するのに血液型がわからないと息子が会話に困るのでは」と思ったようです(笑)
3.現代の「母子健康手帳」
私がもっている一番新しい母子健康手帳です。
平成28年交付(2020年に3歳になる娘の母子手帳です。)

大体の内容は以下になります。
(太字は全世代の母子手帳に共通して記述がある項目です)
□赤ちゃんの写真や家族の写真を貼るページ
□出生届出済証明
□妊娠期の自身の記録(これまでの病気や体重や仕事、各妊娠期の記録など)「はじめて胎動を感じた時の気持ちを書きましょう。」などあります。
□妊婦検診の記録
□妊娠中と産後の歯の状態
□出産時の記録(出生時の体重とかこれが後々色々な書類で書くことに)
□うんちの色カード
□1ヶ月健診、3か月健診、6-7か月健診、1歳半健診、3歳、4歳、5歳、6歳まで記録欄があります。
□発達曲線
□予防接種の記録
□妊娠中の生活指導、夫の役割、シートベルト着用法、薬の服用に関して、食事の目安、など妊婦の健康に関する記述。
□赤ちゃんの保温、母乳、衛生面、検査に関して、やってはいけない事、保健師の家庭訪問、など新生児の健康に関する記述。
□緊急連絡先
□児童憲章(こどものための法律について)
□手形足型ページ
以上、だいたいの内容がこのようになってます。
妊婦さんは妊娠がわかって病院にいって心拍が確認できて
お医者さんから「次までに母子手帳もらってきてね」と声かけられます。
母子手帳って赤ちゃん期はもちろん、そのあともしばらく長いお付き合いになるんですよね。
4.自分の母子健康手帳をみてみる
昭和58年交付のもの。
ちなみに私は1984年生まれ、ねすみ年です。
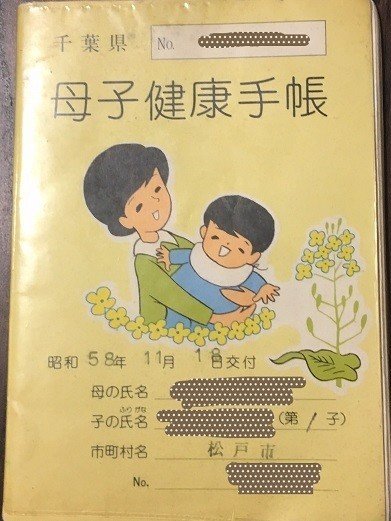
紙質もだいぶ落ちますが、背表紙にある「児童憲章」は一字一句違わずかわりありませんでした。
1ページ目に住所などの情報と「出生届出済証」がありました。
この辺りは30年以上経っても変わりないです。
そして2ページ目をひらくと・・・
「よいお母さんになるために」というタイトルで
食事や仕事の仕方、休息をとることなどの日常に関する注意点、健康診断をきちんと受けること、医師に相談すべき症状、歯の衛生、などざっくりとした注意書きやアドバイスがありました。
いくつか目にとまったところをピックアップします。
□平成の母子手帳にはなかった「近親婚かどうかの欄」・・・。
「無」になってた。よかった(笑)
□生後4週間の赤ちゃんの特徴に「ほとんど眠ってます」って書いてある(うそだーー泣。娘は良く眠ってたのは最初の1週間だけでした。)
あとは母乳が一番、出なくても吸わせましょうって書いてあります。
こうやってみてみるとページ数は平成の母子手帳(96ページ)にくらべて66ページと少なく、自分で記録をつけていくページが豊富です。
自分がいつどんな病気にかかっているかみるのもなかなか面白かったです。
手足口病2回やってる~、娘と同じ種類の注射で熱出してる~など、色々個人的な発見がありました。
皆さんも自分の母子手帳是非みてくださいね。
病院に連れて行った記録や出産にかかった時間など知ることができます。母の愛と頑張りを感じますよ。
5.おまけの妹の母子手帳をみてみる
平成6年交付、10年後に生まれた妹の母子手帳です。
この辺りの世代のママも増えてきてますね。

「よいお母さんになるために」だったタイトルが、
「母と子の健康を守り、明るい家庭をつくりましょう」
に変わってます。
「父親が近親か」の欄がなくなってます。
現代の母子手帳は同居者にも喫煙者がいるか○するところがありますが、
昭和58年と平成6年の母子手帳は母親が喫煙するかどうかだけチェック欄がありますね。今は当時よりだいぶ喫煙者も減ったし、たばこに対する社会の態度もかわったようにかんじます。
3人目だからでしょうか・・・、成長の記録を自身で書いていく欄がほとんど空白です。まぁ、上に2人いてフルタイムで仕事してたら書く時間を睡眠にあてたいですよね。今ならわかる!
それでも予防接種もきちんと受けているし、病院にもかかっているしちゃんと育ててもらっている様子がわかります。
産後鬱に関してもちらっと書いてありますね。不安に感じたり落ち込みやすいことがあるので医師に相談しましょう、とあります。
「育児のしおり」には乳幼児期の月齢別、幼児期の年齢別にどう過ごしたらよいか、気が付くべき点など書いてあります。
6.父の母子健康手帳をみてみる
昭和33年交付の母子手帳です。
今回みる母子手帳で一番古いものになります。
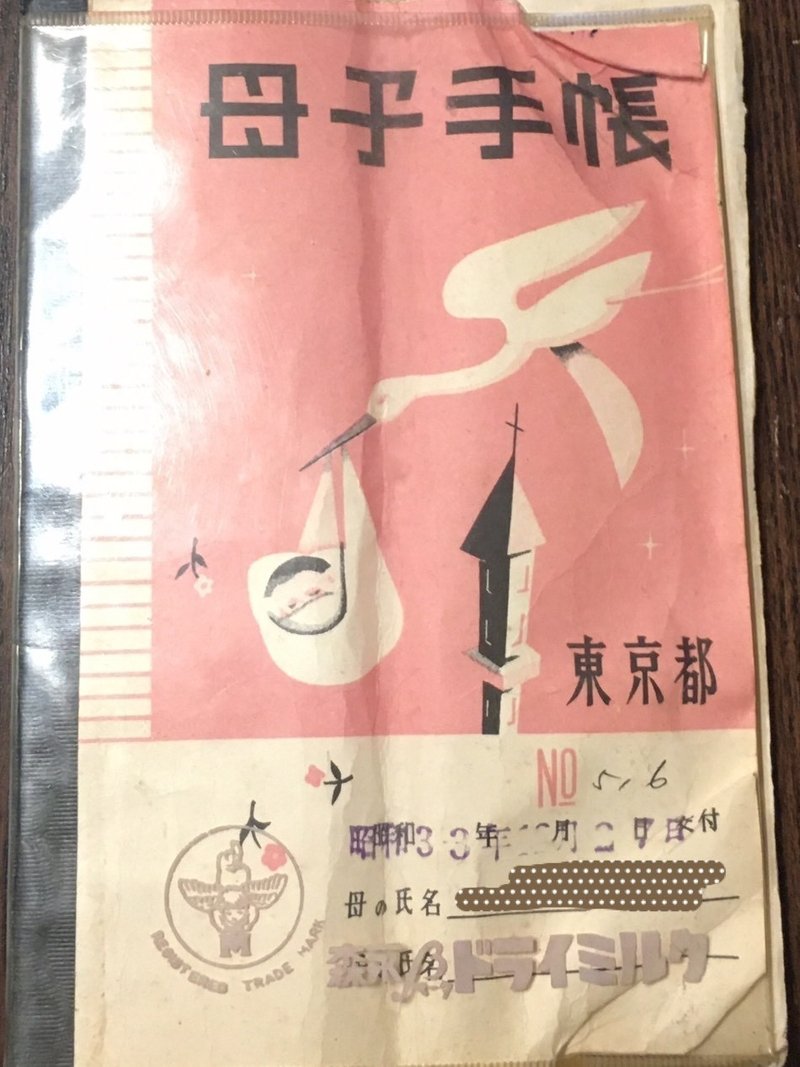
端が折れ曲がってるのが気になって直そうとしたら、手帳とカバーのサイズがあってなくて無理でした。
(祖母が自分でカバーを用意したのかは不明。)
背表紙に「交付されたら先ず一通り読み、そのあとで繰り返えして読んでください。」とあります。
1度でなく、繰り返し読むようにと・・・楽しみです。
(ちなみに”返して””、は”返えして”となってます。送り仮名や拗音など現代日本語とは違うところがありますが、以降できるだけ再現しています。)
最初の見開きページは変わらず「出生届出済証」となっています。
そのあとに続く「妊婦の心得」が色々と厳しい響きなのでちょっとご紹介します。
まず、妊婦向けのページタイトルの変容について。
平成27年→「すこやかな妊娠と出産のために」
平成6年→「母と子の健康を守り、明るい家庭をつくりましょう」
昭和58年→「よいお母さんになるために」
昭和33年→「妊産婦の心得:丈夫なこどもは丈夫な母から生まれます。立派なこどもが生まれるようふだんよりも一層健康に注意しましょう。」
以下、いくつか目に留まった箇所をあげます。
「丈夫なこどもはじょうぶな母から生まれます」というページタイトル、なかなか厳しい口調な印象もうけます。
「お乳を十分に出すため、迷信にとらわれずよく食べること。」(一部省略)
ー 迷信ってなんだろう・・気になる。現代でいうとインターネットの情報にばかりとらわれないようにしましょう、ってところでしょうか。
母乳は現代では「おっぱい」と一般的によんでいますが、当時は「お乳」だったようですね。「お乳が十分でてるのだろうか」と悩むのはいつの世もかわらないですね。どんな迷信があったのか気になりますが、こちらにかんしても調べたらおもしろそうです。
「飲みにくい乳首はなおしておきましよう」
ー マッサージの事ですかね。妊娠中からしっかり乳首を伸ばしておくと後で赤ちゃんが飲みやすいとはいいますよね。ただ、「なおしておきましょう」の書き方に少しクスっときました。陥没してたら吸いにくいですからね。
「妊娠の初期と後期に一回ずつ医師の健康診断をうけましよう。月一回助産婦の保健指導を受けてください。」
ー 妊婦検診、初期と後期の2回だけ。
祖母の妊婦検診の記録をみても、2回のみになってます。
現代では信じられないくらいですが、1回目から2回目までの健診まで不安にならなかったのかしら、と思ってしまいます。
妊婦検診って妊婦さんにとってはちゃんと育っているかの安心材料だったり不安をとりのぞく機会でもあります。
「妊娠と分つたら早くツベルクリン検査とレントゲン検査を受け、病気にかゝつていると分つたならば早く治しましょう。」
ーレントゲン検査!いいの??現代ではできるだけ避けるよう言われますね。現代はCTでも病気をみつけられるからでしょうか。医学の進歩を感じます。
私の経験ですが、第一子妊娠7か月の時、発熱と腹痛が続き1件目の病院で別の病院へ行くよう指示され、2件目では整腸剤をもらい、3件目ではまた別の病院を紹介され、4件目では盲腸かもしれないがレントゲンNGなので切ってみましょうといわれ、5件目でCT検査してもらい腎盂腎炎と診断され、漢方で完治しました。この時ほど医者は全能でないこと、すっきりしない場合は第2オピニオン、第3オピニオンを求めることも大事だと痛感しました。そしてなにより現代の医療技術にも感謝しました。
次に「育児の心得」というページがあります。
こちらも気になるところをピックアップしていきます。
「母乳がでない時は、牛乳や乳製品で育てます。」
ー 粉ミルク、ではなく牛乳だったんですね。
「お乳」にはかわりないですが、やはり栄養状態は現代の赤ちゃんのほうがずっとよさそうですね。そういえば、「はじめてのおつかい」というベストセラー絵本でも、ママが「赤ちゃんにあげる牛乳がないの」というシーンで物語がはじまりますよね。あれは昭和52年4月初判ですが、作者の育った時代を反映しているのでしょうか。現代の様な母乳に近い成分の粉ミルクが作られるようになったのは80年代に入ってからの様です。2019年には液体ミルクが日本でもやっと許可されましたね。おでかけに便利だと思います。
「生後4.5か月になつたら、果物や野菜の汁、重湯などからはじめて、おまじり、つぶしがゆ、半熟卵、煮魚などにうつりましよう。」
まず、「おまじり」って何?となったのでしらべました。
重湯(おもゆ)は米1に水10の割合で煮て汁だけをこし取ったもの,〈おまじり〉は全粥1に重湯9の割合にしたもの (世界大百科事典より抜粋)
若干離乳食の開始時期が早いですね。現代では果物や半熟卵などは与えるんのに慎重な印象です。アレルギーに関する記載はいっさいありませんでした。離乳食は楽しんでいる人は別として、めんどくさく感じるママは手抜き、レトルトで全然OKだと思います。ちゃんと成長してるのであれば全然食べてくれない・・・と悩みすぎなくても大丈夫。ちなみに我が家は子供2人今のところスクスク育ってますが離乳食たべませんでした。
「着物はゆるやかに着せ、時々部屋をあけはなして、新鮮な空気に親しませてください。」
ー着物、という部分が時代を感じさせますね。おそらくただの「着るもの」という意味なんでしょうが、それを「着物」とまだ表現できた時代なのかなと思いました。現代で「着物」といったら着付けに手間のかかるあの着物が頭に浮かびますよね。新鮮な空気に親しませる、という表現も好きです。
「生後一カ月にもなつたら、日なたぼつこから始めて、日光浴をさせましよう。くる病はおもに日光の不足からおこります。」
ー 2020年4月現在、新型コロナウィルス感染拡大防止のため、たくさんの人が自宅で自粛生活をしています。日光浴不足による「くる病」が気になったので調べました。※こちらの記事は医療・医学専門ではありませんので、気になる方は必ず専門医にご相談ください。
くる病は、骨がうまく石灰化できずに柔らかくなる病気です。そのため、骨の成長が遅くなりますし、つかまり立ちや独立歩行をするようになってから下肢に負担がかかると、骨がO脚やX脚に変形することから気付かれることもあります。(http://medicalnote.jpより)
やはり日光って大事なんですね。こんな時ですが、人の少ない場所をえらんで散歩したり、ベランダで新鮮な空気や日光浴を楽しめるようにしたいですね。
「そいねのくせは、母子ともに安眠できませんからやめましよう。ひとりでねるくせをつけると目がさめても1人でよく遊んでいるようになります。」
ー昭和33年のねんね事情は現代の欧米式だったんですね。
いつから添い寝がメジャーになったのでしょうか。
我が家も長男は生後7か月からひとりで寝かせてますが、母子ともに安眠、勝手に起きて一人で遊ぶ、というのはあながち間違いではないです。
「お乳の間隔に泣いたら、お湯か番茶を与えることはよいことです。」
ー 白湯にかんしては賛否両論みかけませんか?
現代アメリカ育児方式だと乳幼児期はお湯は一切飲ませないというスタイルなのでうちはあげなかったのですが、親・祖父母世代は白湯はあたりまえだったようです。番茶はカフェインが少な目なので赤ちゃんでもOKとしているようですね。ネット上でも白湯は飲ませるべきか否かというテーマの記事をよくみかけます。私自身は乳児期に白湯を飲んでます。子供達は飲まずに育ちました。
違いは・・・・わかりません(笑)
「こどもが泣いたら、よく原因をたしかめましよう。泣いたからといつて、すぐお乳を与えたり、抱いたり、おぶつたりするのはよくないことです。」
—平成27年度の母子手帳には以下の記述があります。
おむつの汚れ、空腹以外で赤ちゃんが泣いているときは抱っこして十分なだめてあげましょう。赤ちゃんはお母さんお父さんに抱かれると安心して泣き止みます。抱き癖がつくと心配する必要はありません。(育児のしおり:母子健康手帳平成27年交付)
息子が生まれて数か月後祖母の家に連れて行ったときに(子供からみてひいおばあちゃん)、「抱き癖ついちゃうよ」といわれたことがあります。
ひいおばあちゃんの世代からしたら抱っこしすぎは良くないというのがあたりまえの認識だったのですね。母子手帳にも書いてあるのだから納得です。
この辺りは今後も変わっていくかもしれませんね。ひい孫を抱く未来があったらもしかしたら常識が逆転している可能性だってあります。
育児まっさかりの時は大変でできるだけ手を離したくなるのに、離れたら離れたでもっと抱っこしたらよかったと思うのも事実ではあります。
「1歳半を過ぎたらお友達とあそばせましよう。(一部省略)大人ばかりのお相手や大人がこどもをおもちやにすることはいけません。」
ー 兄弟が多かった時代、ご近所との付き合いが今よりあった時代であれば子供同士であそばせる機会はもっとあったのかなと思います。保育園に幼少期から通わせるのであれば赤ちゃん期から同世代と接する機会がありますね。幼稚園から通わせる、となると支援センターなど通わないと同世代の子供と遊ばせるのは難しいのかな。少なくともお友達の少ない私はそうでした。1歳半のころって友達と遊ぶって様子はあまりみられないようにも思えます。「何歳になったら一緒にあそぶようになるんだろうね」なんて友達と話した記憶があります。個人差もあると思いますが3-4歳になると割と友達とごっこ遊びなんかしているイメージです。
「大人がこどもをおもちゃにする」というのはどういうことでしょうか。からかったりしない、ということ?なんだか意味深です。インスタでみる赤ちゃんおにぎりフェイスはNG?(笑)とにかくこどもの人権を尊重して真剣に向き合ってあげましょうってことですかね。具体例をききたいところです。
「ひとりでできるようにしましよう。例えば、こどもがころんでも自分でおきるように」
ー 転んだ時、「大丈夫?」と手を差し伸べるのか、「一人で起きなさい」とするのか・・・。これも人それぞれな気がしますが、
手を差し伸べれば他人にやさしくなり、見守ればたくましく育つような気がします。もちろん転んだ時の激しさにもよりますよね・・・。
激しく流血してたり頭を打ったりした場合は放っておかないですね。
「ひとりでできるようにしましょう」というのは、着換えとかトイレとか自立を促す意味で賛成ですが、例えの部分が予想外なポイントでした。
もしかして本当に転んだ時、というのではなく比喩的な意味で使っているのでしょうか・・・「人生において失敗したとき」のように(笑)
「親を困らせるようなこと、例えば、泣き虫、わがまゝ、引こみ思案などは、家族の扱い方が悪かつたゝめによく起こります。こどもを叱ることはむずかしいことです。叱るよりも導くようにしたいものです。」
—泣き虫、わがまま、引っ込み思案は家族の扱いが悪い、というのはなかなか痛いところをついてます。
「泣き虫」も「わがまま」も「引っ込み思案」もネガティブなワードですが、「感情豊か」「自己主張ができる」「慎重」ともとれますよね。
この部分はたしかに親を困らせることは多いのですが、もうしょうがないのかな、子供ってそんなもんだとも思います。近年だと発達障害やグレーゾーンなどよくきくようにもなりましたが、おそらく育て方を否定する風潮は昔にくらべ減っているのではとも読み取れます。
後半の「叱るよりも導くようにしたいものです」は激しく同感です。
ついつい叱ってばかりですが・・・・。
この先は今回の記事を書いてみての自分の感想です。短いものですが、楽しんで読んでいただけたら投げ銭していただけると嬉しいです。
7.最後に
ここから先は
¥ 150
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
