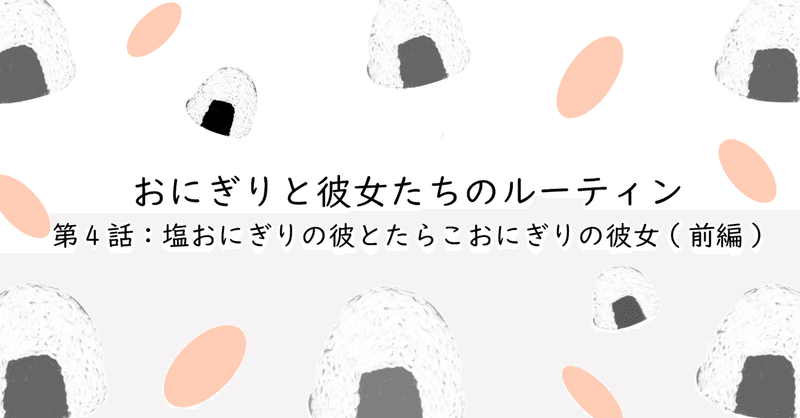
連作短編小説【おにぎりと彼女たちのルーティン(全4話)】第4話〈前編〉:塩おにぎりの彼とたらこおにぎりの彼女
🍙第1話『うめぼしおにぎりの彼女』はこちらから
🍙第2話『ツナマヨおにぎりの彼女』はこちらから
🍙第3話『おかかおにぎりの彼女』はこちらから
■第4話〈前編〉:塩おにぎりの彼とたらこおにぎりの彼女
7:00 起床
7:10 たらこさんのお世話
7:40 ストレッチをしてニュースをチェック
8:00 朝ごはん(おにぎりとみそ汁)
8:30 昼用のおにぎりと漬物とゆで卵を巾着に詰める
8:45 身支度
9:00 出発
朝は苦手だ。
だからといって夜が得意なわけでもないけど。
「たらこさん」
よろよろと立ち上がってカーテンを開けている間に、彼女がカーテンの裾を噛んで引っ張る。
「やめてください」
好きなデザイナーのセカンドラインで作られたこの白いカーテンは、よくよく見ると薄い鉛筆のタッチでお米粒がびっしりと描かれている。集合体恐怖症の人にはおそろしい一枚だが、主張しすぎていない控えめな面白さと、なによりほどよく食欲が湧いてくるというところが気に入っている。
朝ごはん用のお米は前日の夜にセットすることにしている。一気に大きめのおにぎりを5個作り、うち3個は冷まして袋に入れて、お弁当代わりにする。九州の実家では土鍋で炊いていたが、男の独り暮らしではそうはいかない。
「ねえたらこさんってば!」
やや鋭い声を浴びせると、彼女ははっとしてこちらを向いた。三角形の両耳をピンと立てている。今聞こえましたと言わんばかりの表情でこちらを一瞥して、朝ごはんの催促をするためにそろそろと寄ってきた。
彼女と暮らし始めて半年になる。実家では長らく大型犬を飼っていたが猫を飼うのははじめてで、慣れるまではお互いに苦労が絶えなかった。僕の両手は蟻の手足ほどの小さな穴ぼこと擦り傷だらけになったし、彼女は彼女で円形脱毛症になったりもした。
特にはじめましての日のことは今でも脳裏にしっかりと焼き付いている。
彼女は職場の近くにある歩道橋の下にいた。小さな空き箱に入っていて、箱の正面には几帳面な細い字で〝よろしくお願いします〟とだけ記されたメモが貼られていた。
「これは典型的なやつだ…」僕は無意味にそう呟いて立ちつくした。これまで絵本やアニメやドキュメンタリーなどで目にしていた捨て猫のパターンとまるっきり同じだったからだ。独り暮らしで急な出張も多い自分が無責任に手を出せる相手ではないことは明らかだった。だからといって時間帯によっては車の通りが多くなるこの場所に、いつこの箱からひとりでに歩いてゆくか分からない子猫を放置することは気が引けた。そして奇しくもその日は外回りもなく早めに社を後にしていた。僕は先を急ぐべき用事も言い訳すべき重大な理由も持ち合わせていなかったのだ。
ううむ。唸りながらしゃがんで箱の中をよく見てみる。子猫はとにかく眠たいんだと言わんばかりに無防備な姿で寝息を立てていた。そのお腹は薄桃色をしているせいかまるで胎児のようだった。ふと先日まで同じ職場で編集者をしていた後輩のことを思い出して胸が締め付けられた。妊娠していることに気がつかずに普段通り外回りを続けていて、突然出先で倒れたのだ。幸いお腹の子は無事だったが、緊急入院をした。交際している相手はいるらしかったが結婚の予定はなく独り暮らしだったので、退院後は実家に戻り、落ち着いてから在宅勤務に切り替えたばかりだった。
順風満帆とは程遠いその状況に僕は居ても立っても居られなくって、遠隔でお見舞いをした。画面越しとはいえ久しぶりに見る彼女はすっかりやせほそっていて、〝悪阻がひどくてなかなかごはんが食べられないんです〟と言いながら力なく笑った。
「でも、子どもがお腹にいるって不思議と頼もしいんですよ」間髪入れずにそう言った彼女はすでに母の顔をしていた。母の顔になるってどういう顔になることをいうんだろう、と子どもの頃本でよく読むそのフレーズに首を傾げていたけれど、まさか大人になり画面越しの後輩から教えてもらえるとは夢にも思っていなかった。
人生なにがあるか分からない。
テレビ電話を終話してパソコンの画面をそっと落としてから、腹の底でしみじみ思ったのを覚えている。目の前のこの子猫の母親は、どういう顔をしているのだろうか。ふとそんなことを考えてみて、いやいやそんな場合じゃないぞと首をふった。
たらこという名は、最初に目に入ったピンク色のおなかから名付けた。
心の葛藤を繰り広げる僕を尻目に、彼女はそんな状況下にいながらもおなかを出したまますやすやと眠りつづけていたのだ。箱を持ち上げても気持ちよさそうにくーくー寝息をたて、そのたびに薄桃色のおなかが膨らんだり萎んだりする。その薄くおだやかな桃色はどちらかというとゆでたばかりの鶏のささ身に近かったのだが、たらこにしたのには理由がある。なんといっても僕はおにぎりが好きだから。どうせならおにぎりの具にぴったりの名前にしたかったのだ。
たらこがはっきりと目覚めたのは動物病院の待合室だった。それから震えながらも一通りの検査と予防接種を受け止め薬をもらったあたりで、とんでもなく深く僕の左手を噛んだ。親指と人差し指の間に鋭さを差し込んだまま、思い切り顔をうずめている。たとえ小さな牙だとしても、深さが出ればそれなりにとても痛い。それまでは大人しく従順だったからこそ、僕は飛び上がるほど驚いた。歯を立てる瞬間の彼女の顔は忘れられない。気持ちが良いくらいに勇ましい表情をしていた。もちろん猫なので眉毛なんてないけれど、もしも書き加えるとしたら眉尻は明らかに左右とも外側へ上がっている凛とした弧の字型だっただろう。
「たらこっ」
それは始めて彼女の名を呼んだ瞬間だった。ほとんど叫んだと言っても過言ではない。
先生は苦笑しながら傷を消毒しつつ、今後について分かりやすく説明してくれた。そうして雄か雌かの判別もできない僕に、先生はぼそっと「女の子ですね。うん、生後1か月くらい」と言って、診察券にある性別マークに印をつけた。そうして受付のお姉さんから初心者用のしおりを授かって帰路についた。
帰宅するとすぐに、帰り道のペットショップで一通りそろえた子猫用のグッズを取り出し、定位置とおぼしき場所にセットしてみる。そうしてやっと一息ついてたらこを見やると、彼女はケージの中でぎゅっと丸くなって眠っていた。ピンク色のおなかをもう一度見たい衝動に駆られたが、配慮してそっとしておいた。僕が同じ立場であればそうしてほしいと思ったから。
翌日の朝、出勤してまず編集長に報告をした。
「昨日子猫を拾って、そして飼いはじめました」
意識していなかったが困っているように映ったらしい。
「飼い主探してるの?」よく通る声で彼女は言った。「それならすぐに広報するけど」といういつもながら頼もしすぎるお言葉をいただく。
「いえ、一応家もペット可で問題ないのでこのまま飼いつづける予定です」
「予定?」
怪訝そうに片眉があがる。
「いえ、飼い続けます」
僕はすぐに訂正した。
満足げに深く頷く。
猫好きな彼女は猫に囲まれて育ったというが、一人暮らしの自宅では仕事が忙しい為飼っていないとのこと。〝うらやましいわ〟と、感情を押し殺すようにして彼女は言った。心底うらやましいのだと分かった。
彼女はこの出版社でも特例の出世を果たした敏腕編集長で、何もかもが規格外だった。いつも10件以上の案件を同時進行しつつ5部署を統括し、ひと月に3つの新企画を発案している。かつ、人を育てる能力も高くて、彼女の背中を見ながらめきめき力をつける社員は数知れず。まわりにはいつも、彼女を慕う右腕や左腕がごろごろとしている。人の何倍もの仕事量をこなしながらいつも颯爽としていてハツラツとしている。
〝男性ホルモンを適量打ってんのよ〟とあっけらかんとして言う彼女は、女性性と男性性の良いとこどりをし続けたいと豪語しているし実践している。
「それぞれを手に入れて、然るべきときに発揮できていたら最強でしょ 」
ツヤとコシがある長い髪をかき上げて、不敵に笑う彼女に勝てる者はいない。どんなクライアントも笑顔で白旗をふる。
同じ船に乗ればおそらく見たこともない壮大な景色を見ることができると本能で感じるからだ。
この社内で彼女だけが、僕がゲイであることを知っている。
別に隠しているわけではないが好き好んで話すことでもない。僕は外見では気づかれにくい、と歴代の彼氏全員が口をそろえて言っていた。といっても4人ほどだしパートナーがいない時期のほうがずっと長い。仕事柄、人にまみれているというのも関係しているが、僕の根っこは元々淡白なのだと思う。男女問わず、必死になって誰かと関係を結びたいと思うことは早々ない。しかしこの編集長だけは例外だった。
船長。
心からそう思う。
代表取締役社長は別にしても、入社当時から彼女は常にトップだった。彼女が舵をとるこの船は、出版社という肩書を持つ海賊船だ。綺麗ごとだけではないこの世界を悠々とかき分けて進んでゆく。
「名前は?」
突然はっきりとした声で彼女が尋ねた。僕がまた一人で妄想をしているのを察したようだ。
「たらこです」
ふん、と鼻を鳴らす。これは愉快だというサイン。
「良い名前ね。おにぎりにぴったり」
僕のおにぎり好きは社内でも有名だ。一時期は三食おにぎりだったこともある。
入社して7年。僕らが出会ったのは彼女が編集長になって2年目の春だった。部署によって全く顔を合わせない人物もいて、我々はその類だった。芸能関係の出版物を主に扱っていた彼女と、辞書部にいた僕らには物理的にも離れ孤島ほどの距離があった。それがお互いに今の部署へ異動になって5年の年月が経つ。会社の意向により余計な経費を削減するため精鋭の部署選抜となったことが異動の経緯だ。社内には辞書部のような孤島はほぼなくなり、大陸がいくつかという状況になった。そして今なおその大陸を統括し続けているのが彼女なのだ。
「2週間前までに言ってくれたら1週間くらいは面倒見れるから。何かあったら声かけなさいね」
「え?」
「猫。たらこちゃんのこと。急遽家を空けることなんて、大人ならあるでしょ」
そう言い残して颯爽と去ってゆく後ろ姿を見送りながら、あんな大人になりたいと齢33にして心底思う自分がいる。
その日の帰り道、なんとなく靄がかかっている脳みそに違和感を覚えた。何かを思い出せそうだが思い出せず、忘れたわけではないが忘れかけている何かについて思いを巡らせる。温暖化が進むビル街の初夏は、去年よりも確実に数℃上昇した外気温をなだめるかのように生ぬるいビル風を吹かせていた。申し訳程度に植えられた街路樹は心なしか弱々しい薄緑色をしている。
ううむ。なんだろう。たらこのことかな。検診は先週受けたし異常もなかった。家に近づくにつれ絶え絶えとなる頭を振りながら帰宅する。まずポストを開けるとそこには白い封筒が1通入っていた。青い万年筆の文字が懐かしく、右肩上がりで踊っている。
「これだ」
僕は大きめの独り言をつぶやいた。
手紙の主は姪っ子だった。13才年の離れた兄の子で、たしか今年22歳になる頃だろう。
中身は、祖父の17回忌についてだった。
〝しお兄ちゃんはきっと忘れちゃうからお知らせするね〟と、まだ少女だった彼女はそう言って笑ったのだった。手紙が好きな子で、当時も2人で手紙を書く遊びをした。
実家にいる祖母は、なんでも感覚で生きていた祖父とは正反対の理系タイプだった。理にかなったことを穏やかに遂行するのが彼女のやり方だった。祖父が亡くなったあとの集まりは各個人に任せるけれど、17回忌だけは必ず親族一同集まって、自身の終活について話し合う場を設けてほしいと言っていた。
親族は総勢30名ほどで従妹も多かったが、不思議と小さな子どもは姪一人だった。それももう成人しているし、その下の代に子どもはいない。
姪っ子と最後に遊んだのも手紙あそびだったなあと、玄関の扉を開きながら思い返す。それぞれ架空の人物に変身して、それぞれに手紙を書き合うというシュールな遊びだ。姪が思いついた。たしか僕は孫悟空で、姪は歌姫だった。
「時空を超えた二人だね」と僕が言うと、彼女は生え変わったばかりの前歯を見せながらにっこりとした。
手紙はその場で交換せずに、きちんと切手を貼って住所を書いて、ポストに投函するというところまでがルールだった。
当時18歳だった僕がなぜそのキャラクターをチョイスしたのか全く覚えがないけれど、僕は孫悟空にはなれず、彼女だけが本物になった。
リビングの扉を開けるとたらこがサッと部屋を横切るのが見えた。今日もお出迎えはないのですね…。分かっていながらもしゅんとして後ろ手に扉を閉める。きょろきょろと辺りを見回しながら奥へ進むと、カーテンとソファの隙間に消える尻尾の先が見えた。
「めす猫はおす猫に比べて甘え下手な傾向にあります。無理に抱き上げたりかまったりしないでください。それが通常運転だと思って。距離が縮まらなくても、必要以上に自分を責めたりしなくていいですからね 」
初めての動物病院で、生まれて初めて親指と人差し指の間を思い切り噛まれた僕に、医師は優しく言った。
「よく言えばクールなんですね。クールビューティーだ」 と、心なしかハイになりながらふざけて返した僕に彼はほっとしたように肩をすくめ、
「もちろん個体差はありますが、特にめす猫は逞しい男性に懐くパターンが多いです」と言った。咄嗟に、口が滑ったと言わんばかりの表情をして下を向く。僕が逞しい男性に見えないことはその場の誰もが察する事実だった。しかしもっと深いところを先生は気づいていたのだと思う。稀に、何も言わずとも僕の内側、つまり同性愛者であることを察する人がいる。この推察こそ偏っているようでもあるが、そのほとんどが同じ境遇であることが多い。それから先生は静かに立ち上がり、そばで控えていた助手の男性に短い指示を出すとやや硬い笑顔を残して奥へと消えた。
僕には男性女性という定義が未だに分からない瞬間がある。そして自分が本当はどういった分類に所属しているのか、考えれば考えるほど分からなくなるのだ。逞しさってなんだろう。逞しくないってなんだろう。僕の中には世間一般的にいう男性らしさはきっと乏しい。だからといって世間一般的にいう女性らしさが豊富かというとそうでもないと思うし、一体そもそもその〝らしさ〟とは何なのだろう。〝世間一般的〟という尺度だって変わりつつある。この世界は分かりやすさを求めて分類することが多いけれど、一人一人を全く同じ枠にはめて定義付けすることはできないしする意味はない。こんな風に一人でぐるぐる考えることが増えた。これらは批判ではなく、もはや謎解きに近いと感じている。
それから1カ月ごとの定期検診を経て、たらこは問題なくすくすくと育っている。もはや子猫の面影はなく、まさにクールビューティーそのもののすっとした表情で僕を見やっている。
性別が関係あるのか個性なのか分からないが、よく耳にするような家中が傷だらけ、だったり、高い場所へ上りたがり降りられなくなる、などのにゃんこ事件に遭遇することはなく平凡な日々が過ぎていた。
17回忌の日程はちょうど2週間後だった。正直気が重かった。
姪と久しぶりに会えることには心踊ったが、実家には心が通じ合えない伯母がたくさん住んでいる。そのことに思いを馳せると、踊った心は一瞬で奈落の底に引きずりこまれるようだった。折しも帰郷するのが月の中頃であることも、後ろ向きなこの背をもう一段階深いところに押し沈めた。
ほとんどの女性には月に一度の生理がありその前後で心身に何かしらをきたす生理現象が訪れることを僕は知っている。実はそれに似ているものが僕ら男性陣にもあることはあまり知られていない。個人差があることと、関連づける事象が少ないので、単なる体調不良からくる心の不調だと思われることも多い。僕は自分にも月に一度やってくるその不調を把握し分析することでなんとか飼いならしたくて、毎月手帳に症状を書きつけることにした。そしてそれが一定の周期の波に乗っていることと、おおよそパターン化されていることから、女性のそれに当てはまる現象なのではないかと思い至った。
女性の場合にはPMSというらしい。月経前症候群。もちろん男に月経は来ない。この時点で推測は破綻しているし、「今日僕PMSなんで体が重くって」なんて言った日にはまわりの女性陣から袋だたきに合うことは目に見えている。しかし僕の症状はPMSにかなり酷似していた。
念のためにうつ病も疑って心療内科を受診してみたがこちらは違った。〝これは共存する必要があるぞ〟と清算待ちのベンチで、手帳を開きながら決意したことを覚えている。ひらめいた共存法は、目の前の動作に夢中になれることを見つける、だった。俗に言うマインドフルネスというものだ。
その時の僕に心当たる、自分のマインドをフルネスさせてくれる行為は、おにぎりをにぎることだった。
炊きたてのご飯を丼ぶり茶碗に取り分けて、濡れぶきんをかけてから粗熱をとる。小皿に塩を入れておく。岩塩などではなく、細かくてさらさらなタイプが好ましい。それから小さじ1杯分を丼ぶり茶碗のご飯にふりかけ、しゃもじで切るように混ぜ合わせておく。こうすることで最低限ムラのない仕上がりにすることができる。
ご飯の粗熱がとれたことを確認して、片手を軽く濡らす。水で濡らしていないほうの手で塩を小皿からひとつまみだけとって、両手のひらへ落としこすり合わせて馴染ませる。
そうして手の中にすっぽりと収まる量のご飯をすくって、ここからは無心だ。お米を潰しすぎずしかししっかりとまとまり合う塩梅で、三角形を作り出していく。1つ握り終えるごとに、濡れぶきんで手を拭きながら進めるとうまくゆく。
精神統一にも近しい、神聖な行為。心からそう思っている。
月の中頃、ちょうど3週あたりにこれを行ない、生み出した塩おにぎりたちをラップで包みタッパーに入れて、それぞれの用途に合わせ、 冷蔵組と冷凍組に分けて保管する。
そういえば子どものころに夢中になっていたマインドフルネス的行為は刺繍だった。家にある布の切れ端や画用紙に糸をさして模様を作りだすことがとても好きだった。誰にも気づかれないくらいにそうっとワンポイント程度を縫うのが数少ない僕の趣味で、それは過酷で雑多な日常の騒音から僕が僕を逃がすことができる唯一の行為だった。
兄に見つかって禁じられたことで、場所を替えひっそり行なってきたもののすっかり後ろめたいものに変わってしまった。
ちょうどその頃、塩おにぎりをつくる機会を得た小学生の僕は堂々と台所に立ち好きなだけ塩おにぎりをにぎりつづけた。祖母や伯母など大人の数が多い家だったこともあり、褒められるくらいだった。兄は何も言わなかった。ただ時々何か言いたそうにして、大人たちがまだ帰宅しない静かな午後のダイニングテーブルに腰かけて僕の様子をじっと眺めていたことがある。多少誇らしい気持ちで握ってもいたので、兄に言葉をかけてもらえることを期待したけれど、その日の彼はただずんぐりと育った熊のように黙ったまま、大量に出来上がる塩おにぎりを静かに見つめていた。
塩おにぎりはなんにでも変身できる。もちろん冷蔵チームはそのまま食べることが多いが、冷凍チームは解凍したあと、新しいメニューとなって息をふきかえす。にんにく醤油を塗って焼きおにぎりにしたり、
味噌をつけて焼きのりを巻いたり、胃がもたれた日のお茶漬けにもなる。
一人暮らしが長くなるとさらに、控えめで頼もしい彼らの存在に励まされ支えられている自分に気づくのだった。
帰省の日取りをWEB上の共有カレンダーに入力してからすぐに編集長へ電話をした。
「すみません。今日の今日で申し訳ないのですが…」
「わかったわ。いつなの」
「まだ何も言っていませんがありがとうございます。2週間後の金曜日から日曜日までです。最低2泊の予定ですが念のため3泊でお願いしたいです」
「了解。それがいいわ。調整しておく。木曜日の夜に迎えに行くからひととおり準備しておいて」
彼女の勘はテレパシーの域である。要領良く話が進み、まとまり、決定されるのだ。
ほっとしてカーテンとソファの隙間を見たがそこにたらこの影はなく、いつの間にやら僕の足元に寝転がり靴下のにおいを熱心に嗅いでいた。
当日の朝、約束の時間きっかりに彼女は現れた。そこからは驚くほどスムーズだった。準備に不備がないかぎりぎりまでそわそわしている僕をよそに、編集長はひととおり必要な猫グッズとたらこ専用グッズ、たらこの取扱説明書的なメモ紙とを受け取って、颯爽と帰り支度を始めた。
たらこははじめから彼女の猫であるかのような顔をしてうっとりと抱きかかえられ、ケージに入れられるとすぐに体を伸ばしてくつろいだ。
飼い主のことなど瞬時に忘れ去ったようなその様子にダメージを受けていた僕を見かねた編集長は帰り際、「大丈夫よ。正真正銘のツンデレよこの子」と言った。
「知ったようなこと言わないでください。デレは今のところ食事の直前だけです 」
彼女は愉快そうに大きな口を開けて笑うと
「ツンとデレの配分は飼い主の力量。つまりあなた次第でしょうけど。じゃあ3日後にね」そう言って扉をしめた。
残された僕は、予定していた後ろ髪を引かれる思いを体験することはできず、代わりに編集長の言葉を握りしめたまま飼い主としてレベルを上げる必然性をしみじみと痛感していた。
それから力なくうなだれて時計を確認し、空港へ向かうためのタクシー専用ダイヤルに電話をかけた。
実家までは飛行機で片道1時間半、新幹線では約6時間かかる。最低でも2泊3日いてほしいというのは祖母の指定で、どうしても仕事の都合がつかなかったり事情がある者はもちろん免れるが、「免除されるには事情を細かく説明しなくちゃいけないのと、質問攻めにもあうのよね」と一番年が近い叔母さんは半分愚痴のように電話口で言っていた。
彼女は父の妹だ。8人兄弟の7番目だった父以外、皆女性である。完全なる女系の家系で、女性は100歳近くかそれ以上まで長生きをし、男性は病気や事故で早死にするケースが多い。実際に、父は僕が小学生の頃に病気で他界した。母は僕が物心ついた頃に肺炎をこじらせて亡くなった。父方の一族の血を少しでも分け与えてもらえたら、母はもっと長生きができたのかもしれないのにと、母の葬式の日、理不尽に祖母を睨んだ覚えがある。
祖母は忙しく動き回っていて少しも気づいていない様子だった。かつ、完全に理系の彼女がこんなファンタスティックな恨みごとを察することなどなかっただろう。祖父だけが気づき、嫌がる僕を後ろから羽交い締めにして膝に乗せてくれた。
祖父は一族の男性陣の中で唯一、祖父と呼べる歳まで無事に生きていた。見上げるほど大きな彼の胡坐をかいた膝の上は、ちょっとした小舟のようでもあった。
「分けてあげられたら、よかったのになあ」
ふと頭の上からふってきた祖父のその言葉は、完全に僕の心を見透かしていて、ぞっとしたのを覚えている。しかし祖父の両腕はがっちりと僕をつなぎとめたままだったので、顔を上げることも逃げ出すこともできなかった。それも相まって、これは神さまの声なのかもしれないとさえ思った。
その後も祖父には、僕が言葉にしない言葉が聞こえるようだった。兄の漫画の影響もあって、祖父に対してエスパー疑惑をもった時期さえある。
母が亡くなったのをきっかけに、父は都心のマンションを売り払って実家に里帰りした。仕事は僕と兄が落ち着くまでリモートワークでこなし、問題ないことを確認してから職場の寮で単身赴任することになった。父にとって実家が居心地の良い場所でないことは明らかだった。祖母や祖父、妹である叔母と仲たがいすることはなかったが、問題は伯母たちだった。6人の伯母たちは、うち4人が未婚でうち3人がまだ実家に住んでいた。昔ながらの旧家で、庭も含めると600坪はある。しかしそれはあくまで敷地の話で、居住スペースはその三分の一だった。それでもかなり広いが、大の大人が7人と男児2人が常に一つ屋根の下にいるには物理的にも窮屈だったし、何より伯母たちと父の不仲は救いがたいものだった。
単身赴任について父から相談を受けたとき、僕も兄も大きく頷いた。せめてもの救いは、伯母たちが子どもの僕らには当たり障りない態度をとるということだったので、どう考えても賢明な判断だった。父は週末に帰ってきて僕らを外へ連れ出した。男三人水入らずで過ごすその時間が当時最も幸せなひとときだった。
しかしその後父の病が分かってからというもの、幸せな思い出が更新されることはなかった。父は過労で倒れ、それを機に容態が悪化して息を引き取った。半年の闘病生活の末のことだった。
これは決まっていたことなんだと、僕は僕が作り出した神さまに言ってもらうことでなんとか平常心を保っていた。〝猶予を与えてくれてありがとう〟最期の日に神さまにお礼を言ったことを覚えている。
飛行機に乗るのは久しぶりだった。
前回帰ったのは30歳になりたての年だったので、3年ぶりだ。
当時祖母は僕が30歳になったことを驚くほど喜んでくれた。理由は分かっていたが分からないふりをした。無事に年を重ねることや節目を迎えることが当たり前ではないことを、子どもの頃から痛いほど学んできた。実体験として父と母の存在が根底にある。
祖母や叔母が、一族に新しいメンバーと新しい命が加わることを待ち望んでいることは明らかで、それを背中にひしひしと感じながらも触れないでいることについて募る後ろめたさが年々重くなる。帰郷することが億劫なのはそのせいもあった。
17年前がついこの間のような気がするのだから、3年などあっという間だと思う。
祖父は亡くなる直前、僕がこの世に生まれ出たその瞬間に〝その内側に気づいた〟のだと、耳元で打ち明けてくれた。
祖父が言う内側というのは、僕の性対象が男性であることだと瞬時に察した。うなずいた僕をたしかめるようにのぞきこむ彼の目は半透明で、この世のものではなくなりかけていることを物語っていた。
「本来、定義なんてものは宙ぶらりんでいい。どんな姿でもどんな言葉でもどんな価値観でも、人が人にジャッジを与えることなんて許されとらんからだ。それはな志穏、他人だけじゃない。自分自身へもそうやぞ」
祖父の声が突如、父の声に聞こえた気がした。さっきまで息も絶え絶えだったのに、至極力強く野太いその声色に、僕は祖父の最期がやってきたことをはっきりと悟った。
〝最期〟は黒い影になって、ゆっくりとのっそりと歩みを進めてこちらへやって来る。そしてベッドの縁にたどり着くと、おもむろに祖父と僕の間に分厚いカーテンを引き始めた。
「待ってほしい!」
いつの間に発したのかわからなかったが、 僕は強い声で言った。
〝最期〟はぴたりと動きを止めてこちらをじい、と見た。影色をした四本の四肢が膨らんだり縮んだりしている。どこにも名前のある色はないし実態もない。だが確かにそのように動くのが分かった。それは呼吸だった。祖父の呼吸に合わせて¨〝最期〟はゆりかごのように体全体で揺れている。満ち引きにも似たその動きが心なしか、か細く小さくなっているのが分かった。反復の幅が狭くなり、弱々しくなる。
気づけば僕は僕の内側を詳細に、祖父に打ち明けていた。そして祖父の目が完全に濃度を失うまで話し続けた。
僕が好きなこと嫌いなこと。
僕が好きな人嫌いな人。
僕が好きだったこと嫌いになろうとしたこと。
僕自身が僕をどう思ってきたのかどう思っているのか。
祖父は話し終えるまでずっと、ほほ笑みを浮かべながらかすかに頷きつづけていた。
話し終えたころ、ほほ笑みとうなずきは止めずに目だけを閉じていた。
「…答えは、出たんやなあ」
祖父は聞き終えると咀嚼するようにじっくりとうなずいてから、絞り出した声でそう言った。
「変わるかも、しれんがな」
それらはもはや囁きのような音量だったけれど、祖父が渾身の力で発した声であることが分かった。もう呼吸をすることすら難しい彼は、 今一度大きく息継ぎをして最後のターンをするように何かを言った。もう声ではなくなったあぶくのようなその音は、たしかに僕の耳の骨に届いた。
「…でも、それでいい…」
その瞬間、体中の水分が感情をかたどって、奥から奥から瞼を押し開こうとしているのに気づいた。遮るために固く目を閉じる。目の前にいる祖父の両目が完全な形で閉じ終わるのを気配で感じた。ほほえんでいた口角は下がり、かすかな満ち引きの音も消えていく。
傍らでやりとりを見ていた〝最期〟がそろそろと動き始めた。だらりと下がった四肢を力なく持ち上げて、ずず、ずずずと僕らの間にカーテンを引き終えてゆく。
次の瞬間、しいんとなった個室で息をしているのは、僕一人だけとなった。
「ありがとう、ございました」
口をついて出てきた11文字の言葉が、僕の中を繰り返し繰り返し反芻しながら膨らんでゆく。向こう岸までうまく届くよう無意識で祈っていた。その頃には遠くのほうで、目には見えない遠くのほうで、〝最期〟が扉をそっと閉める音が聞こえた気がした。
その音を合図のようにして僕の瞼の門は内側から決壊し、体内の水分が一気に外側へ流れ出た。声にならない声を上げながら、僕は何度も何度も頭を下げた。
数年前、数か月前、数週間前、数日前までは存在していなかったその水分が、たしかな名と形を成して勢いよく溢れ続けている。
僕は崩壊したダムと化した自分の体に身を委ねながら、震える左手でナースコールを鳴らした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
