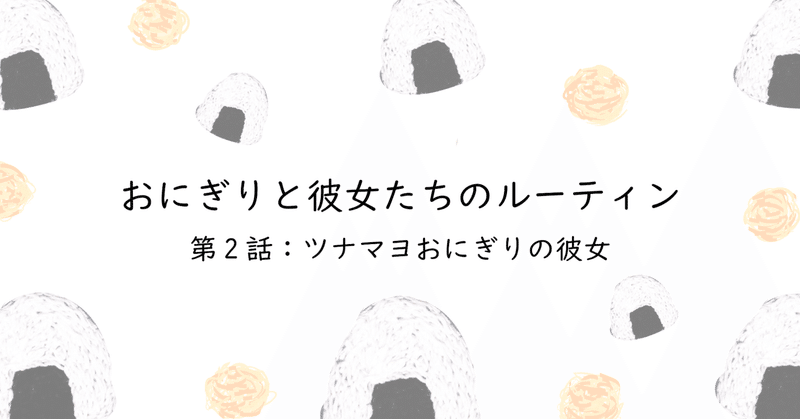
連作短編小説【おにぎりと彼女たちのルーティン(全4話)】第2話:ツナマヨおにぎりの彼女
■第2話:ツナマヨおにぎりの彼女
朝起きたら、まず鏡を確認する。
日によって顔のむくみ具合が変わるからだ。今のところ攻略方法は見い出せていない。休みの日には割とすっきりしているのに、仕事のある日はほぼほぼむくんでいる。ただでさえふっくらとしたほっぺたに上瞼のふくらみが合わさって、顔の大きさは1.5倍に助長されている。そう感じる。
「1.5倍は大げさよ」と、まだ実家に暮らしていた頃母は笑っていたけれど。
7:00 起床
7:15 朝食(たっぷりめ)
7:45 入浴
8:15 身支度
9:00 出発
朝の流れは大体決まっている。
大学卒業を機に不規則だったバイト生活に終止符を打ち、コールセンターの正社員となった。そうして実家を出てから3年が経つ。
10時出社はありがたい。その代わり退勤時間は21時なのだけれど、朝が弱い私には好都合だ。
仕事は楽しさこそないが可も不可もなく、日々は淡々と過ぎてゆく。そこそこ大きな会社の、〝よくつづけられるね」〟とまわりから心配され、ある意味一目置かれている部署で働いている。その為待遇は良い。持続可能な人材が最も尊ばれている、コールセンターのクレーム担当部。ありとあらゆるクレームを私のいる部署が全て一括して受け止めている。
「ゴールキーパーだと思ってください」社内研修の際に上司は言った。そしてクレームには2種類あることを教わった。
一つ目は、本当にその商品やサービスに不備があった場合。二つ目は、仮にその商品やサービスに不備があったとしてもそれほど当人の生活に滞りはないが、日々の憤りをぶつける捌け口とされる場合。
「圧倒的に後者が多いと思ってください」上司は静かな物腰で言った。〝一つ目と二つ目を見分けるのは容易ではない〟とも。
そのため、真摯に受け止めることは大切だが、責任の所在が明らかでないうちには状況確認に徹する。むやみに謝らない。謝らないことで責められた場合には、お手数をお掛けしたことについてのみ謝罪し、まずはお話をよくお聞きしたいと返す。
「大抵のお客様は、怒りをぶつけたいのです。この時間さえ惜しいのにわざわざ電話をしてやったんだ、謝罪から始めろ、という脅し文句をちらつかせながら。結局のところお客様がおっしゃる無駄になったであろう時間への対価について、こちらも時間で返すことが一番平和的な解決方法なのです」
上司はここで一度にっこりとした。そして、と続ける。
「一番大切なことは、親身になりすぎないこと」
その場の誰もが一斉に彼を見た。笑顔が張り付いたまま続く。
「お客様に感情移入しすぎてしまった場合、自身や会社の体勢について不条理を感じ始めるのは時間の問題です。なぜなら電話口でお客様が求めてくるのは、先ほど私が述べた時間を差し上げる解決方法ではないケースが多いから。求められることの多くは、社を上げて取り組まねばならないような抜本的な改善策の提示や金銭での解決だ。しかしそれらを私たちが提供することは不可能です。そのうち応えることができない自分には力がないと感じたり、聞き入れない会社に不信感が募る。自分はなんて仕事をしているのだろう…。最終的にそう感じることとなるでしょう。親身になったことで辿り着くのは大よそこのような負の思考だと思います」
そこまで一続きに言ってから彼は少しの間だけ口をつぐみ、やがてこの日最も通る声で話し始めた。
「会社が最も大切にしたいのは、〝この部署で働き続ける君たち〟です。お客様の身になること、初心を忘れないことはたしかに大事ですが決して飲み込まれてはいけない。そしてこれだけは絶対に忘れないでほしいのですが、〝君たちがいないことには、この会社は成り立たない〟そう言っても過言ではないのです。都合の良いことを言って都合の良い仕事をさせていると思うかもしれません。しかし、この会社のどの部署よりも、必要な仕事を任せている。これは絶対です」
彼はここで一呼吸置き、卓上にあったお茶のペットボトルを手に取った。まだあたたかいのか、啜るように一口飲んでから向き直る。
「お客様はたしかに大事です。私たちは元を辿ればお客様からお給料をいただいているようなものですからね。ですが、自身の時間に勝手な価値をつけていちゃもんをつける人間が、果たしてお客様と言えるのか…。
そんなことを頭の隅に置いて対応してほしい。この会社が最も遵守していること、それは質の良いお客様を一人でも多く獲得し、長くお付き合いできる関係性を築けるよう努力し続けること。そんな中でこの部署に求められることは、言葉は悪いがお客様の仮面をかぶった質の低い人間を振り分ける門番としての役割です。この発言は問題視されるかもしれません。しかしとても重要なことなのです。この部署は、選ばれた人材で構成されている。なぜなら会社側がどの人材よりも長くこの会社で働いていてほしい、必要だと思っているのだから。お客様の仮面をかぶった質の低い人間の捌け口になり事なき終えることなんて、早々できることではない。こういうとどこまでもハードルは高くなるかもしれませんし気を悪くするかもしれませんが…。要するに自己のマインドコントロール力に優れている君たちだからこそ、お願いしている仕事内容だということを分かっていてほしい」
そうして彼は傍らのお茶をもう一口だけ啜り、丁寧にキャップを締め、目の前にこつん、と置いた。それは燃え終わる手持ち花火の最後の火種のようにも見えた。
「あとは実務の中で感じたことや改善したいこと、困りごとがあれば私に相談してください。必ずいつでも話を聞きます。万一、私が不在の際や相談しづらいと感じた時には別部署の上長に相談することも可能ですので遠慮なく。繰り返しになりますが、 会社が最も大切にしたいのは、この部署で働き続ける君たちであることをいつも心に留めておいて下さい。その他質問があれば各自お声かけ下さい。以上で本日の研修を終了します」
彼はそういうと、3秒ほど首を垂れてお辞儀をした。薄くなった後頭部が露わになり思わず目をそらしたけれど、自分には合っている職場だと再認識したのを覚えている。
私には怒りの感情が欠如している。と時々思う。特に理不尽な事柄に対して。そう感じ始めたのは小学校高学年の頃だった。
3つ年の離れた兄がいて、彼は言葉を発することが苦手だった。そして彼はいつも遠くを見ていた。目を見ながら質問されれば、〝はい〟か〝いいえ〟で返答するけれど、彼自身が第三者に声をかけることはほとんどなかった。学校から何度も呼び出しを受けていた母は、学校側の勧めもあり兄に検査を受けさせることを決意した。結果は、発達障害とのことだった。
結果確認に家を訪れていた兄の担任教師は30代前半の黒縁眼鏡をかけたひっつめ髪の女性で、爪に甘噛みの痕があるところからしてあまり好きではなかった。
彼女は大げさに肩を落とし、「やっぱり」と言った。そしてそれを合図のようにして、兄の学校での様子を包み隠さず母に報告し始めた。いじめを受けているようだが原因はコミュニケーション不足の兄にあり、担任もいじめの内容に合わせていじめた側へ注意をしているが、シチュエーションを確認するとやはりいつも兄が返事をしなかったり輪に入らなかったり、そればかりかクラスメイトからの誘いや声掛けを無下に断っていることが引き金になっている。と言う。そのうち彼女はだんだんと勢いづいてきた。半分陶酔した様子の薄い唇から流れ出て止まらない言葉たちは、体裁よくあつらわれているものの、異臭がする腐った菓子のようだった。腐るということは、すさまじい勢いで歳をとっていくことなのかもしれない。人はこうして老いていくのだろうかと恐ろしくなった。それと同時に、黒ずんだ自己保身の盾から何度も突き出される、自分の兄を蔑む言葉の槍に、妹として耐えがたい苛立ちを感じた。
私はその時、彼女の目の前にある茶菓子をコーヒーカップごと蹴り飛ばしてやりたい衝動に駆られたが、母の表情を見てその気が失せた。下を向いてじっと聞いていた母は一見耐えているようだったが、よく見るともはや耐えることを通り越して、ほとんどあきらめていた。それはそれははっきりと。明確に。その目はどこにも何にも向かっていなかった。
一方担任教師は、すべては発達障害である兄が引き起こしたことだから自分に否はなく、これからもどうしようもないことを示し終わり、肩の荷がおりた、という顔をしていた。
私はその両者にぞっとしていた。
こんな思考がまかり通っていいのか、まかり通っていくのだ、ということを時間をかけて消化しようとしている自分の脳みそにさえ〝待った〟をかけることもできずその場に立ち尽くしていた。
兄はその頃、家の一番奥の突き当りにある自室で絵を描いていた。これまで一度も扉を開けたことがないので詳細はわからないが、2Bの鉛筆が〝しゃしゃしゃしゃっ〟と勢いよく紙の上を走る音が廊下まで聞こえていた。それは淀みがなく一定で、自室にいる兄の存在を感じられる唯一の音だった。私は無意識にその音から、彼の生存を確認していたのだと思う。
ふと、いじめとはどのようなスケールで行われているのだろうと漠然と思った。担任教師はことこまかに説明していたようだったけれど、いまいち理解できなかった。兄はどれを、何を、いじめと感じるのだろうと考えたとき、彼がこれまで父から受けてきた仕打ちについて思いを馳せた。あれに比べたら、ランドセルに黒いマジックで落書きがあろうと、ノートがびりびりに裂かれようと、兄の体に傷や痕が増えないことが、せめてもの救いだとさえ思えた。
心の傷は消えないとはよく言うけれど、しかしそれらは私の兄の鉛筆を止めることはできない。止まるときは大抵、父が帰ってきているとき。その時間が、おそらく私の中の最大の怒りを少しずつ少しずつ削り取っていったのだと、大きくなってから気づいた。
父は長距離トラックの運転手だった。月に3度ほどしか帰ってこない。お酒を飲まないときには普通の父親。飲めば恐ろしい戦車になる。その矛先はもれなく兄だった。父が気分よく話しかけても返事をしない兄は、一瞬で面白くないぬいぐるみに変わる。その時間だけ、兄の淀まぬ清流のような鉛筆の音が途切れた。兄の部屋に私が入らないのは、父が残した爪痕を、目撃したくなかったからに他ならない。
母は父に、兄の発達障害はもちろん、検査を受けたことさえも話していないようだった。事態を悪化させないための懸命な判断だった。
父と母の離婚が成立したのは、それから1年後のことだった。
母の友人に市役所員の方がいてしばらく遠方で働いていたがたまたまこちらへ戻ってきたのだ。母の幼馴染であり唯一本音をこぼせる人だった。父が兄へ行なっている暴力を知るやいなや、彼女は即座に法的な措置を下すための手助けをしてくれた。父が帰ってくる期間を狙って兄の部屋にカメラを設置し、回収した後に役員数名で兄の部屋の状態と身体の状態を確認した。全ては速やかで滞りがなかった。父は一度では聞き入れなかったが、十分すぎる証拠を突き付けられ、二度目の話し合いで受け入れたという。
母があきらめたものは数知れないけれど、母のあきらめ=受け入れることだけではなかったことが、私たち兄弟にとって大きな救いだった。
そうして私たちは、慣れ親しんだその街を出て都会へ引っ越した。父と接点のない場所で自由に暮らしたいという気持ちと、出入りの激しい都会のほうが目立つことなく暮らしていけるのではということでの選択だった。
新しい家はリビングが一番奥にある構造のマンションで、兄の部屋は玄関からリビングの間にある6畳一間になった。相変わらずほとんど口をきかずに、かつ高校は通信制を選択していた為ほとんど家にいたが、それが私を少なからず安心させた。玄関で靴を履くとき、淀みない鉛筆の音がする。それがもう二度と、理不尽に止められることはない。
それから数年が経ち、鉛筆の音はパソコンの作業音に変わった。カタカタとカチカチが交差する。兄が生まれて初めて母に物をねだり、数年分の誕生日をまとめてでいいからこれが欲しいと、雑誌の切り抜きを手渡したのだ。それがパソコンだった。
兄は高校卒業後、アニメ制作会社に就職した。いつのまにか履歴書を出し、いつのまにか面接を受けて、いつのまにやら内定通知が届いた。兄は依然として実家にいたし、仕事を得たからといってコミュニケーション能力が格段に上がったわけでもなかったが、私も私ができることをしなくてはと強く決意したのはこの頃だった。
職場には広大なカフェテラスのような場所があり、お昼頃になるとほとんどの社員が集まる。もしくは気分転換に外食をしたり、公園に出たり、断食だと言ってデスクで眠っていたりする。
クレーム担当の部署は社内でも最も日当たりの良い場所にあるが南側の一番端に位置する為、1階東側のカフェテラスからは少し離れている。そのためか、部署のある通路の廊下を挟んだ向かい側には専用の休憩スペースがあり飲料水と軽食の自販機が一台ずつ設置されている。休憩スペースの入口に扉はなく広さは8畳程度だが、全ての窓が大きいので広々とした印象だ。角の西側に面した窓から夕陽を眺めることができるところが特に気に入っている。昼間利用するときにはほとんど人はいない。お弁当を持参するメンバーが限られているからだ。私は大抵サンドウィッチかおにぎりを持ってくる。水筒には必ずあたたかい黒ウーロン茶を入れることにしている。主食がどちらでも相性が良い。かつ脂肪の吸収を穏やかにしてくれるという強力なおまけ付き。
数少ないお弁当持参組はもう一人だけいる。鈴木君だ。彼は入口から一番遠いはしっこの席に一人で座り、お弁当のようなものを広げて静かに食している。ようなもの、というのは後ろ側からはよく見えないからだけれど、蓋がついており、お箸入れを持参しているところから、おそらくお弁当なのだろうと推察する。私が食べ終わるころには、手帳かノートのようなものを取り出して、熱心に何かを書きつけている。
私はそれほど人を観察するタイプの人間ではないけれど、奇妙な人物であることに間違いはない鈴木君は興味をひいた。耳の下あたりまでに切りそろえられているさらさらの黒髪。前髪が長いので顔はよく認識できない。さらに黒縁眼鏡をかけているのでますます顔の全容は謎に包まれているのだけれど、ななめうしろから見た時の輪郭や骨格で、なんとなく整った顔立ちをしている気がした。革細工が好きなようで、革靴はもちろん、ベルトや持ち歩いている小物はすべて、上等そうな革製のものだった。どれも使い古されているものの、毎日丁寧に磨いているのか光沢がある。私は特別革が好きというわけではないが、このように手塩にかけて育てられている革製品を身近で目にすることは少ないため、目にとまるとじっと眺めるようになった。
鈴木君は、まるで気づいていないようだった。
それもそのはず。私は鈴木君のななめうしろ、いやほとんど後ろ側で、かつ1メートルほど離れた場所から彼を眺めているのだから。眺めている間に愛着が沸き、遂には彼の線の細いシルエットに対して、一日の食事はまさかあのお弁当だけなのではないかとお節介な心配をする始末だった。
鈴木君を含め、このクレーム部署には合計5人の社員がいる。研修時に10人だったメンバーはすぐに半分退職して、この人数に落ち着いた。受電枠は基本的に2人。平日は3人が出勤し交代しながら受電業務をしている。土日は受電枠が3人に増え、5人全員が出社する。土日の受電件数が多いことが理由だが、1件あたりの拘束時間も長くなるため、そのうち2人は部署内で事務仕事をしながら待機し、1件終わるごとに交代することになっている。派遣もバイトも先輩も後輩もいない。5人が全員同期入社で、その前にいた先輩方はみな部署異動した。私たちの一代前まで、一定の期間在職すれば部署異動が許される制度があった。先輩方はそのタイミングで一人残らず異動を希望したのだ。
そういえば私たちは全員が新卒というわけではなかった。過去に別の職種を経験したのちに入社しているメンバーが多い。年齢も境遇も違うが、特異な職種の中皆が同期入社ということでメンバー間の結束はそれなりに強い。しかしそれはあくまで仕事上でのこと。プライベートは白黒つける。無理やり親交を持たない。個々の時間を大切にする。それが暗黙の了解であり、私がこの職場を最も愛する部分でもある。このスタンスを堂々と取れる人間であることが、人材選抜の要であったのだろう。そして実際には5名の人員で問題ないが入社後に半分は脱落するであろうことを見越しての採用人数。研修内容や実務の配分についても、これまで会社側が苦労したと思われる部分に対する改善策が網羅されている。
平日のお昼時は、商品についての困りごとを含めた受電が多い。限られた時間の中、手短に済ませたい場合が多いので、本当に困っていたり止むに止まれぬ事情を抱えたお客様が増える。
この時間のお客様の声は貴重だ。そのため3名がフルで受電できる状態で待機するので、うち2名のお昼休憩は14時からになる。2名が不在となる14時からの時間帯は、11時から休憩を取っていた1名が残って受電する。この11時から休憩をとることを早昼というのだが、これは順番に回ってくる。
14時休憩のメンバーは、昼休憩までの時間が長いため、12時までの間に15分間の朝休憩というものを自由にとっていいことになっている。早昼のメンバーにはもちろんこの朝休憩がない。その分、1時間早く帰ることができる。これは早くお昼を食べることにより生活リズムが崩れるリスクを伴うことや、昼食後の勤務時間が長くなる点について、異動した先輩方が現役の際に上司に相談し、あっさりと通った制度だ。できるかぎり負荷を減らし働きやすい環境を整えて、一日でも長く勤続してほしいという会社の意向が揺らぐことはない。さすがに早帰りをした1時間分の給与までは支給されないため、21時までの勤務で問題ないというメンバーは自主的に通常の時間帯で働いていいという特別ルールも付与されている。
私が早昼当番になる日の帰宅時間は、その日の気分や体調で決めている。のだけれど、この日は20時に帰るぞ、と決めて業務の時間配分をしていなければ、気づけば20時30分ということは日常茶飯事である。
鈴木君はもれなく20時に帰る。
14時休憩組はお昼休憩が終わると、20時までの間にまた15分間の休憩を2度までとっていいことになっている。この時の時間設定は個人の自由であるので、なんとなく個性が出る。
14時から20時までを均一に等間隔で区切って休憩する者、時間を決めず適当に15分ずつとする者、そして私のように、夕暮れを感じられる時間帯に設定する者。夕陽を見ることができる大よその時間を行きのバスに揺られながら確認し、デスクに付箋で貼っておく。アラームをつけるまではないが、電話対応が長引いて逃した日は残念な気持ちになる。
これは私だけの楽しみかと思っていたが、鈴木君も似たような時間帯に午後の休憩を取っていることに気づいたのは入社してから半年ほどしてからのことだった。夕陽は向かいの休憩室からじゃないと見ることができないと思い込んでいたけれど、実は男子トイレの手前あたりにある小さな窓からも見えるのだそうだ。ある日その小窓から夕陽を写真に収める鈴木君を目撃したことで知ることができた。突然のシャッター音に驚いて立ちすくむ私に振り向いた彼は、少し罰が悪そうに
「今日の夕陽。特に良かったんです」
と言って、照れたように笑った。
この時の鈴木君は顔半分が夕陽色に染まり不思議な美しさを放っていて、私のほうが後ろめたい気持ちになった。
私にはコンプレックスが山ほどあるけれど、その中の大部分は肥満に関するトピックで占められている。ほぼ遺伝であることは母の体型から嫌でも自覚しているけれど、だからこそあきらめやらなにやらが混ざり合った複雑な感情に支配されてしまう。
これでも年頃になったら、メイクや服でなんとか実際の体系よりもほんの一回りほっそり見せることができるようになった。そのようにして少しずつでも印象を変えることができることを学び、実践してきた。食事もできるかぎり抑え、なにより間食を必死の思いでやめたことで数字の上では体重は落ちてきたけれど、体のラインはなかなか思い描くものまで到達できない。今ではなんとか〝ぽっちゃり〟と表現される部類に入っていると自負しているけれど、メイクやヘアセットに少しでも手を抜いたらその枠からはみ出てしまうかもしれない…暖色系の服を着たいけれど問答無用で膨張することを考えたらどうしても着ることができない…などなど。上げれば切りがないこまかな悩みは、満ちては引いてゆくさざ波のようである。
でも不思議とこれまで、その悩みのせいで生活に支障をきたすことや心の病気になるようなことは一度もなかった。根っから能天気なのだろうと高をくくっていたけれど、大学の授業でホルモンが関係していることを知った。
幸せホルモンと呼ばれるセロトニンやオキシトキシンが生まれつき豊富でかつ増やしやすいタイプの人間がいて、自分はそれに該当するようだった。それでも生活習慣によっては減少し鬱を発症する可能性さえあるということ。どうやったら増えてどうやったら減ってしまうのか。不足したら具体的にどうなってしまうのか…。増減のメカニズムを含め独学でも勉強したところ、面白いほど自分の生理周期と連動していることが分かった。セロトニンはいわば精神安定剤のような働きをするホルモンだから、実際に物理的な悩みがあれど、そこからさらに想像力で膨らませたり引きずったりする負の思考をシャットアウトしてくれる。ネガティブな感情をゼロにすることはできないけれど、持続せずにいられる。この事実を知って頼もしさを感じるとともに、これらがなければ自分は一体全体どうなっていただろうと思うとぞっとした。
ホルモン変化を理解して生活しようと思ったのは、この恐怖からである。いつまでも良好な状態が続く保障はないとともに、少しでも傾けば真っ逆さまに崩れ落ちる状況下に自分がいることを理解したから。この当たり障りない性格も、前向きなホルモンたちにより形作られてきたのだ。可もなく不可もないこのキャラクターは、人の目につきづらいので平穏でいられる。学生の頃、無意識的に得たものだ。そしてそれと連動するように、外見もできるかぎり人並みになることを心と体は求め続けている。雑誌やテレビ、ネット記事の最新トレンドから、最低限自分が良く見える方法を研究してきた。太っているのではなくぽっちゃりの部類に入り続けることが、自分の人生において最優先事項であることを悟った。
本当の自分なんてものはよく分からないけれど、ほどよい努力で無理せず世間に馴染んでいる、というその状態こそが私の心の平和を保ってくれている。
無理をしない状態について考え始めたとき、PMSについて思い当たった。私の生理痛はとても軽いほうだが、その代わり生理開始前の1週間ほどはおおよそ自分とは思えないような状態に陥る。感情面での起伏はそこまでないけれど、注意力が持続せずに四六時中ぼんやりとして何も考えられない。始終、世界に靄がかかったような感覚となるのだ。そしてとんでもなく眠たい。ベッドに潜り込む妄想で一日が始まり一日が終わる。そんなとき私は重たい頭をふりふりしつつ、いつもの自分に還る儀式を始める。
それは、おにぎりをにぎること。
ツナマヨネーズをぎっしりとつめた大きめのおにぎりに、大判の海苔をぐるぐると巻きつける。そうして出来上がった巨大な二つのおにぎりは、車のタイヤのように見えなくもない。恥も外聞もなく、お昼はそれを思いっきり頬張るのだ。混ぜ合わせたツナ缶とマヨネーズのコラボレーションは、カロリーの高さが気になり普段は禁じている。だからこそ密の味というべきか、口の中で極楽浄土のそれに近くなる。でもいつものお昼は手のひらサイズのミニおにぎりを3個程度としているから、大型車二輪のおにぎりを食べ進めていると微かにお腹が苦しくなってくる。そのあたりでようやく冷静になることができる。天国から地獄までの下降はしないまでも、ひとまず現実というニュートラルで少々過酷な世界に身を置いていたことを思い出すのだ。そうしてなんとか人間らしい思考を取り戻した状態で午後からの業務に臨む。
午前中はどうしているかというと、ほとんどハリボテのような状態だ。幸いにも、午前中の受電は少ないということと、そもそもトークスキルをさほど必要としない業務スタイルであるため大きなトラブルに発展したことはない。それでも、「あなた聞いてるの?」と言われることは度々あるのでそこそこ支障はきたしていると言えるかもしれない。そろそろいろいろ見直したほうがよいのだろうか。夕陽を見送りながらぼんやりと考えて、ひとまず明日からにしようと考え直す。今日は今日で精一杯なのだから。
その日は早昼の日でもあったので1時間早く退勤した。帰宅すると、お兄ちゃんから手紙が届いていた。
そもそも筆不精の私と手紙を結び付けてくれたのは、友人の梅子ちゃんだった。彼女と話していると、背筋が伸びる。それは緊張感を伴うものではなくって、むしろ心地の良さを感じる類のもの。物事を掘り下げて考え続けるその姿に、はっとさせられたり学ばされることが多い。彼女を一言で表すならばきっと、「進化するおばあちゃん」。古き良き時代の良いものが、彼女の中には流れているような気がする。
携帯電話を持っていない梅子ちゃんとの連絡手段は手紙がメインだ。
彼女と文通を始めたころ、何の気なしに実家へ手紙を出してみた。それ以来、お兄ちゃんから月に一度ほどハガキが届くようになったのだ。
元気か?という一言で始まり、あとは箇条書きで端的に近状が記してある。兄らしい、感情の読み取れない文章と、筆圧が強いまっすぐな文字。
彼の字を初めて目にした時、心の奥の奥で頑なに冷え続けていた氷の塊が、じわり、と溶けかけた気がした。
内容はこうだ。
都奈、元気か。
こちらは元気だ。
仕事に慣れた。
仕事は少し増えたが前よりも早くできるようになっている。
新しい作品を始めた。今度は大掛かりで時間がかかる。大作だ。
母さんは相変わらず。太ったかもと気にしている。どこがどう変わったのかは分からない。
こんな箇条書きの話題でさえ、これまで面と向かって会話したことは一度もない。ふだん何も考えていないようでも、言葉にしないだけで淡々と、でも着実に兄は今を生きていたのだ。
月に一度の兄便りのようなこれはかれこれ1年、続いている。
しかし今日は様子が違う。ハガキではなく封筒だ。違和感を感じながらも封を開けようとハサミを探し始めたそのとき、母から着信があった。実は昼間から何度も着信がありメールも届いていたようだが、充電が切れていた為に確認することができなかったのだ。
「ああ、やっとつながった。もう!メール読んだ?」
充電が切れていたことを説明してから、まだだよ、と返事をすると
「今日話したいことあるから駅前のファミレスで待ってる」と母はメールの内容をそのまま読み上げた。
「え?どこの駅?」
彼女は私が住んでいる町の駅名を告げた。
急いで家を出た。兄の手紙をベッド脇に置いたままだったことを思い出したが電話をしながらそのまま駅へと向かった。
「なんで?それもメールに書いてたの?」
小走りなので問い詰めるような口調になる。
「書いてない。会って話す予定だったのよ。あなた今日はちょっと早めに帰ってこれたのね。明日は休み?」
「っていっても21時だけどね。明日は休み」
ぶっきらぼうに返してから、母は一体何時から待っていたのだろうと思ったが聞かなかった。切羽詰まっているような声色ではないので、トラブルや緊急事態ではなさそうだと悟り少しほっとする。
実家とは同じ路線上で5駅程度離れているだけなので、母はたまに会いに来るが、なぜか家には寄らずに最寄り駅周辺のファミレスに入る。大抵はたわいのない話で、母の職場での愚痴や兄の話題が多い。
兄が就職してから4年。私の目には大きな変化は映らないが、実の母から見れば豆苗のような成長を感じられるそうだ。その内容を話したり、ましてや自慢したりする友人はこの近辺にはいないから、必然的に私が聞き役として抜擢される。そして最後には必ず、兄からの手紙の内容を聞きたがる。母はその都度、うんうんと頷きながら、ほほえんだり涙ぐんだり、日報か!と突っ込んだりする。
母の話がひととおり終わってから、デザート感覚で始まるこの時間を、私は悪くないと思っている。デザートレターとさえ名付けて良いのではと思うほど気に入っている自分に気づいて、少し恥ずかしくなったりした。
だがこんな夜の待ち合わせ(呼び出しともいう)は初めてのことだった。駅が見えてきたので、早歩きから小走りに切り替えてファミレスに突入した。
母は年甲斐もなく奥の席から顔だけを出して、小刻みに手を振っている。
シングルマザーとなってから、白髪こそ増えたが彼女は数段明るくなった。やはり父といた頃と比較すると別人のように生き生きとした表情をしている。喜怒哀楽が子犬のように分かりやすい。180度変わったといっても過言ではない母の変化に、心の底から安堵している自分がいる。
席に座るやいなや、「夜ご飯これからでしょ。何がいいの」と言う彼女は高揚しているように見えた。注文が終わるまで待ちきれないという様子でメニューを選ぶ私を見つめている。
野菜タンメンとドリンクバーを注文して、ドリンクバーで野菜ジュースを注ぎ席に戻った。母はホットココアを飲んでいた。
「野菜づくしね。いい心がけだけど」と早口で言ってから、私からの質問を待つ顔をする。
「それで?今日はどうしたの」
私が求められているべき言葉を発すると、すっと曇った表情に変わった。シリアスな状況から話は始まるらしい。女優よろしく眉をひそめて母は話し出した。
「お兄ちゃんのお給料がね、突然倍くらいに増えたの。ある日」
兄の通帳は母が管理している。それは3か月前のことで、何かの調整かボーナスのようなものだろうかと思って様子を見ていたら、その後も変わりなく増額したままの給与だったのだそうだ。兄に聞いても、増えた、としか返ってこない。
「心配になって、もちろんあなたに相談しようと思ったのだけど、ちょうどあの子の会社の近くを通ったから…。行ってきたの今日」
今日?!私は野菜ジュースを吹き出しそうになりむせた。ちょうど近くを通ったというのもかなり怪しかったが、相談せずにいきなり動いた母の行動力に若干おののいた。
「普通、親が子の勤め先に出向く?しかも心配だからという理由で」おののきを悟られないように呆れ声で言うと、彼女は小首をかしげて肩をすくめた。
兄の勤め先は大手のアニメ会社だ。大手とはいえど老舗で趣があり職人技を最も優先する、マニアから根強い人気のある事務所であった。もちろん一般企業に比べると異色な職種であることは間違いないが、いくらなんでもそんなことをしては迷惑だろうと母を睨んだ。
「だって。あの子の発達障害のこと、先方はどこまで理解しているのかお母さん全く知らないし、いきなりお給料が大幅に増えて不安だったのよ。何かこわい仕事任されてるんじゃないかとか…」
兄が所属している部署は把握していた為、その部署の責任者と話がしたいと窓口を訪ねたらしい。会議室のような場所へ通されてから数分して、40代後半くらいの男性が部屋に入ってきた。渡された名刺には、代表取締役社長と書いてあったという。
社長さん?!
そう。と母は今度は放心したような顔になった。その時のことを思い出しているのだろう。
「社長さんは、なんだかお若い実業家、って感じの方でね。お母さんそんな人と面と向かってお話するなんて初めてだったから緊張しちゃった」
今度はうっとりとした表情になり、ふふふとはにかんで笑う。
「わかったわかった、で、どんな話をしたの?」
母はおもむろにガサゴソとかばんの内ポケットから紙を取り出した。ボールペンで何かびっしりと書きつけてある。
「帰りのバスでメモしたの。忘れないうちに」母は胸がいっぱいだという顔をしながら噛みしめるように言った。
その紙には社長が母の目をしっかりと見すえ、落ち着いた声で答えてくれたという話の内容が記されていた。
「息子さんの給与が倍になったのは必然です。私が判断し決定しました。
しかし無理な業務を行なっているわけではないので安心してください。
彼の才能は神がかっているだけではなく、努力により磨かれ日々進化している。
確かに言葉は少なく、一般的な協調性という観点から見れば大幅にはみ出していると言わざるを得ません。
モノづくりの現場でスタッフが一丸となり一つの作品を生み出すとき、コミュニケーションは必要不可欠です。ですが私たちは一般的な協調性を重要視していません。この職場においてコミュニケーション方法は言葉でなくても良いのです。
息子さんは、絵や図形、実務を介して表現することでメンバーへ考えを共有しています。
面接の際、彼は自身が発達障害であることをまず私たちに告げてから、この場所で自分が何を行なうことができるのかについて、絵やデータ、アニメーションを使いながら分かりやすく懸命に伝えてくれました。
視覚に特化したプレゼンテーションのようなものだったのです。
その際にエンジニアとしての技術が十分であることも分かりました。正直に言って、秀逸でした。
私も父も絶句しました。祖父が生きていれば、その場で彼と絵を交わし合うセッションをはじめていたかもしれません。
私が代表取締役になったのは、じつは半年前のことでして。創業者の祖父はもともと名の知れた漫画家でした。そこに技術を組み入れアニメーションとして確立させたのが二代目である私の父です。この事務所は、大企業とはおよそほど遠い場所ですが、アニメーションをこよなく愛する者、その情熱を形にしてより多くの人に届けたい、語り継ぎたいと願う者の集合体です。父は祖父から、私は父からこの思想を受け継ぎました。おかげさまで、この事務所から生まれた作品たちは、同じくアニメに愛情を注ぐ視聴者の元で光を浴び根を張って新たな種や芽を育み続けています。
人材育成という言葉がありますが、父は嫌いました。人は育てるものではない。お互いによく観察し合い育ち合うものだと。私も同意見です。そうしてその考えを元に、会社が大きく豊かに育ったことで得たその報酬は、作品作りだけでなく土壌となる社員に還元したいと思うようになりました。
お母さん、彼は今、主要な制作チームのディレクターなのですよ 」
この時点で、母は号泣していたという。私も目頭が熱くなってゆくのを感じた。
「この事務所では大きな変革がある際、携わるメンバー全員と個別に面談をする習わしになっているのですが、彼に関してはどのメンバーの口からも、〝然るべき人選だと思う〟という言葉が出ました。確かに入社当初、彼とメンバーがコミュニケーションの部分で苦戦していることは明らかでした。しかしこの4年で、その溝は埋まり、彼への畏敬の念さえ生まれている」
氷山の一角が音を立てて崩れていくのが分かった。私はペーパーナプキンを無意識に引き寄せて、慌てて目頭にあてがった。
「もちろんディレクター を任せるからにはある一定の成果を…という部分は会社としてどうしてもありますが、我々も彼自身もこの昇格を特別視していません。というのも、然るべき働きをしてそれに適正な役職名がつき、さらに彼自身の努力と実績に見合った給与となったというだけだからです。責任転嫁や過度な業務の追加、勤務時間の延長などは全く考えていません。
金額の変化について説明がなかったのは、減額ではなく増額であるという点と、記帳すれば確認できる内容なので報告は不要という彼なりの判断だったのかもしれませんね」
母は仕事中だった兄には会わず、訪ねたことを黙っていてもらえるように頼んで帰ってきた。兄が母を叱ることはなくとも独断で事務所を訪ねたことに不信感を感じる可能性はあったので、良い選択だと思った。
母を駅に送り届けて家に帰宅したころには0時を回っていた。
帰宅するとまず、ベッドに置いてあるふわふわの抱き枕にダイブする。その日の疲れに応じて、ふわふわが芯から抱きしめかえしてくれる感触に身を委ねるのだ。
22:00 帰宅
22:30 夕食(できるかぎり軽め)
23:00 着替え・メイク落とし・肌ケア
24:00 フリータイム
24:30 就寝
普段、帰宅してからは大体このように過ごしている。
この日は大幅にずれたけれど夕食もすませてあるし、部屋義に着替えてからメイクだけを落としてベッドに入った。ふと置きっぱなしにしていた兄からの封筒が目に入った。母は「たぶん完成試写会の招待チケットよ」と自慢げに言った。
「私にも封筒に入れて渡してくれたから間違いないわ。始めて監修したアニメがやっと完成したらしいのよ」
母はその時の様子を思い出したのか、じんわりと涙目になって遠くを見ていた。
起き上がり、封を切る。手紙はなくチケットだけが入っていた。なぜか2枚だ。母にも手渡しているのだから、母と二人でという意味ではないだろう。入れ間違いなのだろうか。深夜0時過ぎに難問を解く気力は残っていなかったので私はそっと瞼を閉じてみた。
それでも嬉しい気持ちはこみあげてくる。スキー場を舞台にしたロボットもののアニメーションらしい。チケットのイラストをうっすら思い出しながら、ジャンプ台について思いを馳せる。母は、控えめに控えめに、細心の注意を払って兄の身の回りの道を整えていた。これ以上、悲しいことにならないように。それが過保護と呼ばれても、自身で過保護だと反省しながらも、そろそろと続けていたその行為は私たち兄妹用のジャンプ台作りだったのだと大人になってやっと気がついた。母がせっせとこさえて整備しつづけたそれで助走をつけ、兄は見事に遠くへ飛んだ。
私のジャンプが見事かどうかはさておいて、兄の背中を、空を仰ぐように眺めることができるようになった私たち親子は幸せ者なのだと心から思う。
突然枕元の携帯電話が揺れて、メールを受信しているのが分かった。短時間の充電しかしていなかったから、帰宅するまでに携帯は再びただの静物になっていたのだ。復活したそれはお尻を充電ケーブルに繋がれながらも誇らしげに震えている。通知メールを開くと、友人のおかかちゃんからメッセージが届いていた。彼女からの連絡は、sayu関連のものが主なので胸が高鳴る。次回のワンマンライブのお誘いだった。
彼女とは、sayuが初のワンマンライブを行なった際に出会った。
〝個人的なサーカス〟というテーマのライブで、会場には大きなサーカス幕がかかり巨大なテントが張ってあったけれど収容人数は20人までと小規模だった。
運悪く、当日はPMSが一番ひどい日だった。私の脳みその皺という皺に大量の靄が立ち込こめていて体も重く、さらに瞼へとのしかかる重力は通常の倍以上に感じられた。
そうして私は見事なまでに重大なミスをおかした。チケットを家に忘れてきたのだ。気がついたときには既に会場に到着しており、いくら早めに来たとはいえ家に戻るには片道1時間という場所だった。
私は呆然と立ち尽くした。5分ほどあたりをうろうろとして、神に祈りながらカバンの中身を一つ一つ取り出しては戻し、絶望のためいきをついた。念の為係りの人に事情を話そうと思い立ちよろよろと受付に向かい始めたとき、小柄な女性が一人、目の前に立ちふさがった。チケットを二枚手にしている。
「もしかして、、、チケットお忘れですか?」
私は女性が手に持っているsayuのチケットと彼女の顔をまじまじと見比べ、要件を話し出される前から〝神さまはいた〟と思った。期待した通り、彼女は連れが急な仕事でたどり着けずに持て余したチケットを手にして途方に暮れていたのだ。
私はふかぶかと頭を下げ、チケット代を払おうとした。
彼女は「いいんですよっ。突然不要になってしまったものですし、活用してもらえるだけで十分です」と言ってにっこりとした。私は土下座しそうな勢いで頭を下げなおし、両手でチケットを受け取った。受付を済ませてサーカス小屋のようなテントに入るとあたりは薄暗かった。しかし天井にある空気口から中央付近目指して自然光がまっすぐに差し込んでいることに気づいた。
そこにはドーナツ型のテーブルが一つ置いてあり、sayuがいつも路上で使っている楽器や音を奏でるための日用品が置かれていた。
客席はその円形テーブルを囲むように配置されていたが、隣接せず各々等間隔の距離があり、不思議なことに一席ずつがカーテンよろしく棒と布で仕切られていた。
チケットには受付を済ませた印のスタンプが押され、表記された番号が各椅子の背に印字されていた。女性はにっこりと会釈をすると静かにななめ前を指して、手を振りながらカーテンの向こうへ消えた。私も数字を頼りに該当する椅子を見つけ出してからカーテンを開いて腰を下ろし、受付で配布されたパンフレットに目を落とした。
〝ようこそようこそ。
ここは 《個人的なサーカス》です〟
パンフレットには手書きの文字が躍っている。路上ライブで目にする看板の文字だった。 sayuの字だ。
----------------------------------
〝個人的なサーカスとは、あなたひとり用のサーカスという意味です。
歌うたいはあなたの椅子の前に座り、あなたの好きな歌を一曲うたいます。
楽器は歌うたいが選びます。
あなたは開演までに、目の前にある白い紙に好きな歌の名前を書いて、歌うたいがあらわれたら渡してください。
歌うたいはあなたと、あなたの選んでくれた歌にあわせて即興で演奏します。
もっとも、あなたへの音はまわりに聞こえますが、楽器の形状や演奏の様子はカーテンのこちらがわ。
あなただけの音楽は、あなただけの小さなサーカス会場で生まれてあなただけのものになります。
※ひとつだけお願い※
心と体で楽しんでいただきたいので撮影や録音はご遠慮くださいね〟
----------------------------------
まるで手紙を受け取ったようなあたたかさを感じたまま、なんと私はそのまま気を失うように深い眠りについてしまった。奇跡的に、さゆが目の前で演奏してくれる直前に目を覚ましたが、最後まで夢うつつだったためほとんど白昼夢のような記憶となってしまった。ただ特別に幸せな心地だったことは間違いない。
帰りの電車が同じだったこともあり、チケットを譲ってくれた女性とお茶をした。お礼も兼ねてささやかだがお茶くらいはごちそうさせてほしいと申し入れて。
「わたし、丘 花 といいます。おかかって呼んでください」ソイラテを一口飲んでから、おかかちゃんはそう言ってにっこりとした。もうじき、急な仕事で同席できなかった恋人が現れるというので二人で待つことにした。
ころころと表情を変える軽やかな彼女のトークに魅了されつつ、なんて可愛らしい人なのだろうとうっとりしながら相槌を打っていたら、外が騒がしいことに気がついた。外壁はガラス張りになっているので、おかかちゃん越しに様子をうかがうことができる。取り巻きのような複数名の女性の真ん中に、すらりと背の高い男性が一人立っている。横顔なので顔はよく見えないが、取り巻きの様子やシルエットから、かなり整った姿かたちをした男性であることが分かった。彼の手がゆっくりと片耳に添えられてゆく。電話をかけるようだ。
「芸能人、、、ですかね?」私が言うと同時に、目の前のおかかちゃんの携帯電話が鳴きだした。小鳥がさえずる着信音だったため、店内が一瞬森の一部になったような錯覚を覚えた。彼女は電話には出ずに後ろを振り向いて、ガラス越しの彼へ手を上げた。気づいた彼はこちらを向いて軽く手を上げ、 わたしに気づくと会釈した。
想像を絶する美青年だった。いつのまにか小鳥たちは静かになっている。「ま、まさか、、、あの人?」私がギャグマンガよろしいリアクションをしたのでおかかちゃんはふふふと笑って頷いた。
その日から2年が経つ。職場も住んでいるエリアも離れているので路上ライブではなかなか会えないが、定期的に会ってお茶をする仲となった。
ベッドに横たわりメッセージを開く。ブルーライトが一瞬のうちに脳裏を貫いたけれどかまわない。内容はやはり、来月のライブのことだった。
〝ライブ楽しみだね!会場で落ち合おう〟という内容だった。すっかり深夜になってしまったから、明日の朝返事をしよう。
ブルーライトに攻撃されたことなんてなんのその。眠気は動じず枕元で丸くなっている。
来月のお楽しみを思い浮かべほころんだ自分のほっぺたをそっとさすってから、ふわふわの睡魔を抱きしめて眠りについた。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
