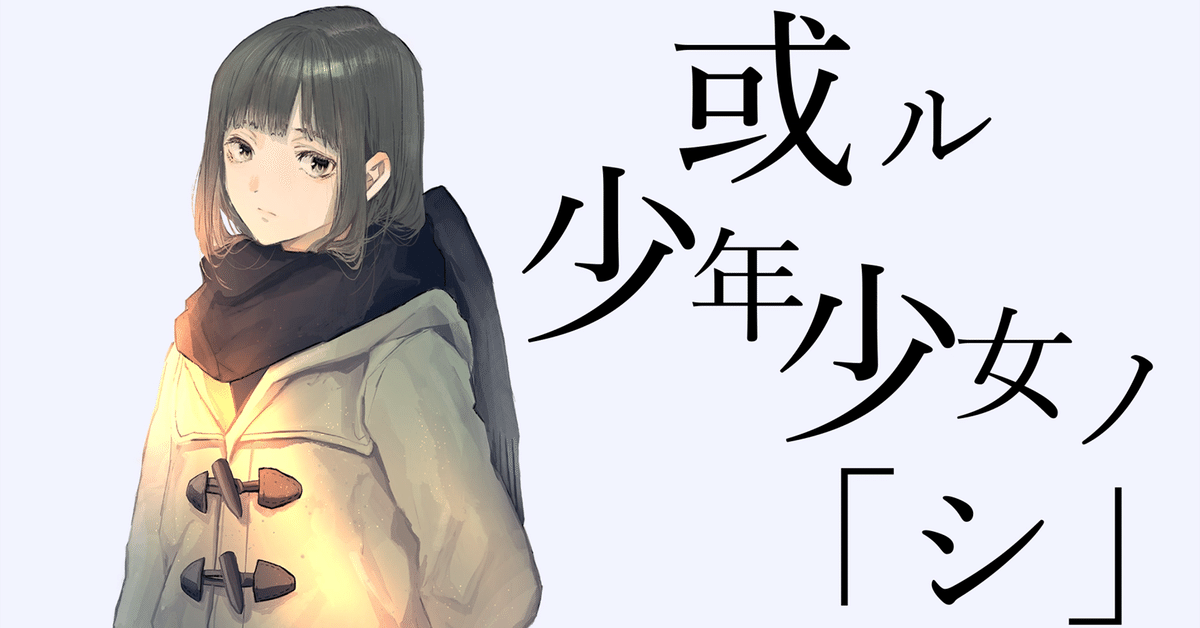
【掌編小説】 『スマイル・オン・フリーデッド』 (From『或ル少年少女ノ「シ」』)
悲しい話で泣けるのに悲惨な現実に泣けないぼくも、端末から聞こえる無機質な音声に胸を痛めた。たしかゲームかアニメのキャラクター。標準設定されているAI。人身事故のため、電車全線で遅延が発生したとのレポートを告げてくれた。AIの人工的なグラフィックがわざとらしく悼んでみせた。キャスター風の女性キャラクターが語るのは自殺志願者集合体『スマイル・オン・フリーデッド』との関連性だ。
ここ数ヶ月、報じられる自殺の大半は、『スマイル・オン・フリーデッド』という団体に所属するメンバーによるものだった。キャスターは団体についてを簡単な説明を述べる。構成するメンバーはほとんどが少年少女。団体の声明文では、彼ら彼女らの悲しい過去が語られていた。いじめ、虐待、生まれつきの病気による差別。
まるで無理やりに悲しみをしつらえたような、作り話みたいなその話に、思わず心が飲み込まれたから、現実だったと思い出す。思い出したら泣けなくなった。
「ミア、やっと電車がきたよ」
ホームで待たされ続けたぼくらの体はひどく冷えてしまった。電車は意外にも空いていて、それでも暖房が十分に効いていたから、肌が火照ってしまう。マフラーにぶつかって膨らみ上がっていたミアの長い髪の毛は、ミアがマフラーをほどくと同時に、美しい爬虫類の尾みたいに、しなやかに動いて、ピンと張った。
ミアの通う心療内科は駅を五つ挟んだところにある。週に一度の決まったルーティーン。何も変わらないのだとわかっていても、辞めさせる理由もなかった。
一駅も移らないあいだに、雨が降り始めた。
ぼくもミアも傘を持っていない。電車の窓から覗く限りは、にわか雨のようには見えなかった。端末のAIはいまさらになって降雨の予報をぼくに告げた。どうやら少し故障しているみたいだ。
駅に停まり発車し、また次の駅。様々な路線が乗り入れているターミナル駅だ。
ぼくたちのいる車両に、発車のベルと同時に、一人の男性が乗り込んできた。ボロボロのリュックサックを背負っている。二十代、いや、十代だろうか。口元とあごの無精髭のせいで老けては見えるが、ぼくたちとそう変わらない歳のようだった。
まだ席はいくつか空いているのに、彼は座ろうとはしなかった。
やがて、彼は車両の中心にまで歩いていき、電車が十分に加速したころに、声を発し始めた。
それは立派な声の演説だった。
「ぼくらは、スマイル・オン・フリーデッド」
彼はたった一人なのに、たしかに「ぼくら」という言葉を使った。
ぼくを含めて乗客は皆、なんとなく耳を傾けていた。物珍しさからか、嘲るような笑みを浮かべながら端末で撮影する者もいた。
尊厳、平和、世界の選択肢。強まる雨に負けないくらい、彼の語調はますます荒くなっていく。
それでも皆、それぞれの駅で降りていく。傘を抱えて降りていく。
あの人はきっと、雨が止むまで語り続けるんだろうな。なんとなくそんなふうに思った。
たどり着いた駅でぼくは、傘はないけど電車を降りようとした。
「ミア?」
ミアは立ち上がろうとはしなかった。ただ、いつもの眼差しで、演説を続ける彼を眺め続けていた。
「ミア、降りないと」
降りないと、なんなのだろう。ふと浮かんだ自問に答えはなかった。心療内科の予約に遅れる、受付の女性に嫌な顔をされる。時間に間に合ったところで、それらを避けられるだけだ。
ミアの手を強く引く気は起きなかった。ぼくは諦めて座り直した。
電車が発車する。
男は演説を続ける。
「孤独であること、自由であること。美しくあること。それを一番示すのは、ぼくらの死だ」
『スマイル・オン・フリーデッド』が、それまでにもあった自殺志願者たちの集まりと異なっていたのは、彼らは「自ら命を断つこと」を決して否定しようとしない、ということだった。
──だから危険なんです。キャスター風のアイコンがしたり顔で語っていたのを思い出した。
彼の言葉はふざけている。でも、ぼくには聞き流すことができなかった。少なくとも、ぼくが過ごす日々には、彼の言葉に対する答えはない。
男は演説を終えた。拍手もなく、野次もない。ただ数人、車両に残っている乗客たちは皆、彼に向けていた視線を手元の端末に戻した。ミアを除いて。
ぼくもまた、端末を開いて時刻を確かめる。次の駅で降りて引き返せば、ぎりぎり間に合うな、なんてことを思った。
「イオリ……」ミアがぼくの名前を呼ぶ。
「降りて……」
「ミア?」
「早く、降りて」
「まだ、駅に停まってないんだよ。次の駅で降りよう」
「だめ、離れて。早く、あの人から離れて……」
「どうしたんだ、ミア」
「離れてって言ってるの!」
叫ぶようなミアの声。
演説の男の方を見る。目が合った。なぜか笑みを浮かべている。彼は背負っていたリュックサックを足元に置いた。
鈍い音がした。嫌な予感がした。
ぼくはミアの手を取って、強く引っ張った。気のせいだろうか。ミアの手が重い。
ミアを見る。後ろめたそうに、ぼくから目をそらした。
車両と車両とをつなぐ扉。こじ開け、次の車両へと移り、思い切り閉め、振り返る。
何も起きる様子はなかった。電車がゆっくりと減速を始める。
完全に停止し、扉が開く。
ミアの手を引く。やはり、気のせいではない。ミアは車両に残ろうとしている。
「どうしたんだ、ミア」
「もう少しだけ、乗っていこうかな、って」
ミアの気まぐれに振り回されるのには、もう慣れている。だが、ミアを置いていくわけにはいかない。
明るい発車のベルの音。そのメロディの最後、ミアはぼくを強く押した。
ぼくはホームに倒れ込んだ。ミアは電車に取り残されたまま。
「ミア!」
ぼくが立ち上がるころには、電車は湾曲した線路の向こうへと、遠く離れかけていた。
瞬間、オレンジの光が膨らんだように見えた。
違和感。そのすぐあとに、甲高く、重い響き。
爆発、炎、煙。
周りの喧騒が耳に入らない。
端末のAIが速報を告げる。
──『スマイル・オン・フリーデッド』のメンバーが、都内路線で爆発テロを起こしました。声明も届いています。同団体による初の暴力的行為です。繰り返します。『スマイル・オン・フリーデッド』のメンバーが、都内路線で爆発テロを起こしました……。
延々と繰り返されるレポートを何度も聞いて、やっとぼくは悲しくなった。
ミアがいなくなってしまったことよりも、ミアがぼくを連れて行ってくれなかったことに、悲しくなった。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
