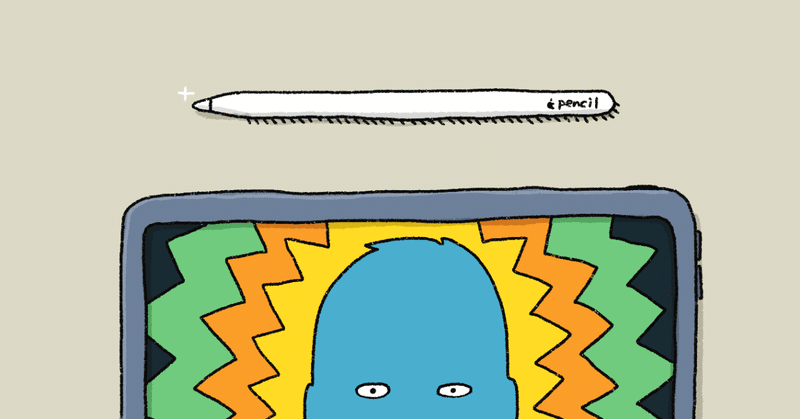
「苦しさ」と「ゆるさ」の共有で、人はオンラインの限界を越えられる?
急に日常になった在宅勤務。最近、zoomを使わない日がない。
人間は思ったよりも、「視覚」と「聴覚」以外でコミュニケーションをとっているのだなと思う。
対面だと楽しく終えられる2時間のミーティングも、オンラインだとぐったりする。
小さな相槌や息遣い、身体の姿勢や仕草から感じられるテンション。
そういう普段は自然と認識するものを、どうにか四角形の画面のなかから、拾おうとしているようだ。
みんなが正面を向いているというのも、意外と不自然だ。
一昨日も、お客さんと同僚と私、3人でのミーティングで、「なにかほかにありますか?」と言ったら、2人が同時に反応してしまった。
対面のときは、顔や身体を向けた方向で、誰に話しているか示していたらしい。
そこで思い出したのが、この本に書いてあったことだった。
ポール・マッカートニーとジョン・レノン、ゴッホと弟のテオ、ジョブズとウォズニアック……彼らが歴史に残る偉業を成し遂げられたのは、2人組のペアだったからなのではないかという仮説のもと、「2人」だからこそ生まれるクリエイティビティを紐解いた1冊だ(働いている先で出している本だけど、一読者として好きな本)。
思い出したのは、この本の序盤で触れられている、クリエイティビティと物理的な接触の関係について。いくつか引用する(太字は個人的に印象に残った部分に追加している)。
人と人とが物理的に接することは、創造的な活動にとってきわめて重要だ。(中略)同じ分野の研究者は、同じフロアで働いているほうがエレベーターで1つ上の階にいる場合より、協力する傾向が2倍高かった。さらに、異なる分野の研究者が隣り合って座っている場合、同じ部署で違うフロアにいる同僚より強力する傾向が6倍高かった。
2010年の調査によると、ハーバード大学の研修者が1人以上名を連ねる生物医学の論文3万5000本について、物理的な距離が近い共同執筆者の論文のほうが、遠く離れている共同執筆者の論文より引用される回数が多かった(引用回数は研究の重要度の指標とされる)。
肝心なのは、言葉だけでなく体を使ったやり取りだ。非言語のコミュニケーションの重要さは十分に証明されている。複数の研究によると、身体の仕草は言葉より4倍、有力なツールになる。
個人的な接触がもたらす強みは、私たちが意識できない経験にも及ぶ。心理学者のダニエル・ゴールマンの著書『SQ 生き方の知能指数』(日本経済新聞出版社)によると、他人と共有する空間で、私たちは「肌や頭脳の垣根を超えて体と体をつなぐ」、「神経回路のWiFi」や「フィードバック・ループ」に接続する。
会話をしている人を録画してコマ送り再生すると、言葉以外の要素が同調していることがわかる。重なり合うリズムは、ジャズの即興演奏を導く拍子のようだ。(中略)体の動きも数分の1秒単位で同調する。ただし、情報を意識的に処理するテンポはもう少し遅い。2人で会話をしていると、「(2人で無意識に踊る)複雑なダンスに思考が追い付かない」と、ゴールマンは書いている。
あらためて読むと、いまzoomで感じる物足りなさは、これかぁと思う。
空間を共有することで、私たちは無意識にジャズの即興演奏のように、同調しているらしい。
この「ジャズの即興演奏」の感覚を、強く感じたことがある。
大学の同級生と3人で10年以上、休日に写真展や発信をする「Salmons」というなんとも説明しがたい活動をしているのだが、その活動でのことだ。
それぞれの仕事の事情で、うち8年くらいはSkypeを使って遠隔で活動していた。
石巻ー東京ー愛知、トルコー東京ー愛知、カメルーンー東京と、かなり距離も時差も、生活環境の違いもあった8年間だった。カメルーンにいるメンバーがいた時代は、大雨でネットが途切れることもよくあった。
8年遠隔でやって、全員が東京で暮らすようになったのが、3年前。
直接話して、そのスムーズさに驚いた。
いろいろなことが決まるのが早いし、お互いにイライラすることもあまりない。遠隔のときと同じような意見の相違でも、違いのなかから、その先の選択を見出せる。
どうでもいいと思える雑談から、新しいことをやってみようと盛り上がれる楽しさもある。
遠隔のときは、誰かがアイデアを言って、それを他の2人が評価するような感覚だった。
なにより、延々と楽しく話していられる。
昼間にはじめて、いつも気づくと夕飯時だ(なにもできていなくても、楽しくその時間になっていることも多々ある…)。
それがこのコロナの影響で、先月から久しぶりにまたオンラインになった。
やはりリアルで会っているときのように、そこまで延々と話すことにはならない。同じメンバーなのに、不思議だ。
ただ8年間遠隔でやっていたときにくらべて、やりやすくなったように思う。
思い当たることは、2つある。
1つ目は、マイナスの状況を共有していること。
緊急事態制限の出た東京で、不安と不便を共有しているというのは、とても大きい。
震災後の石巻、駐在の孤独、インフラのととのっていないカメルーンの村……お互いが経験したことがない苦難をそれぞれ持っていたことは、あのころ私たちを隔てる壁になっていた気がする。
2つ目は、やたらとリラックスしていること。
遠隔だった8年間は、成果をだそうと頑張っていた。
そのときとくらべると最近は、成果よりも、休日に共感できる仲間と話すことを大切にするようになっている。
活動自体もゆるいし、雑談し放題である。
リラックスしているので、画面で見える姿勢も、ぐにゃぐにゃしている。
お互いに共通する苦難を分かち合うこと。
めちゃくちゃリラックスすること。
「苦しさ」と「ゆるさ」という対極の感覚を共有することで、人はオンラインの限界を少し越えられるのかもしれない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
