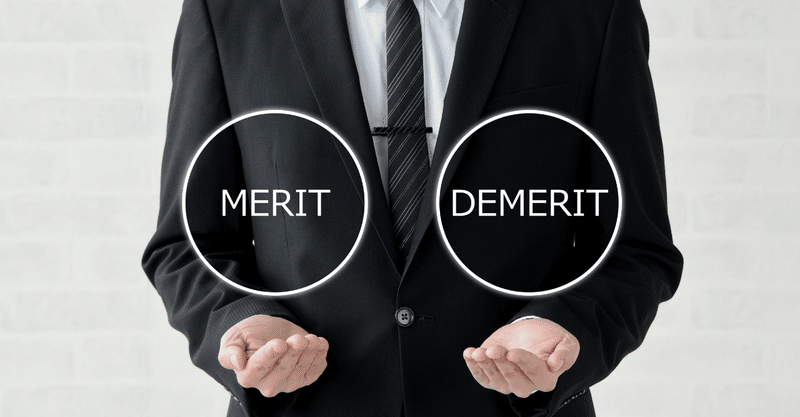
読書のデメリットとは何か?
こんにちは、Yukiです。
今回の記事では、読書のデメリットを考えてみたいと思います。
一般的に、読書は良いことだとされています。
ネットで調べると、読書のメリットがズラリと出てきます。
僕も読書は良いと思っています。では、読書を手放しに、盲目的に良いことだと言えるかといえば、そうではないと思います。
僕はデメリットもあると考えています。しかしながら、メリットの部分が強調され、デメリットについてはあまり触れられていないのが、現在の状況だと感じます。
そこで今回はあえて、デメリットを考えてみたいと思います。
具体的に、僕は読書には3つのデメリットがあると思っています。
①他人を見下すようになる
②考え方・物の見方が偏る
③考える力を失ってしまう
以下、1つずつ見ていきましょう。
①他人を見下すようになる
世の中には、数え切れないほど多くの本があります。
総務省統計局の統計データによると、令和元年に出版された新刊は71,903点にもなるそうです。これは、単純計算で1日に約200冊もの新刊が出版されていることになります。
これだけの数の本が出版されているので、当然多くの人に読まれる本と読まれない本にわかれます。
多くの人が知らない本を自分は知っている、読んでいるということも十分にあり得ます。
ところで、人間には自分だけが知っていることに優越感を感じる心理があります。本に当てはめると、他の人は読んでいない、自分だけが読んでいるということに優越感を感じます。まだ、それだけなら良いと思います。
しかし、中には自分だけがその本を知っている、読んでいるということでマウントを取る人がいます。
また、あるジャンルの本を読んでいる人を馬鹿にするような発言をする人もいます。これは僕が実際に経験したことでした。
その人は、「ビジネス書読まないで平気なの?」とか「ビジネス書以外の本なんて読書じゃない」と言っていました。おそらくその人にとって読書とはビジネス書を読むことであり、ビジネス書こそがNo.1という考え方なんだと思います。ビジネス書至上主義と言えるでしょうか。
全員がとは言いませんが、こういった他人を見下す心理には、気をつける必要があるでしょう。
②考え方・物の見方が偏る
基本的に人は、自分の好きなジャンルの本、好きな著者の本を読むと思います。
それは良いのですが、あまりにも自分の関心のある分野だけの本を読んでいると、偏りが生じます。
読んでいる本が偏っているということは、それから得られるものも自然と偏ってきます。そうすると、自分の物の見方・考え方も偏ってしまう可能性もあります。
食事を例にすると分りやすいです。
毎日自分の好きな食べ物だけを食べていたら、栄養バランスは偏ります。そうすると、不足している栄養素がある一方、過剰に摂取している栄養素も出てきます。
その結果、体内の栄養バランスが崩れ、自分の体に悪影響を及ぼします。
読書も同じで、偏りによって悪影響悪影響が生じることが考えられます。
ではなぜ偏りが生じるかといえば、人間には様々な認知バイアスがあるからです。認知バイアスには様々な種類がありますが、ここで関係してくるのは、確証バイアスと呼ばれるものです。
確証バイアスとは、自分にとって都合の良い情報だけを無意識的に集め、反対に都合の悪い情報は無視してしまう傾向のことです。
自然と普段読まない本を読むようになるようにはなりません。
ですので意識して、普段触れないような分野にも目を向ける必要があります。
僕は本屋に行ったら必ず、自分の興味・関心の薄い分野の本のコーナーにも行くようにしています。そしてもし面白そうな本があれば、買うようにしています。
最近では今まで全く読まなかった「詩集」を買いました。
普段読む本とは全く異なる雰囲気が、とても面白いです。
このように意識的に偏りを壊すことで、広い視野を手に入れることができます。また、全く関係ないと思っていた分野同士が、繋がることもあります。
時々立ち止まって、自分が読んでいる本の傾向を見直してみるのも良いかも知れません。
③考える力を失ってしまう
これは、ショウペンハウエルという人が『読書について』という本の中で、言っていることです。
最近いろんな人に取り上げられているので、聞いたことがあるかも知れません。
彼はこんなことを言っています。
読書は、他人にものを考えてもらうことである。本を読む我々は、他人の考えた過程を反復的にたどるにすぎない。習字の練習をする生徒が、先生の鉛筆書きの線をペンでたどるようなものである。だから読書の際には、ものを考える苦労はほとんどない。自分で思索する仕事をやめて読書に移る時、ほっとした気持になるのも、そのためである。(中略)ほとんどまる一日を多読に費やす勤勉な人間は、しだいに自分でものを考える力を失って行く。つねに乗り物を使えば、ついには歩くことを忘れる。
岩波文庫、斎藤忍随訳『読書について』P127-128
本に書いてあるのは、著者の考えです。それは決して読者が考えたことではありません。ですので、読書とは他人が考えたことをそのままなぞっているにすぎません。
ところが、それを意識しないとあたかも自分が考えたような気分になってしまう。考えたつもりになっている。
実際には何も考えてないのに考えたつもりになっているので、自分の主観と実際の自分の考える力のズレが起きてくる。ということだと思います。
ショウペンハウエルの指摘はかなり鋭いです。
更に詳しく知りたい方は、アバタローさんの動画が参考になると思います。
終りに
今回は僕が考える読書のデメリットについて見てきました。
「読書=良いこと」と疑わずにいることで、足元をすくわれるかもしれません。
きちんとデメリットも認識して読書をしていくことで、読書の良さを更に引き出せると思います。今回の記事が、そのきっかけとなれば嬉しいです。
ここまで読んでいただきありがとうございました!
↓参考図書
↓最近読んでいる本
読んでいただきありがとうございます! 他の記事も読んでいただけたり、コメントしてくださると嬉しいです
