
書評:『クリーンミート 培養肉が世界を変える』
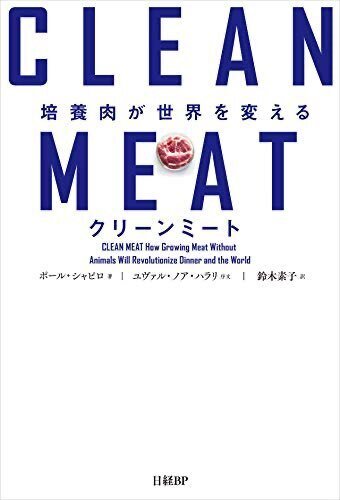
『The Game Changers』というドキュメンタリー映画を見た。世界の様々なスポーツのトップアスリートの間で、肉食をやめ菜食に切り替えたらパフォーマンスが向上することが注目を集めている。彼等が肉などの動物性タンパク質の代わりに食べているのが、植物性タンパクの大豆ミートだ。この映画を見て以来、我が家でも大豆ミートが食卓に上るようになった。
私たちが生きていく上では、安心安全な食材を口にするが大切だ。それだけでなく、われわれは食材の生産における地球環境への負荷軽減かという問題にも直面している。そんな食料問題の有効策となると考えられるのが、最新のバイオ技術を使って肉の細胞片から肉をつくりだす「培養肉」である。『クリーンミート 培養肉が世界を変える』では、培養肉という新しいテクノロジーの商品化を実現しようと、スタートアップ企業や研究機関、さらに彼等を取り巻くベンチャー投資家たちの姿が臨場感を持って描かれている。
培養肉とは
培養肉は、もともとは医療の現場で移植を目的として研究された技術を使っている。人の組織を増殖させる培養技術を肉の生産に適用させ、牛の細胞を完全無菌の培養器の中で人が食べられる大きさの肉にまで大きくする。できあがったのは、大豆ミートに代表される「フェイクミート」ではなく、正真正銘の肉だ。この生産方法は「細胞農業」とも呼ばれ、家畜を殺さないだけでなく、抗生物質やコレステロールなど体に害のある物質を取り除けるなどの利点を持つ。
培養肉という考え方は最近にできたのではなく、1894年にフランスの科学者のマルセラン・ペルテロが次のような世界の到来を予測していた。
「2000年までに、人間は殺した動物の肉ではなく、実験室で育った肉を食べるようになるだろう」
培養技術を使った生産は、牛肉から始まった。その後、様々なスタートアップ企業が参入し、鶏肉や鶏卵やレザー商品までと、そのすそ野を広げている。
なぜ培養肉が求められるのか
国連経済社会局人口部が発表した『世界人口推計2019年版:要旨』によると、現在の地球には77億人の人が暮らしているが、2050年には97億人と20億人増加することが予測されている。人口増加の多くは、アフリカやインドなどの途上国からもたらされるが、人口が増えるだけでなく多くの国で生活水準が向上する。国が豊かになると、人は肉、卵、乳製品などを求めるようになる。
しかし、畜産物を生産するためには大量の水や土地などの資源が必要になる。畜産に必要とされる水を合計すると、全世界の淡水量の27%に達する。例えば、
食肉用の鶏を一羽育てるのに、1000ガロン以上(3800リットル)が必要
鶏卵を一個作るのに、約190リットルの水が必要
牛乳1ガロン(3.8リットル)を作るのに、約3400リットルの水が必要
また、現在世界で生産されている小麦や大豆の大半は、人が食べるためでなく、家畜用の飼料として使われている。どのくらい使われているかと言うと、食肉の生産のために地球上の氷に覆われていない土地の4分の1以上が家畜用の牧草地に、耕作地の3分の1が家畜の飼料用となっている。非常に広大な面積が必要だ。人口拡大するスピードにあわせて農作物を提供しようとすると、いずれ生産に適した土地がなくなってしまうことが予想されている。
さらに、畜産は、地球の温暖化にも深刻な影響を与えている。あまり知られていないが、牛のゲップなど家畜から出される二酸化炭素は、世界の温室効果ガスの約14%を占め、すべての乗り物から排出される温室効果ガスの総量に匹敵している。また、家畜の食肉処理場からは、解体の過程で糞便などの有害物質が排出され、周辺地域に環境汚染を引き起こしている。
一方で、培養技術による肉の生産は、従来型の畜産による環境破壊の影響を抑えることができる。これまでの牛肉の生産と比べて、エネルギーは最大45%、土地面積で99%、水量で96%少なくて済むという。
普及に向けた課題
地球に与える負荷を減らすという点で、培養肉は有望な解決策の一つである。実験室レベルでその技術は確立したものの、市場で販売するためには莫大な資金が必要となる。多くのスタートアップ企業の悩みは、「資金獲得」だ。しかし、培養肉の有望性は多くの投資家の注目を集めている。マイクロソフトのビル・ゲイツやアマゾンのジェフ・ベソス、バージンのリチャード・ブランソンなどの富豪がベンチャーキャピタルを設立した氏、グーグルの共同創業者であるサーベイ・ブリンは、世界初の培養肉ハンバーグを作るために約33万ドルを出資した。今後、より多くの投資家からの資金が投資されることが期待される。
しかし、培養肉が普及するためには、政府の規制、生産コストの削減、消費者から認められることなど課題は多い。
消費者に培養肉の安全性や有用性を理解してもらうために、まず培養肉ベンチャー企業が取り組んだのは、製品名称を見直すことであった。当初は、「試験管ミート」や「フランケンシュタインミート」など揶揄されていたが、紆余曲折を経て「クリーンミート」という名称が使われるようになった。
最後に
この本を読んで、日々何気なく食べている肉を作るのに大量の資源の投入や糞尿による環境汚染など、知らないが多かった。「食べる」ことは、ヒトが生きていく上でかかせないが、習慣的になった行動を変えることに抵抗を示す人は多いはずだ。しかし、その時は当たり前でも技術革新によって、生活の様相が大きく変わることはよくある。本書の中でも、かっては照明に用いられていた鯨油が石油に置き換わった事例が紹介されている。
培養技術がより多くの人に受け入れられるためには、本書にあるように食用ではなく、まずは身に付けるレザー製品で消費者の意識を変えるのは、有効な手段だ。
わたしたちの食生活を考える上で、有効な情報法を提供してくれる一冊です。
最後に、ヴァージン・グループのリチャード・ブランソンを…
「30年ほどたてば、動物を殺す必要はなくなるだろうし、肉をすべて、いま食べている肉と同じ味のクリーンミートが、または植物由来のフェイクミートになるだろう。しかも、その肉はきっと、いまより健康的になっている。将来、私達は昔を振り返って思うだろうね。動物を殺して食べていたなんて、祖父母の代はなんて野蛮だったんだろうって」
『クリーンミート 培養肉が世界を変える』 ポール・シャピロ (著), 鈴木素子 (訳), 日経BP社
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
