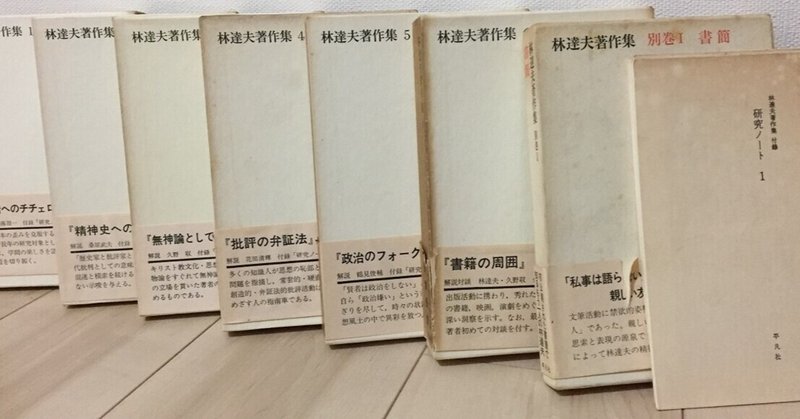
<書評>「蜘蛛男」,「猟奇の果」,「魔術師」

「蜘蛛男」(1929~30年初出),「猟奇の果」(1930年初出),「魔術師」(1930~31年初出)江戸川乱歩推理文庫 8巻(1987年),9巻(1988年),10巻(1988年)講談社
1.はじめに―乱歩にたどり着くまで―
講談社が発行した,江戸川乱歩推理文庫全65巻のうちの3巻である。特に「魔術師」の巻末エッセイ「乱歩と私」に,私の敬愛する作家中井英夫が優れた乱歩紹介文を書いている。
大学生の頃に中井英夫が大好きになり,小学生時代にはコナン・ドイルも少し読んでいたわりには,私の子供時代は,少年探偵団シリーズの江戸川乱歩を読まず,さらに推理小説の大家である松本清張は,今になっても全く読んでいない。その理由は,江戸川乱歩の作品は,子供だましのレベルの低いものだと馬鹿にしていたことと,同様に松本清張も人気作家ということで,中身のない低級な読み物と一方的に馬鹿にしていたためだった。まさに,偏見に満ちた先入観の失敗例だろう。
しかしその代わりに,エドガー・アラン・ポーやヘミングウェイの翻訳作品を読んだ末に,中学生時代に一番面白くて熱中したのは,イアン・フレミングのジェイムズ・ボンド(007スパイ)シリーズだったのだから,読む方の私のレベルもたかが知れたものだった。当時の私は,「勉強しなくとも試験は大丈夫」という妙な確信を持った「中二病」だったのかも知れない。
それから,高校を卒業して大学に入った頃,渋澤龍彦や種村季弘を読んでいくうちに,生涯最高の作家と信じる中井英夫に出会い,中井が師と仰ぐ江戸川乱歩の価値をようやく知ることになる。思えば遠回りしたものだ。しかし,その当時も,まだ江戸川乱歩を読まなかった。
なぜかといえば,たとえばニーチェの「ツァラツゥストラはかく語りき」を中学生くらいで読んでいたら,その難解さのため半端な理解となったのにも関わらず,ニーチェの超人思想に熱狂的に感化されていたと思うが,一方ではその恐ろしさを直感していたので,私はつい最近まで「ツァラツゥストラはかく語りき」は読まなかった(むしろ,年を重ねてから読んだので,内容が良く理解できたと思う)。とはいえ,大学生の時に「悲劇の誕生」を読んで,ニーチェ思想に十分感化されていたのだが,それでも「悲劇の誕生」はニーチェの文献学者としての著作であったから,影響は軽度で済んで良かったと思っている。
同様に小学生の頃に,もしも少年探偵団シリーズを読んでいたら,もうその世界にどっぷりとはまってしまい,その後の人生をずっと怪奇幻想の世界に生きていたかも知れない。実際,小学生の同級生だったHは,少年探偵団の「信者」であり,クラスの中でも少し異様な雰囲気を持っていた。将来,推理小説作家になると言っていたが,果たして今は何をしているのだろうか。もしかしたら,既に怪奇幻想の世界そのものの住人になっているのかも知れない。
そういう点では,生き馬の目を抜くように世知辛く生きにくい,サラリーマンとしての生活をようやく終えられる定年退職を迎える時になってから,こうして私が乱歩のような憂き世離れした世界に没頭できるのは,存外年寄りに許された良い愉しみだとも思っている。
2.読後感―昭和一桁という時代―
これらの3作品は,皆昭和一桁に書かれている。世界が第一次世界大戦を終え,アメリカを中心とする繁栄の時代を迎えている中,日本も関東大震災からの復興を成し遂げて,新たな娯楽であった映画産業が勃興してきた時代だ。
こうした時代だから,今なら差別語として禁忌されている,身体障害者,職業などへの別称がごく普通に使用されている。また,小説という形態に不慣れな読者を想定した,作者からの丁寧な説明が入っている。さらに,登場人物の台詞がまさにこの時代に使われていた日本語会話をよく再現していて,たとえば小津安二郎作品に出てくる女優が使う言葉と,全く同じ台詞が多く登場する。ここが面白い。
「蜘蛛男」では,当時の東京の狭い町並みが浮かぶような描写がある。今の東京と比べると,23区のさらなる内側が生活圏=都会であったことがわかる。そして,警部と探偵との親密な関係は,今では想像もできないものであるし,さらに警部は着物姿であることが,時代感を良く表している。
「猟奇の果」では,猟奇という言葉がいろいろな意味で使われている。大正時代の名残でいえば,「エロ・グロ・ナンセンス」ということだろうか。主人公は,戦前の暇をもてあましている金持ちの旦那だ。そして,彼は名古屋に住んでいながら,毎月東京の別宅に来るという設定が面白い。そして,東京の友人に会うだけでなく,当時の靖国神社の例大祭の屋台の風景,浅草の各種演芸場の風景などが,興味深く描写されている。そのまま,映画のシーンとして再現したら,かなり面白い「絵」になりそうだ。
しかし,「猟奇の果」は,前半こそ面白い構想で読ませたが,後半は大人版「少年探偵団」のようなストーリーになってしまって,ちょっと気抜けした。はっきり言って失敗作だと思う。その中で面白かったのが,共産主義者イコール悪という図式であることや,政治家に対して当たり前に尊敬している描写が描かれているところが,今から見ると不思議な気分になる。これが昭和初期という時代を,良く反映しているのだろうと思う。もっとも,マルクスもエンゲルスも「共産党宣言」で,自ら共産主義者を悪魔に例えているから,まんざら外れているわけでもないが。
また,後半部分の今でいうところの高度な整形外科手術の部分は,当時としてはおどろおどろしい魔術のようなイメージだったのだろうが,今ではかなり普通になっていることに驚かされる。そう考えると,戦国時代でいうところの「影武者」の現代版が,あちこちにいても不思議ではなさそうだ。むしろ乱歩が想像したもの以上に,世の中はより一層奇怪になっているようだ。
「魔術師」は,3作品の中では,一番出来が良いように思う。解説によれば,乱歩自身も「プロットとしては,私の通俗長編のうちでは,ややまとまりのよいものの一つではないか」と思っていた。しかし,横溝正史は,ストーリーがあるため低俗な印象があると評価しなかった。そして,解説の中島河太郎は,「筆致の充実しているのは,なんといってもこの作品が第一ではないか」と高く評価している。
巻末エッセイに,私の尊敬する中井英夫が,よしなしごと風に乱歩の紹介文を書いているが,乱歩の最高傑作として,長編で「孤島の鬼」,短編で「目羅博士」を挙げている。そして,挿絵の竹中英太郎をひどく絶賛している。一方,「乱歩自身は自分を一種のマイナーポエット,初期短編のいくつかの他は忘れ去られ消し去られても悔いのない異端の小作家でありたいと念じ続けていたに相違ない」と見事な乱歩像を描き出している。私も,直感でそう思う。乱歩は不本意ながら流行作家になってしまったのではないか。
そうした「小作家であり続けたい」はずの乱歩が,思わず構想(ストーリーとプロット)に興が乗り,さらに主人公でもある明智小五郎に女性2人を絡ませる(まるで,フィリップ・マーロウのようではないか?)ことまでもしてしまった長編作品が,この「魔術師」だったのではないだろうか。
ただ個人的には,終わり方が少ししつこい感じがした。魔術師の死で物語としては大団円=カタルシスを迎えている。その後に,もう一山短編として繰り返すような物語は,むしろ不要だったのではないか。最後の話は,別の作品として膨らませた方が良いように思えた。
話は変わる。乱歩のような作品が出現し,またその作品世界に合わせたような不思議な時空となっていた1920年代は,世界的に「エロ・グロ・ナンセンス」の時代でもあった。芸術の世界で,シュールレアリズムが流行し,吸血鬼や精神病患者の世界が映画化された。おびただしい人命が失われた第1次世界大戦(戦死者992万人)と第2次世界大戦(軍人2,500万人,民間人3,700万人,計6,200万人の死者)の狭間にあって,第1次大戦の怨霊から強い影響を受けた後に,第2次大戦の引き金となるような,百鬼夜行=ゲーテの描く「ワルプルギスの夜」のような時空を出現させたのが,1920年代=昭和初期だったのではないだろうか。
今は,第1次大戦から100年が過ぎた。第2次大戦からも75年が過ぎようとしている。いやもっと正確に言えば,百鬼夜行の1920年代からちょうど100年が経った。100年前の百鬼夜行は,芸術やエンターテイメントの世界だけで収まっていたが,今や,乱歩の描き出す夢想のイメージよりもっと激しい,異常かつ猟奇的な事件が世界中で頻発し,そうした事件の渦中に生きる人々の頭の中は,ますます錯乱して,猟奇の世界大戦の渦中にいるように見える。
もしかしたら,乱歩のような気分になっている天上の存在=全能の神が,一人ほくそ笑みながら,次のストーリーを描きつつ筆をなめているのかも知れない。ハハハハハハ(乱歩の表現による,明智小五郎の笑い)。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
