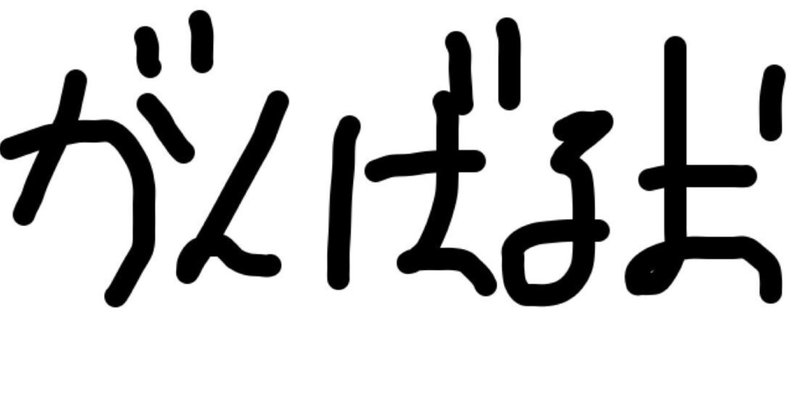
FP3級:社会保険
年金のこともお金のことも無知すぎてFP3級の勉強始めた
ファイナンシャルバンクインスティテュート株式会社編『うかる!FP3級 速攻テキスト 2022-2023年版』参考
インプットだけじゃ意味ないと思うので覚書きの場としてnoteに書いていくことにした
将来の自分が見返して「頑張ったね自分~」とか「ここ分からんかったのね~」と思いたい~
※間違ってる箇所あったらよければ教えてください( ˘ω˘)
社会保険
日本人なら加入してる。日本の社会保険制度はしっかりしてるって言われてるやつ。社会保険料控除の対象。
社会保険料控除=払った分は所得に入れずに、差し引いた分に課税
⑴医療保険
健康保険(健保)、国民健康保険(国保)、後期高齢者医療制度の3種
1⃣健保:組合健保と協会けんぽ
プライベートでやってもーた時
保険料は労使折半。大企業は組合健保(お給料から天引き)、中小は協会けんぽ(都道府県毎に平均寿命が違うから、保険料が都道府県によって異なる)
①療養給付
「3割負担」って聞くやつ。幼稚園児辺りは2割、75歳~は原則1割。というか75~は後期高齢者医療制度に加入
②高額療養費の給付
医療費高すぎた時!うぃ!
③傷病手当金
怪我病気が原因で、お仕事3日休んで4日目から/日給の3分の2/最大1年半
④出産育児手当金
1児産んだら42万、双子なら42×2=84万給付
⑤出産手当金
出産前42日前、後56日(労基で働いたらあかんってなっとる期間)/日給の3分の2
⑥埋葬料
被扶養者・被扶養者死亡時
★任意継続制度
元々サラリーマンを2か月以上してた人/退職日の20日以内(入りたいなら急げ)/最長2年間
健保の方が国保より安い場合、健保に最大2年間加入し続けれる。ただ会社にとって何のメリットもないから、労使折半ではなく、全額自己負担。
2⃣国保
被保険者:自営業者
被扶養者の概念無し、1人1人が加入し市町村に保険料を払う。
健保にあった手当金も無し
3⃣後期高齢者医療制度
健保・国保加入どっちでも75歳以上になったら後期高齢者医療制度にぶっこまれる。原則1割負担、お金ある人は3割負担。保険料は年金から天引き。
⑵介護保険
介護が必要な人にかかる介護費をさぽーと
1⃣保険料
65歳以上の人が年金から天引きやけど、それだけじゃまかなえへん
⇒40~64歳の人にも手伝ってもらう(所得から天引き)
65~:第1号被保険者、40~64:第2号被保険者
自己負担
双方原則1割
2⃣被保険者
☆第1号被保険者
介護認定か支援認定を受けた人/理由不問
☆第2号被保険者
介護認定か支援認定を受けた人/老化が原因
⇒交通事故で介護が必要になってももらえない!
⑶労災
通勤中、お仕事中にやってもーた時/全額事業主負担
⑷雇用保険
基本手当(失業手当)をベースとする保険
1⃣失業手当
☆自己都合退職
離職前2年間に社員期間が
1年以上10年未満→90日間もらえる
20年以上→150日間 etc
☆会社都合
離職前1年間に社員期間が
1年未満→90日間
20年以上かつ45~60未満
(20年も頑張ってくれた、子供養育してる可能性有)→330日
2⃣育児休業給付
出産56日後まで出産手当金入ったところで、育てなあかんねんからすぐには働けんし、いきなり何の給付なくなっても困る
⇒1歳未満の育休中に給付される
最初の半年はお給料の3分の2(=傷病手当・出産手当)
3⃣教育訓練給付
雇用保険に3年以上/受講費用の20%(最大10万円)
④その他省略
⑸年金
日本に住んでる人(20~60未満)は国民年金にぶっこまれ、65~給付されるお金。
1⃣何払うんか
1号・3号⇒国民年金
2号⇒厚生年金
2⃣払うのきつい時:免除と猶予
☆1号のみが対象☆2号は会社が勝手に払っとるから「払えん」とかない。
追納せんと将来の年金額は減る(※但し産前産後の免除)
追納は過去10年前まで遡れる。
①免除(払わんでええ):要届け出の法定免除と要申請の申請免除
法定免除⇒そもそも払うの大変な人向け、全額免除
申請免除⇒所得によって免除率が違う
★産前産後の免除
働けない人がどう保険料払うんか→無理
⇒出産予定日の前月から4か月間は免除、将来の年金が減額することもない
②猶予(待ったるわ、後で払ってな)
学生納付特例⇒20~の学生本人の前年度所得による
保険料納付猶予⇒50未満本人や配偶者の前年度所得による
3⃣給付されるタイミング
①長生きしちゃった⇒老齢給付
②障害で働けなくなった⇒障害給付
③誰か遺して現世からさようならしちゃった⇒遺族給付
★国民年金加入者⇒○○基礎年金、厚生年金加入者⇒○○基礎年金と○○厚生年金
①老齢給付
Ⅰ老齢基礎年金
保険料納付期間+免除期間+合算が10年以上/65歳から給付
最大40年(20-60未ちゃんと払った)で80万程度、納付期間によって給付される年金額が増減する。
ⅰ繰上げと繰下げ
基本的に65~給付だが、以下の①②が可能
①もっと早くほしい!繰上げ
⇒60~64歳の間からもらえるが、その月分×0.4%減額
②まだいらん!繰下げ
⇒66~75の間に貰えるようにでき、その月分×0.7%増額
ⅱ付加年金
また、2号は厚生年金あるからまだええけど、1号は老齢基礎年金だけじゃ生きてけん。この分を付加年金で補うことができる。
希望者は月々の年金に400円多く払う。そしたら年金もらう時期に、200×付加年金保険料を納めた月分増える。
老齢基礎年金の繰上げ・繰下げとは連動する
Ⅱ老齢厚生年金
1か月でも厚生年金に加入しとったら老齢基礎年金と同時にもらえるやつ。
ⅰ繰上げと繰下げ
老齢基礎年金の時と中身・計算は同様。
老齢厚生年金を繰上げ⇒老齢基礎年金も繰上げ
繰下げ⇒老齢基礎年金も繰下げる必要はない
ⅱ加給年金
家族を扶養する用的な感じ
社員20年やってた者が年金受給者に
→扶養してる配偶者(65未満)や子(18未満、場合によっては20未満)がいる場合、それまでのお給料より低額の年金だけでは暮らせない
⇒加給する
★配偶者は65未満
配偶者も65~自身の老齢基礎年金貰えるからそれでなんとかしろ
★子は原則18未満
18~自分で働く者もおるやろ?自分でなんとかせえ
ⅲ在職老齢年金
60↑/ 月給+月年金額=47万以上
⇒「そんなにお給料もあるんやったら年金減ってもいけるよな?」と年金減らす。
②障害給付
年齢関係無し、何かしらの障害でもう働けなくなった時
障害等級1級に近づくほど、重い
Ⅰ障害基礎年金
対象者:障害等級1級・2級
要件:初診日に国民年金をちゃんと払ってる人
⇒初診日も加入者やし、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料納付
年金額:子供養ってたら約80万なんかじゃ足りんので、子の加算がある
2級:約80万+子の加算
1級:2級分×1.25+子の加算
Ⅱ障害厚生年金
対象者:障害等級1級・2級・3級
要件:初診日に厚生年金をちゃんと払ってる人
⇒初診日も加入者やし、初診日の前々月までの被保険者期間のうち3分の2以上保険料納付
年金額:こっちは3級以外は配偶者の加算がある
3級:収入に応じた年金分(報酬比例部分)のみ
2級:報酬比例部分+配偶者の加算
1級:報酬比例部分×1.25+配偶者の加算
③遺族給付
Ⅰ遺族基礎年金:亡くなった人の子ども養育費
⇒子がいないと貰えない。
受給対象者:
原則18↓の子がいる、遺された配偶者
OR
両方の親がいなくなった、原則18↓の子
子がおらず遺族基礎年金が貰えない、
死別した配偶者がサラリーマンではなく自営業の為に遺族厚生年金も貰えない、遺された配偶者は??
⇩
ⅰ寡婦年金
(女性のみ)
10年間の婚姻関係/ 夫が国民年金保険料を10年以上納付していた
⇒60-65未まで、夫の老齢基礎年金の4分の3給付される
※59までは保険料払う期間、65以上は自身の老齢基礎年金が給付される歳
ⅱ死亡一時金
3年でも国民年金払ってたら遺族がもらえるやつ
Ⅱ遺族厚生年金:遺族の生活費
受給対象者:死亡者の被扶養者(優先順位あり)
年金額:老齢基礎年金の報酬比例部分(死亡者が貰えるはずだった年金)の4分の3
ⅰみなし
★社員期間がわずかしか無かったら?(早死等)
⇩
遺族には少ししか入らない、何の足しにもならん
⇒社員期間が300月以下の場合、もう300月とみなす。
ⅱ中高齢寡婦加算
(女性のみ)
★18未とかの子どももいないため遺族基礎年金はもらえない、
サラリーマンだった夫が亡くなった、もうこれから働き始めるのが難しい妻
⇩
遺族厚生年金だけでは足りない
⇒妻が40-65未の間は中高齢寡婦加算で補う
(※40↑女性は就職が難しい、65~は自身の老齢基礎年金もらえる歳)
★夫亡くなる⇒遺族厚生年金受給開始、18未の子どもいた⇒遺族基礎年金受給開始、その後子供が18↑⇒遺族基礎年金打切り
⇩
遺族厚生年金だけになり、生活が大変
⇒この場合にも中高齢寡婦加算受給対象。
(但し妻が65になるまで。65~は自身の老齢基礎年金が入るからそれで何とかしろ)
4⃣企業年金
国からの年金だけじゃ足りん、自分で積み立てて将来受け取るやつ
個人型(いでこ)はよー聞く
メリット
掛金納める時に税金払ってないから、老後貰うときに一定程度の税を納めなあかんけど、それでも退職所得控除か公的年金控除でお得らしい
掛金納める時も、納めた分は「小規模なんちゃら」ゆうやつで所得控除なって良きらしい
税金のこと未知すぎてこの辺よー分からん
掛金には国民年金の被保険者別に上限額が異なる
★個人型(iDeCo)の場合
1号:「厚生年金貰えへんから多めに掛けとけよ」⇒上限68,000円/月
2号:「厚生年金貰えるけどまあそれなりに掛けとけ」⇒23,000円/月
3号: 同上
★企業型の場合
2号が会社と積立て頑張る的なんもできるんやね!
上限は55,000円/月
企業入ってないから実感なくて最後らへんまじでよー分からん
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
