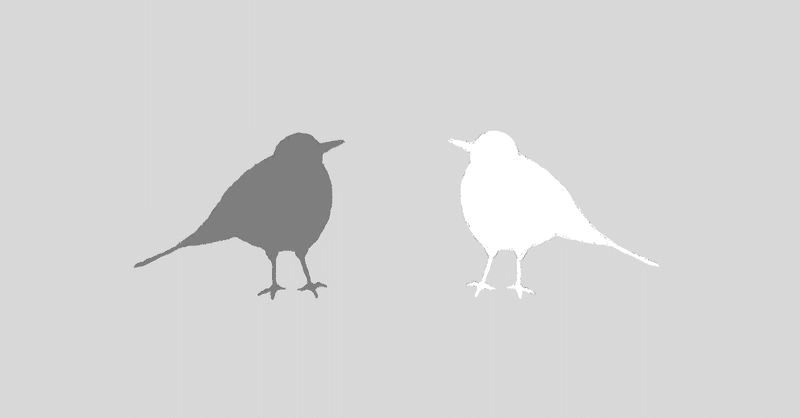
ゆめゆめ、きらり #5
すこしずつ、もやもやした視界のなかに緑が戻ってきて、薫りが強くなったなとみかこでも感じられるようになったころ、急に、視界がぱっとひらけた。
そこは、ほの暗い、緑の箱の中みたいなところだった。
絡まりあうツタと鳥の足あとのような大ぶりの葉っぱが重なって、四角い部屋をつくりだし、隙間からちらちら見える白くて細い古びた角材が骨組みになって、その空間を支えている。
天井から、ところどころにぶら下がっているぶどうのような赤いふさは、濡れそぼったつららのごとく、しっとりと、あでやかだった。
キャスケットは、そこにいた。我がもの顔で座りこみ、赤いふさにばくり、ばくりとかぶりついている。
「兄さん」
とがめるような声を出して、シルクハットが近づいた。みかこも続く。キャスケットは、ばくりばくりの合間に、彼らを一瞥しただけだった。澄まし顔でむしゃむしゃして、また、ばくり。
「心配したんだがね、兄さん」
顔をしかめたシルクハットは、けれど、それ以上なにも言わなかった。キャスケットは拍子抜けしたように目をまんまるにして、弟ネコを見やった。
みかこは、天井に顔を向けた。
赤いつららは、みかこの頭よりもすこし高い位置にぶらさがっている。両手を伸ばした。もぎってみる。手のひらからこぼれ落ちそうな粒たちは、ひとつひとつがつるつるしていて、まるで、クランベリーがぎゅっと身を寄せあっているかのようだった。
一粒もぎって、目をきらきらさせて覗きこんでいる少女に渡してあげる。みつまりを膝に置いた彼女は、それよりふたまわり以上も大きな粒をかかえるようにして受け取った。
「食べてみなよ。あまくてうまいよ」
口のまわりを果汁でまっかにしたキャスケットがうながす。
みかこは、もう一粒もぎって、かじってみた。ぷつ。皮の切れる感触があって、みずみずしい甘さが口いっぱいにはじけた。酸味も渋味もなく、ただただ、あまい。よく熟れたいちごみたいだった。
みかこと少女が顔をほころばせる。
「どれ」
と、ステッキの柄を引っかけてひとふさもぎとったシルクハットも、一粒つまんで口の中にひょいと入れた。咀嚼して、ほお、と感嘆の声をあげてから、また一粒。ふむ、とうなずいて、また一粒。
みかこたちは、しばらく、夢中になって、そのあまくておいしい果実をほおばった。そのうち、一足先に満足したらしいキャスケットが、すっかりみすぼらしい姿に変わった茎をぽいと捨て、げふっとにごった息をはいた。
「兄さん」
「ふう。腹がふくれた」
「兄さん」
「うん、わかってる」
「口のまわりもよごれている」
「わかってる、わかってる。これからきれいにするところだ」
「それならいいがね」
シルクハットは、それきり口をつぐんで、ふらっとみかこたちから離れた。ぶらさがるふさを吟味して、ステッキの柄を引っかける。
そんな弟ネコの後ろ姿を、キャスケットは目をまんまるにして眺めていた。
「弟がへんだ。気味がわるい」
みかこは笑った。最初の一粒を、やっと半分まで食べ進めた少女を見やる。
「怒られたのよね、さっき。お兄さんのこと、悪く言ったらだめって」
「そうか。それでか」
少女が、ちょっぴり焦ったふうに身じろいだ。
「あのね、悪くっていっても、べつに悪口を言ってたんじゃなくてね」
「うん、わかってる」
キャスケットは、少女をさえぎってうなずいた。手をなめ、よごれた口まわりをこすりはじめる。
「弟のあれは、ころころ変わる口癖みたいなもんだ。それに応える、おれのあれも。おれたちのけんかは、ぴりっとからい、ただの会話だ」
それを聞いた少女がうつむいた。
「ごめんなさい。私、よけいなことを言ったみたい」
「よけいなもんか。いいくすりだ、弟にも、おれにも」
キャスケットは、食べかけの実をつまみあげた。あ、と少女が驚くうちに、自分の口の中にぽいとほうりこんでしまう。
「それにしても見る目がないなあ。あっちのほうが熟れてるよ」
そう言って彼がとってきてくれた新しいふさは、見た目こそまったくおんなじなのだけれど、食べてみると、彼の言うとおり、とびっきり、あまかった。
「これ、おばあちゃんに持っていってあげたいな」
少女が、みつまりとあまい実をどうやって一緒に持っていこうかとむずかしい顔で試行錯誤をはじめたので、みかこはくすっと笑って、鳥の足あとみたいな葉っぱを一枚ちぎり、赤い実を数粒、ていねいにつつみこんで、ポケットにそっとしまっておいた。
すっかり満足したみかこたちは、冬枯れの雑木林を抜け、緑豊かな森を歩いて、ひとまずの目的である『キリカブ』を目指した。
前を歩くふたりのネコはしばらく黙りこくっていた。けれど、ふと、シルクハットが口をひらいたことで、こんな会話が交わされた。
「兄さん。私はそんなにつめたいかね」
「つめたい」
「そうか」
「それにくわえて気味がわるい、いまのおまえは」
「失敬な。そういう言い方はよくないと思うんだがね」
「おれが一度でも、いい言い方をしたことがあるか」
「ないな」
「だろう。おまえもそうだ、おれに対しては」
「ふむ。確かにそうだ」
兄弟ネコは、それきりまた黙りこくって、肩を並べててくてく歩いた。
森を抜けたみかこたちは、やっと、川岸に出ることができた。
みかこはほっと安堵した。久しぶりとも思える川の景色は、森に入る前となんら変わりがない。どのくらい下ったんだろう、『キリカブ』とやらはどこにあるんだろう、と、あたりを見渡した。
すると、ちょうど森と川岸一帯との境目あたりに、少年がいた。
おしりを置いてもまったく余る、大きなキリカブに腰かけて、森に、みかこたちに背を向けて、川に向かって絵を描いていた。というよりも、絵の具を塗りたくっているみたいだった。土に差し込んだイーゼルに横向きに乗せられたキャンバスは、すでに色であふれている。それでも少年は、絵筆を動かし続けていた。
興味をひかれるまま、少年の背後にそっと寄ったみかこは、驚いた。
そこに描かれていたのは、ぼうぼう伸びた草むらと、大きくうねる濁流だった。空は原色の青色で塗りつぶされていて、川の向こうにそびえる森は、黒をまぜこんだ暗い緑で彩られもわもわ動くかたまりのようである。
目に映るものとは、まるで違う。
全体的に太く、濃い配色で、独創的とも思える絵だった。
少年は、みかこに気づくなり、ぎょっとして立ち上がった。とさりと落ちた絵筆が、うぐいす色の草に青いしみをつくる。
「ごめんなさい、驚かせて」
みかこは絵筆を拾って差し出した。
けれど、少年は受け取らない。パレットを握りしめ、拳を脇に垂らしたまま、いぶかるように、みかこをじろじろ見た。それがあんまりとげとげしくて強い視線だったので、みかこは萎縮してしまった。肩に乗っていた少女も、みつまりでさっと顔を隠してしまう。
みかこの後ろから、ふたりのネコがひょっこりと顔を出した。
「ふむ。これはなかなか」
「へんな絵」
少年の頬がかっと赤らんだ。乱暴にキャンバスを掴むと、なんのためらいも見せずにぶんと腕を横に振り、川に向かって、それを放り投げてしまった。
「なんてことを。もったいない」
少年は、シルクハットをにらみつけた。ふいっとみかこたちに背を向けて、どかっとキリカブに腰を下ろす。パレットを叩きつけるようにして横に置いた。
「兄さんが失礼なことを言うからだ」
「おまえだって」
「私は、芸術的だと褒めるつもりだった」
ぼそぼそ言い合う兄弟ネコの声は、少年にも届いているはずだった。けれど彼は、腕組みをしたままぴくりとも動かず、なにも言わない。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
