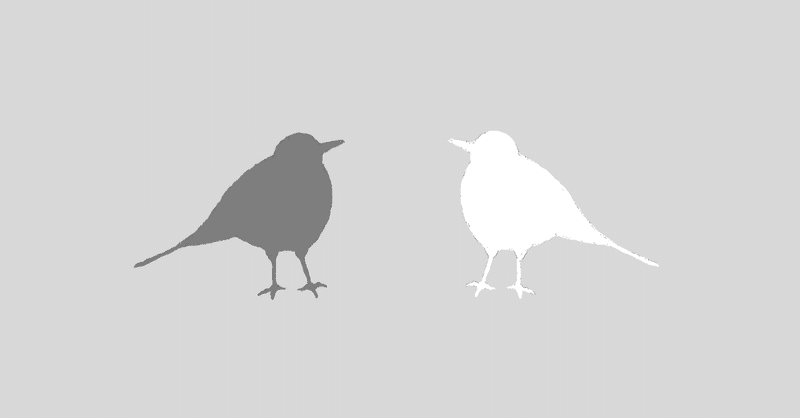
ゆめゆめ、きらり #6
「ごめんなさい。邪魔をするつもりじゃなかったんだけど」
みかこがもう一度謝ってみても、少年は押し黙ったままでいる。隣にしゃがんで、これ、とふたたび絵筆を差し出したとき、ようやく彼の黒々とした瞳がついっと動いた。絵筆を見下ろす。
「いらないよ」
「でも」
「いらない」
みかこはすっかり困りはてた。さすがにキャスケットもまずいと思ったのか、おずおずとみかこの傍らに立ってしっぽを垂らす。
「すまん。へんだなんて言って」
少年の瞳が、またついっと動く。
「べつに。ぼく、怒ってるんじゃないから」
「じゃあどうしてそんなこわい顔をしてるの」
少女が、みつまりから目をのぞかせた。けれど少年の瞳がそっちに動いたとたん、またすぐに隠れてしまった。少年はそれをじっと見たあと、穏やかな川へと視線を投げた。
「つまんないからさ」
「つまんないの?」
少女が目をのぞかせる。
「そうだよ、つまんない」
「どうしてつまんないの? なにがつまんないの?」
少年の口がへの字に曲がった。それに気づかない少女は、なおも重ねて聞く。
「つまんないから、こわい顔をしてるの?」
「うるさいな」
いらだった少年の声に、少女は慌ててまりを持ち上げた。見兼ねたシルクハットが口をはさむ。
「君、そういう言い方はよくない」
「うるさいってば。あっち行ってよ」
少年の表情がゆがむ。くるしんでいるみたいな顔だった。
「絵、すきなの?」
みかこが聞いた。
「べつに。つまんないから、描いてるだけ」
「そう」
みかこは少年の答えを、こころそのままのものとは受け取らなかった。けれど、それを表に出すこともしない。ただちいさくうなずいて、相槌を打った。
少年がちらりとみかこを見た。みかこは気づかないふりをして、さらさらと、涼やかなせせらぎが聞こえてきそうな川面を眺めた。
「私は、絵を描くのすき。昔ね、絵の勉強をしたことがあるの。そのくらい、すき」
少年はなにも言わなかった。みかこが続ける。
「この世界をえがけたら、とってもすてきね」
「ぼくはきらいだ。だいっきらい」
少年は、低くうめくようにして言った。
「絵のこと?」
「この世界のことだよ」
「どうして。こんなにきれいなのに」
「きみはこの世界のひとじゃないから、そんなふうに言えるんだ。ぼくがきみの世界に行ったら、きっと同じことを言うよ」
その反論は、みかこにとって意外だった。ぱちりと瞬いて、少年を見る。
「そうかしら」
「そうだよ」
「きれいじゃなくても?」
少年は答えなかった。ただ川を見据え、まわりの空気をいっそうかたくさせるばかり。
この少年は、削りたてのエンピツのつんととがったさきっちょみたいだ。やさしい水彩画のような世界の中で、彼だけがひとり、がりがりそがれた黒鉛みたいに、重たくとんがっている。
みかこは、絵筆へと瞳を落とした。乾きはじめた筆先が、癖づいた形を取り戻そうとばかりにぼわんと広がっている。みかこの目に、強く握りしめた絵筆をキャンバスに押しつけ、乱暴に動かしている少年の姿が浮かんだ。
「きみの世界の話をしてよ」
ぼそっと聞こえた少年の声に、みかこは顔を上げた。思わぬ要望にちょっとびっくりして、呆けた顔で聞き返すと、少年は、同じことを同じ調子で繰り返した。
みかこは、首をかしげてうなる。
「ううん、どんなことを話したらいいのかしら。話せるような特別なことなんて、なんにもない。色であふれるこの世界と、ぜんぜん違うんだもの」
「たとえば」
少年は、みかこを見もせず淡々と聞いた。
「そうね。森も川もあるけれど、どこか灰色っぽい気がする。空だって、どんよりくもってばかりだし。ひともそうよ。みんなみたいにきらきらしてなくて、いつも、毎日、追い立てられてるみたいなの。自分のことでせいいっぱい。私もそう。私のまわりのひとたちもそう。みんな、そう」
少年は黙って聞いていた。けれど、みかこの声が途切れるなり、またぼそりとつぶやいた。
「きみはばかだ」
え、とみかこがまたびっくりすると、少年は振りかえって、「ばかだ」ともう一度言った。
少女がむっと眉を寄せる。
「どうしてばかなの」
少年は、みかこの手から絵筆を奪い取った。彼が向き直ったイーゼルには、不思議なことに、いつのまにかまっさらなキャンバスが掛けられている。
絵筆を握りしめた少年は、パレットを取り上げ、紺色をすくって乱暴に筆先をすべらせた。
「きみは知らないんだ。つまんないの本当の意味を。ぜんぶ知ってるみたいな顔でいて、それだけはわかっちゃいない」
上半分が、紺一色に塗りつぶされた。ゆっくりと離れた筆先が、違う色をひろう。
「ここがきれいだと思うのは、くすんだ空を知っているからだ。きらきらして見えるのは、暗い夜を知っているからだ」
夜空に、黄色、白、赤色の点がぽつぽつと乗せられていく。乾ききらない紺色がにじんで、打たれた点が、見る間に暗く染まっていく。
「ぼくは、この世界の色の一部でしかないから、……」
少年は、先の言葉をのみこんでしまった。唇を真一文字に引き結び、キャンバスをにらみつける少年の瞳に、悔しさとかもどかしさとか、はがゆさとか、いらだちだとか、そんなさまざまなものが浮かんでは消え、にじんではとけていった。
「ふむ、ひとつわかったことがある」
それまで沈黙していたシルクハットが、まじめな顔を少年に向けた。
「君がつまらないんだな」
「さっきからそう言ってるじゃないか」
「そうじゃない。この世界がつまらないんじゃない、君自身がつまらないやつだと言ってるんだ」
少年は、強張った表情のなかですこしだけ目を見ひらいた。顔をゆがめて、シルクハットをにらみつける。
シルクハットは、臆することなく続けた。
「だってそうだろう。きれいなものをきれいだと思えないなんて、世界がつまらないからただつまらない気持ちでいるなんて、そんなつまらんことはない。私の兄を見たまえ」
突然矛先を向けられたキャスケットは、きょとんとしたまま、なんだ、と言った。
「兄さん。腹がへったらどうする」
「食う」
「食べものがなかったら」
「さがして、食う」
「それがまずかったら、どうする」
「うまいものをさがして、食う」
「ほらごらん」
シルクハットは少年に向き直った。
「私の兄は、こうだ。君は、どうだ」
少年がうつむく。握りしめた絵筆が、ふるふると静かにふるえた。
たしかに、そう。
シルクハットのそれは、正論に違いない、けれど。
みかこは、パレットに乗った白色の絵の具を、指先でちょんとつついた。ひとさし指にくっついたそれを、すっかり乾いた夜空の上で、横に、横に、動かしてみる。筆よりも濃く、でも不思議と色が絶えることはなく、白い線がいくつも伸びていく。
「ながれ星みたい」
少女が声をはずませる。みかこはただ、ふふ、と笑った。
今度は、パレットの上で緑と白をまぜあわせて、クリームみたいな薄緑色をつくった。キャンバスの下のほうに、好きに、気ままに、縦の曲線をえがいていく。
「夜がすきなの?」
「わかんない。じっさいに見たことがないから」
少年は、みかこの指がえがくものを食いいるように見つめたまま、ほとんど無意識みたいな口調で答えた。
「見たことないの?」
「うん」
「夜がないんだ、ここは。ずうっとこうだ」
キャスケットが指さした空は、一点のくもりもないかわりに、太陽の姿もどこにも見えなかった。このとき初めてそれに気づいたみかこは、なんとなく、なんとなくだけれど、少年の言う「つまんないの意味」を知ったような気がした。
みかこは息吹きはじめたキャンバスを眺めたあと、青と白をすくってまぜあわせた。
「雨はふるの」
「雨もふらない」
「じゃあ嵐もこないのね」
「うん、こない」
「あの川も、森も、空も、ずうっときれいなままなのね」
少年の返答はなかった。みかこは、つくったばかりの水色を、夜空と草むらの間に、横向きにすべらせていく。
「私、あなたの絵、すき」
少年は、やっぱりなにも言わなかった。けれど不意に、絵筆をぽいっと草むらに投げ捨てた。ちいさな指先に青い絵の具をちょんとつけて、みかこの引いた水色の上に横筋を描き足していく。
それを見守りながら、みかこは、ぽつりとひとりごちた。
「何色かしら」
「青だよ。見てわからないの」
少年は、今度こそ本当に馬鹿を見るみたいな目をみかこに向けた。みかこは思わず、ぷ、とふきだす。
「違うの。そうじゃなくて。ぼくはこの世界の色の一部――って、さっき言ってたでしょう。そうだとしたら、何色になるんだろうって思って」
「ああ、そういうこと」
納得したとたん、少年の関心はキャンバスへと戻っていった。みかこもまた、彼の指の動きを見守った。
「透明じゃなくて、ちゃんと自分に色があること、知ってるのね」
「……透明かもしれないよ」
「そうかしら」
「知らないよ。ぼくにだってわからない。だからきみに、そうとも違うとも言えるはずないってことだよ」
少年の声がとげとげしだした。口がへの字になった。
けれどみかこはひるむことなく、むしろ、いたずらをしかける子供のように肩をすくめて、
「言えるの、じつは」
と、笑んでみせた。少年の瞳がついっと動く。
みかこは川に視線をやって、そこに、流れてしまったのか沈んでしまったのかわからない、あのごうごうした少年の絵をうつす。
「透明なひとには、きっと、あの絵は描けない。それにね」
みかこは少年に瞳を戻して、また笑んだ。
「どう見たって、透明人間には見えないもの」
少年は、ぽかんと口を開け、キャンバスから指を離してみかこを見た。
「違いない」
そう言ってシルクハットが笑いだした。つられるように、少女も、うふふ、と肩を揺らした。
少年は、みかこたちをぐるりと見回してから、口を引き結んで、黒い瞳をキャンバスに戻した。
そこに描かれた不自然な世界。夜ににじんだ星が飾り、真昼に見るような若草が飾り、そして、夜空を映す水面とは思えない、陰影のついた水色の川が、その間を一直線に流れている。なにもかも、ちぐはぐ。けれどみかこは、とても満足のいった顔で、その絵を眺めた。少年も、眺めた。
「へんな絵だ、さっきより」
キャスケットがそうつぶやいても、少年は怒らなかった。無言のままパレットから黄色をひろって、左の草むらに塗りこみはじめる。
みかこは立ち上がった。ポケットを探り、たたんだ葉っぱを取りだした。赤い実を一粒つまんで、少年の横に、キリカブに乗ったおしりの隣に置いておく。
ネコの兄弟たちと、その場を離れようとしたときだった。
「また来てもいいよ」
ひとりごとのように、ぶっきらぼうに少年が言った。
みかこはちいさく笑った。それから、キャンバスの中の夜のような初夏のような風景と、黄色いまるが草むらのはじに集まっているのを眺めて、ふたりのネコと少女と一緒に、川下に向かって歩きだした。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
