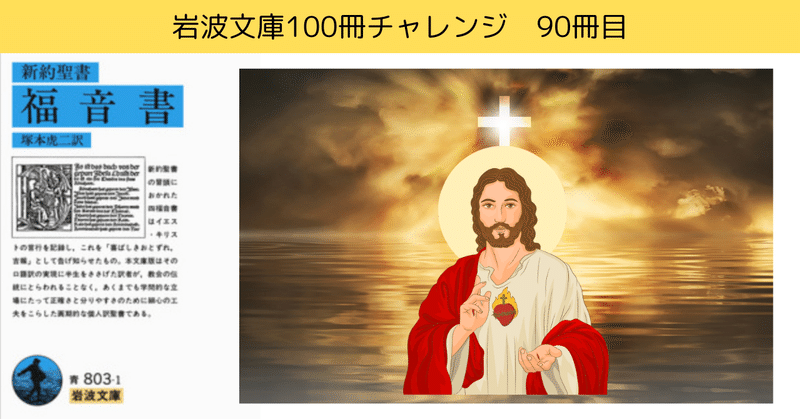
急所だけ!新約聖書おさらい【福音書】岩波文庫チャレンジ90/100冊目
チャレンジを通して岩波文庫の旧約聖書「創世記」「出エジプト記」「ヨブ記」を読んできた。いよいよ新約聖書へ突入!(この機会に聖書関連をマガジンに致しました)
急所と言っても色々あるので、気になるところをつまんでどうぞ!
キリスト生誕から復活までの大まかな流れになっていますが、目次にしているのは有名だろうエピソードだけです。
そもそも聖書って
旧約聖書39巻、新約聖書27巻、本来は計66巻。
現在岩波文庫で学んでいるのは、ごく一部。
聖書のことをバイブル、ビブリヤとも言う。
ビブリヤはギリシャ語で数冊の本、ラテン語では一冊の本を意味するらしい。なるほど、数々のエピソードを1冊にまとめたものだ。
旧約聖書はユダヤの経典、ユダヤ人にとっての聖書は旧約聖書だけ。
新約聖書はキリストの経典、キリスト教徒にとっての聖書は新旧両方の聖書を指すらしい。
根底にあるもの
・神は選民ユダヤ民族に、永遠の国を与える事を約束
・1人の救世主が現れて人々を救い、永遠の幸福が訪れることを預言
・救世主はヘブライ語でメシア、ギリシャ語でキリスト
・ガリラヤのナザレに生まれたイエスは、自分が救世主であると宣言
・怒ったユダヤ人は、イエスを神を冒涜するものとして十字架に磔にした
この流れで、新約聖書ではキリストを救世主とする数々の奇跡が記される。といっても新約聖書は、キリストの奇跡(歴史)である福音書+手紙+ヨハネの啓示(最後の審判)までを指す。
と、ここまで本書にあった解説の内容でございます。
マルコ・マタイ・ルカ・ヨハネ福音書
本書には4つの福音書が収録。同じエピソードが含まれており、いずれかの福音書にしか含まれていない話は少ない(ルカだけは、親切なサマリヤ人、放蕩息子、不埒な番頭などの特有エピソードが多い)。
おかげで同じ話を4回読める。いずれにも出てくる話はそれだけ重要なんだろうと思いつつ、以下は一般的に有名と思われるエピソードを抜粋。
4回も読んだのにいずれ忘れてしまわぬために・・
数々の奇跡&有名エピソード
有名エピソードだけ小見出しがついています。
それでは一気見を、どうぞ!
〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜〜
・受胎告知
天使ガブリエルが、ガラリヤのナザレに遣わされ、ヨセフとまだ婚約関係にあったマリヤに告げる「あなたは子を授かり男の子が生まれる。その名をイエスとつけよ」(ルカ)
・東方三博士
東の国の博士たちが、ユダヤの町ベツレヘムで誕生した救世主を拝み、黄金・乳香・没薬を捧げる。幼子イエスを殺そうと目論むヘロデを出し抜いて国へ帰る(マタイ)。
・イエス、洗礼者ヨハネからヨルダン川のほとりで洗礼を受ける
・湖で網を打っていた漁師の兄弟を最初の弟子にする
さぁ、ついてきなさい。人間の漁をする漁師にしてあげよう
・カペナウムで数々の病気を治癒、悪霊を退治
・カナの婚礼
ガリラヤのカナで婚礼がある時、イエスと弟子も招かれた。宴会の最中に酒がなくなった。「水瓶に水をいっぱい入れよ」と言われると、水が酒に変わった。(ヨハネ)
・12使徒選ばれる
・サンタ・マリア・デレ・グラツィエ教会の食堂に描かれた「最後の晩餐」
・左からバルトロマイ、小ヤコブ、アンデレ、イスカリオテのユダ、ペテロ、ヨハネ、キリスト、トマス、大ヤコブ、ピリポ、マタイ、タダイ、シモン
*ちなみに、12使徒にキリストを加えた13が縁起が悪いとされる所以です。

・洗礼者ヨハネの首を
ヘロデ王は兄弟の妻と結婚、咎めたヨハネを牢につないでいた。その事でヨハネを恨んでいた妻。ヘロデの誕生祝いで娘(サロメ)が舞をまう。人々を喜ばせたので「欲しいものがあったら言ってみよ、褒美にやろう」。母の願いを聞いていた娘は答える。
洗礼者ヨハネの首を
王は悲しんだが、ヨハネの首を持ってくるよう命令。首斬役はヨハネの首を盆に乗せて娘に渡し、娘はそれを母へ渡した(マルコ)。
「サロメ」も感想を書いているのですが、初期に書いたブログ・・なんて拙い😂読み直して自分に衝撃を受けた(笑)。
・五千人のパン
伝道の旅から帰った12使徒「村で何か食べるものを買わせてください」。イエス「手許にいくつパンがあるか見て来なさい」。使徒「パン5つと、魚2匹です」。すでに多くの群衆に囲まれていたイエスは、人々を1組1組分けて座らせ、5つのパンと2匹の魚を人々に配った。皆が食べて満腹した。その数男5千人。
・湖の上を歩く
集まった群衆を解散させるため、弟子たちを強いて舟に乗らせ、イエス自身は陸に残っていた。舟が湖の真ん中へきた頃、ひどい向かい風で漕ぎあぐねていると、イエスは湖の上を歩いて来られた。「安心せよ、こわがることはない」と言ってイエスが船に乗ると風は止んだ。
・姿が変わる
イエスはペテロ、ヤコブ、ヨハネだけを連れて高い山に登られた。すると彼らが見ている前でイエスの姿が変わり、真っ白に輝き出した。イエスはエリヤ*とモーセと共に話をされていた。
*エリヤとは、モーセと並ぶ預言者の代表格的存在
*ラファエロの絵で見るキリストの両側2人がエリヤとモーセですね

・皇帝のものは皇帝に
イエスを快く思わない者が、言葉尻を捉えようと尋ねる「わたし達は異教人である皇帝に、税を納めてよろしいでしょうか。納めるべきなのでしょうか」。イエスは彼らの偽善を見抜いて答える「デナリ銀貨を見せなさい、これは誰の肖像か」。彼らが言う「皇帝のです」。イエスが答える。
皇帝のものは皇帝に、神のものは神に返せ
・天国の鍵
イエスが弟子に尋ねる「世間はわたしのことをなんと言っているか」。ペテロ「救世主、生ける神の子!」。イエスは喜んでペテロに答える「私もあなたに言おう。あなたはペテロ(岩)、私はこの岩の上に集会を建てる。黄泉の門(死の力)もこれに勝つことはできない。私はあなたに天の国の鍵を預ける」(マタイ)
・ユダの裏切り
それぞれの福音書で少しずつ内容が足されていて面白い。
マルコでは、イエスを売ろうと大祭司連の所へ出かけ、金をやると約束される。
マタイでは、イエスを売る代わりに、銀貨30枚を払い渡される。
ルカとヨハネでは、裏切りのユダにはサタンが入った事になっている。
*12使徒の所に載せた「最後の晩餐」、よ〜く見るとユダの手には銀貨
・最後の晩餐
種なしパン*の祭の初めの日、過越*の食事の席でのこと。
「あなたたちのうちの1人、私と一緒に食事をする者が、私を敵に売ろうとしている!」
パンを手に「取りなさい、これは私の体である」
杯を手に「これは多くの人のために流す、私の約束の血である」
*種なしパン、過越の日は共に旧約聖書に出てくる内容
・今夜、鶏が2度鳴く前に
イエスが弟子に向かって「今夜、あなたたちは一人残らず信仰につまずくであろう。“私は羊飼いを打つ。羊は散り散りになるであろう“と、聖書に書いてあるから」。決してつまずきませんと言ったペテロに対して、
今夜鶏が2度鳴く前に、あなたは3度、私を知らないと言う
・ゲッセマネの祈り
*十字架に処せられる前夜の祈り。「オリーブ山の祈り」とも呼ばれる。
オリーブ山の麓ゲッセマネにて「私の祈りが済むまで、ここに座って待っておれ」と言われると、急に怯え出し「心が滅入って死にたい位だ。ここを離れずに、目を覚ましていてくれ」。祈り終わったイエスが戻ってくると弟子たちは皆寝ていたため叱責される。
・ユダ「私が接吻するのがその人だ」、イエス捕縛される
・最高法院の審問で死罪が確定
・イエスの仲間だと言われたペテロ「3度知らない」と言う
・ピラトの審問
・ゴルゴダの丘(とヴェロニカのハンカチ?)
民衆はイエスに紫の衣を着せ、茨の冠を被らせ王に見立てる「ユダヤ人の王、万歳!」と叫んで喝采。葦の棒で頭を叩き、唾を吐きかけた。十字架を背負わされながらゴルゴタの丘(髑髏の所)へ。
紫の衣を脱がせて元の着物を着させ、籤を引いてその着物を自分たちで分けた。民衆が罵倒する中、イエスは息絶えた。すると聖所の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。
「この方は確かに神の子であった」
遠くからマグダラのマリヤ、小ヤコブの母マリヤ、サロメの他、多くの女たちが眺める。
*あれ?ヴェロニカのハンカチエピソードがない?
「ゴルゴダの丘へ向かう途中、ヴェロニカがキリストの顔をハンカチで拭うと、キリストの顔が浮かび上がっていた」
有名ですが、福音書には出ていないエピソードでした。
・アリマタヤのヨセフ
磔刑の日は、安息日の前日。安息日にはシ体を十字架にかけておくことが許されなかったので、アリマタヤのヨセフが来て、イエスの体の下げ渡しを乞うた。それから墓へ埋葬した。
・復活
翌日、日が暮れて安息日が終わる。先の女3人がイエスの体に香油を塗りに墓場へ出かけると、墓の入り口に転がしてあった大きな石がない。近くにいた白い衣の青年「十字架につけられたイエスは、もう復活されてここには居られない。さぁ行って、弟子たちに“イエスはあなたたちより先にガリラヤにいかれる“と言いなさい。」
イエスは預言通り、そのシ後3日後に復活。そして弟子たちに言われる。
全世界のすべての人間に福音を説け。信じて洗礼を受けるものは救われ、信じない者は罰せられる。
譬話とその意味
キリストは教えを話される時、弟子たちには意味を説明しても、弟子ではない民衆には譬しか話さなかったと言う。
・種まきの話
種まく人が種まきに出かけた。まく時に、あるものは道端に落ちた。鳥が来て食ってしまった。またあるものは土の多くない岩地に落ちた。土が深くないためすぐ芽を出したが、日が出ると焼けて、しっかりした根がないので枯れてしまった。またあるものは茨の根がはっている中に落ちた。茨が伸びてきて押さえつけたので、実らなかった。またあるものは良い地に落ちた。伸びて育って実って30倍、60倍、100倍の実がなった。
ー種まく人とは神の御言葉をまく人
ー道端のものとは、御言葉がまかれた時、サタンが来て御言葉をさらってゆく人
ー岩地にまかれたものとは、御言葉を喜んで受け入れるが、信仰の根がなくすぐに信仰から離れ落ちる人
ー茨の中にまかれたものは、世の中の心配や惑わしで御言葉を押さえつけられ、実らない人
ー良い地にまかれたものとは、御言葉を聞いて、受け入れ、実を結ぶ人
・タラントの話
天の国は、旅行に出かける人が僕たちを呼んで、財産を預けるようなもの。
ある時主人が、僕のそれぞれの力に応じて1人には5タラント(1500万円)、1人には2タラント、1人には1タラントを渡して旅行に出かけた。5タラント預かった者は、働かせてさらに5タラント儲けた。2タラントの者も2タラント儲けたが、1タラント預かった者は、地中に金を隠しただけだった。
日が経って主人が戻り、お金を清算。5タラント預かった者「ご覧ください。他に5タラント儲けました」。主人「感心感心。忠実な僕よ。忠実であったから、多くのものを管理させよう」。2タラント設けた者にも同じように言われた。
1タラント預かっていた者には「怠け者の悪い僕よ、埋めておくだけなら銀行に入れておくべきであった。利子をつけて戻してもらえたのに」そう言って、1タラントを取り上げ、10タラント持っている者に渡され、外の暗闇に放り出した。
持っている人はさらに与えられてあり余るが、持たない人は持っているものまで取り上げられる(マタイ)。
遥かなる記憶を辿ったら「座右の寓話」にも「与えられたタラント」として同じ話が載っていました。以下はこちらの本の解釈の内容です。
*タラントはタレント=才能、の語源
*冒頭の1文と合わせて考えると、旅に出る主人から与えられたタラントとは、各人が神から与えられた才能。主人の旅とは人の一生。主人の帰宅は寿命が尽きたこと。旅から戻ってきた主人が財産を数えるのは、シんだものが天国に行けるかどうかを判断したことを意味する。天国に入れる人は、自分の才能を無駄にしなかった人。天国に入れない人は、自分の才能を無駄にした人。
・断食問題
最後に断食問題。どの福音書にも説明がない。
「ヨハネの弟子とパリサイ人の弟子は断食をするのに、なぜあなたの弟子は断食をしないのか。」
イエスが答えて言う。
「婚礼の客は花婿がまだ一緒にいるうちに、断食をして悲しむことが出来ようか。もちろん花婿と一緒にいる間に断食は出来ない。しかしいまに花婿を奪いとられる日が来る。その時、彼らは嫌でも断食をするであろう」
「真新しい布切れで古い着物に継ぎを当てる者はない。そんなことをすれば、新しい当て切れは古い着物を引き裂き、裂け目はますますひどくなる。
また新しい酒を古い皮袋に入れる者はない。そんなことをすれば、酒は皮袋を破って、酒も皮袋もだめになる」
最初の「花婿」は、イエスを指すとすれば辻褄が合う。だが下の2つは全くよく分からなかったので調べてみると、どうやら「古いものは新しいものを受け入れられない」と言う意味を含んでいるようだ。
では、次の事は何を意味するのだろう。イエスが、民衆には譬を使って教える理由を説明した時のもの。
彼らが見ても見てもわからず、聞いても聞いても悟らないようにするため
一見すると譬を使わないと民衆に伝わらないから、と取りたくなる。ただ後半に「悟らないように」とある。訳で色々違いがあるだろうけど、この部分ががちょっと分からない。
考えを持たせずただ信じようとさせたのか、自分で答えを見つけるまで考えさせようとしたのか、どちらでもないのか。
岩波文庫表紙に「正確さのと分かりやすさのために細心の工夫を凝らした画期的な個人訳聖書」ある。この点は、他の訳も見てみたい。
その他の有名な言葉
・自分を愛するように隣人を愛せよ
・誰かが右の頬を打ったら、左をも向けよ(マタイ)
・敵を愛せよ「天の父上の子であることを示すため」(マタイ)
・何事によらず自分にしてもらいたいと思うことを、あなたたちもそのように人にしなさい(マタイ)
・与えよ、きっと与えられる(ルカ)
・求めよ、きっと与えられる(ルカ)
・Quo Vadis 「クォ・ヴァディス」
ペテロがイエスに言った言葉「主よ、どこへ行かれますか」
映画にもなっている「クォ・ヴァディス」。映画のイメージがあったので、初読でスルーしてしまった言葉。ちゃんとメモしておこう。(ヨハネ13章36節)
映画での使われ方は、
迫害を避けてローマ大火を逃れようとしたペテロが、イエスにかけた言葉。
ペテロはローマに戻るが、暴君ネロに捕らわれて、逆さ十字にかけられる。手には天国の鍵。
・私の右に座りなさい
「右に座りなさい」とは、神様がイエスに言われた言葉。
右というのは新約聖書で右は善、左は悪という概念から出ている。有名絵画では、私たちから見て左が天国、右は地獄に描かれている構図が多いよう。神様の立ち位置では右が天国、左は地獄。
*ちなみに英語で右をrightと言うが、「正しい」という意味もある
*オリンピック表彰台でも銀メダルは金メダルの右で、銅メダルは左

!!
日本語だと「左右」と言って左が先に来る。
有名かもしれないが、調べてみたら色々と面白かったので少しだけ紹介。
唐の時代の中国では「皇帝は北極星を背に南に向かって座る」のが善しとされた。そうすると皇帝から見て、左(東)から日が昇り、右(西)に沈む。だから東西南北。上下左右。
とはいえ、左遷や右腕など、右上位になる言葉もあるが、日本のマナーでは左上位(国際的には右上位)、覚えておいて損はない。
・個人的に好きな「権威問題」
最後に個人的に好きな「権威問題」をおいておきたい。なぜ好きなのか。イエスの切り返しが冴えていると思うのと、困る質問をされた時に使えそうだから。
「何の権威があってするのか」(教えを説いたり、救世主と名乗ったり)
イエス
「では尋ねたことに答えよ。その上で何の権威でそれをするのか言おう。ヨハネの洗礼は、天の神から授かったのであったか、それとも人間からか」
彼ら密かに考える。
「もし天からと言えば、なぜヨハネを信じなかったかと言うであろうし、それとも人間からと言おうか」ヨハネを本当に預言者だと思っている民衆を恐れて「知らない」と答えた。
イエス
「では何の権威であんなことをするのか、私も言わない」
読了後、何度も見たダン・ブラウン原作「天使と悪魔」を再度見た。目を覆うシーンは多いけれど、終盤に天国の鍵が逆さになっているシーンを確認。こうやって、読んだ本の内容が連鎖するのが面白いんだ。
岩波文庫100冊チャレンジ、残り10冊🌟カウントダウン!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
