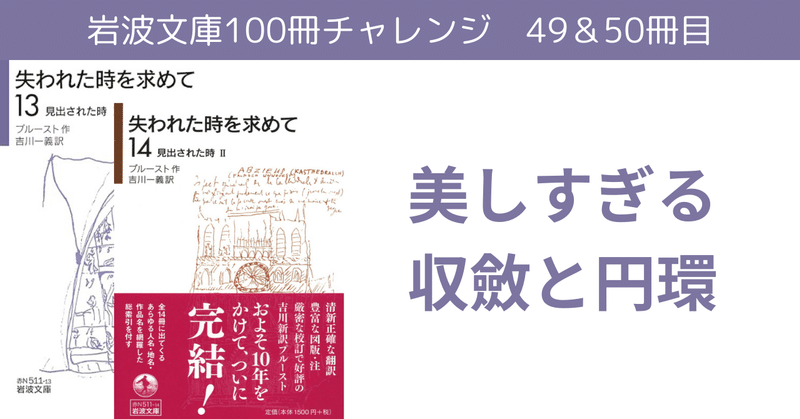
岩波文庫チャレンジ49&50/100冊【失われた時を求めて13・14巻】
岩波文庫100冊チャレンジが節目の50冊を迎えるとともに、大長編「失われた時を求めて」全14巻も読破!ちょっと気持ちが良い✨
全編通しての感想は別におきたいので、今回は今まで通り13&14巻についてのまとめ。
長かった物語。ここまで読んできて本当に良かったと思えた13巻。ここへきてのあまりに素敵なタイトル回収に感動と興奮。一見するとどういう意味だろう?と思うタイトルが物語と繋がった時、それが物語の主題であった時、雷に打たれる衝撃と同じくらい、ジーンと染み渡るものがある。
ストーリー(ネタバレ含む)
一時世間を二分していたドレフュス事件は収束し、目下第一次世界大戦。「私」は療養生活のため遠くから見ている立場にあるが、不言実行・憂国の士であるサン=ルーは戦場で部下の退却を援護して殉シをとげる・・
自分の肉体の生命は、相対的にさほど重要なものではなく、自らのうちに存する正真正銘の生命の核たるくだんの内的部分のためならやすやすと犠牲にできるものであり、個人の存在はその核を保護する表皮のような価値しか持たなかった
一方で、サン=ルーとソドムの関係にあった、名誉心も無私無欲もないモレルは脱走兵となっていたが、見つかって逮捕される。がまもなく釈放。さらに、サン=ルーから大事にされていたことが考慮され、前線に送るだけに留められ、戦功十字章つけて帰還・・
かと思えば、戦時下とは思えぬ相変わらずの生活を続けるヴェルデュラン夫人とシャルリュス氏。サロンを開催し続ける夫人。主な話題がドレフュスから戦争に変わっただけで、相変わらずのお喋りが繰り広げられる。
戦火に荒廃した町を歩き疲れた「私」は、渇いた喉をうるわそうと、たまたま目にしたホテルで、サン=ルーらしき人物が急いで出ていくのを目撃、そこで何か飲ませてもらおうと足を踏み入れる。
多くの軍人がいたその館は、シャルリュスがジュピアンに任せた男娼館だった。そこで性欲を満たすシャルリュスのXXシーンを覗き見・・
シャルリュスが魅力的「時流に流されず、厳密な論理に支えられている言説」な反面、なかなかえげつないシーンだが、正欲とは。
新聞の報じることによってのみ判断を下している世間の人が、自分自身で判断を下していると想い込んでいる
そして急いで出てきた人物は、やはりサン=ルーだった事が、そこで落とした戦功十字章で分かる。(なんたる皮肉)
壮大なタイトル回収
この物語のタイトル回収は、戦争終結から長い月日が経ったある日、「私」がずいぶん老年になってから訪れたゲルマント大公邸サロンで始まる。
これまでの「無意識的記憶現象」が結実化し、「私」が物語を描く決意をするに至る。圧倒的!プルースト自身の文学談義も含まれ、真ここに極まれり。
(引用多め)
「真の楽園は、失われた楽園」
思い出は、忘却のおかげで、思い出と現在の一刻との間にいかなる絆を結ぶこともいかなる関連を設けることもできず、ひとえに元の場所と元の日付に留まり、他のものとは距離を置き、ある谷間の窪みやある頂の先端などに孤立していたからこそ、突然、我々に新たな空気を吸わせてくれる。
「無意識的記憶現象」は、
「私」に昔の日々を、失われた時を見出せる力を持っていた。
皿にぶつかったスプーンの音や、不揃いなタイルや、マドレーヌの味覚などを感じたのは現在の瞬間においてであると同時に遠い過去の瞬間においてでもある。
つまり時間を超えた領域でその印象を味わっていたのであり、(中略)その時の私が時間を超えた存在(以下略)
かつて聞いたことのある音や吸い込んだことのある匂いを改めて聞いたり吸いこんだりすると、その音や匂いは現在のものであると同時に過去のものであり、現在のものではないのに現実的であり、抽象的ではないのに理念的である
時間の秩序から抜け出した一瞬の時が、これまた時間の秩序から抜け出した人間を我々のうちに再創造し、そのエッセンスを感じさせてくれる
「私」は、こういうたまにしかない瞬間の喜びこそが「ただひとつの実り豊かな正真正銘の喜び」と感じる。
それに引き換え「社交の喜びが与えてくれるのは、せいぜい卑しいものを食べて消化不良を起こしたときのような不快感に過ぎず、友情も見せかけに過ぎない」と喝破。
「私はまたしても騙されたくは無い」
そして芸術作品を作ることを決意。
芸術作品こそが失われた「時」を見いだすための唯一の手段
プルーストの文学談義、作家とはかくあれ
「失われた時を求めて」がどういう考えに基づいて構成されたか、プルーストが作家として大事にしていた事は何か、が読み取れる。引き続き引用が多くなるが、好みなのでおいておきたい。
芸術家はいかなる時も自分の本能の声に耳を傾けるべきで、そうしてこそ芸術はこの上なく現実的なものとなり、人生のこの上なく、厳格な学校となり、真に最後の審判となる。(中略)同時に、現実が我々に書き取らせた唯一の書物、現実そのものが、我々のうちに「印象」を「印刷」して作らせた唯一の書物。(中略)想念の具体的な形、印象こそ、その想念が必然的な真実である証。
印象だけが真実の指標となり、それ故精神によって把握される価値があるのは印象だけである。と言うのも印象から精神が真実を引き出すことができるなら、印象だけが精神を一段と大きな完成と導き、精神に純粋な歓びを与えることができるからである。
中には小説は諸々の事物を映画のように羅列すべきだと言い募るものもいる。こんな考えほど馬鹿げたものはない。そうした映画もどきのビジョンほど、我々が現実に知覚したものから遠いものはないからである。
1時間はただの1時間ではなく、様々な香りや音や計画や気候等で満たされた壺である。我々が現実と呼んでいるものは、我々を同時に取り巻いているこうした感覚と回想とのある種の関係のことであり、(中略)この関係こそ、作家が感覚と回想と言う2つの異なる項目を自分の文章の中で永遠につなぎ合わせるために見いだすべき唯一のもの。
あることが何らかの印象を与える時、(中略)本質的な書物、唯一の真正な書物はすでに我々一人ひとりのうちに存在しているのだから、それを大作家は普通の意味でなんら発明する必要がなく、ただそれを翻訳すれば良いのだということに私は気づいたはずである。作家の義務と責務は翻訳者のそれなのである。
作家にとって文体とは、画家にとっての色彩と同じで、テクニックの問題ではなく、ビジョンの問題。文体とは、世界が我々に現れるその現れ方の質的相違を明らかにするものであり、(中略)我々は芸術によってのみ自分自身の外に出ることができる。
語るべきことは、ここまでで十分に語られる。
そして、最終巻にて円環する
最終14巻では、考えを巡らせていた「私」が、まだサロンへ来たばかりだった事を思い出し「私」を含めみんなの晩年の姿に想いを寄せる。
歳月は過ぎ去ること、青春もいつしか老年となること、いかにゆるぎない財産や王位といえども崩壊すること、名声は束の間のものであること
これまで親交のあった人の老いた変わり様、外見と内面、地位すら逆転、サロンでの世代交代。人は変わる。
短所や長所は、個人の外にあると言っても過言ではなく、個々の人間は、まるで夏至や冬至のようにあらかじめ存在する避けようのない普遍的な点を通過するかのように、短所や長所という光の中を通過する
人々の変わり様を目の当たりにして初めて、自分が晩年に来ていることを自覚。これまでの人生、出会った様々な人を振り返る。
人生が無数の神秘の糸を織りなしている、人生がそうした糸を交差させ、その糸を何重にもより合わせて太い横糸を作りあげている
(中島みゆきを思い起こしたのは自分だけではあるまい・・)
そしてこれまでの人生を振り返った「私」は、悲嘆こそが精神の力を強化してくれた事にも気づく・・プルーストセレクション(PART2)の方に記載
人は愛するものを捨て去ってこそ、それを作り直すことができる
そしてこれが最後の文・・すき
必ずや私は、その作品の中に人間を描く際、たとえそれが人間を怪物に見せる結果になろうとも、なによりもまず人間を、極めて広大な場所を時間の中に占める存在として描くだろう。
人間の占める場所は限りなく伸び広がっているのだー果てしない「時」の中に。
14巻にはプルーストのこんな想いも(読者の反応に対する反論)。
真実の捉え方に共感してくれた人たちでさえ、その真実を私が「顕微鏡」で覗くように発見したと褒め讃えてくれたが、様々な事柄を知覚するのに使ったのはそれとは逆の「望遠鏡」であり、それらが確かに極めて小さく見えるのは、遥か遠くにあるから
余人にはほんの些細な事と思われる「匂い・音・感触」。でもそれこそが、感じやすい「私」(いわんやプルースト)の人生の歓びであった。なぜなら人は本当の事を言わないし、人は変わるから。自分の抱いた「印象」こそを大切にし、その「印象」を芸術に昇華できるのは、翻訳者たる作家だけ。
こうして「失われた時を求めて」は始まる。
最後まで読んで、もう一度始まる。円環小説。そして、この物語の中で、この物語を書いている物語。
長かったけれど、最後のつながり方が素敵すぎて、読んでよかった小説に間違いない。プルーストにも感動したが、同じくらい訳者にも感動し、普段は気にもしない校訂も正確無比に素晴らしいものだと分かった。
最後に、自分が気づかなかった訳者さんの好きな指摘を2つ。
①サン=ルー嬢への収斂
一見、相容れないものに見える両サロンには、ともにスワンが出入りし、いずれブルジョア階級と貴族階級の混じり合うことが見通されていた(サロンであり、婚姻であり、その子サン=ルー嬢)
②なぜプルーストは「私」が小説を書く「決意」をする所で終わらせたのか
実現されたものは「理想」たりえないことを熟知していたのだろう。「私」が小説を書く決意で終わっているのは、他でもない、文学の執筆を神話たらしめる壮大な賭けだったのではないか。
あまりにも綺麗で、好きすぎる。
ありがとうプルースト、ありがとう岩波文庫。
岩波文庫100冊チャレンジ、残り50冊🌟
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
