
小さい頃は作家になりたかった話
「将来の夢」というのは、誰もが幼い頃から持っているものだとは思うけれど、僕の場合は「作家になりたい」と思っていた。
思い出してみると、小学校中学年頃に「眉村卓」さんの小説なんかに出会ってSFめいたものが好きになり、それから自分でも「小説」まがいのものを作るようになっていった。
小説は「書く」のではなく、「作る」ものだった。
白い紙を折りたたんで、ある程度のサイズにしてホッチキスで止め、表紙の絵とタイトルを書いて、そこから文章を書き込んでゆく。
裏表紙には、自分の似顔絵と近況を添えて、出版社みたいな屋号を書き入れて完成する。
つまりは、小説を書くとは「本を作ること」でもあったわけである。
ある程度おっさんの方なら懐かしいと思うが、その自作の小説の装丁は、「カッパノベルス」をまねたもので、”YOSHIIE NOVELS"なんて書かれているのだ。ああ、思い出しても恥ずかしい。
ここでカッパノベルスが出てくるあたりでお気づきになるかもしれないが、その頃は赤川次郎さんなんかが全盛期である。当然文体も真似てしまうので、自分で書いた小説にもやたら
「……」
が出てくる。ああ、恥ずかしい。(いや、赤川次郎さんが悪いのではなく、それを真似る僕が悪いのだが。)
小学生の頃は、何十冊も自作の小説を「出版」した。そりゃあ、紙と鉛筆だけあれば、山ほど量産できる(ただし、全部一点モノである)のだから、次々に新作を繰り出しては、クラスの友達に強制的に読んでもらう。
意外と友達は喜んでくれて、小さな小さな自己満足がそこにあった。
中学生になると、小説の主人公をクラスメイトに当て書きして、活劇の中で大暴れしていただいた。A君とB子ちゃんが好き同士だなんてことがわかると、当然物語のなかにそれをロマンスとして盛り込んだので、さらに内輪でウケた。現実と虚構が交錯しながら、「ヨシイエは将来作家になるんだろう」と多くの友人が思っていたに違いない。
高校生になっても、小説は「作る」ものであることは変わらなかった。まず新聞部のワープロとか、親父のワープロとかを借りて「縦書き」で印刷するようになった。「文豪」とか、「書院」とか、懐かしいだろう?
友達のタカハシくんの実家が工務店で、コピー機を持っていたのでそれを借りて、ワープロ原稿を複製することを覚えた。ここでようやく一点モノから、「量産」できるようになった。
タカハシくんのお父さんに、コピー代を払っていない気がする。ああ、恥ずかしい。
次に厚紙を買ってきた。厚紙を切って、複製されたB4サイズのコピー用紙をあてがって切り貼りする。そうだ。ハードカバーを作り始めたのである!
手製本のハードカバー小説は、友人や先生に売りつけた。毎年新刊が出て、十数部ずつ売りさばいただろうか。ああ、もう穴があったら入りたいくらいだ。
高校3年生の時の作品には、巻末に四コマ漫画が載っていた。「まんがライフ」とか「まんがくらぶ」とか四コマ誌も全盛期だったからだ。ああ、懐かしい。
ハードカバー製本の技術を身につけたのは、今でも役に立っている。ほら、手帳型スマホケースくらいは、ちゃっちゃと自分で作れてしまうのだ。


大学生になって、めっきり小説を書かなくなった。作家になりたい!と思って文学部国文学科に入ったのだが、ダイガクで勉強するのは、作家になることとちょっと方向性が違っていた。けれど、小説を書くのが嫌になったとか、ダイガクの勉強を「これは違う」と感じたとかではなく、もっとポジティブに「いろんなことを知って、楽しくなった」のである。
今から思えば、あの頃の小学生にとっては、「空想の世界を文字で書く」以外に自分の存在を伝える方法がなかったのだと思う。文字を書くか、絵を書くか、スポーツで結果を残すか、くらいしか80年代小学生にとっての「承認欲求を満たす方法」はなかったのである。
だから、僕の場合はそれが「作家になること」「小説を書くこと」だったのだろう。
大学時代は、勉強や自分の専門分野の研究めいたもののほうがはるかにおもしろく、ほとんど小説を書かなかった。
それから社会人になり、思い出したように短いのを少しだけ書いたこともあるが、「作家になる」という話は、どこかへ消えてしまった。
けれど、作家になりたい、という思いを完全に忘れてしまうのは、少々昔の僕に対して失礼な気がするので、それは忘れないでいよう、とは思っていた。まあ、こうして今でもブログを書いたりするのはその名残りかもしれない。
そして、2012年のこと。
そこまで小説を書くことからは遠ざかっていたのだが、その頃の僕は、転職してすぐで、前任者が残した売掛回収に走り回っており、そのことを思わず小説にしてしまった。
それが
https://www.itmedia.co.jp/makoto/articles/1211/17/news001.html
「営業刑事は眠らない」
というめっちゃ短い、短篇小説である。
これがITメディアさんの小さなコンテストで大賞を取り、あろうことかiPhone(iOS)の電子書籍になってしまったのである!
ああ、恐ろしい!
なんかよくわからんけど、原稿料をもらい、いちおうアプリとして無料ながら流通してしまったので、かりそめながらも僕は、「作家になる」という小学生レベルの念願は果たしたことになる。
もちろん、商業作家として食べていけるわけでもないし、これを「作家」となのるにはおこがましいことは重々承知の上だが、それでもタイムマシンがあれば、小学生の自分には自慢できるに違いない。
それが、誰か他人に自慢するものではなく、あの頃の自分に対してだけできる「小さな自慢」だとしても。
ところが、2017年になって、天下のアップルさんがiOSのバージョンアップをしたせいで、ヨシイエの「営業刑事は眠らない」はアップルストアから消えてしまった。ああ、営業刑事は眠りについたのである!
本業の作家さんでも、増刷がかからなければ、せっかく出版した本が消えてゆくと聞く。作家になる、小説を世に出すのは簡単でも、それで食べてゆくのは夢のまた夢といったところだろう。
だから、僕にとっては、これくらいの夢の実現でちょうどよかったのかもしれない。まあ、人生というのは、そんなものである。
ところが、である。失われた過去の思い出というのは、時にあざやかに蘇ることがある。はるか昔に別れてしまったあの子に、町の雑踏の中ですれ違ってしまったくらいには、心が沸き立つ瞬間というのは誰にでもあるものだ。
iOSをバージョンアップさせると、古いアプリは消えてしまう、というか動作しなくなる。アプリによってはアップルさんからも削除されており、二度と出会えないということもよくあるのだ。当然ながら、「営業刑事は眠らない」は、今あなたの手元のiPhoneから検索しても、ストアには表示されず、入手することもできないはずだ。
唐突だが、僕にはいま、10歳になる息子がいる。その子が悪さをしながら家のiPadやらiPhoneをいじくり倒すのだが、「そういえばお父さんは、昔アプリを出したことがあるんだぜ」くらいはカッコつけたいのに、それができないもの悲しさがあるわけだ。これが実際の印刷物なら、「ほらこれがお父さんが出した本だぜ」くらいには言えるが、電子書籍はそれができない。
ああ、物悲しい!
そんな時に、中古のiPod touch4に出会った。めっちゃ安かった。数台まとめてだったので、一台200円くらいである。
iPod touch4はiOS6で止まっているので、ぶっちゃけ2021年の今となってはほとんどのアプリが動作せず、実用性はない。
ところが、である。どんなアプリなら動くんだろう、と、かつてのアカウントを入力して、検索してみたら、

いた!
あった!
残ってた!
のである。
今となっては、他の誰も見ることができない「営業刑事は眠らない」がアップルのサーバーの奥深くに、
眠っていた
のである!!!

震える手で、インストールのボタンを押した。
ダウンロードバーが青く伸びていった。
アイコンが出た。「新規」のマークが表示されている。

押してみた。
動いた!!!!!
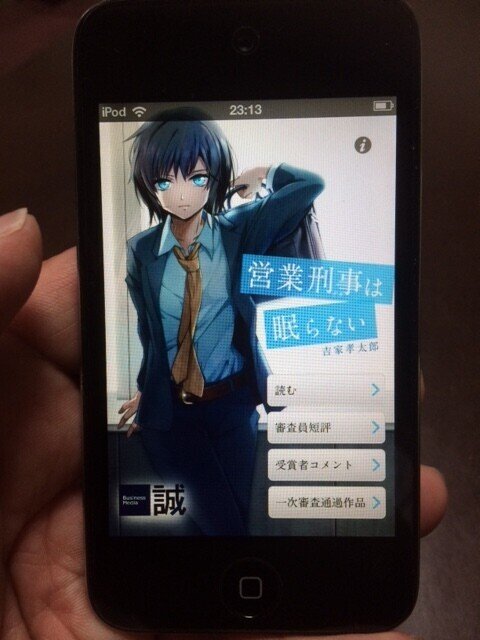
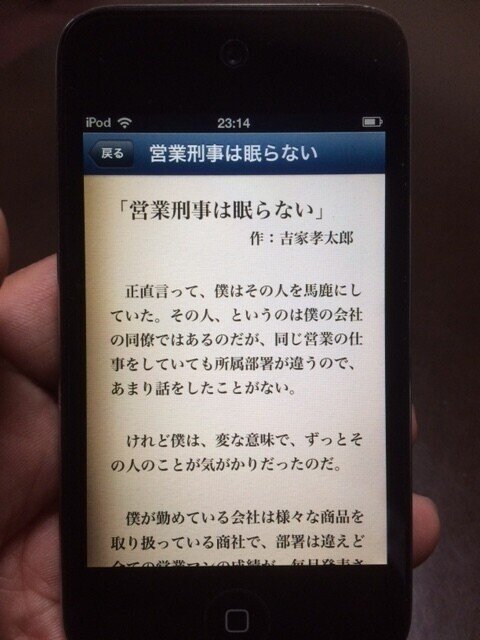
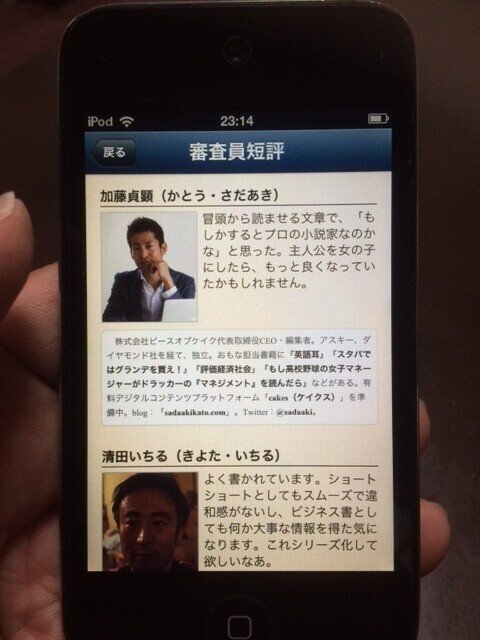
それはもう、自分自身との対面のような、懐かしいような恥ずかしいような、嬉しいようなもの悲しいような、なんとも言えない気持ちであった。
小学生の頃の思い出から、40歳を軽く過ぎてアラフィフになった現在までが、一気に押し寄せるような、そんな感覚に襲われた。
ああ、僕は作家になりたかったんだ、と思った。
この話は、たぶん誰にとってもあまり関係のない、どうでもいい話だと思う。けれど、僕にとっては、それがどんな人生であっても、「生きてるっておもしろいな、幸せだな」と思える体験だ。
もしかすると、職業作家として生きていた未来もあったのかもしれないが、それと比べても、この小さなアプリの復活で一喜一憂している自分の人生も「悪くない」と思える。
もちろん、増刷や再販に一喜一憂する作家人生もおもしろいかもしれないが、自分の息子にネタとしてアプリの話ができる人生だって、捨てたもんじゃないと思うのだ。
コロナ前の未来とコロナ後の未来が大きく変わってしまったように、人生とはわからないことだらけだけれど、こんな小さな出来事を積み重ねながら、生きていることを楽しめるのであれば、それは幸せなのだろう。
そうか、僕は作家になりたかったのか。と、小学生の自分を思い出す。
そうか、僕はもうおっさんになったんだな、とも思う。
それもまた、良し。
それもまた、楽し。
息子よ、君は将来何になりたいんだい?
(おわり)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
