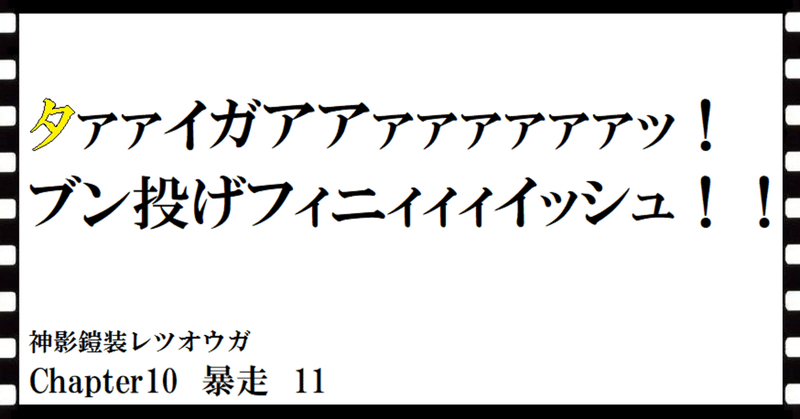
神影鎧装レツオウガ 第九十話
Chapter10 暴走 11
「あァ?」
ハワードは鼻白んだ。
真正面。朧《おぼろ》が発射した一対の鉄拳こと、タイガーロケットパンチとやら。それは確かに強力なのだろう。一目で分かる。速度、霊力量、どちらも尋常では無い。
だが同時に、あまりに見え透いている。
遠過ぎる間合い。直線過ぎる動き。絵に描いたようなテレフォンパンチだ。
罠か。少々あからさま過ぎるが。
しかして、今の朧は両腕が欠損している事もまた事実。致命打となり得るサークル・セイバーを拳ごと飛ばした今、それをかいくぐってしまえば攻略は容易い。
そして、何よりも。
仮にアメン・シャドーが敗北した所で、もはや計画には何の影響も無いのだ。
「よォし」
そうした思案を秒単位で終え、ハワードは決断する。
「乗ッてやるかねェ、その罠!」
アメン・シャドーの背部スラスターへ霊力光が灯る。狙うは真正面。一対の鉄拳と、その向こうで滞空する獣鎧装《じゅうがいそう》、朧。
「行くぜェ!」
アメン・シャドーの背部スラスターが唸る。迫り来る鉄拳が、相対的に更に速度を増す。朧の狙いは正確であり、このままでは直撃は必至。
故に。アメン・シャドーは鎌を垂直に構えた。
「フッ!」
そして、小刻みに左右へ動かした。
メトロノームじみて振れた鎌の柄は、それぞれ鉄拳の側面を素早く、強かに叩いた。
タイガーロケットパンチは軌道を逸らされ、アメン・シャドーの側面を虚しく飛んでいく。切り払い成功だ。
更にアメン・シャドーはスラスター推力を緩めず、瞬く間に朧へ肉薄。
「おぅルぁア!」
垂直に構えていた鎌を、朧目がけて振り下ろした。
斬。
刃を五本に増やした鎌は、腕無しの朧をナマスのように斬り捨てる――そう、ハワードは踏んでいた。
がぎん。
だが、実際に帰って来たのは刃の軋む声。受け止められたのだ。
「な、に」
「成ぁる程。恐っそろしく早い熊手ソードじゃのう」
響く雷蔵《らいぞう》の声。ハワードはすぐさま間合いを放そうとする。
出来ない。がっちりと捕まれているからだ。
「じゃが威力ならこちらも負けちゃおらんぞ?」
そう、鎌は捕まれたのだ。朧の右腕の接続端子《ジョイント》、そこから出現した新たな上腕に。
色は赤。先程射出した鉄拳とは違い、丸太のように太く、長い。異形としか言いようのない形状だ。
先端には鋭い爪を備えた五本指が生えており、これが斬撃を受け止めたのである。
「勝手な名前をつけんじゃねェ、コイツにはゴールド・クレセントって名前があンだよ」
「そうかい。そりゃすまなかったね」
小刻みに揺れる刃の向こう、飄々と巌《いわお》が応える。肩をすくめる姿が見えるようだ。
「しかし……何なンだ、そのウデはよォ」
「奥の手さ。言葉通りの、な」
そう巌が言うなり、朧のカメラアイから光が失せる。更にヘッドギアの左右からシャッター状の装甲が展開し、顔を完全に覆い隠してしまう。
そして入れ替わりに、胸の虎の双眸が、ぎらりと光を強めた。
「ぐ、る、ぁ……! では、いかせて、もらおうかのぅ」
鋼の口角から獣の吐息が漏れる。五指に捕まれた鎌が、みしみしと軋みを上げる。
「な、ンだ」
何か、まずい。構成霊力は無駄になってしまうが、それでもアメン・シャドーは迷わず鎌を手放した。
本体と切断され、即座に形を失うゴールド・クレセント。その刃が完全に揮発するよりも先に、アメン・シャドーはステイシス・ドライブを起動。突撃前までの間合いに一瞬で戻りつつ、背部光輪へ霊力が集中し――コロナ・シューターを発射。
「行けィ!」
数は八。円弧を描いて迫る誘導弾の群れに、しかし朧は動かない。代わりに僅かに上体を丸め、未だ肘部接続端子が剥き出しの左腕を掲げる。
水平。その角度で止まると同時に、接続端子へ霊力光が灯る。光は幾条もの線に分岐し、迸る。針金細工にも似た線の束は、一瞬で寄り集まり、やはり巨大な赤色の左腕を形成。
丸太のような二本の腕を、朧はだらりと下ろす。長く巨大な赤色は、朧の爪先よりも下の位置で爪を光らせる。
そんな朧へ、八発のコロナ・シューターは狙い違わず着弾。炸裂、爆音、霊力光が乱れ飛ぶ。
「や、」
ったか、と。
ハワードは、言い切る事が出来なかった。
真正面――いや、もはや指が触れる程の至近距離。緑色の双眸をぎらつかせた虎が、アメン・シャドーの目前に居たのだ。
「ぐ、る、る、」
虎が、朧が唸る。獣性剥き出しの吐息を、ハワードはモニタ越しに嗅いだ。
「な、」
んだと。
そうハワードが呻くより先に、衝撃がアメン・シャドーを襲った。
殴り飛ばされたのだ。朧に。一回り以上のサイズ差があるのに。
「づ、ぁ」
きりもみ、吹き飛び、しかしどうにか姿勢制御を取り戻すアメン・シャドー。
「なんて、ヤツ」
毒づくハワードだが、多少間合いを稼げたのも事実。状況を見定めつつチェックプログラムを走らせる。
衝撃こそ派手だったが、辛うじて致命傷では無い。防御が何とか間に合ったからだ。
しかしてそれと引き替えに、アメン・シャドーは右腕手首が吹き飛んでしまっていた。恐るべき威力と速度である。
もっとも、それもその筈だ。朧の新たな赤い両腕には、レツオウガが搭載しているタービュランス・アーマー、その改型が組み込まれているのだから。
その名はタービュランス・アーム。霊力装甲としての防御性能をオミットした代わり、霊力の噴射性能を強化した代物だ。これによって今の朧は、両腕の動きを自在に加速させる事が可能となっているのだ。
コロナ・シューター全弾を竜巻じみた回転で撃ち落とせたのも、アメン・シャドーへ一瞬で肉薄出来たのも、タービュランス・アームのブーストが背部スラスター加速に合算していたから、という訳だ。
「が、あ、ア」
腰を落とし、両腕を水平に構える朧。一見すると、隙の大きい奇妙な構え。だが実際は、タービュランス・アームと背部スラスターの推力合成に最も効率の良い姿勢だと言う事が、今のハワードには良く分かった。
「チ、後手後手かよ」
舌打つハワード、身構えるアメン・シャドー。それに応えるかの如く、朧の両腕とスラスターに霊力が寄り集まっていき――それが解き放たれるよりも先に、胸の虎がカメラアイを明滅させた。
がくん。糸が切れたように、目に見えて脱力する朧。水平の構えだけはどうにか維持しているが、それでも赤腕が橋から揮発し始めているのは隠せない。
「今度はなンだァ……?」
訝しむハワードは、すぐさま理由を察する。
「……そォか、霊力切れか」
霊力を回して仮の右腕を再構成しながら、ハワードはにやりと笑う。実際、その見立ては正解だ。
クリムゾンキャノンの発射、タイガー全力疾走ブレイクの発動、そして今に至るまで繰り広げた激しい戦闘の数々。如何に大量の霊力を貯蔵できるI・Eマテリアル搭載機といえども、流石に限界が訪れたと言う訳だ。
「ハ! 笑わせてくれンじゃねェの!」
かくして再構成したゴールド・クレセントを振りかぶりながら、アメン・シャドーは踏み込んだ。
「おゥるァ!」
それがもう一人のパイロット、巌の目論見通りだと言う事も知らずに。
◆ ◆ ◆
「ふむ、想定より早いか」
赫龍《かくりゅう》側のコクピット内で、やかましいアラートが跳ね回る。霊力切れが近い事を告げるその音に、巌は鼻をならした。
「ぬぅうぐるるるぁああ!! 動けぃ! 何故動かん!」
無論同じアラートは迅月《じんげつ》側でも騒いでいるのだが、雷蔵は気にする素振りすらなく操縦桿を振り回している。
まぁ仕方のない事だ。タガを外れた禍《まがつ》の獣性が、そんな小賢しい事を気にする筈も無いのだから。
このままでは、稼働時間はもってあと数分。手始めにただでさえ消費の激しいタービュランス・アームが悲鳴を上げ、末端からじわりと揮発し始める。
『……そォか、霊力切れか』
モニタの向こう、アメン・シャドーが笑っている。巌は片眉を吊り上げた。
「ご明察」
まぁ仕方無い事だ。そもそも霊力切れ自体は、設計段階から利英《りえい》が指摘していた懸念事項の一つなのだから。
合体システム。様々な術式の搭載。雷蔵の獣性を前提とした機体設計。そして何よりも、対神影鎧装との戦闘を前提とした出力調整。それら全てを支えるため、赫龍と迅月には霊力貯蔵用のI・Eマテリアルが、確かに内蔵されている。
だが。
『多分ゼッタイ恐らくあわよくば霊力足りなくなるよねイエッフー!』などと、利英は設計段階で目をぐるぐるさせながら言っていたものだ。
故に。
それを克服するための手段を、巌は用意して来た。
二年前。ヘルガの、あの一件の後から。
「チェンジ、カートリッジ」
呟いたのは、かつて辰巳《たつみ》がブーストカートリッジ装填の際に放っていたキーワード、その原型。
応えたのは、巌の正面にある多目的コンソール。その中央部が二つに割れ、内部から一本のアームが迫り出してくる。
何かのソケットと思しき窪みを備えたアーム先端を見ながら、巌はポケットへ手を入れる。取り出したのは一本の弾倉《カートリッジ》。前にも何度か取り出したが、結局使いそびれていた代物。
まだI・Eマテリアルの開発が間も無い頃、利英に無理を言って作って貰った、大容量霊力貯蔵デバイス。
「コイツのチャージには三ヶ月かかったが……」
『ハ! 笑わせてくれンじゃねェの!』
好機と見たアメン・シャドーがスラスターを全開し、一気に間合いを詰めてくる。まさに頃合いだ。
「……使うとなれば一瞬、か!」
巌は躊躇無く、ソケットへ弾倉を差し込んだ。三ヶ月かけて充填された、I・Eマテリアルにも匹敵する大量の霊力が、朧の霊力経路の隅々まで瞬く間に行き渡る。
朧が、霊力切れから解放される。
『おゥるァ!』
膂力、加速力、遠心力。考え得る限り最高の威力を伴ったゴールド・クレセントが、朧の脳天目がけて唸り迫る。
「グぅルぁ!」
しかして悲しいかな、その動きには工夫がなさ過ぎた。鎌の軌道を容易く読み切った雷蔵は、左拳で刃を殴り弾き、返す刀で右拳を叩き込む。
「ガルるゥぁっ!!」
「グアあ!?」
完全に虚を突かれ、くの字に体を曲げて吹き飛ぶアメン・シャドー。それでもどうにか体勢を立て直すべくスラスターが小刻みに火を噴くが、上手く行かない。
「ち、く、ショ」
もがくハワード。その様を嘲笑うかのように、背後からの衝撃がアメン・シャドーを殴りつけた。
「ぐあッ!?」
すわ新手か。コクピットを揺るがす衝撃に歯を食いしばりながら、ハワードは後頭部モニタへ視線を移す。
「な、に」
そして、言葉を失った。
さもあらん。そこに浮かんでいたのは新手の大鎧装などではなく――先程朧が射出した、タイガーロケットパンチの右腕だったからだ。
「飛ばして終わりじゃァ、無かったッてのかァ!?」
「当然だ。そも、何のために僕が同乗していると思ってるんだ」
用済みのカートリッジを抜き取った後、巌は操縦桿を握りしめる。
――本来ならば、相当な実力者である筈の巌。それが雷蔵のサポートに徹しているのは、二年前の事件が端を発している。
あの事件の折。巌はパートナーを失い、正体不明の少年《ゼロツー》を保護し、自己の霊力の九割近くを自主的に封印する事となった。
なので現状の巌が使える霊力は、残りの一割を少しずつ充填したカートリッジと、吸引術式で一時的に得た余所の霊力くらいしかない。
『でもそれってヨ! 霊力をコントロオルするウデマエ自体はじぇんじぇん落ちてないってことだよネェェ!』
嵐のようにキーボードを叩き続けるモニタ前。目を血走らせ、口端から泡すら零しながら獣鎧装の設計をしていた利英に、巌は頷き返したものだ。
そして、利英の見立てに間違いは無い。赫龍の前身となった大鎧装、赤龍《せきりゅう》を駆っていた頃の技量そのものは、多少錆び付きつつも五辻巌の中に根付いている。
天才技術者である酒月利英は、そこに着目した。
既存の大鎧装を大きく超える性能を備えた機体、神影鎧装《しんえいがいそう》。同型のレツオウガが部隊に所属しているとは言え、それはたったの一機。対応出来なくなる局面は、必ず出て来る――まぁ、今が正にその局面なのだが。
何にせよ、レツオウガだけでは戦力不足に陥る事は自明の理。さりとて必要なのは数で無く質である。
最も手っ取り早い解決策は、隊内で二番目に秀でた雷蔵の戦闘技巧を、十全に活かせる大鎧装を造る事。だが知っての通り雷蔵は禍憑き《まがつき》であるため、戦闘中にタガが外れ、禍の獣性へ飲まれてしまう可能性が大いにある。
その解決策を、利英は巌の技量に見出した。
二人の精神を同調させれば、巌の技量そのものを雷蔵のタガにする事が出来るのでは無いか、と。
『しかし、まぁ、なんだ。設計した僕が言うのもなんだが、コイツはハッキリ言って、狂気の産物だ。幾ら同調を最小限にしようと、一歩間違えれば精神に変調を来しかねないよ。それも重大な、ね』
不眠不休の向こう側。ナチュラルハイ過ぎで逆に理性の光を取り戻した利英は、再三にわたってそう警告した。
だが、それでも巌と雷蔵は同調を、酒月式試製三型精神装甲術式――マインド・ディフェンダーの搭載を了承したのだ。
「ふ、う」
巌は目を閉じる。瞼の裏側、今も感じ取る事が出来る。二年前、雷蔵に憑依した虎型の禍。
その凄まじき獣性が、薄皮一枚にすら満たない鼻先で、嵐のように渦巻いているのが良く分かる。
それもこれも、術式によって雷蔵の精神との境目が曖昧に、朧気《おぼろげ》になったがためだ。
だからこの獣鎧装には、『朧《おぼろ》』という名がつけられたのだ。
どうあれ巌は己の精神を、その渦への防波堤とした。理性という方向性を与え、適切な操縦が出来るよう手綱をくくりつけた。迅月単機時と違って雷蔵が暴走しないのは、この同調があったこそ、というわけだ。
『ぐ、る、ア』
当然、自由を奪われた虎からすればたまったものではない。渦巻く嵐はしばしば刃となって、邪魔な巌を八つ裂きにせんと唸りを上げるのだ。
物理的な圧力すら伴った殺意。それを手際よく回避しながら、巌はタイガーロケットパンチ――もとい、ストリーム・シールドを操作する。
スタンレーから個人的に譲り受けた、カルテット・フォーメーションの術式データ。それを元に――まぁマリアが使っている最新型ではないのだが――造り出された無線制御式多目的攻撃ユニット、ストリーム・シールド。
指揮棒代わりの操縦桿を握り直しながら、巌は雷蔵の獣性を読み取っていく。
「思うままやれファントム2! こちらでサポートを行う!」
「言われずともよォ!」
吼え猛る雷蔵、渦を巻く禍の獣性。それらに裏打ちされた朧が、タービュランス・アームが、唸りを上げる。
「こうなった儂は! 気が済むまで止まらんぞぉ! ぐるるるぁああ!!」
構えも形振りもない、しかし速度だけは尋常でない踏み込み、及び両手突き。
恐るべき撃力を伴った赤腕が、アメン・シャドーをブン殴る。
「ぐあぁァ!?」
ハワードが体勢を立て直そうとした、まさにその直前。叩き込まれた朧の一撃はアメン・シャドーの胸部装甲を割り砕き、更に大きく吹き飛ばす。
響くダメージアラート、悲鳴を上げる霊力経路、歯噛みするハワード。
だが。
「この反動にスラスターを合わせりゃ、ちったァ距離を――」
稼げる。そう言い切るよりも先に、またもや背中からの衝撃がハワードを襲った。アメン・シャドーは為すがまま、ピンボールのように逆方向へ弾き飛ばされる。
「がァ!? クソッ、なンだってンだ!?」
苦し紛れに振り返ったアメン・シャドー、そのカメラの端には、霊力光の尾を引く朧の右鉄拳が映っていた。ラピッドブースターによる加速力の成果か、と思考の冷静な部分が分析していた。
そうして吹き飛ぶアメン・シャドーの正面には、当然のごとく朧が待ち構えており。
「タイッガーァおかえりパアァンチ!」
スラスター推力と雷蔵の膂力に充ち満ちた赤い拳が、アメン・シャドーを再びブン殴る。
「ぐ、お、アッ」
再び、今度は真上に弾き飛ばされるアメン・シャドー。血飛沫代わりの霊力光と装甲破片を撒き散らすそのシルエットを、朧はケダモノの如くに追従。
「まだ、まだ、まだァ!」
強引極まる軌道変更。フェイントも何も無い、まっすぐすぎる朧の鼻先へ、ハワードはその気になれば霊力弾やコロナ・シューターを叩きつける事が出来ただろう。
「左。セット、バルカン」
だが。そうした隙を補うため、朧は最初にタイガーロケットパンチを、ストリーム・シールドを射出していたのだ。
『Roger Vulcan Etherealize』
アメン・シャドーの頭上には、既に五指を広げる朧の左鉄腕。雷蔵との思考同調により、完璧なタイミングで配置されたその掌へ、霊力光の球体が現われる。構造は先程赫龍が展開していた霊力機関砲と同じだが、口径は二回り程大きくなっており。
かくて左腕機関砲はアメン・シャドーの周囲を旋回しながら、執拗に、かつ正確に弾丸を叩き込んでいく。
狙いは頭部、及び推進部。それぞれ視界と動きを封じる算段か。
「クソ、この、羽虫モドキが……ッ」
全身で生じる小爆発に苛まれながら、それでもアメン・シャドーは右手を掲げる。震えながらも朧の左拳へ照準する掌へ、霊力弾の光が灯り。
「タイガー追いつきパァンチ!」
それが放たれる直前、追いついた朧が再び全力の打撃を見舞った。渾身の赤い両手突きは、いよいよもってアメン・シャドーの基礎フレームを軋ませ始める。
「が、っア!」
またもや別方向に、野球ボールの如く弾き飛ばされるアメン・シャドー。その進行方向には、やはり先程と同様朧の右鉄拳が回り込んでおり。
「右。セット、ラピッドブースター。行けッ」
右腕の打突、吹き飛ぶアメン・シャドー。そこへ左腕が回り込み、更なる打突。吹き飛ぶアメン・シャドー。そこへ朧が旋回し、全力の打撃。吹き飛ぶアメン・シャドー。
「こ、れ、はッ」
旋回、打撃。旋回、打撃。旋回、打撃。朧と鉄拳、雷蔵と巌、途切れる事を知らない阿吽のコンビネーション。これこそ、巌が言ったランページ・アタックの本質だったのだ。
「ぐ、う、ウッ」
嵐のような、竜巻のような打撃の豪雨。それでもアメン・シャドーが撃墜されないのは、偏に巌がアメン・シャドーの急所を意図的に避けているためである。
「聞きたい事は、山程、あるからな」
ちりちりと、脳裏を苛みつつある雷蔵の獣性。その感触を努めて無視しながら、巌はアメン・シャドーの解析データを照合する。
どこにコクピットブロックがあるのか。どう破壊すれば、そこを効率よく抜き出す事が出来るのか。その計算を、今まさに巌は終えた。
「ファントム2、そろそろ決めるぞ!」
「応ともよ!」
応えながら、雷蔵は一際強烈な赤拳をアメン・シャドーへ叩き込む。もはや声すら上げられないアメン・シャドーは、受け身すら取れずに吹っ飛んでいく。
「今だッ! ソニック・バインド!」
「ぐるルあぁオオオオッ!!」
雷蔵が猛る。胸の虎が顎《あぎと》を開き、咆吼と霊力波を発射する。
ヴォルテック・バスターを応用した霊力砲は、竜巻のように渦を巻き、拡大し、直撃する。
頭から爪先まで、為す術無く光の奔流に飲み込まれるアメン・シャドー。その上下へ朧の鉄拳がそれぞれ飛来し、丸盾側をアメン・シャドーへ向けて滞空。
「ストリーム・シールドッ! バインドフィールド展開!」
アメン・シャドーを挟む二枚の丸盾、ストリーム・シールドの表面へ術式が走る。
サークル・セイバーを遙かに超える精緻さで描かれる電子回路は、程なく霊力光をまっすぐに投射。光はアメン・シャドーを翻弄している竜巻に絡みつき、一体化し、球状のフィールドとなって空中に固定。
霊力の、引いては雷蔵の獣性の奔流《ストリーム》を補助する酒月式多目的フローター・デバイス。それがこの丸盾の、ストリーム・シールドの名の由来だったのだ。
「腕部射出! 続いてタービュランス・アーム、パージ!」
『Roger Turbulence Arm Canon Mode』
電子音声の返答と同時に、朧の赤い腕――タービュランス・アームが切り離される。更にストリーム・シールドから向きを変え、腕部のみを朧へ向けて射出する。
朧は腕の接続部から即座に牽引《トラクター》ビームを照射。青い光は鉄拳を捕捉し、元の場所へ速やかに引き寄せる。
同時に朧の真正面で、切り離された左右のタービュランス・アームが合体し、変形し、大きな円筒の砲身――クリムゾン・カノンを形成。
「クリムゾン・カノン! スピアーモード!」
『Roger Crimson Canon Spear』
赫龍が形成していたものよりも大口径の砲身は、しかし引き絞られるように集束し、伸長し、円錐状の刃を伴って凝集。それと同じタイミングで、元の鉄拳が朧の両腕へ再接続。頭部フェイスガードが展開し、開かれた鋼の五指が赤い槍を掴む。
「Get Set Ready』
朧のカメラアイが輝く。敵機を、アメン・シャドーが囚われたフィールドを、巌と雷蔵は睨む。
「出力良し、照準完了。行けッファントム2!」
「お応《お》ぉぉう!!」
雷蔵の雄叫びとともに、朧は赤い槍を、クリムゾン・キャノン・スピアーを振りかぶる。クリムゾン・キャノンと同等の霊力を集束した切っ先が、バインドフィールドを睨む。
朧の膂力の全てが、振りかぶった右腕に充ち満ちる。
そして、解き放たれる。
「タァァイガアアァァァァァァッ! ブン投げフィニィィィィィィィイッッシュ!!!」
投擲。
残光すら伴って空を切る赤い槍は、狙い違わずバインドフィールドの中央、アメン・シャドーへと直撃。胸元を貫通する赤い切っ先は、そのまま圧縮状態から解放され、爆発。
野放図に拡散する奔流《エネルギー》は、しかしストリーム・シールドの形成するフィールドによって無理矢理に軌道を変更。
中央へ、中央へと織り込まれる爆発エネルギーは、そこへ固定されたアメン・シャドーを完膚無きまでに分解し、焼却し、灰燼と化してしまう。
――これこそ五辻巌が編み出した、対神影鎧装撃破方法の答えだ。
神影鎧装《てき》はその名の通り、神の力を模している。それ故、何をして来るのかまったく予測出来ない。よしんば出来たとてしも、対策する事は非常に難しいだろう。
ならば。
それを使う前に敵を翻弄し、隙を突いて極大火力の一撃を叩き込み、何かしてくる前に叩き潰す。そうした戦法を成し遂げるため、朧は建造されたのだ。
そしてその戦法を完璧に成し遂げた雷蔵は、高らかに朧の両腕を水平に掲げる。
「見たかっ! これぞ蒸し焼きの極意よォ!」
同時に、ストリーム・シールドがフィールドを離れる。制御を失ったバインドフィールドが、轟音と共に爆散する。
「……いや、まぁ。分かりやすく言えばそうなんだがな」
呟く巌。同時に爆煙を引き裂きながら、ストリーム・シールドが朧へと帰還し、両腕部へと再接続。その右シールド上には、強制的に抉り出されたアメン・シャドーのコクピットブロックが、霊力の線で絡め取られていた。ストリーム・シールドを経由した、巌の霊力制御による離れ業である。
「まずはこれで良し。次は――」
カートリッジをもう一本取り出しつつ、巌はEフィールドへとカメラを向ける。
「――な」
そして、巌はカートリッジを取り落とした。
さもあらん。Eフィールド中央、フェンリルと組み合っていたオウガ。
その頭部が、コクピットブロックが。
巨大化したフェンリルの顎に、今まさに、食い破られていたのだから。
【神影鎧装レツオウガ メカニック解説】
朧(2) 武装一覧
ここから先は
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
