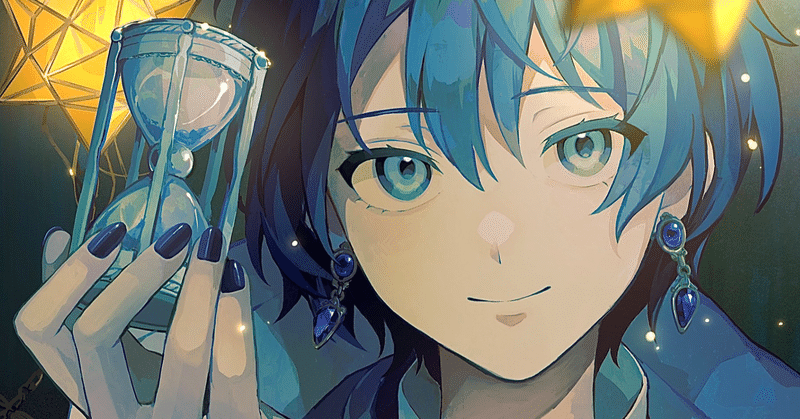
Minstrel(後)
【Notice】
この作品は2024年12月27日リリース、酔シグレ 2nd Full Album「吟遊詩人の人生録」に付随したオリジナル小説です。24曲で1つの物語が完成するこのアルバムの後編であり、MVは順次公開予定です。
この記事では、後編12曲の物語がお読みいただけます。
前編アルバムティザー動画はこちら↓
物語前編「Minstrel(前)」のオンライン記事はこちら↓
「世界はね、いつだって理不尽で不平等だ。だけど、命と死だけは平等に与えられている。この世界でたった二つだけの、平等なものだ。」
1 Prelude
遠い昔の話だ。
雪降る森の中で、あの人が言っていた言葉。もう顔も思い出せないほどに、記憶の中の景色は色褪せてしまっている。
僕は、あの人から沢山の言葉を貰った。顔や声や笑い方、すべてを忘れてしまっても。貰った言葉だけは、僕の記憶に染み込んで、浸透して、僕を形作るものになった。一度染みついた思想は、剝がそうと思っても中々剝がれないものだと僕は知っている。
傍らを歩くあの人の歩幅は、いつも大きかった。僕はあの頃と、背格好も外見も何も変わらないのに。いつの間にか、あの人に合わせて歩いた一年が染みついて、僕の足跡も間隔が広くなった。
「…っ、時雨…待って…もう少しゆっくり…」
「あ…ごめん…」
ハッとした。振り返れば、息を切らせたノワールが足を止めている。気持ちが急いて、自然と速くなっていた歩み。普段あちこち歩き回っている僕はともかく、基本出歩かないノワールには少々厳しかったようだ。
「…っ、そうだね…急いだって仕方ないし…」
「そうよ…大丈夫、きっとまだ詠ちゃんは大丈夫だから…」
言いながらノワールは、一冊の本を開く。僕が手渡した、詠の人生録だ。
「…ほら、まだ自室にいる。眠っているみたい」
「…なら、いいけど」
追いついたノワールを待って、再び歩き出す。今度は少しゆっくり、気を付けて歩を進める。サク、サクと踏みしめる雪の音。白いマントに落ちる、白い粉雪。
この森はいつ来ても美しいのに。鈍色の空も、青々と茂った木々に雪が舞い降りる瞬間も。気持ちが沈んだ今は、見え方が違う。全てが薄ぼんやりとして、鮮やかさがなくなってしまったように見える。
「…向こうの世界では、まだ五、六時間しか経っていないもの。朝になるまで、もう少し時間がかかるはずよ」
「ああそうか…その概念、忘れてた」
詠には話す機会が無かったが、現世とこちらの世界では時の流れ方が違う。詠と出逢ってから今日まで、こちらの世界では七日間経った計算だが。実際に現世で流れた時間はその二分の一。つまり、三日程度しか経っていない。
「詠ちゃん驚くでしょうね…説明しておいてあげればよかった…」
ポツリと零したノワールの言葉に、僕は肯定も否定もしなかった。
もうすぐ第二街区が終わる。そうすれば、寧々のいる第九街区。そしてそこを突っ切れば、第七街区に着ける。最短距離で向かってはいるが、あと半日はかかる。
現世の時間に換算すると、約六時間。朝目覚めた詠が、すぐ行動に移してしまったら間に合わない。
僕の心情を理解したのか、ノワールの手がそっと肩に置かれる。
「大丈夫よ…別れの準備が出来た時って、“最後”が凄く重たく感じられるから、今まで見えなかったものが見えるようになる。詠ちゃんもきっとそう。すぐにこちらに来ることはないと思うわ」
「…それは…いろんな人間を見てきたノワールの経験則?」
「いいえ?ただの、勘よ」
悪戯っぽく笑うノワールはいつも通りで。自分の中にあった焦燥感が、少しだけ薄まっていく。苦笑を零した僕の袖を、ノワールがそっと引っ張る。
「まあ、急いだほうがいいのは確かだし!行きましょ、時雨」
「…疲れて“待って”って言ったのはノワールじゃないか…」
「もう平気よ!ほら、早く」
僕より先を行くノワールの背中を見つめる。濃紺のドレスの裾が、雪を引きずって少し白くなっている。ふと、誰かの後に続いて歩くこの感覚を懐かしいと思った。
僕がずっと後ろを歩いていたあの人の背中は、もっと大きくて豪快だったと、思い出しながら。
2 クレセント・レム
この世界では、時間の長さが現世と比べて倍になっている。
僕がその事実を教えてもらってから、どのくらいの年月が過ぎたのかもう思い出せない。こちらの時間軸では優に、二百年~三百年は経過しただろう。
よく物語なんかで「〇年後」という描写があるが、描かれていないだけで、物語の登場人物たちはその「〇年」を必死に生きている。現実世界の人間と同じように、一日一日に中身の詰まった日常がある。挫折も苦悩も絶望も、そこにちゃんと。
現実でも、他人の描写は省かれて伝わる。自分が知っている範囲のその人しか見えない。だから、“大変なのは自分だけじゃない”のは誰だって理解しているものの、表面的に見える極一部だけで判断してしまう。苦しい状況下に置かれた時ほど、他人の幸せは眩しくて鮮やかだ。
『比べていいのは、過去の自分とだけだ。他者と比べるなど愚か者のすること』
遠い、遠い昔に。まだ僕が現世にいた頃に、父からもらった言葉だ。もう古い記憶すぎて、自分が生きていた頃のことは全然思い出せないが。色んな場面や感情の断片だけ、心に突き刺さって抜けない。
父はいつでも正しかった。自分や身内に厳しく、他人に優しい。その権化みたいな人だった。僕は父を尊敬し、慕っていた。
父は音楽が好きだった。幼い内に僕はヴァイオリン、ピアノ、ギター、声楽…様々な音楽教養を身に着けさせられ、その中でもピアノが一番好きになった。
父がプレゼントしてくれたレコードで、世界中の素晴らしい音楽家の演奏を聴いた。その中でも僕は、ある若きピアニストに憧れを抱き、いつしかその人に並ぶピアニストになることが夢になった。
ステージや人前で演奏するより、僕は独りの練習時間が好きだった。楽譜と向き合って、遥か昔の作曲家が遺した音楽を、丁寧に忠実に再現する。隠された思いを読み解いて、一音一音を大切に聴いて。その過程が濃密で、楽しかった。
十歳を少し過ぎた頃、父の命令に従って、僕は様々なコンクールに出るようになった。どれも一番いい結果を持ち帰っては、父にさも当然、という顔で出迎えられるのが悲しかった。過去の自分と比べて、僕は確実に成長しているのに。コンクールでの常勝を当たり前と考える父は、他者と比べることにしか興味がないようで。もう、僕にあの言葉をくれた頃の父ではなくなっていた。
幼いころに浴びせられた言葉は、その人の人格を作り、思考を作る。僕は文字通り、父の言葉の支配下に置かれた。自分に厳しすぎる“僕”になった。
上に立つ人間が、様々な素質を持たされた人間が、その地位を維持するのは凄く苦しい。「出来ない」が「出来る」に変われば褒められるのに、「出来る」がデフォルトになってしまうと後は降下するだけ。失望されるだけになる。
『才能を持って生まれた人間には、“才能の責任”がある』
これもいつか父が言った言葉だったと思う。嫌いで仕方ないものならば、切り捨ててしまえたのかもしれないが。幸か不幸か、僕は音楽が好きだった。音楽を辞める、なんて選択肢は到底浮かばなかった。
次第に僕は“若き天才ピアニスト”として国内で有名になった。父はより一層僕を売り込もうと、あらゆる手段を尽くした。僕は使い回され、あちこちで有名な曲ばかり演奏させられ、取材を受けさせられた。練習をする時間は殆どなくなって、弾きたい曲は弾かせてもらえず、演奏技術は衰えるばかりだった。
ある時、僕がずっと憧れていたピアニストとの共演話が来た。「若き天才ピアニストたちの共演」と称して、二台ピアノの演奏会をする企画だ。彼の方が年上だったし異国の人だったけれど。音楽に対してとても誠実で、僕らはあっという間に親しくなった。二人で試行錯誤したあの時間は、音楽に向き合ったあの時間は、本当に幸福だった。
『誰に何と言われようと、君は音楽に対して誠実だ。僕は君の音楽が好きだよ』
別れ際に彼がくれた言葉だった。僕はその言葉を指針にした。周囲からの賞賛も、名声も要らない。大勢に聴いてほしいなんて思わない。
ただ誠実に音楽がしたかった。自分が誇れる自分でありたかった。だから父に抗議し、音楽を学び直す時間を作ってもらえるよう説得しようとして…できなかった。
口から出かかった反論は、父を前にすると喉の奥に引っ込んで。僕を“理想を叶えるための道具”としか見ていない父の、怒鳴り声を浴びて。僕は結局説得も出来ず、上辺だけの音楽を奏でる「天才もどき」で在り続けた。
数年後、憧れだったそのピアニストが亡くなった。世界的に有名な若きピアニストの死は、一週間ほど世間を賑わせた後、灰のように散り名前すら聞かなくなった。
憧れを失くした僕には、呪いだけが残った。父はそのピアニストの死を“好都合だ”と語った。これでようやく、自分の息子のライバルが消えた…と。
世界各国で行われるコンクールで、僕は望まずして数多の賞を獲った。理解できない。その頃の僕の演奏は、音楽への誠実さなど欠片もない、酷いものだったのに。
神童だ、天才だと持ち上げる紙面。歯の浮くような称賛の羅列。僕はただ、楽しく音楽と向き合いたいだけなのに。称賛もタイトルも要らない。練習する時間が欲しい。必死に練習して、切磋琢磨して、最高の音楽を奏でられる瞬間がほしい。
自分の才覚のせいで、父は変貌した。僕の音楽を好きだと、誠実だと言ってくれた彼はもういない。音楽は僕にとって、息をするのと同じことだった。
息をするのが、苦しい人生になった。
それ以降は、あまり覚えていない。年月だけが過ぎて、憧れだった彼の年齢は疾うに超えた。音楽への気持ちは満ち足りることのないまま生きて。
覚えている限りの、最後の記憶の断片は。
大雨の中佇む僕と、もう一人の誰か。誰かは危険な凶器を手にしながら、僕に向かって何かを叫んでいる。それを見つめながら、僕はぼんやりと思うのだ。
ああ…羨ましいな、って。
その人は僕に向かって走ってきて。僕は何もしないで、ただ立っていて。周囲の人間が慌てふためいたり、悲鳴を上げたりして。
もう一度、彼と一緒に演奏がしたかったなあ。
そんな身勝手な夢を思い描きながら、僕は何かが欠けたままの心で、そっと微睡みに落ちたのだ。
「…れ、時雨…!」
「え、ああ…なに?」
先を行くノワールが足を止めていた。振り向いた彼女のシルエットの奥に、青白い三日月が浮かんでいる。
「もう…さっきから生返事ばかり…きっと今私が尋ねたことも聞いていなかったのでしょう?」
「聞いてたよ。彼の居場所のことだろう?」
「あら、聞こえてたの」
うっすら微笑んだノワールに早足で追いついて、再び二人で歩き出す。数時間前に雪降る森を抜けて、雨の街を突っ切り、寧々のいるターミナルを通り過ぎて、今僕らは第七街区の入り口付近まで辿り着いていた。
第七街区は、遺跡の街。今歩いている道も、古めかしい大木に囲まれ、崩れかけた石畳で出来ている。蔦の絡んだ柱が立ち並び、生物の気配は一切感じられない。
「ここに居るといいけど…あいつは結構な頻度で他の街に出払ってるからなあ…」
「でも、つい最近ここで見かけたって言っていた人が居たわ」
「ノワールの“つい最近”は信用ならないよ。いつの話さ?」
「んー…に、二カ月前、とか…」
「ほら見ろ…」
呆れて言えば、ノワールはムッと口を結んで歩調を速める。
「仕方ないでしょう?いつもはずっと書斎で記録の管理をするだけなんだもの」
「それは分かってるけどさ…」
言葉を濁す。気まずそうに肩を竦めた僕を見て、ノワールはふっと優しい笑みを浮かべた。
「時雨が来てからは、ずっと楽しくなったけれどね。私一人でこの世界のこと、すべてを把握するのは難しいから…時雨と寧々が手伝ってくれるようになって、とても助かっているわ」
「…まあ、寧々に関しては…」
今の困った状況を引き起こしたのも寧々なので素直に肯定は出来なかった。それを察したのか、ノワールの眉尻が少し下がる。
「…寧々を許してあげましょう。寧々の気持ち…私だって少しわかるもの」
「うん…分かってる。寧々のしたことは間違っているけど、別に寧々を恨んではいないよ。腹が立ったのは…自分にだけだ」
止められなかったこと。寧々の寂しさや詠の考えに気づけなかったこと。挙げればいくらでもある。
「馬鹿だったな…僕は」
「…“私たちは”でしょう。止められなかったのは私も同じよ。だからこうして、二人でここに来ている」
ノワールの言葉に、少しだけ頬を緩める。僕はいつもノワールに救われている。一緒に背負おうとしてくれる彼女に、僕はどれだけの恩があるだろうか。
「…そうだね。まずは、彼に会おう。話はそれからだ」
大きな石造りのアーチが見えた。あの先に、第七街区の中心部がある。一時間もしない内に、中心部まで行けるはずだ。
「…ねえ、時雨。今日は歌ってくれないの?」
「ええ?こんな時に?」
「こんな時だからこそ、時雨の音楽が聴きたいんじゃない。私、貴方の作る歌が好きなの」
『僕は君の音楽が好きだよ』
ノワールの声と共に、その言葉が反芻する。一瞬、足が止まる。
「…時雨?」
不思議そうに見つめるノワールの碧い眸。僕は一つ小さな笑みを零した。
「…何でもないよ」
三日月が、淡く美しい光でそっと僕らの行く先を照らしていた。
3 最果ての憐歌
鳥が囀っている。
ゆっくりと重い瞼を開けば、陽の光の眩しさに再び目を細めた。レースのカーテンが揺れている。開いた窓から、優しい秋風が吹いている。
上体を起こせば、窓の外から子供の話し声が聞こえた。たまに車の走行音。ぼんやりとした思考を、徐々に覚醒させながら。私は自分の両手をかざす。
茜色のカーディガン、薄茶のブラウス。長い夢の中で、私が着ていた服と同じだ。
「…っ、」
ガバッと上体を起こし、辺りを見回す。床に散らばった白い紙。ベッドから飛び降りて、手に取る。ゴクリと唾を呑み込んで、裏返しになったその紙束を表に返す。
「…夢じゃ、ない」
“あまりある残像”と書かれた筆跡。その文字を、音符を、書いていたペン先。メロディーを口ずさむ、濃紺の髪と碧い眸をした横顔。
「…時雨…」
その名前を口に出した時、全ての時間が、七日間の思い出が蘇って。私は空を仰いだ。何もなかったかのような、綺麗な秋空が広がっていた。
まず、部屋を片付けよう。そう思い立って、午前中の一時間と少しを掃除に使った。今まで捨てられなかった物も、何の躊躇いもなく捨てられた。物が減ると、部屋ってこんなに綺麗になるんだ…と当たり前のことを学んだ。
よく、心が荒んでいると部屋も汚くなる…という説を見かけるが。それは真理だったのかもしれない。そう思う程には、小一時間で部屋はピッカピカになったし、心に詰まっていた何かが取れたように感じた。
今日を最後に私は、この部屋にもう二度と戻らないつもりでいる。
無造作にゴミ袋を、玄関に並べた。どうせ、数日後にはこの部屋にも警察だのなんだのが来るんだろう。見られて恥ずかしいような物は何もない。ゴミだって、二、三日放っておいた所で悪臭が他の部屋まで渡ることはないはずだ。
そうして一通りの片づけを終え、空っぽになった部屋の真ん中で、私は手紙を書いた。一通は両親宛、もう一通は会社宛に。
会社からは夥しい量の電話が入っていたが、起きてすぐに確認したきりスマホの電源を切った。迷惑をかけているのは申し訳ないが、私一人居なくても案外世界は上手く廻る。
二通の手紙を書き終えて、柄のない真っ新な封筒に入れ、部屋の中央のテーブルに置いた。立ち上がって、グルリと部屋を見渡す。
引っ越して数日…を名乗れる程度に物の少なくなった室内。随分長くこの部屋に住んだな…と感慨深く一周する。ベッド、座椅子、テーブル、棚、冷蔵庫…必要最低限の家具が並ぶ中、一つだけ異質なそれに近づく。
埃をかぶったキーボード。部屋の隅に置かれた、その鍵盤を私は指でつうっとなぞった。右の人差し指についた埃をフッと吐く。
この部屋の角で、何度も何度も夜中に泣きながら曲を作ったっけ。音楽を辞めた後は、見向きもしなかった。でも、どうしても捨てられなかった。
「…やっぱりこっちにしよう」
呟いて、私は二通の手紙をテーブルからキーボードの鍵盤の上に置き直した。この方が私らしい気がしたのだ。
もうこの部屋に用はない。用意したボストンバッグを片手に、立ち上がる。薄手のトレンチコートを羽織り、一番歩きやすいスニーカーを履いて。
最後にもう一度だけ、振り返った。
「…行ってきます」
行ってらっしゃい、は当然、返ってこなかった。
部屋を出たのは、正午を少し過ぎた頃で。私はまっすぐ最寄り駅に行き、新幹線が出発する駅まで向かった。平日ということもあり、電車の中に人は少ない。小さい子供連れのお母さんやお年寄り、学校をサボっているらしき制服姿の女の子。普段はあまり見かけない種類の人たちが、沢山いた。
新幹線の駅に着いて、切符を買う。無事、目当ての券と駅弁を手にした私は、そのスタイリッシュな車体に乗り込む。
出発してすぐに、駅弁の封を開けた。朝から何も食べていなかった腹ペコの私にはありがたい御馳走で。あっという間に平らげて、ゴミを片付けて。ふと外を見た。ぼんやりと景色を眺めながら、時雨との旅を思い返す。そういえば向こうの世界に行くまでは、食べ物も味がしなかったのに。こんなに美味しく食べられるようになったのは時雨たちのお陰だと思った。
目を開けば、燃えるような茜色の空が視界に飛び込んできて。私は慌てて時計を確認した。時刻は夕方の五時半を差している。いつの間にか眠ってしまったらしい。
乗り過ごしたのでは…と焦ってドア上の表示を見る。点滅した駅名と共に、あと五分でその駅に到着することがアナウンスされた。私が目的としていた駅だ。ほっと胸を撫でおろす。
なんとなく癖でスマホを見ようとして、電源を落としたままなことに気付く。本当は通知なんて見たくないが、到着してからの道筋は調べないと分からない。観念してスマホの電源を入れる。
案の定、会社から入っていた鬼のような通知を一タップで消去して、道筋を検索する。こういう場合にはやはり、文明の利器は便利だな…と感じてしまう。
到着駅から次の目的地までは、ローカルな電車でおおよそ一時間ほど行き、途中で乗り換えて更に電車で三十分。私が覚えていたよりも、ずっと遠く感じた。訪れるのが、久しぶりだからかもしれない。
新幹線から降りた後、スマホで調べながらローカル電車に乗り換える。田舎だというのもあって、一両につき乗車客はほんの数人だった。
一人、また一人と客が下りていく。皆、日常の中に戻っていくのだ。これからあの人たちは、家に帰って温かいご飯を食べて、話をして眠って、また明日を迎えるのだろう。そういう毎日をずっと繰り返す。それが当たり前の、あるべき日常。
ゴッと、横の板に頭をもたれさせる。電車のこの角の席が好きだった。こうして体を傾けても、支えがあるこの席が。両側を他人に挟まれることのないこの席が。
窓の向こうに見慣れない高原が広がっている。夕闇の薄紫に染まった空が、美しかった。
最後の一人が下りて、とうとう貸し切りになって。夜に吞まれていく窓の外の光景をぼーっと眺めながら。頭にこびりついて離れない“あまりある残像”のメロディーを、囁くような声で口ずさむ。何度も、何度も。
乗り換えに使った駅は、無人駅だった。私は人生で数えるほどしか手にしたことのない紙切符を買って、電車が来るのを待った。もうすっかり夜の帳が落ちた無人駅は、少し怖かった。
やっと来た一両電車に揺られること三十分。自室を出て八時間あまりが経った頃、私はようやく目的地…故郷の街に辿り着くことができた。
向こうの世界で時雨と歩き回っていたお陰か、足腰はそこまで疲労していなかったけれど。やはり長旅で疲れは溜まっていたらしい。新幹線内で予約した地元のホテルに着くと、すぐにベッドにダイブして眠ってしまった。
そこで見た夢も、やっぱり時雨と旅する光景だった。
翌朝。ゆったりと朝九時に目を覚ました私は、ホテルで朝食をとってチェックアウトの時間ギリギリまで部屋で過ごした。きっと今日が、こっちの世界で過ごす最後の日になるんだろう。そんな思いを胸に、一つ息を吸ってホテルの外に出る。
故郷はいつも、色んな香りで私を迎え入れてくれる。
春は、のどかで温かい緑の匂い。夏は青々と広がる草原の香り。秋は少しひんやりした香ばしい匂い。冬は吸い込むだけで凍り付きそうな、ツンと透き通った香り。季節ごとに違った香りを含んだ、故郷の空気が私は大好きだった。
見覚えのある懐かしい道を歩く。荷物が軽い。何かを忘れたのではないか…と一瞬よぎった不安はすぐに消えた。背負うものなど何もない。私はここに、別れを告げに来ただけなのだから。
ロータリーの真ん中に聳える時刻灯は、午前十一時八分を示している。パッポー、パッポー、と礼儀正しく歩行者信号の音が鳴っている。数台しか車の通らない横断歩道を小走りで渡った。
音が少ない。耳に入る雑音が、少ない。都会に居る時はいつも、イヤホンをして歩いていた。雑踏の音が嫌いだった。見知らぬ人の話し声も、ゲラゲラと品のない笑い声も、電車が通過する煩い音も、あちこちで騒ぐ広告の音楽も全部、全部、聴こえないように。大きな音で、適当な音楽を流して歩いた。
ここでは、余計な音は何も聞こえない。こんな場所に、私は住んでいたのだっけ。
こんな、静かな所に。
十分ほど歩いて、街の中心部から少し外れた広い道の真ん中で立ち止まった。私の記憶では、この十字路を右に曲がって少し歩けば、目的の病院が見えるはずだ。
腕時計を見る。十一時二十分。確か病院の面会可能時間は十三時から。まだあと一時間半もある。どこかで時間をつぶそうか。
少し考えて、真っすぐ進むことを選んだ。また横断歩道を小走りで渡る。青信号がチカチカ点滅した。
余った時間で私が立ち寄りたかったのは、通っていた小学校だった。とはいっても、中に入っては不審者扱いされてしまうので、校門の前で止まる。
今はちょうど授業時間なので、生徒の姿は一人も見当たらない。数多の教室の窓を眺めながら、私にもあそこで勉強していた日々があったんだな…としみじみ思う。
赤いランドセルを背負った自分が、中から今にも飛び出してきそうだった。あの頃は何を考えて過ごしていたんだろう。あの頃の私は、何になりたかったんだっけ。
「…もう、どうでもいいけど」
私は母校を後にした。
「…あら、お見舞いですか?」
「あ…お世話になっております…私、鷹森小夜の孫の…」
一時間、近くのカフェで時間を潰した後。向かった先は街の外れの丘に聳える病院。その広い駐車場を突っ切って入り口前で足踏みしていると、看護師さんが声をかけてくれた。名札には「小鳥遊(タカナシ)」と書かれている。小鳥遊さんは目尻に小さなシワを沢山浮かべて、ニコニコと私に駆け寄った。
「まあまあ…!貴方が詠ちゃんね…!まだ面会には少し早いけど、どうぞ!」
「あ、いえ…!全然もう少し待ちます…」
「駄目よ…!一刻も早く会いたいはずだわ…。いつか孫が来るかもって、写真とかお手紙とかいろいろ見せてもらっていたのよ」
小鳥遊さんが存外強めの力で、私の背中を押して中へと促す。ズキと、胸の奥が痛んだ。久しぶりに会えるのは嬉しい。でも楽しみになんてしないでほしい。
私が居なくなった後の祖母のことが、気になってしまうから。
居なくてもいい存在なのだと、都合よく思っていたいのに。
「…あら、詠…」
「…久しぶり、おばあちゃん」
ガラガラ…とスライド式のドアを開けるとすぐに、祖母がこちらを向いて。そこに私が居ることが、信じられないみたいに目を見開く。私はぎこちなく微笑みながら、祖母のベッドサイドまで移動した。
「これ。お見舞い」
「あら、ありがとう…へえ、知らない作家さんね?」
祖母はお見舞いに、花を好まない。三か月前に長期入院が決まった時、『もし見舞いに来るなら詠の好きな作家さんの本を持ってきて』と、わざわざ手紙で釘を刺されたのだ。私が手渡した本の表紙を眺めて、祖母は少し頬を緩ませた。深緑の森の中に、鳥居が一つ立っている絵が表紙のその本は、私が一時期ハマっていた作者さんの最新作だった。買ったまま読めずにいて、読めずに終わる本だ。
バッグを空いた椅子の上に置き、コートを脱いで椅子の背にかける。そのままスッと無言で腰掛ければ、その様子をじっと見つめていた祖母が口を開いた。
「…今日は平日よね」
「そう」
「…お仕事は?」
「休み取った。有給、溜まってたから」
「そう。…ああ、手紙ありがとうね」
「ううん、最近書けてなくてごめん」
祖母は余計なことを聞かない人で。ポツ、ポツと必要な言葉だけを発する所は、私によく似ていた。…いや、私が祖母に似たのだろう。
祖母は携帯を持たない主義だ。なので中学卒業と同時に上京した時から、私は手紙を一カ月に一度祖母に出していた。近況報告を兼ねた、便せん一枚程度の味気ないものだったけれど。祖母は毎回必ず、返事をくれていた。
三か月前に書いた手紙の返信に、入院のことが書かれていた時は驚いたけれど。毎日仕事や生活に忙殺されて、その後手紙は出せなくて。我ながら酷い孫だったなと思う。祖母が元気だからよかったものの、自分の忙しさを言い訳に大変な状態の家族をほったらかしにして。
「…ごめんね、三か月もお見舞いに来られなくて」
「すぐに謝らないの。詠の悪い癖よ」
「あ…ごめん」
つい反射でまた謝ってしまい、慌てて口を押える。祖母は怒っている様子ではなく、ただ目を細めて私を見つめていた。
「…詠、何かいいことがあったの?」
「え?」
「この部屋に入ってきた時から、雰囲気が変わったなと思っていたの」
祖母はそれ以上言及せず、ただ私の言葉を待つ。矢継ぎ早に質問したりせず、いつも祖母はこうやって中々言葉が出てこない私の話を聞こうとしてくれた。
いいこと。確かにあったけれど。正直に話すわけにもいかない。少し考えて私は、話の核は変えず、一部嘘を交えて伝えることにした。
「あのね…素敵な出会いがあったの」
そうして私は時雨のことを話した。旅をした、なんていうと非日常感が漂ってしまうから。新しい友達が出来てね…と真実を少し濁して。時雨の人となりや、音楽をもう一度好きにさせてくれたことだけを伝えた。祖母はただ相槌を打って、とりとめのない私の話に耳を傾けてくれて。
「そう…それは、良かったわね」
「うん。…よかったんだ」
嘘の中にスプーン一杯分くらいの真実を混ぜると、本当になる。それは事実のようで。祖母は私の話をすっかり信じてくれたらしい。時雨に関する質問を、一つ、また一つと繰り出す。私はそれに答える。
一通り話し終えて、二人とも黙り込む。次は何を話そうか…と考えを巡らせていると、向こうから助け舟を出された。
「…最近は連絡してるの?」
「…ああ、母さんたちに?うーん…夏に電話したきり、かな…」
父と母とは随分前に疎遠になった。私が半ば家を飛び出す形で上京した三年後、高校を卒業する年に両親は離婚している。そのまま二人とも仕事の関係で別々の場所に引っ越して、父に至っては今再婚して別の家族がいる。
二人ともたまに連絡はくれるけれど、私のことにさして興味はないようで。私も私で、今更両親に執着などなく。結果、今ではお互いに何をしているかすら知らない関係になった。
そう。だから私は、両親に対しての未練はない。申し訳ないとは思うけれど、大して悲しまないだろう。悲しむ人がいるとすれば。
「…ねえ、おばあちゃん」
「うん?」
「…昔、よくおばあちゃんの前で、一人ステージしてたの覚えてる?」
「ああ…もちろんよ」
小学生の頃、両親が仕事で家に居ない時はいつも祖母が来てくれて、私の遊び相手になってくれた。私の遊びは常に音楽で、ダンスしたり歌ったり。それを祖母がニコニコ微笑みながら見ていてくれる…その空間が堪らなく好きだった。
「…久しぶりにね、曲を作ったの。聴いてくれる?」
そう告げれば、祖母は目を丸くして固まった。何も聞かれなかったけれど、ある日を境に私が音楽の話を手紙にピタリと書かなくなったことに、気づかなかったはずはないのだ。
少しの間をあけて、祖母はニッコリと微笑んだ。
「ええ…聴かせて」
そうして私は、鞄から“あまりある残像”の楽譜を取り出した。病室なので楽器はないから、アカペラだけど。ここじゃない世界で、時雨と一緒に紡いだ旋律を祖母に歌って聴かせる。
歌いながら、幸せそうに目を細めて聴く祖母の顔を横目に。なぜか涙が出そうになった。私が居なくなった世界で、祖母は何を思うんだろう。最後にこの部屋を訪ねてきた私を、今この歌を歌っている私を、どんな風に思い出すのだろう。
歌い終えて、しん…と静寂が訪れる。刹那、祖母がゆっくりと控えめに拍手し始める。目尻にうっすらと浮かんだ、その涙を見て。
私はなんて、身勝手なんだろうと思った。
こんなにも思ってくれる人が、私にはまだ居るのに。いなくなったら悲しむと、分かっているのに。
それでも。あの世界を見てしまったから。時雨に出会ってしまったから。
私の心は今もまだ、囚われている。
4 Nightmare
「…ここにも居ないわ…」
コツン、と石畳を踏んだノワールの靴音が反響する。不規則に剥がれた石づくりの壁。苔の生えた柱。退廃したこの街は、いつも寂寥感と神聖さが漂う。
「やっぱり出払ってるのかしら…」
「だとしたら今どこの街に居るのか、寧々に確認して早く向かわないと…」
そう言いながら、分かっていた。それではきっと間に合わない。
馬鹿だった,、と今更ながら自責の念がこみ上げる。ここに来る途中に第九街区は通ったじゃないか。何故あの時、ターミナルに寄って寧々にあいつの居場所を確かめておかなかったのだろう。焦ってばかりで冷静な判断が出来なかった。
きっとここに居る。そんな確信だけで来てしまった。
「…どうしましょう、時雨…」
途方に暮れたノワールと目が合う。打開策は何も浮かばない。
「…誰をお探しかな?」
その時。頭上から降ってきた一つの声。少し鼻にかかった、それでいてよく響く不思議な声色。バッと視線を上に向けた。崩れかけたその廃墟の、屋根の上。真っ黒なタキシードに白いマント、金のリボンがあしらわれたシルクハットという特徴的なシルエット。
「ヴァル!」
嬉しそうにノワールがその名を呼べば、彼…ヴァルは意味深な笑みを浮かべたままスッと地面に着地する。銀髪の下で、紫色の眸が怪しく光る。
「珍しいお客さんだねえ」
「よかった…!あなたに急ぎの用があるの」
すぐに駆け寄って本題に入ろうとするノワールを、ヴァルがそっと手で制する。
「…折角久しぶりに会えたんだ。少しお話しないかい?」
「悪いけど、そんな時間はないんだ。手短に済ませたい」
悠長なことを言い出すヴァルに、若干の苛立ちを覚えながら答える。ヴァルは一つ肩を竦めて、僕とノワールを交互に見比べた。
「ま、二人揃って会いに来るなんて、並みの用事じゃないのはわかるさ。…いいよ。で、オレに何の用?」
「教えてほしいことがあるんだ」
「ふうん?内容次第じゃ、タダでは教えられないかもよ」
悪戯っぽく笑うヴァル。相変わらず、何を考えているのかよく分からないやつだ…と内心で警戒度を高める。明らかな温度差のある僕らを、ノワールは一歩下がって心配そうに見つめている。
「… “現世に渡れる方法”を知ってるか?」
一呼吸置く。ヴァルは特に顔色を変えることなく、不敵な笑みを浮かべたまま探るように僕を見ていた。
「少しの時間でいいんだ。向こうへ行きたい」
「…どうしてオレに聞くんだい?そんなこと」
「忘れたとは言わせないよ。あの時…あの人が去ったあの場所で、君が僕に言ったんだ。必要になったら取引しに来いって」
僕の言葉に、今度は少しだけヴァルの表情が動いた。だがそれは一瞬で。
「…ああ、あったね、そんなことも。随分昔の話だ」
そう答えたヴァルは、また元の胡散臭い貼り付けた笑みに戻っていた。
「うーん…どうしようかなあ…その答えはイエスだ。オレは君が向こうに渡れる唯一の方法を知ってる。でもうまくいくかは分からないよ?」
「構わない。可能性があるなら、試したい」
「…危ない方法じゃないわよね?」
ノワールの問いに、僅かにヴァルの眸が濁る。
「どうかな。時雨と寧々に関してはイレギュラーだからなんとも」
「ヴァル…!」
諫めるように声を上げたノワールを、僕は片手で制する。ヴァルの言っていることは間違っていないし、彼が何を言おうとここで引き下がるわけにはいかない。
「僕にできる範囲の取引なら応じる。先にそっちの望みを言ってくれたっていいよ。だから…頼む、教えてほしい」
ヴァルの双眸を、射貫くように見つめ返す。少しだけ、その目が丸く見開かれた。
「へーえ…君がそこまで言うなんて。でも…本当にいいのかい?」
「構わない。今回は百パーセント僕に責任がある。…僕が片をつけたい」
その言葉を聞いたヴァルが、ふうっとため息を吐く。
「…いいよ。じゃあ、取引といこうか」
ニヤッと口の端を歪めて、ヴァルがタキシードの懐から何を取り出した。
ヴァルは、旅商人だ。あちこちの街を巡って旅をする…というその性質は僕と似ているが、ただ音楽を奏でて回るだけの吟遊詩人である僕とは違う。彼は辿り着いた街で、願いや頼み事、困ったことがある人間を見つけては、取引を持ち掛ける。
形ある物、形ない物、知りえない情報、誰かに会いたいという願い…どんなことでも、ヴァルは叶えられる。ただし、それには代償が必要だ。
代償が支払えない場合、取引はご破算。ヴァルはタダ働きはしない、現金な奴だ。気まぐれで気分屋、神出鬼没でその本心は誰にも分からない。
だからこそヴァルの存在は、どこの街でも御伽噺のように扱われている。巡り合えた者だけが、望みを告げて取引が出来る…そんな魔法のランプのような御伽噺。
ヴァルが懐から取り出した物は、一本の万年筆だった。碧いボディに、金のペン先。それを見たノワールが一瞬目を丸くする。
「簡単なことだよ。これで書き換えればいいのさ」
「書き換える…?」
首を傾げる僕と、何かに気づいたような表情のノワール。僕たちを見比べながら、ヴァルは可笑しそうにククッと肩を揺らす。
「そうだ。君も知っての通り、人生録には基本誰も干渉できない。他人が干渉出来てしまったらこの世界に居る人間は皆、現世に居る人を自由に操れてしまうからね。本は本らしく、読めるだけ、見るだけ…それが人生録の掟だ」
「でも…この万年筆だけは例外よ。これだけは唯一、人生録に加筆・修正を加えることが出来るの」
驚いて、ヴァルの手元の万年筆に視線を遣る。何の変哲もない、普通の万年筆だ。
ふと、僕はその碧い万年筆をどこかで見たことがあるような気がした。ヴァルではない、別の誰かの手がその万年筆を握っている…その光景を。
「…これはこの一本だけなの?」
「いいえ、私の書斎にもあるわ。この世界に元々居る者だけが持ってるの」
「何かイレギュラーがあった時、対処出来るように持たされているんだろうねぇ」
どうにも既視感があったのは、ノワールの書斎で見たことがあったのだろか。ヴァルの持つ万年筆を凝視していたノワールが、ほんの少し眉を顰める。
ノワールの表情の変化に気づけなかった僕は、「それで?」と続きを促す。
「人生録は、その人の魂の器だ。一冊につき、一つ。現世に存在できる魂の数には限りがある。だから一冊の本が終われば、次の本へと移る。魂の総数は結果的に変わらない」
「…だとしたら、例え誰かの人生録を書き換えたとしても、僕が現世に渡るのは無理じゃないか?現世の魂の総数が合わなくなる」
「いいや?それも単純だ。中身だけを入れ替えればいいのさ。要は魂の総数が増えなければいい。君が一方的に現世に行けば、魂の数はキャパオーバーだけど…人生録にちょこっと加筆して、器の中身を入れ替えるだけなら…」
地面から二つの石をヴァルが拾い上げる。両の手のひらに乗った石。右が黒、左が灰色。次の瞬間、パン!と両手を合わせ、二つの拳が差し出される。握られた拳の中は見えない。
マジシャンのようにゆっくりと、思わせぶりに拳が開かれる。左が黒、右が灰色。左右の石は入れ替わっていた。
「理論上、問題はないってわけさ」
「…なるほどな」
「ちょっと待って…!確かに可能かもしれないけれど、危ないわ…第一、誰の器を…人生録を使うの?」
「それは…すぐ詠に会えなきゃいけないから詠に近しい人…」
答えながらハッとした。詠のことばかり念頭にあったが、魂そのものを僕と入れ替えるということは。
「…その相手はどうなるんだ?入れ替わった、現世側の人間の魂や記憶は…」
「多分だけど、君たちが言う“詠ちゃん”みたいなことになるんじゃない?君が向こうに居る間は、こちらの世界を彷徨うことになるね」
薄ら笑いながらそう口にするヴァル。僕は言葉に詰まる。詠を助けたい、そのためなら僕自身はなんでもする。だけど何かのアクシデントで、入れ替わった相手に危険が生じるのは耐えられない。
「…戻り方は?」
「勿論、万年筆で加筆するんだよ。オレかノワールのどちらかが」
僕は二人を見比べる。ノワールは不安そうに小さく首を横に振った。やめた方がいい…、と言いたげな視線を僕に向けて。
「さて、どうする?決めるのは君だ。取引相手は君だからね」
僕は無言のまま、自分の手荷物から再び詠の人生録を取り出す。パラパラ…と捲って、一番新しいページを開いた。詠の現在地、今何をしているかを確認する。
「…故郷に、居るのか…うーん…今は一人みたいだ…」
「…もしかして入れ替わる器をお探しかい?それももしよければ、僕の方で手配できるよ。…代償は高くなるけどね」
予想外の言葉に、視線を上げる。ギラッとヴァルの眸が怪しげに光る。
「…知ってたのか?詠のことも、僕らがここに来るであろうことも」
「まあね。でも君は僕の取引を断ると思ってたからさ。そこは意外だったよ」
「…誰の人生録を使えと?」
「んー?この子でどうかな?」
ヴァルが懐から一冊の本を取り出す。青色の表紙、厚みはまだそんなになく、魂の持ち主が若年層であることが伺える。
どういう魂胆があって、わざわざ人生録まで用意しているのか知らないが。訝しがりながらも、僕はその本を受け取る。中身をそっと開いてみた。
「…沼名ライラ?…十八歳…なぜこの子を?」
「さあ?読めばわかるんじゃない?」
肩を竦めたヴァルは、僕からひょいと人生録を取り上げ、パラパラとページを少し戻す。目的のページを開いた状態で、再び僕に手渡した。
「…えっ…」
「一石二鳥だと思わない?いい案だろ?」
沼名ライラ。その子の過去が記された一頁。そこに書かれていた記憶の断片に言葉を失う。思わずヴァルを見た。彼の紫色の眸からは、何も読み取れない。
「…どういうつもりだ?どうして」
「ほーら、早くしないとその…詠ちゃん?だっけ?間に合わなくなるよ?」
「…っ、!」
茶化すように嗤う、ヴァルの一言で。僕はその続きを言えなくなる。確かに、今は四の五の言っている暇はない。ここまでお膳立てしてあるということは、この方法が成功する…という確かな根拠があるんだろう。
僕はノワールを振り返る。やはり心許なげに視線を揺らしてはいるものの、もう彼女は首を横には振らなかった。
深く、一つ、息を吸う。
「…わかった。この方法で、僕を向こうに送ってほしい。」
「取引成立だね。じゃあ、始めようか」
ニヤッと笑みを深くして、ヴァルがノワールに目配せする。不安そうな表情のまま、頷くノワール。
「悪いけど、意識のある状態でこれをやるのは危険だから。君には眠っててもらいたいな…またミルテの花でいいかい?」
「…最高に楽しそうに人の失態を掘り返す辺り、性格悪いよね、ヴァルは」
クツクツと肩を揺らしながら、ヴァルがどこからともなく小瓶を取り出す。
「ミルテの花の蜜だけ入ってる。君が眠ったらすぐに始めてあげるよ。大丈夫、取引はちゃんと遂行するし、今回はノワールって監視役もいるしね」
慎重に小瓶を受け取る。ヴァルはそのまま、青色の人生録の真っ白なページを開いた。左手に万年筆を持って。
僕は出逢ったこともない、沼名ライラという女の子に思いを馳せ、呟く。
「ごめんね…少しだけ、その器を貸してほしい」
ポン、と小瓶の蓋を開けた。中から甘い香りが漂う。心配そうなノワールと視線がぶつかった。僕は安心させるように、ふっと微笑む。
「大丈夫、すぐに戻ってこられるよ。詠ともちゃんと、ケリをつけてくる」
「うん…私はいけないけど、見守っているわ。気を付けてね、時雨」
「ありがとう…じゃあ、始めるよ」
僕は小瓶を口元に近づけた。飲み干そうと傾けた所で、バッとその手を掴まれる。
「!?」
「代償をまだ伝えてないのに始めないでよ。今回の取引、僕からの条件はね…」
耳元でヴァルが二、三言囁く。僕のズボンのポケットに、そっと何かを滑り込ませながら。それを聞いた僕は、意味が分からず眉をしかめる。
次の瞬間、パッとヴァルがその身を離した。小瓶を掴んだ手も自由になる。
「どういうことだ…?」
「まあ、いけばわかるよ。じゃあよろしく、早く飲んでよ」
ヒラヒラと手を振られ、僕は若干カチンと来たその勢いで小瓶を傾けた。トロッとした液体が喉を通り抜ける。甘すぎて思わず顔を顰めた、その時。
ふっと意識が遠のいて。
「…じゃ、頼んだよ。」
「いってらっしゃい、時雨」
二人の声が、淡い光の中に溶けていく。
ペンを走らせる音が、聴こえる。
5 廻航
祖母の病室に小一時間ほど滞在した後、私は笑顔でその場を去った。祖母は最後まで幸せそうに手を振ってくれて。カタン、と病室のドアが閉まった瞬間、泣き崩れそうになるのを必死に堪えて歩く。
ナースステーションでお礼を告げて、足早に外に出る。もうここに用事はない。この街にも、この世界にも未練はない。
外は、信じられないくらい澄み切った美しい青空だった。肺いっぱいに空気を吸い込む。あの時、『あまりある残像』を作った第一街区の森の匂いに、少し似ていた。
「…こっちの世界にも、こんな綺麗な空があったんだ」
しばらく空を仰いで、ハッとする。ほんの少しだけ、気持ちが揺らいだ自分がいた。祖母に会って、感傷に浸って。未練を失くしに来たのに、最後の挨拶のつもりで来たのに。後ろ髪を引かれている自分に、気づきたくなくて。
頭を振る。これ以上揺らぐ前に、もう行こう。最後の目的地は決まっていた。今から向かえば、日暮れまでには辿り着けるはずだ。
来た方角とは反対方向に歩き出す。丘を下って、あとはバスを乗り継いでいけば着く。病院の駐車場を横切って、敷地の外へ出た…その時。
「…って、おーい、ちょっと待って、そこのお姉さん!」
「…え…?」
背後から呼び止められ、振り返る。タタタタッと見知らぬ女の子が駆け寄ってきて、目の前で止まった。
鮮やかなブルーのショートヘア、大きな黒いリボンのピン。黒いブラウスに白いシャツを羽織ったその子は、息を切らせながら右手を差し出す。
「これ…病院の廊下に…落としてましたよ…」
「あっ…!」
彼女の手のひらに乗っていたのは、私の音符のネックレスだった。慌てて自分の首元を触る。そこにあるはずのネックレスはない。いつの間にか外れて、落としてしまったらしい。
「ありがとうございます…これ、大事なもので…」
「ああ、よかった…」
ショートヘアの女の子はふっと笑った。第一印象は二十代前半くらいのかと思ったけれど、微笑んだ顔は少し幼くて。もしかするとまだ十代かもしれない。
「一階の廊下でお姉さん見失っちゃって…諦めようかなと思ったんだけど。“ただのネックレス”なのか、“命より大事なネックレス”なのかは人によって違うから」
「…諦めないでくれてありがとう…私にとっては、後者だったの」
受け取ったネックレスはチェーンが途中で切れていて。もう付けられないけれど、大切に私は鞄のポケットにしまった。
「ううん…私もこのネックレス失くしたら立ち直れないから。」
青髪の少女は、胸元に光る金色のリボンのネックレスにそっと触れた。日差しを浴びて、キラリと反射するそれを見て、「可愛いね、それ」と微笑む。
「ありがと。じゃあ、私はこれで!」
軽く手を振って、彼女が踵を返す。足取り軽く病院の方に戻っていくその子を見送って。私はまた、歩き出した。
だけど。十秒も経たないうちに、背後で悲鳴のような声が上がる。
「…ちゃん、…ちゃん!?」
胸騒ぎがして振り返った。鮮やかな青髪が、地面に倒れ伏している。院内からたった今出てきたであろう看護師さんが、駆け寄っていく。
何が起きているのか分からないまま、私はつい先ほど大事なネックレスを届けてくれた少女に駆け寄った。うつ伏せに倒れた彼女は、ぐったりと目を閉じている。
「あの、私先生を呼んでくるのでライラちゃんを見ててもらえますか!?」
「あっ、は、はい!」
反射的に返事をすれば、看護師さんは慌てて中へと消えていった。ライラちゃん、というのはきっとこの子だ。看護師さんが名前を知っているということは、この病院の患者さんか、はたまた私のように患者さんの親族か。
私は為す術もなく、出逢ったばかりの彼女の背中にそっと触れる。大丈夫、温かい。心臓が脈打っているのも、ちゃんと感じる。
つい数秒前まで元気に話していた人間が、今は意識なく倒れ伏している…その事実を、堪らなく恐ろしいと思った。見ず知らずの、ついさっき会っただけの人なのに。目を開けて、と願った。怖い、恐ろしい、心臓がバクバクと早鐘を打っている。
刹那。スッと、彼女の両目が開いた。
「…あっ、!」
声が出る。視線は虚ろなままだが、確かに目を開けていた。どうしよう、どうしようと気持ちばかりが急いて、思わず立ち上がる。
「だ、だれか…あのっ、彼女目を開けて…!」
見てて、と言われたことも忘れて、つい院内に人を呼びに行こうとする。自分一人では心許ない。確実に助けられる誰かに来て欲しい。私の一挙手一投足が、彼女の命を左右してしまうかもしれない。それが怖い。判断を間違えたくない。
入口のガラス扉をくぐろうとした時。
「…っ、詠、逃げるぞ!」
信じられない、声がした。
心臓が、痛いくらいドクンと大きく脈打つ。体が震える。ぎこちなく振り返った。バッと、右手を掴んだその人は。
ライラちゃんと呼ばれていた、私にネックレスを届けてくれた彼女の服装、そのままだけど。
「し、…しぐれ…?」
私を見つめ返す眸の色が、碧い。
「…っ、行こう…!」
院内からガヤガヤと何かが近づいてくる音がした。もう頭の中がグチャグチャでどうしようもなくなった私は、ただ手を引かれるままに走り出す。
先を行く、その背中が。白いシャツを羽織った、その背中が。
時雨の白いマントの後ろ姿と重なる。
「…あっ、ちょっと、ライラちゃん…!」
後ろから誰かが叫ぶその声にも足を止めずに。私たちは、病院を後にした。
青空は、ずっと先まで続いている。
「…はあっ、はあっ…」
人生で両手の指に入るくらいの回数しかしたことがない、全力疾走。肺が悲鳴を上げている。ようやく足を止めたのは、走り出してから十分ほど経った時。土地勘のない先導者に連れてこられたその場所は、海岸沿いの一本道。
私たちの右手側には、浅葱色の海が広がっている。まだ二時半を少し過ぎた海岸には、誰もいない。
少し先で、膝に手をついて息を整えるその背中に。もう一度声をかける。
「…しぐれ…なの?」
ゆっくりと振りむいた、その顔を見て。「あっ」と小さく声が漏れた。
時雨だった。濃紺のショートヘア、碧い切れ長の双眸。服装こそ違えど、そこに居たのは私の記憶の中に居る時雨そのもので。
「…ごめん、驚かせて…僕もちょっと想定外で…」
申し訳なさそうに眉を顰めながら、頭のリボンのピンを外す。声も、私がもう一度聴きたいと願った、その声。
ぶわああっと何かが、胸の奥からこみ上げる。
「…っ、時雨…っ!」
驚きよりも、困惑よりも。何故か涙が最初だった。戻ってきてから、私は泣いてばかりだ。バッと時雨に飛びつく。
「…ははっ、ルナみたいなことするね」
「…あっ、ごめん…」
我に返って、慌てて身を離す。「別にいいよ」と微笑んで、時雨ははだけそうになったシャツを直した。冷静さが少し戻った私の頭が次に浮かべたのは、沢山の「どうして」だった。
顔にそれが表れていたらしい。時雨の笑みが、苦笑に変わる。
「聞きたいことが沢山あるって顔だね…そりゃあそうか。僕も詠に話がある。少しゆっくり話をしないか?」
時雨の視線がスッと横に移動する。砂浜を見渡して、倒れた大木を指さす。
「あそこなら、座って話が出来そうだ。…どう?」
戸惑いながらも、頷く。目を細めて、時雨が先に土手を駆け降りる。
大木に背を預けた私たちは、しばらく無言で海を眺めた。私は時雨が話を切り出すのを待っていたし、時雨は私が何か言うのを待っているみたいだった。
沈黙に負けたのは、私の方で。
「…どうやって、ここに来たの?」
この問いは勿論、時雨も予想が付いていたらしく。私がこちらに戻ってきてからの一部始終を、簡潔に分かりやすく話してくれた。ヴァルという旅商人の存在、こちらの世界に来た方法…全てが驚きばかりだったけれど。私は最後まで口を挟まず耳を傾けた。
「…で、目を開けたら詠の顔が目の前にあってさ。驚いたのも束の間で、詠が慌てて人を呼ぼうとするから…咄嗟に手を取って逃げてしまったって訳だ…」
「…説明のしようがないもんね」
「ああ。病院に連れていかれて検査や治療をされたら、堪ったもんじゃないし…」
「人の体を借りてるってことだもんね…」
言いながら、私は気まずい思いで空を仰ぐ。時雨が何をしに来たのかは、とっくに分かっている。私がそこまでさせてしまったのだということも。
しばらく、無言の時間が続いた。時折海猫かカモメか、分からない鳥が鳴いて。さざ波が寄せて、引いて…を繰り返して。私は言葉を探していた。謝罪と、言い訳と、説得の言葉を。
「…詠、」
優しくて、でも悲しそうな声音で呼ばれて。
「…どうして、あんなことを?」
「…ごめんなさい」
一つ謝ってから、それでもと口を開く。
「眠らせて、嘘をついて、居なくなったのは悪かったと思ってる。でも…私、決めてるから」
「詠、」
「止めに来たんでしょ?私のこと」
遮って、その目を真っすぐに見つめる。
「…それだけは、出来ないから。戻るから、私」
ワガママだ。小学生の頃、欲しいものが手に入らなくてグズッていた頃の自分みたいだ。正しいのは相手だと、分かってる。それでも、譲れなかった。
僅かに揺らいだ時雨の目に、厳しい光が宿る。
「駄目だ。させないよ。…僕が、させない」
「…無理だよ。時雨だってずっとこっちに居られるわけじゃないでしょう?時雨が居る間は無理でも、時雨が戻ったら私…」
「戻ってきてからの詠を、見てたよ。すぐに実行に移されたらどうしようって気が気じゃなかったけど…君は、すぐには死ななかった。わざわざ故郷に来て、会いたいと思う人に会って…その時点で君は一人じゃない」
咄嗟に言い返せなくて、口を噤む。時雨の口調が、畳みかけるように強まる。
「一つでもここに居たい理由があるなら、まだ君は生きるべきなんだ」
「…そんなの、わかってる」
雫が落ちるように。葉が枯れるように。言葉がポツリと落ちる。
「…でも…ここで生き続けることは、時雨に二度と会えないのと同じ意味なんだよ?私一人居なくたって廻る世界と、時雨と一緒に廻る旅路…天秤にかけて、どちらが幸せかなんてわかりきってる」
「それは…」
「時雨にとっては…!」
つい語調を荒げる。必死な私の弁明に、気圧された時雨が黙り込む。
「…時雨にとっては、何百年と旅してる中で偶然出会って助けた…くらいの存在かもしれないけど。何もかも忘れる筈だった私は、大勢の中の一人でしかなかったかもしれないけど…でも、」
ザザーッと波が寄せる。
「私には、たった一人の恩人なの…私は救われたの、貴方に…貴方の音楽に。」
ザザーッと波が引いていく。
時雨は押し黙ったまま動かない。見たことのない表情をしていた。遠い過去の何かを思い出しているみたいな、切ない光が眸に映る。
「…わかる。わかってるよ…」
やがて時雨の口から出てきたのは、そんな言葉で。私は時雨に認めて、許してほしかった。でも時雨はそれ以上何も言及せず、そっと視線を海に移した。肯定も否定もされなかった私の感情は、宙ぶらりんのままだ。
諦めて、私も海を眺める。どうすればよかったのだろう。何が正解だったんだろう。私は間違えたのだろうか。今も、間違えているのだろうか。
いっそ出逢わなければよかった…なんて、思う程度には。
あの不可思議な七日間は、あの旅は。私の全てを変えてしまったのだ。
互いに何も言えないまま、二十分程経った。
はあ…と自然に溜息がこぼれる。時雨がチラッと私を見た。
「…そういえばさ、」
一旦空気を入れ替えるみたいに。時雨が軽い声音で言う。
「ヴァルとの取引の代償。頼まれごとだったんだ」
「…頼まれごと?」
ぎこちなかった空気にヒビが入る。問い返せば、頷いた時雨がズボンの…正確にはライラのズボンのポケットから小さな紙を取り出した。
「なんか…ここに行って、この人を探せって」
手渡された紙片は真ん中で折られていて。開いてみれば、中には住所と人名らしき文字の羅列が記されていたのだが。
問題は、その住所。
「…え…この場所…」
「ん?知ってるのか?ここから近い?」
「ぜんっぜん近くないよ…むしろ正反対…」
書かれていた地名は、遠く南の外れにある島だった。今いる私の故郷からでは、一度出発地点の都会に戻った後、更に乗り物で半日ほど移動しなくてはならない。
その旨を聞いて、絶句する時雨。
「ええ…あいつ阿呆なのか…?あ、いや。詠の故郷がどこにあるかなんてあいつも知らなかったのかな…」
「ここに行ってこの…霜月さんって人に会えたとして、その先は?会ってどうするの…?」
「伝言を頼まれてるんだ。それもよく意味の分からない伝言」
返した紙片をもう一度見直して、時雨が大きな溜息を吐く。
「そんなに遠い場所だなんて…参ったな…」
途方に暮れる時雨を見て、なんだかちょっと不思議な気持ちになった。向こうの世界に居る時は、「何でも知ってる仙人」みたいに思っていたが。
思わずクスッと笑みを零せば、訝しげな眼差しが向けられる。
「…まあ、取引なら行くしかないもんね。…時雨、行き方に検討はついてるの?」
「…まったく。正直今の現世のことは詳しくない…」
「じゃあ、今度は私が案内するね」
思わず笑みを零しながら立ち上がる。時雨は驚きの目で見つめている。
「とりあえず駅に行って、列車でスタート地点まで戻ろう。島への行き方はその間に私が調べるから」
「…やけに協力的だね…?何か魂胆でもあるの…?」
「別に何もないよ。ただ…」
しゃがんだままの時雨に、手を差し伸べる。
「また時雨と、旅が出来る。それが嬉しいの」
「…君は本当に…いや、何でもない」
呆れと、感傷とが半々になった時雨の言葉。結局胸にしまい直したのか、勢いよく私の手を掴んで立ち上がる。
「じゃあ、案内よろしく」
「うん…!じゃあ、行こう」
海を背に、二人で土手を上って。来た道を戻る。病院の人に見つかると厄介なので、迂回ルートを選んだ。奇しくもそのルートは、私の中学生の時の通学路で。見慣れた道を、何の彩もなかった道を、時雨と二人で歩く。
存在しないはずの時雨と。出逢うはずのない、時雨と。
あの世界で、一緒に歩いたように。
駅に辿り着くと、時刻は昼の三時を回っていた。物珍しそうにあたりを見回す時雨の背を押しながら、電車に乗せる。
故郷の街が遠ざかる。ここを最期の場所にするつもりだった私の隣には今、時雨が居る。確かに、ここに。
私の人生録に、少しでも多く時雨との時間を綴れるのが嬉しくて。
堪えきれない笑みを零した。
6 雪華鏡‐ゆきかがみ‐
『雪ってさ、どうして冬にしか降らないのかな?』
懐かしい声がする。パッと目を開けると、空が白い花を…雪を降らせていて。
『…さあ。確か冬は寒いから、雲を作ってる水の粒が凍ってそれが解けずに地上まで降りてき…』
『もー!そういうことじゃなくって!ライラはロマンがないなあ…』
私のことを呼ぶ声は、鈴みたいに軽やかで、高くて、凛としていて。対する私は、自分の声が苦手だった。女の子らしくない、ハスキーで大人びた声。
『昼間に降る雪もいいし、夜の雪は幻想的だけど…この時間もいいよね!』
『…そう?なんか色のコントラストが変じゃない?』
『もーいいよ!ライラにこの良さを分かってもらおうとした私がバカだった!』
プン!とそっぽ向くその子。髪に大きなリボンをあしらったその子。怒るといつも、シマリスのように頬を膨らませるその子。
フッと自然に頬が緩む。
『…まあでも、綺麗だとは思うよ。…この景色』
私は視線を目の前の海に移す。冬の海は死ぬほど寒くて、手がかじかんでもう動かなかったけれど。舞い落ちる雪も、反射する水面も、綺麗だと思った。
確かに、この時間の雪も悪くない。夕暮れの茜色に映える白。もうじきあの夕陽は水平線の彼方に消えて、夜が訪れる。
…ずっとこの夜が続けばいいのにな。
そう呟いた声は、彼女に…ルナに、聞こえていたのだろうか。
「…ちゃん、ライラちゃん…」
誰かが呼んでいる。瞼が重い。固い地面の感触。ざわざわと、何かが擦れるような音。あの夕暮れの海で嗅いだような、微かな冬の匂い。
「…ライラちゃん!」
ハッと意識を覚醒させる。勢いで起き上がれば、目の前に見知らぬ女の人の顔があって。
「わっ!?」
思わず身をのけぞらせる。その女性…銀髪に黒っぽいドレスという珍しい装いの彼女は、慌てて早口で捲し立てる。
「ご、ごめんなさい…!驚かせるつもりはなくて…大丈夫?」
「え…あの…あなた…というかここどこ!?私さっきまで…」
さっきまで病院に居たはずだ。昔お世話になった看護師さんに、久しぶりに挨拶しようと病院に着いて。一通り挨拶を終えた後、知らないお姉さんに落とし物を届けてあげて二言三言会話して。荷物を取りに病院に戻ろうとして、そして…。
「…あれ?どうしたんだっけ、その後」
「あー…」
首を捻る私の前で、ドレスの女性は言葉を探すみたいに視線を彷徨わせる。
「君は倒れたんだよ。病院に戻る前に」
「え?」
背後から声がして振り向く。今度はシルクハットにマント…というもっと特徴的な見た目の男性がそこに立っていて。しかも私が今居るのは、何やら遺跡みたいな崩れかけの建造物の石畳で。段々、わかってきた。これはきっと…
「夢、だ」
「え?」
「そっか。私、倒れちゃって、今夢見てるんだね」
倒れるほど体調が悪い自覚はなかったけれど。確かに最近は、ダンスに打ち込みすぎてちょっと無理をしていた気がする。そのせいで私は倒れて、ここはきっと夢の中なのだ。そうじゃないと、この奇怪な現象に説明が付かない。謎の風貌の男女と遺跡に囲まれている私。
「…まあいっか、それで。と、いうわけで今から君に良いものを見せてあげる。彼女についていくといい」
「一緒に来てくれる?…会わせたい人が、いるの」
普段の私ならば警戒して絶対についていかないけれど。ここは夢の中、いずれ目が覚める。それなら、好きに動いたっていいだろう。
穏やかで柔らかい、神秘的なオーラを纏った、その女性に歩み寄る。
彼女は少しだけ、悲しそうに微笑んだ。
「行きましょう…あなたもきっと、会いたい人だから」
そうして黒いドレスの女性に先導された私は夢の中を歩いた。今まで見たどの夢より景色が鮮明で。木も石畳も夜空も、全部本物みたいだ。
夢では大概、意味の分からない現象が起きる。一緒に居るはずのない、小学校の友達と高校の先輩が仲良くサバイバル生活をしてる…とか、そんな感じの。だからこの夢も同じ類なのだと私は納得した。見ず知らずの人が出てくるパターンは初だったが。何かこんな夢に繋がるようなアニメでも最近見ただろうか。
そんなことを考えながら歩くこと約一時間。いつの間にか全く違う景色が広がっていて。現実世界に近い、ビル群。雨が降っている、街…のような場所に出る。
歩いている間ドレスの女性は色々と話しかけてくれたが、よく覚えていない。思考がぼんやりして、記憶に霞がかかったみたいだった。
意識がハッキリしたのは、謎の真っ黒なタワーに連れていかれて、プラネタリウムみたいな部屋に入れられた時。紫のパーカーを着た少女と女性が何かを喋った次の瞬間、私は青空の下にいた。
波音、海猫の鳴き声、船、綺麗な晴れの空。
さっきまでいたはずのタワーはどこにもない。唖然として辺りを見回す私の横で、ドレスの女性は涼しげな顔で立っている。
「…瞬間、移動…?」
「ええ、まあ…そんなところかしら」
女性は曖昧に笑った。今日の夢は、随分ファンタジー要素が多い。
そうして彼女とまたポツポツ会話をしながら、浜辺を歩いた。海を見ると、いつも思い出してしまう。あの雪の日に、ルナと一緒に見た海。
茜色の空と、小さな雪の粒。
私がルナと出逢ったのは、小学五年生の時。
昔からどこか冷めていて、現実主義な子供だった。他の友達が「スーパーヒーローになりたい」「プリンセスになりたい」と話す中、「あれは全部御伽噺だから、ヒーローにもお姫様にもなれないよ」と答えるような子供。
優しさのつもりだった。だって、叶わない夢を信じ続けるなんて可哀そうだ。早く教えてあげた方がいいじゃないか。
でも、そんな私を周りの子たちは嫌がった。意地悪だと言われ、泣かれ、仲間外れにされるようになって。結局、小学校の高学年になるまで…ルナに出逢うまで、私に友達はいなかった。
ただ、私は別に友達が居ないことを寂しいとも、空しいとも感じなかった。むしろ一人で過ごす方が気楽だ。何も気にせず、気を遣わず、好きなことが出来る。
そう、私はダンスが好きだった。テレビの歌番組でたまたま見かけた、アーティストのパフォーマンス。中央で歌うその歌手よりも、私の視線はバックダンサーの一人に釘付けになった。
その人は、まるで重力なんて無いみたいな軽やかさ、しなやかさで。小柄なのに、信じられないくらい迫力があって。一瞬で、魅入られた。
親に初めて我儘を言い、ダンススクールに通わせてもらった。小さな教室だったが先生は凄く熱意のある人で。嬉しいことに私にはダンスの素質があったらしい。熱心な指導のお陰で、入って三年目には教室で一番の実力と言われるようになった。
私は放課後も毎日、空き地で好きな曲でダンスを練習した。同級生がそれについてコソコソ噂をしているのも知っていたが、気にならなかった。
私にはダンスがある。それだけでいい、と思っていた。
ある日の黄昏時。いつもの空き地に先客がいて、近くの別の小さな公園に行った。寂れたその公園には誰もいなくてラッキー、と音楽を流しながら練習をしていると。
『~♪キミの世界がミタイ、ミタイ~』
流している音源とは別に歌声が横入りして。びっくりした私は思わず振り返る。
『…あっ、ごめん、邪魔しちゃった?』
そこに居たのは、水色のブラウスに紺のスカートを纏った、同い年くらいの女の子。頭に大きなリボンを付けた彼女は、ニコニコしながら私に駆け寄ってきた。
『いいよね!その曲!私も大好きなんだ!』
『…ふうん。そうなんだ』
一目見て、相容れないと思った。女の子らしい…を体現したようなその子は、よく私の陰口を言う女の子たちとタイプが似ている。ショートカットに、パーカーに短パンで踊っているような私とは、絶対に気が合わない。
だけど、その子…ルナは目を輝かせて私に話しかけ続ける。
『ここのサビのメロディがね、私のすっごく出しやすい音域で…』
『…音域?』
『あ、音の高さの幅のこと!私、歌が好きで、いつか歌手になるのが夢なんだ!だから音楽の勉強してるの!』
『…へえ、そうなんだ。』
他に言う言葉が見つからず、似たような相槌を打つ。明らかに冷たい私の態度に一ミリも臆せず、ルナはちょこん、とブランコの柵に腰掛ける。
『ねえねえ、ここで見てていい?』
『え?』
『ダンスの練習、してるんでしょ?口ずさんでるだけで、邪魔はしないから!』
本当は今すぐ帰って…と言いたかったけれど。言い返して問答になるのも面倒だった。『好きにすれば?』と冷たく返して、私はまた続きを踊り始める。
『~♪主観に占領された~偽りの箱庭~』
音源の歌声と、ルナの歌声、二つが重なる。うるさいとは思わなかった。ルナの歌声はパワフルで、芯があって、聴いていて心地が良い。歌手になりたい、というだけはあるな…なんて。少し上から目線な感想を抱きながら、日が暮れるまで私は彼女の歌声に合わせて踊り続けた。
『ねえねえ、ライラはさ、ダンサーになるのが夢?』
『うーん…』
あの、夕暮れの公園で出逢った日から。ルナはよくダンスの練習をする私の所へ、遊びに来るようになった。あまりにも毎日来るので嫌がっていた私も観念して、ルナがそこに居るのを許すようになった。
そうして二カ月が過ぎたある日、唐突にルナが繰り出した質問は私の心を小さく揺さぶる。
『…ダンサーになれるほど、上手なわけじゃない』
『えー?ライラのダンス、かっこいいよ!私は好き!』
花が綻んだような笑顔。ルナは茜色の太陽みたいに、いつも眩しい。
『…中途半端にかっこいい、じゃダメなんだよ。プロっていうのは、誰が見てもかっこいい、凄い、じゃなきゃダメ。ミスも許されない。』
『じゃあ、そうなればいいよ!』
俯いたままの私に、さも当たり前のようにルナが言う。思わず視線を上げれば、自信満々の笑みでルナが見つめ返していて。
『ライラは、絶対なれるよ!私が保証する』
『…軽々しく保証とか言わない方がいいよ』
『ううん!軽々しくない。心から言ってる。ライラがその未来を信じられないなら、私が代わりに信じてあげる!』
どうして、こんな真っ直ぐに誰かを信じるなんて言えるんだろう。
ルナは、スッと右手の小指を立てて私に差し出す。
『約束しよ!ライラは世界一のダンサーになる!私は世界一の歌手になる!それで、二人で一緒に舞台に立つの!』
『…何それ、そんなの絶対…』
『無理じゃない!』
言いかけた「無理」を先に封じられて、口を噤む。少し声を荒げたルナは、無理やり私の右手の小指に自分の小指を絡ませる。
『できるって信じなきゃ、できないんだよ!』
ルナの言葉は、彼女の後ろで燃えている夕空よりも。ずっとずっと熱くて、力強くて、眩しかった。
『約束ね!』
誰かと…友達と。約束をしたのは、これが初めてだった。
それから、ルナと私は親友になった。
ルナと居る時間は楽しくて。最初ダンスや音楽の話しかしなかったけれど。次第に学校の話、勉強の話、家族の話…互いの全てを打ち明けるようになった。
私は世界中に嫌われたまま生きるんだ…なんて、ずっと思っていたけれど。たった一人でも、自分の味方でいてくれる友達が居る。
それだけで、世界はずっと輝いて見えた。
ただ一つだけ、心配なことがあって。
ルナは体が弱かった。中学生になって、私たちは同じ学校に通うようになったのだが。ルナは度々学校を休んで、教室に来られない日が多かった。深刻な病気なんだろうか…と何度か恐る恐る尋ねたが、ルナはいつも笑って「体調崩しやすいだけなの!」と答える。私はそれ以上追及せず、ルナが休んだ日は必ずルナの家にプリントを届けに行った。
あっという間に三年が過ぎて中学生活もあと四か月…に迫った十一月のこと。その日もルナは休みで、私はいつものようにルナの家のインターホンを押したのだが。
『…ああ、ライラちゃん、ありがとうね…』
いつも笑顔で応対してくれる、ルナのお母さんが。真っ赤に泣きはらした目で、震える声で私に言う。すぐに何かあったのだと察した。
『あの…ルナに何か…?』
そこで私が聞いたのは、ルナの命の灯があともう少しで消えてしまう…という。到底信じがたい事実だった。
ルナは、治療のため遠くの田舎の病院に長期入院になったという。
私は学校を休んで、すぐルナに会いに行くことにした。私の両親は理解のある人たちで、旅費を出してくれて、病院までも一緒に行く…と言ってくれたけど。私はそれを断って、一人で旅立った。親に泣き顔なんて見られたくない。
移動する新幹線の車内で、色んなことを考えた。こうしてる間にも、ルナが居なくなってしまったらどうしよう、とか。やっぱり重い病気だったじゃないか、とか。ルナへの文句、泣き言、全部がグルグル反芻して、ずっと心臓が痛くて。
死、は誰にでも平等なはずなのに。近づくまで一切その足音は聴こえなくて。気づいた時にはもう遅い。ただ、近い未来に大切な人を失うかもしれない…という恐怖だけが募る。
何一つ思考がまとまらないまま、ルナのいる病院に着いた。
田舎町の、丘の上にある病院。こじんまりしていて、とてもじゃないけれど高度な設備が整っているようには見えなくて。
看護師さんたちは優しくて、皆温かかった。面会時間まで待つ間、待合室でぼんやりと外の美しい海を眺めながら。私はなんとなく察してしまった。
治療のため、ではない。きっと、ここに来たのは。
『…え!?ライラ!?』
二週間前まで、何も知らず元気に学校で話していたルナは。病院着に身を包んで、ベッドに背を預けて、入り口に立つ私をまん丸の目で見つめていた。
『ど、どうして…』
『…ルナのお母さんが、教えてくれた』
案の定ルナは一瞬、悔しそうに顔を歪める。でもそれはすぐに消えて。
『…えへへ、ごめんね?だって、ライラには知られたくなかったんだもん…』
困ったように笑う、ルナのその顔は。いつも通りに見えた。いつもの、眩しくてキラキラした笑顔。
『…違うでしょ。言い訳は聞きたくない』
ルナの笑顔が陰る。腹の奥でふつふつと煮えていた何かが爆発して。私はルナに詰め寄った。点滴の刺さっていない腕をガッと掴む。
『できるって信じなきゃ、できないんじゃないの?私が聞きたいのは、どうして生きるのを諦めようとしてるのかってことだよ!』
『あ、諦めてなんか…』
『諦めてるでしょ!こんな田舎の病院で、治療のため?そんな訳ない。最期だから、景色が綺麗で海の見える病室で…って、そういう魂胆丸見えなの!』
『ち、ちが』
『違くない!…治療にお金がかかるとか、そういう理由?なら私が稼ぐよ。バイト何個掛け持ちして、借金したっていい。学校なんて辞めてやる。』
『ライラ!』
上がった息を整える。珍しく大声を出したルナの、険しい眸を真っすぐに見つめ返す。ルナは私の手をそっと振りほどく。
『…私だって、私だって…嫌だよ。本当はライラと一緒に居たい。歌だってもっと歌いたい。諦めたくなんかないよ』
うっすらとルナの目に涙の膜が張る。それは初めて見る、ルナの泣き顔で。
『高校行きたいもん。歌手になるって夢も、叶えたいもん。ライラとまだ一緒に舞台に立ってない…約束…守りたいよ…』
さめざめと泣くルナに。不器用な私はかける言葉を持たなくて。
『大好きなのに…幸せなのに…家族もライラも友達もみんな…歌も…音楽も…』
とりとめもなく言葉を、涙を零すルナの体をぎゅっと抱きしめて。そのままずっと、背中をさすり続けた。ルナの背中は私の涙でびしょびしょになった。
それから。月に二回、隔週で私はルナのいる病院を訪れるようになった。
遠いから交通費はそれなりにかかるのだけれど。両親は『友達との時間を大事にしなさい』と文句一つ言わずにお金を渡してくれた。両親に一生分の恩が出来た。
季節は秋から冬になり、木枯らしが舞って、初雪が降った。初雪が降ったその日は、偶然私がルナのお見舞いに来た日で。ルナの体の調子もいい日だったので、日が暮れるまで…という条件付きで、外出許可が出た。自力で歩くのは少ししんどそうだったので、私が車いすを押して歩く。
浜辺に行こう、とルナが言い出して。茜色に染まった空と、水平線を見に行った。正直、砂浜は車いすには不向きだったが。久々の外出ではしゃぐルナの望みを叶えてあげたくて。ダンスで鍛えた腕と足腰で、必死に砂浜の上も車いすを押した。
暫く海を眺めていた時、初雪がはらはらと舞い降りてきて。
『…約束、守れなくてごめんね』
ポツリ、とルナが海から目を離さずに零す。私は無言だった。
ルナの病気を治すには海外で手術をするしかないのだという。でも、とても高度な手術が必要で多額の手術費がかかる。その上、手術の順番を待っている人が沢山居て、長ければ数年待たなければならないらしい。
物語の世界でよく見る話が、いざ身近な人で起こると実感がまるで湧かなくて。
中学生の私なんて何の役にも立たない。手術のためのお金も、ルナを救える技術も私は持っていない。
無力だった。世界は不平等で、残酷だ。
答えられない代わりに、私はルナの手をぎゅっと握った。涙が頬を伝うのを感じながら、二人で夕陽を眺める。
『…ライラが居てくれて、よかった。ありがとう、ここまで来てくれて』
もう、夕陽は八割海の底に沈んでいて。夜が来る、来てしまう。戻らなくちゃいけない。この時間が終わってしまう。
『…ライラ。』
『え?』
驚きの眼差しが私に向く。ルナが私を呼んだのではない。自分の名前を、私が口にしたのだ。
『ライラって名前ね、ラテン語で琴座って意味なの。そこから取ったんだって。私、誕生日が七夕だからさ。琴座のベガは、織姫の星じゃん?』
『…へえ、そうなんだ…』
素直な驚きと、どうしてその話を今するんだろう…という困惑。両方入り混じった声音で、相槌を打つルナ。
『琴座にはね、神話があるの。ギリシャ神話。オルフェウスの竪琴の物語』
『…どんなお話なの?』
『ある時ね、琴弾きのオルフェウスの妻が毒蛇にかまれて死んじゃうんだ。悲しみに暮れたオルフェウスは、冥界の王ハーデスの所へ妻を迎えに行くの。そして頼み込む。“妻を生き返らせてほしい”って琴を弾きながらね。その旋律があまりにも美しかったから、ハーデスは妻を生き返らせてあげよう、って誓うの』
『へえ…!良かったね!』
パッと顔を輝かせたルナに、私は首を振った。
『いや…ハーデスは一つだけ条件を出すの。“帰り道で絶対に妻を振り返ってはいけない。最後まで振り返らなければ、目が覚めた時現実で妻が迎えてくれる”って。でもオルフェウスはどうしても気になって、途中で振り返ってしまった。』
『…それで?』
『それで、妻は結局戻らず、絶望したオルフェウスは自害してしまうんだよ』
『…ええ…バッドエンドじゃん…』
眉を思い切り顰めるルナ。私はオルフェウスの気持ちがよく分かる。大事な人を取り戻せるチャンスを自ら棒に振ったのだ。あともう少しだったのに。絶望して当然だ。だけど。
『私も、絶対に迎えに行くから』
『え?』
『振り返らない。ちゃんと生きてから、必ず会いに行く。ルナがどこに行っても、どうなっても、絶対に見つける。冥界でも、天国でも、来世でも。』
ルナの眸が丸く見開かれる。もう薄暗くて、ハッキリとその顔は見えないけれど。
『約束する、必ず迎えに行く』
力強く、言い切る。一筋の涙がこぼれて。
ルナは、花が綻ぶように、優しく微笑んだ。
『…うん。必ず、待ってる』
それから二か月後のある朝。学校へ行こうとした私の家にかかってきた一本の電話。母がとって、私を見て、唇を震わせたその瞬間に。
私は膝から崩れ落ちた。こんな朝が来ないようにとずっと祈っていたのに。
二月二十九日。四年に一度しかない特別な日。あと一日で暦上春が訪れる、そんな日のこと。
ルナは雪の花となって散った。
大事な人が居なくなっても、当たり前のように朝日は昇り、夜が来て、季節は廻った。悲しみは時間が解決してくれる…というのは真理で、一年、二年…と時が経つにつれて、鮮明だったすべての記憶は少しずつ朧になってゆく。
覚えていようとした。声も笑顔も話したことも、全部。だけど人間の記憶は残酷で。ちょっとずつ薄れていくのを、止める術はなくて。
記憶の退化に抗うのは無理だと悟った私は、せめて。ルナが信じてくれた夢を…ダンサーになるという夢を、叶えようと思った。前を向かないと、ルナに笑われる。めそめそ凹んでいるより、思い出して胸を痛めるより、その方がルナは喜ぶだろうと。そんなの、生き残った私の自己満足かもしれないけれど。
でも。ダンスを踊るたび、やっぱり蘇るのは親友の顔で。
辛い。もういっそ忘れてしまいたいのに、心臓が、魂が、忘れたくないと叫んでいる。矛盾した感情を抱えたまま生きるのは、あまりにも苦しい。
どうしようもないまま、三年の月日が経った。
「…ここよ、この家。」
長い、永い記憶の旅から浮上して、ハッと頭を切り替える。まだ夢の中にいる私は、ドレスの女性に連れられて白い小さな家の前に居た。三角形の、テントみたいな形の家だ。見覚えはない。
訳も分からないまま促され、インターホンを押させられる。
数秒の間。ガチャ、とドアが内側から開いて。
「はーい!あ、ノワール!久しぶ…」
ドレスの女性から、私に視線を移したその人を見て。石のように、体が固まる。頭が働かない。だって、そこに居たのは。
「ル、ルナ…?」
信じられない。そう口から出かけた言葉は、引っ込んだ。
そうだ、これは都合のいい夢なんだ。
「…やっと来てくれた…思い出したよ、そうだ…私はライラと、約束をしたんだね」
目に大粒の涙を溜めて、微笑むルナも。
「…うん、やっと迎えに来られたよ」
ボロボロ泣きながら答える私も。
「覚えててくれてありがとう」
「待っててくれてありがとう」
全部全部、都合のいい夢。
もう少しだけ、ここに居させて欲しい。浸らせてほしい。
幸せな時間を。一緒に居られるこの時間を。
噛み締めていたいの。
Interval
「…何を考えているの?」
「ん?何がだい?」
ライラちゃんを、ルナの元に送り届けて。多分時雨はあと二日(現世時間で一日)は戻らないだろうと考えた私は、水入らずの時間を楽しんでもらおうと第七街区に一人帰ってきた。
ヴァルは、人生録…ライラちゃんの青い本と、時雨の青い本の二冊を広げて、遺跡の石段に座り込んでいる。左手には、例の万年筆を持って。
「入れ替わる対象に、ライラちゃんを初めから選んで…時雨を現世に行かせて、ライラちゃんをルナに会わせて…ヴァルは何が目的?」
「別に?何かするたびに理由が必要なのかい?」
人生録から目を離さず、ヴァルは気のない返事をする。
「…ヴァルは、理由もなく人に何かしてあげるタイプじゃないでしょう?」
「ええ?心外だなあ…オレはただ自由に生きてるだけ。たまには気まぐれで人助けだってするかもしれないじゃないか」
「…そう?じゃあ質問を変えるわ。…その万年筆。」
ピクリ、とヴァルが身じろぎする。
「確かに私の物と同じよ。だけど…どうして貴方がそれを持っているの?」
「…どういう意味だい?」
「…その碧い万年筆は、セツナのものだわ」
ヴァルの口元に浮かんでいた笑みが、消える。
加筆できる万年筆は、この世界に三本。紫が私、赤がヴァル、そしてセツナのは碧色。なのに何故、ヴァルがそれを持っているのか。
「…へえ、君はてっきり全部知っているものだと思ってたんだけどな」
「…何のこと?」
「…ふふっ、いいよ。同類のよしみで、君には教えてあげる。セツナについてはどこまで知ってる?」
「…時雨に聞いた限り」
「…ふうん。じゃあ殆どは知ってるってことだね」
そう言って立ち上がったヴァルは、なぜか万年筆を胸元にしまいこんで。代わりに石段に置いていた一冊の青い人生録を…時雨の、人生録を拾い上げる。
「君も知っての通り、時雨の人生録は一度焼失してる」
「…ええ。その時にセツナが時雨を救ったんでしょう?」
「救った…かどうかは分からないなぁ。だって本来は転生するはずだった時雨が、永久にここに居る羽目になったんだから」
ヴァルがパラパラッとページを繰る。どこかのページに目をつけて、開いた。
「…その時にセツナから伝言を頼まれたんだ。で、取引した」
「じゃあ…その万年筆は…」
「もらったんだよ、セツナに。…代償としてね」
懐から再び取り出した万年筆を、クルッと回して。ヴァルは意味深に微笑む。
「因みに、オレが今回時雨に与えた代償は頼み事。ある人に、ある伝言を頼まれてもらった」
「…ある人?伝言?」
ヴァルはまた懐から本を出す。さっきまで眺めていたライラちゃんと時雨の本ではない。緑色と、薄紫色の…二つの、誰かの人生録。
「ほら、見てごらんよ」
差し出されたその二冊の、開いたページを見る。そこに書かれていた事実を目にした時、私は唖然として言葉も出なくて。
「これ…本当なの…?」
「ああ。だから試してるんだよ…全部上手くいくか、変えられない運命なのか…」
不安でざわつく胸を必死に抑え込む私を、月は無情に見下ろしている。
厳かに。静謐に。
7 Troubadour
暗闇に佇んでいる。
眠りに近い感覚だったが、思考はハッキリとしているのに体は動かない。水中にいるような、宙に浮いているような、何とも言えない無力感。
その中で僕はずっと、ライラという少女の記憶を辿っていた。
僕が器を貸してもらっている彼女は、今あの世界に居て。僕があの子の動向を知るはずはないのに、なぜかすべての情報がちゃんと頭に入ってくる。
ルナとの出会い、思い出、別れ、そしてあの世界でルナと再会した喜び。全て自分がたった今体験しているかのように鮮明で、リアルだった。
器を入れ替えるというのは、魂を入れ替えるのと同義だ。
寝ている間は魂と器の境界が曖昧になるのだろうか。だから僕にもライラの記憶が、情報が流れ込んできた?
埒が明かないので、一旦考えるのをやめる。とにかく、ルナがずっと待っていた相手と再会出来たことは僕にとっても感慨深かった。
第三街区にルナが来たのは、確か向こうの時間で…六年ほど前だった気がする。僕にとっては割と最近の部類なので、よく覚えている。夕暮れの空の下で泣いていたルナを。
そのルナが絶対に譲らなかった約束。迎えに行く、と言ってくれた誰かを待っていたい。ルナはいつもそう言っていた。相手の…ライラの記憶は失ってしまっていたのに。約束だけは、魂の中に焼き付いていたのだろう。
転生の順番は、基本的にランダムだ。僕もその辺のことはよく知らないが、順番が記されたリストのようなものがあるらしい。管理しているのは、ノワールと寧々。あの世界に降り立ってすぐ、転生する人もいれば。逆に長く留まる場合もあるにはあるが…大体の人間が数カ月程度でいなくなる。
但し、自分の番が来て呼ばれても「もう少しここに居たいから」と順番を後回しにしてもらうことも可能だ。ルナと藍珠はそうしてあの世界に留まった。転生が決まった人間は第五街区の神殿か、第九街区のターミナルを通過して来世へと向かう。その人の人生録には終止符が打たれ、その本は二度と開かなくなり。
そして新しい、真っ新な人生録が与えられるのだ。
『まったく別の人間に生まれ変わるって、どんな感じだろうね?』
声がする。大らかで勇ましくて、少しおどけたような声音。
『輪廻転生?っていうんだっけ?現世の一部の宗教では』
勇ましい声は、喋り続けている。顔は見えない。一つに結った長い銀髪が揺れる、後ろ姿だけがぼんやりと浮かび上がる。
『…あっはっは!たった十数年生きたくらいで、なーに全部悟ったみたいな顔してんの?』
豪快な笑い声。何もかも見透かしたような、それでいて力強い眼光。
『時雨、世界はね…』
僕を呼ぶ、その人は。
チリンチリーン、と。涼やかに風鈴の音が聞こえる。
「…ぐれ、時雨!」
ガタン、と体が揺れた。同時に、窓ガラスに思い切り頭をぶつける。
「いった…!」
「だ、大丈夫?…っていうか駅、もう着くから降りなきゃ」
ぶつけた頭の痛みで、だいぶ意識がハッキリした。僕は詠の向かいの席に戻ってきている。
詠が手配してくれた列車はとんでもなく高速で、詠曰く四時間程度乗っていれば目的の駅に着くらしい。始めの内、僕と詠はポツポツ会話をしていたのだが。真剣な話をしようとすれば、詠はそれを上手に躱すのだ。車内で言い争うわけにもいかないので、僕も自然と言葉を引っ込める。曲でも作ろうか…と思ったけれど、生憎僕は手ぶらだ。何も持っていない。他人が居る車内で歌うわけにもいかない。
徒歩での旅が、もう恋しい。
『あと五分でなんたら駅』とアナウンスする声を聞き流しながら、窓の外を見る。
詠が住んでいたという都会。街中が眩しい。光が多すぎて、最早綺麗かどうかも分からないほどに。様々な文字の羅列、窓からは見上げられない程高い建物。第九街区の塔だってこんなに高くはない。
僕の知っている現世はこんな場所ではなかったけれど。心の片隅に、一抹の懐かしさがあって。
「…もう、ずっと前のことなのに」
到着後、二人で列車を降りた。他にもぞろぞろと乗客が列をなして降り、一瞬人波に呑まれて詠を見失いそうになったが。何とか必死で食らいつく。
「…ところで詠、まだ目的地までしばらくかかるんだよね?…もうかなり夜遅いけど、どうするつもり?」
「ふふ…とっておきの秘策があるから大丈夫…」
歩きながら、珍しく詠が意味ありげに笑う。ワクワクしているのか、詠の足取りは軽やかで少し速い。
そうしてまた詠の後について歩く。川を逆流しているような気分だった。次から次へと目の前に人間が現れる。僕は真正面を見て、人を避けるのに必死だった。
迷宮のような建物をひたすら詠について歩くこと、十数分。僕と詠は、再び駅のホームに戻ってきていて、目の前には見たこともない立派な列車が止まっている。
「わあ…寝台列車乗ってみたかったの…嬉しい…」
詠は、藍珠の塔で初めて本棚の壁を見た時のような、キラキラした目で列車を見つめた。確かにかっこいい車体だが、僕は何がそんなに楽しみなのかが分からない。
「…えーと、これに乗るの?」
「そう!今日は平日で、オフシーズンだから偶然ツインが余ってたの!」
「…これに乗るとこの紙の場所に行けるの?」
「うん!あ、って言っても直接ではないけど…この列車に乗ると、朝目的地の最寄りの駅に着いてね。そこから船で一時間くらい行くと、この場所みたい」
「まだそんなにあるのか…」
うんざりした顔をすれば、詠はまた楽しげに目を細める。
「ふふ…なんかやっぱり、向こうに居た時と立場が逆転したみたいだね。なんにも知らない時雨と、何でも知ってる私」
「詠が楽しそうで何よりだよ…」
恨めしく詠をじとっと睨みながら、僕は先に列車に乗り込んだ。
列車の中は思ったより広くて、快適そうだった。二階建てになっていて、詠がとってくれた二人部屋は二階だった。二台のベッドが横に並んだ個室。詠が大きな車窓側のベッドを選んだので、僕は壁側のベッドに座る。
列車はしばらくすると動き出した。不規則に体が揺られる感覚。窓の外には相変わらず、ギラギラした夜景が広がっている。
「…明るいな」
「外?いつもこうだよ。…はあ…藍珠さんの居た第四街区の星空が恋しい…」
「…僕もだ」
「あ、電気消してみようよ。そしたらもう少し綺麗に見えるかも」
パチッと詠がスイッチを押す。部屋の灯りが消えた。
「…まあ、さっきよりは…でもやっぱり明るいな」
結局、外の光が眩しすぎてとてもじゃないが星なんて見えない。キラッと反射した街灯の光に目を細める。詠の姿が、逆光で黒いシルエットになる。
「…少しは私の気持ち、分かってくれた?」
暗がりから、詠の声がした。薄明りの中、眉尻を下げた困り顔の詠と目が合う。
「…いいところじゃないでしょ、ここ。」
「…まあ、そうだね」
「いいところっていうか…私には生きづらい場所なんだ。騒がしくて、眩しくて、せわしなくて、理不尽」
詠が窓の外に目を遣る。沢山の光がまだ、ビルの窓に灯っている。
「私を大切に思ってくれてる人も、まだいる。でもその人は、きっと私より早くあの世界にいってしまう。…他に私を繋ぎとめてくれる人はいないし。」
「…これから出来るかもしれないよ」
「無理だよ。時雨以上に一緒にいたいと思える人なんて、きっといない。時雨の作る音楽より、聴きたい音楽なんてない」
「そんなことは…」
「あるの」
ピシャリ、と放たれた鋭い声。グッと握りしめた詠の拳が見える。説得する言葉は、思い浮かばなかった。重苦しい沈黙が続く。
「…時雨は、いつ向こうに戻るの?」
「…知らない。ヴァルの頼みごとを完遂してから、かな。でも長くいるわけにはいかない。この体は僕の物じゃない。きっといれてあと一日、二日」
詠は押し黙る。なんとなく僕は、詠が呑み込んだ言葉がわかる気がした。詠はそのまま何も言わずに布団をかぶって。窓の方を向いたまま振り返らなかった。
ガタン…ガタン…
揺れる車内に、時折刺すような光が入ってくる。列車はかなり進んで、ギラギラしたビルの灯りはだいぶ減った。眠れない僕は、どうすれば詠をここに留まらせることが出来るのか、そればかり考えている。
今の詠には、僕や僕の音楽、あの世界で旅をした思い出。それしか見えていない。でも僕にはその気持ちが痛いくらい分かった。だから否定も出来ない。大切にしたい誰かがきっとこれからできるよ、とか。長く生きればいいことあるよ、とか。そんなの無責任な僕の願望だ。実際にこれからの人生を生きるのは詠で、消えようとしている僕に、一緒には居られない僕に、言えることではない。
結局は、その人の命だ。他者が正論を振りかざした所で、「じゃあ貴方がどうにかしてくれるの?」と問われれば答えられない。
命の責任は、他人には取れない。
『時雨、世界はね…』
また、あの台詞だ。心臓が貫かれたみたいに痛んで、ベッドの上で身を縮める。
聞き覚えのある声。詠じゃない、ヴァルでもノワールでもない。ルナ、藍珠…僕は記憶の限り知っている声を辿る。物凄く身近な、何度も聴いている声。
心臓の音が煩い。たまらず目を閉じる。暗闇に呑まれたその瞬間、気づいた。
この声は、セツナの。
(…?)
パッと目を開くと、目の前には紫色の小さな家があった。
僕はその家に凄く見覚えがある。風鈴のついたアンティーク調のドア、レースのカーテンが覗く小窓、三角屋根。
中に入ろうとした。体が動かなかった。視点も変わらない。
すると、内側からガチャッとドアが開いて。
『…もう…別にいいじゃない?明日でも…時間はたっぷりあるんだからさあ』
『駄目だよ。そう言って一週間放置するのがセツナだろう』
中から出てきた人影を見て、僕は息を呑む。後から出てきたのは、昔の僕。「昔」とは言っても、今と風貌も服装も全く変わらないが。
僕の目をくぎ付けにしたのは、先に出てきた女性だった。長い銀髪を一つに結わえた、グレーの双眸と、紫ベースのジャケット。
(…セツナ)
セツナは、「うんざり」を隠そうともしない表情で歩き出す。それを追い越してズンズン歩いていく僕。
そうか、これは記憶だ。確かに僕は、セツナとこの道を歩いた記憶がある。あの長い銀髪が揺れる、後ろ姿を見ながら。
『昨日だって夜遅くまで色々手を加えたんだし…』
『でも結局完成しなかったじゃないか。明後日のお祭りで聴かせてって言われたんだろう?もう時間がないよ』
『どうせパッと明日くらいにいいメロディーが思いつくって!』
『いいや、今日の内に構想は固めておくべきだ』
はああ…と女性…セツナが盛大に溜息を吐く。
『まったく…いいかい?吟遊詩人ってのは、気の赴くままに旅をしながら、音楽を紡ぐのが仕事なんだ。そんな“いついつまでに作らなきゃ”って根詰めたっていい音楽は絶対にできやしないよ』
『…でも頼まれて、引き受けたんだよね?』
ウッとセツナが言葉に詰まる。目を逸らした彼女に、今度は過去の僕が大きくため息を吐いた。
『セツナは狂ったように毎日曲を作ってる時と、一切作れない時があるよね』
『音楽家なんてみんなそんなもんじゃないのかい?時雨だって…』
言いかけた言葉が尻すぼみに消えた。察した過去の僕は、苦笑する。
『…別に、過去の話に触れられたって嫌じゃないよ。ま、僕はちゃんと毎日ピアノ弾いてたけどね。サボり魔のセツナと違って』
『…だー!もうわかったよ!行けばいいんでしょ、行けば!』
開き直ったセツナが、大股でズンズン歩き出す。おいていかれた過去の僕が慌てて走り出す。
懐かしい。遥か昔で朧げだった記憶が、見える。今、鮮明に。
セツナは吟遊詩人だった。
僕があの世界に降り立って、最初に話した人。
僕が降り立ったのは第八街区。水の都と呼ばれるその街には、カラフルな石造りの家々と運河がある。大きな運河は様々な方向に枝分かれしていて、基本街の人は皆小舟で移動するのだ。
詠と違って僕は、ちゃんと自分の最期を記憶したままあの世界に辿り着いた。「ここが天国か…」と、のんびり街の暮らしを楽しんで。
現世で音楽に苦しめられた僕は、暫くの間音楽に触れなかったけれど。結局、また音楽が恋しくなって。街外れの塔にピアノが置いてある…と噂を聞きつけた僕は、そこに向かった。それは、セツナが管理している第八街区の塔だった。
『凄いね!緻密に考えられた精巧な音楽だ…君は音楽家なのかい?』
ピアノを弾いていたら、唐突に声をかけられ。そのあまりにフレンドリーな態度に面食らったものの、僕は『ピアノ弾きだった』と答える。するとセツナは一瞬おかしな顔をして首を傾げた。
『…何?』
『いや、君ほどの演奏が出来るなら“ピアニストだった”が正しいんじゃない?』
『…ピアニストは、名乗れないよ』
最後の方、僕は誠実に向き合っていなかった。音楽にも、ピアノにも。そう答えれば目を丸くした後、豪快に笑いだすセツナ。
『面白いことを言ったつもりはないんだけど…』
『あっはっは!ああ…ごめんごめん。向き合えなかったって、自分でそう言ってる時点で君は音楽に対して誠実だよ。それに…』
セツナがバッと取り出したのは、見たことのない木製の小さな笛。
『音楽は自由だ。誠実な音楽だけが正しいわけじゃない。君の好きなように弾いたらいいさ!』
そうしてセツナは、聴いたことのないメロディーを奏で始める。クラシックとは違う、僕の知っている音楽ともまた違う。温かくて、優しい、個性的な旋律。グッと心を掴んで離さない、魅力的な。
『…それ、なんていう曲?』
『ん?名はない。今適当に吹いた』
『即興演奏…?なるほど…じゃあ、貴方は作曲家なの?』
驚いて問い返す僕を横目に、セツナはニッと口の端を持ち上げる。
『いいや、私はトルバドゥール…吟遊詩人だよ』
吟遊詩人。各地を旅しながら音楽を作り、歌って歩く人。
『トルバドゥールってのは最古の言い方なんだ。派生してその後ミンストレル、とかトルヴェールとか違う言い方もあるらしいんだけどね。この世界には私しかいないから、私が先人!一番乗りだ!』
セツナは大きくなりすぎた子供…を体現したような人だった。真っすぐで純粋で自由。僕は幾度となく振り回され、うんざりする時もあったが。彼女の作る音楽は何故か懐かしくて、優しくて。ずっと聴いていたいと思わせる何かがあった。
彼女は吟遊詩人を名乗りながら、僕と出逢って数週間、他の街に移動する形跡はなかった。理由を尋ねれば、「移動が面倒だから」という身も蓋もない回答が返ってきて。
『この街の家が一番気に入ってんだよね。入口の風鈴、可愛いでしょ?』
と悪戯っぽく笑うセツナに、僕は溜息を返す。
『じゃあ、暫くこの街にいるの?』
『ま、そうなるかな!時雨は?会ってから結構経つよね?まだ呼ばれないの?』
“呼ばれないの?”とは、転生の順番が…という意味だろう。僕は首を横に振る。誰がどういう風に伝えにくるのかは知らないが、こちらに来て約一か月経っても僕にお呼びはかかっていない。
『んじゃあさ、私の曲、弾いてよ!』
『え?』
『ピアニストなんでしょ?やった!専属ピアニストが手に入って嬉しいわ!』
満面の笑みでセツナはピアノ椅子をバンバン叩く。早く座れ、とでもいうように。
『…はあ…で?何を弾けばいいの?』
『いやあ、この曲に伴奏つけたくてさ…』
そんなわけで、僕はセツナの曲を演奏するようになり、次第に曲作りにも口を出すようになり。遂には、一人で曲を作れるようになった。
案外作曲というのは面白い。今までは偉大な作曲家が作った曲を、どう表現するか…それだけだったけど。自分で作るとなれば、表現したいことは自分が詰め込まなくちゃいけない。
ずっと音楽をやってきた僕は、知識だけ豊富だった。セツナが生み出すような天性のメロディーは書けないが。人のことを想いながら、題材を決めて言葉を紡いで、メロディーをつけて、伴奏をつける。その過程すべてが楽しかった。
いつの間にか、僕は作曲の虜になった。
『ねえ、時雨』
『ん?何?』
セツナと出逢って、半年が過ぎた。僕たちはまだ、相変わらず第八街区の風鈴の鳴る家に居て。毎日第八街区の塔にいっては、曲を作って過ごしていた。
『まだ呼ばれないのか~?随分と長くない?』
『…来ないものは来ないんだ。気長に待つしかないだろう?』
答えながら、若干の後ろめたさが胸をよぎる。
実はもう二回ほど、呼び出しが届いていた。しかも二度目の時は、ノワールという黒いドレスの女性が、直々に足を運んでその旨を伝えてくれたのだが。僕はもう少し此処に居たい、とその呼び出しを断っている。
『ふーん。ま、長い人もいるか!あのさ、実はもうそろそろこの街に飽きたから別の街に行こうと思ってるんだよ』
『…え?』
譜面を書いていた僕の手が止まる。上げた視線が、セツナのグレーの眼差しとぶつかる。僕は次にお別れを切り出されるのだと察して咄嗟に、それは嫌だと思った。
だけど、セツナが口にしたのは予想外の言葉で。
『だからさ、一緒に行かない?』
そうして僕は、セツナと旅して廻る吟遊詩人になった。
半年かけて、第六、七、四街区を巡り沢山の曲を書いた。セツナは本当に自由人で、困らされることも多かったが。同時に世界の全てを知り尽くしていて、僕に沢山の知識をくれた。
途中、ヴァルという旅商人に会った。商人を名乗っておきながら売り物は何一つ持っていないその男を、僕は少なからず警戒したが。セツナとは旧知の仲らしく、他愛無い話を少し交わしてまた去っていった。去り際にちらりと僕を見た彼の、意味深な笑いが気になったけれど。
『ねえセツナ』
『あー?なにさ?昨日の曲ならまだできてないよ!』
『違うよ。聞きたいことがある』
『え?なに?』
お菓子を食べながら譜面と向き合っていたセツナと目が合う。僕らは第四街区の森の中にテントを立てて、数週間滞在していた。
『セツナは…人間じゃないのか?』
『は?何言ってんの、人間だよ』
『だけどそれなら…時系列がおかしい。街の人たちの口ぶりじゃ、まるで…ずっとこの世界にいるみたいに』
僕の言葉を聞いたセツナの、顔つきが変わった。
各街を旅して、セツナは前に何度もそれぞれの街を訪れていること、やけにこの世界に詳しいこと、そして呼び出される様子が全くないことが気になって。尋ねるタイミングを見計らっていたのだ。
『…ま、隠してもしょうがないね。そうだよ。あたしはこの世界の管理者の一人だからさ。お呼び出しはないし、ずっとここにいるんだ』
『…やっぱりそうか』
『だーかーら!アンタがずっと呼び出されてんのに、先延ばしにしてることも実は知ってるんだなあ~』
そこに話が繋がるのは想定外で。目を逸らした僕に、セツナがすり寄ってくる。
『ノワールが何度も呼びに来てるでしょ?あたしはノワールとも仲間なんだよ?ぜーんぶ筒抜けさ』
『…ならそう言ってよ。隠してた僕が馬鹿みたいじゃないか』
『ええ?言いづらいし。それに…まあ、あたしも初めて連れが出来て嬉しかったからさ!もうちょっとくらい良いかな…って、あんたの嘘を見ないフリしてた』
揺れるランプの光で、セツナの横顔にユラユラと影が重なる。少し寂しげな横顔。だけど、僕が口を開きかけた次の瞬間。凄い勢いでセツナに肩を組まれる。
『うわっ…!?』
『けど!駄目だよ。もう一年近く経つでしょ?次、ノワールが呼びに来たら…行きな。これ以上ここに居たら、互いに未練がましくなっちゃうよ』
振り返ったセツナの顔には、曇りのない笑顔が浮かんでいた。しゃかんだままの僕は、その笑顔を何とも言えない顔で見つめる。
『…なに?その反抗期の子供みたいな顔は』
『反抗期の子供はいつだってセツナの方でしょ。僕は面倒見る側だよ』
『はあ!?あたしを何歳だと思ってんの~?』
そこからはいつもの軽口大会になり、いつも通り僕がセツナを言い負かして、不貞腐れたままセツナはそっぽ向いて眠りについた。僕は苦笑しながらその様子を眺め、ランプの灯りを消して目を閉じて。
その数時間後の出来事だ。
やけに騒がしい声がして、僕は目を覚ました。まだ眠ってから数時間しか経っていないので、真夜中の三時くらいだろうか。
隣で眠りこけているセツナを横目に、一旦外に出た。誰かの怒鳴り声が響いている。僕は声のする方向に走り出した。
走り出してすぐに、気づく。何かが焦げたような匂い。視界の先に白く立ち上る煙と、微かに揺らめく赤色。嫌な予感がした。
全速力で走り抜けること、数分。足を止めたその先には…燃え盛る一つの家があって。火は暴れ馬のように揺らめいて、とてもじゃないが近寄れそうにない。
『…っ、中に人は!?』
すぐ傍にしゃがみ込んでいた男に尋ねる。男は酷く狼狽した様子で、家を指さして『ここに住んでるやつの姿が…見えない…』と零した。
炎に包まれた家を見つめる。僕の脳裏にはいつかセツナと交わした会話が蘇る。
『この世界にも“死ぬ”って概念はあるのか?』
『あるよ。…死者の世界なのに、可笑しいって思うでしょ?』
確か第七街区を歩いていた時だ。セツナは少し寂しそうな横顔をしてた。
『寿命や病気で死ぬことはない。でも不慮の事故や誰かの、或いは自分の意志で命を奪うことはできちゃうんだ』
『…この世界で死んだ場合は、どこに行くのさ?』
セツナがその時に見せた表情を、今でも覚えている。冷たくて真っ黒な、色のない眸をしていた。
『人生録ごと消滅する。すなわち…転生も出来ない。完全な、死だよ』
『…っ、あっ!ちょっと、あんた何して…!』
背後から声がする。躊躇わなかった。足が勝手に動く。燃え盛る火の勢いが、一番弱い側面の大きな窓を思い切り体当たりして割った。中にそのまま押し入ると、部屋の隅で膝を抱えて、気を失っている女性を見つけて。
煙が目に入って痛い。咳が止まらない。それでも、なんとか女性の所までたどり着いた。幸い彼女は小柄で、僕でも運び出せそうだ。
無理やり彼女を背中に担いで、立ち上がる。今僕が通ってきた道はまだ、火が弱い。このまま出られる。
どうにか力を振り絞ってよろけながら窓を越えた…その時。
ドサッと、何かが落ちる音。振り向いて、気づいた。懐にしまっていた本が…僕の人生録が、部屋の中に落ちていて。あっという間に本は、目の前で炎の波に包まれる。表面から少しずつ、焼け焦げていく。
段々視界が暗くなっていくのを感じながら、僕はそれでも背中に乗せた彼女を死なせまいと必死に足を動かし続けて。
『…っ、時雨!』
聞き覚えのある声で呼ばれたのを最後に、僕の視界は黒く染まった。
眠りの中で、どこか懐かしい歌が、声が…聴こえる。
再び目を覚ました時。僕はテントの前に倒れていて。
『…やあ』
『…どうして君がここに…っ、彼女は?』
僕を見下ろしていたのは、旅商人のヴァル。最後に見た時と同じ、意味深な笑みを浮かべたまま近づいてくる彼に、僕は警戒心ギラギラの視線を向ける。
『あの女性は無事だったよ。よかったねえ、でも君に一つ残念なお知らせがある』
『…残念?』
おうむ返しに問う。何のことか予想はついていた。表面が黒く焦げていた、自分の人生録が脳裏にちらつく。だけど、返ってきたのは予想もしない答えで。
『君は今日から、この世界に未来永劫居続けなくちゃいけなくなった』
『…何を言ってるんだ?大体僕の人生録は…』
『燃えてしまったから、もう転生できないと思った?…まあ本当はそうなるはずだったんだけどね』
そこでヴァルの口から語られたのは、僕が気を失ったあとの顛末。
死にかけた僕を救うために、セツナが自分の器を…即ち、この世界にずっと存在し続ける力を、譲り渡してくれたという事実だった。
倒れた僕を見つけたセツナは、ある方法でその力を僕に譲ったためにこの世界から消滅してしまったのだと。その場に居合わせたヴァルに取引を持ち掛け、僕への伝言と置き土産を預けて。
全て聞き終えた僕は、呆然とそこに座り込んだまま動けなかった。セツナがもうこの世界に居ないという事実が、信じられなかった。
『…え、じゃあセツナは…』
『もう戻らないよ。…ああ、これはその預かりもの。ちゃんと渡したからね』
ヴァルが懐から何かを取り出す。サク、サク、と一歩ずつ。草根を踏んで近づいてきたヴァルが、紙束を差し出した。
『じゃ、オレはこれで。まあ…もし君もオレと取引したくなったら、おいで』
その言葉も聞き流してしまう程度には、酷く動揺していて。
いつの間にかヴァルは森の奥に消え、僕一人が取り残される。
そっと開いた、その紙束は一曲の楽譜。一番上に見覚えのある筆跡で。
『君にこの楽譜を託すよ。いつか必要な時が来たら、使うといい』
その一文だけが書かれていた。
ポタッと、そこに落ちる一滴の雫。
『…馬鹿じゃないの…』
その日から僕は、ミンストレル…吟遊詩人になった。
セツナが託してくれた命で。旅をして回って、誰かの物語を音楽にして。
ずっとセツナの面影を、思いを、背負いながら。
今度は僕が、誰かを救う音楽を作れるように。
8 哀色あいろにい
自然と瞼が開いた。
不規則な揺れと、背中に固い感触。視界には、まだ明けていない夜の、藍色。電線と電柱が時折、視界の中に流れていく。
…そうか。寝台特急に乗ったんだ。
ほんの少し、空の果ての方が白み始めた明け方。こんな時間に起きたのは久しぶりで。私はしばらくぼんやり寝転がっていた。
隣から微かな寝息が聴こえる。首だけそちらを向けば、目を閉じた時雨の横顔が見えた。まだ、時雨はここに居る。その事実に少しホッとした。
起き上がるのは億劫で、でも眠るには勿体なくて。段々と薄まっていく藍色を、明けてゆく空を。ただ、眺めて過ごした。
「…ここが、この紙に書いてある場所?」
「うーんと…正確にはもう少し船で移動があるけど。もうすぐだよ」
列車を降りた後、一旦作戦を練るため駅前広場のベンチに腰掛ける。私と時雨は、ヴァルという人が渡した紙とスマホの地図を見比べた。
まだ朝七時半の広場には、全然人が居なかった。一応この辺りでは中心部の大きな駅のはずなのだが。平日の、出勤ラッシュのこの時間にこんなに人が居ないのか…と少なからず驚く私。
「…なんかここは、少し息がしやすいね」
「…そうだね」
「…ねえ、時雨」
「うん?」
「…お腹すいたからさ、ごはん食べない?船の出航時間まで、まだあと一時間くらいあるみたいだし…」
遠慮がちに提案してみる。昨日の夜は随分早めの時間に食べてしまったのだ。朝、車窓から明けの空を眺めている時には既に、空腹で何度もお腹が鳴っていた。
時雨は目を丸くした後、クスっと笑う。
「いいよ。何が食べたい?」
広場の近くにオシャレなパン屋さんがあったので、そこで朝食を取ることにした。昨日に引き続き今日も、雲一つない快晴で。少し肌寒かったけれど、外のテラス席に好きなパンを買って、持って行って食べた。
私も時雨も、昨晩寝る前に話したことには触れなかった。向こうで旅した時のように、何も知らなかった頃のように、笑って話した。
食後の珈琲を楽しむ間、時雨は少し神妙な面持ちでルナとライラちゃんの過去について、私に教えてくれた。魂を入れ替えたことで、その記憶や現在を眠りの中で見たのだという。
「…そっか。じゃあ今ルナは、ライラちゃんと一緒に過ごしてるんだね」
「うん。…嬉しそうだったよ、ルナ」
「よかった…“待ってなきゃいけない人”ってライラちゃんのことだったんだ」
私は一瞬しか本物のライラちゃんと会話していない。でもあの時確か、ライラちゃんはリボンのネックレスを「命よりも大事だ」と言っていた。リボン、と言われて思い出すのはルナの顔で。
「あれももしかしたら、ルナから貰ったプレゼントだったのかな…」
しみじみ呟けば、通りの向こうに見える海に視線を遣りながら時雨も小さく笑う。
私はライラちゃんのことを想った。たった一人の親友と理不尽に引き剝がされて。悔しかっただろうな。無力な自分に腹が立っただろうな。
それでも、腐らず前を向いて生き続けて。
「…ライラちゃんは、強いよね。ルナに会えなくなった後も、ちゃんと生きて」
その言葉をどう受け取ったかは分からない。私は揺れる珈琲の表面に映る、自分の歪んだ顔だけを見ていた。
「…彼女はそれを“強さ”とは捉えてなかったよ。自己満足で、薄情で…ルナの分まで夢を叶えるって決めた自分を、綺麗ごとだって否定したりして」
時雨は淡々と語る。温かくも冷たくもない、平坦な声音。第五街区で真実を語ってくれたノワールの話し方に、少し似ている。
「死は理不尽にやってくるけど、人間は全員いつか死ぬ。それだけは平等だ。死が身近に現れた時、『前を向いて精一杯生きる!』も、『一生思い出して悲しんで悼む…』も。間違ってないと僕は思うよ」
「…じゃあ、私の選択は?」
遠くからどこかの学校のチャイムが、秋風に乗って運ばれてくる。
「死を選ぼうとした私の選択は…間違ってる?」
チャイムが消えて、静寂。鳥の鳴き声、車の走行音、微かな風の音。
「…それは僕には決められない。詠の命で、詠の人生だから。だけど…」
落ち着いた、深い海の底みたいな声音で、時雨が言う。
「結果詠は、死ななかった。それには意味があると思う」
心の奥底で、何か一つ。鍵の開く音がした。
九時に出航した船は、とても豪華な二階建てで。一階には車やバスを乗せる車庫があり、二階に人が乗る仕様だった。
船の内部には窓側にボックス席、真ん中に横並びのベンチ席が固まっていて、まだ朝早いせいか人の姿はまばらだった。私と時雨は最初、窓側のボックス席に座ったのだけれど。デッキにでて海風を感じたくなった私は、時雨を誘って外に出る。
「ねえ、ところで着いた後どうやってこの…霜月さん?を探すの?」
「…ヴァルのことだから、ここに辿り着けば自然と会えるものだと思ってるんだけどな…」
苦い顔で、時雨が手元の紙片を見る。随分、ヴァルという旅商人を信用しているんだね、と言えば更に時雨の表情が曇った。
「信用はしてないさ。ただ、あいつは無意味な取引はしない。あと取引は必ず遂行するのがヴァルだから。そこは心配してない」
「そ、そうなんだ…」
ヴァルの話になった時だけ、時雨はあからさまに嫌な顔をする。誰に対しても人当たりの良い時雨にしては、珍しい。何か過去に因縁でもあるのだろうか。
しばらく無言で海を眺める。遠くに小さな島が見えた。緑しかない…無人島だろうか。生まれてこの方無人島なんて見たことがない私は、思わず目を凝らす。
「…そういえば詠、音符のネックレスは?ライラに拾ってもらったんじゃ…」
「あ。あれは…チェーンが切れちゃってたから、もう付けられないの。」
鞄から壊れたネックレスを取り出して時雨に手渡す。本当だ…と呟きながら切れたチェーンを持つ時雨。
「…それ、小さい頃おばあちゃんがくれた物だった。向こうの世界に居る時は思い出せなかったんだけど…。十歳の時、大好きだったアニメがあってね。それに出てくる凄く好きなキャラクターが、音符のネックレスをしてて…」
確か、戦闘物のアニメだったと思う。キャラクターたちが変身して、毎回街で起こる様々な敵を倒し、事件を解決していく…そんな定番の。
「アニメも好きだったけど、作品の中でその子が歌う曲が凄く好きで。毎日おばあちゃんの前で一人ステージしてたんだ。そしたら、十一歳の誕生日におばあちゃんがこれを買ってくれたの」
「へえ…その曲、今でも覚えてる?」
「勿論!えーと…あれ?出てこないな…」
死ぬほど歌って死ぬほど聴いた曲なのに、ど忘れしてしまった。うんうん唸りながら思い出そうとする私を見て、時雨が笑う。
「思い出したら、歌って聴かせて。」
そう言って、壊れたネックレスを私のカバンにそっと滑り込ませた。
辿り着いた最果ての島は、自然豊かで人が少なくこじんまりとした場所だった。
降りてすぐ、船のチケット売り場の優しそうなおばあさんに歓迎され。この住所へはどう行ったらいいか…と尋ねると、親切にバス乗り場まで案内してくれた。
バスを十分ほど待って、乗り込む。都会で使っていた電子カードは使えず、小銭で二人分支払った。バスには私たちの他に、老人が一人乗っているだけだった。
目的のバス停は、島中心の丘の上にあった。三十分で到着して降りる。
「…え、ここで合ってるよね?」
スマホの位置情報と住所を見比べる。あと徒歩一、二分の差しかない。
「とりあえず…行ってみようか。」
困惑した表情で、時雨が先に上に続く道へ進む。
また時雨の後について歩く。ふと振り返れば、かなりの高台にいるようで。碧い海、隣に浮かぶ島、昼間の月。緑いっぱいの島の中に、ポツポツと立ち並ぶ家。
「…第三街区とちょっと似てるよね」
「え、私は第四街区に似てるなって思ったよ?森の中に家が隠れてる感じが…」
「第四街区はそもそもこんな明るくないじゃないか」
いつの間にか隣に並んで、海を眺める時雨と。そんな軽口をたたく。
「…綺麗な場所だな」
「…うん、そうだね」
初めて来た場所なのに、ほんの少し懐かしさがあって。故郷に雰囲気が似ているからだろうか。それとも、時雨が隣にいるから?
じんわりと胸に温かい何かが広がるのを感じながら、再び私たちは丘を登った。
「…え?たまにしかここに来ない?」
「この…霜月さんって人ですか?」
私と時雨が同時に問い返す。顔を見合わせた。二人から問い詰められたカフェの店員さんが、困り顔で視線を落とす。
「はい…彼女、普段は島を出て本土の介護施設で仕事をしていまして…休みの時はうちのカフェを手伝ってもらってるんですけど…」
「そ、そうなんですか…」
指定されたのは、島が所有している庭園のような場所で。一番近くのカフェに聞きこみに行った私たちはそこでその事実を知らされた。
「ヴァルのやつ…どういうつもりだ…」
「…単純に知らなかったのかもよ?たまにしか来ないこと」
聞き込みだけで帰るのも申し訳ないので、少し早めの昼食を…と席に座り注文する。店員さんが去った後、時雨が大きな溜息を吐いた。
「とりあえず職場の名前は聞けた。また船で戻ってそこへ向かうしかないな」
「でも仕事中は無理だと思うよ。夜まで待たなきゃ」
介護の仕事の人は、昼勤や夜勤など働く時間が様々なイメージがある。今日はそもそも出勤日じゃないかもしれない。
「はあ…全くヴァルは何がしたいんだ…」
悩む時雨の横で、私は内心喜んでいた。その人に会えてしまったら、時雨との旅が終わってしまう。ヴァルという人が何を思ってこの場所を指定したか分からないけど、私にとっては好都合で。さり気なく提案する。
「…折角だから、この島を観光して帰らない?どうせ時間余ったんだし」
「…まあ、仕方ないよね。他にやることもないし。いいよ、詠は何がしたい?」
渋々受け入れてくれた時雨にニコッと笑顔を返して、私は最初に貰った島の観光地図を広げた。
そんなわけで。カフェで美味しいハムサンドをご馳走になり、昼の一時を過ぎて。まずその庭園周辺を散策する。
この島はオリーブが名産品らしく、至る場所に沢山オリーブ製品が売っていた。買うつもりは無かったのに、いざ名産品を目の前にすると購買意欲が高まる。結局大きいものは買えないので、オリーブの葉を閉じ込めた栞を一枚買った。
「詠、第三街区に居た時も栞欲しがってたよね。ステンドグラスのデザインの」
「あー!あれは本当に欲しかったなあ…心残りの一つ…」
思い出して残念がる私を、時雨は優しい目で見つめていた。
続いて、もう少し丘を登った所にある風車に向かう。
そこは魔法映画のロケ地になった場所らしい。自由に乗って撮影できる、魔法使いの箒が用意されていた。私と時雨も箒に跨ってみたはものの、それ以上どうしようもなくて一分で返却した。
その丘は心地の良い風が吹いていて、誰もいなかった。草むらに寝転んで、日向ぼっこしようと提案する。
「日向ぼっこには寒くないか…?」
「いいの。空を眺める時間も必要でしょ」
そうして二人、暫く仰向けのまま空を眺めて過ごした。変わった形の雲を見つけて、時雨に何に見えるか問う。時雨の感性は独特で、毎回私が予想もしないような答えが返ってきて面白かった。
次第に睡魔が襲ってきて、少しだけ眠った。森のざわめき、緑の匂い。まるで第一街区の森に居る時みたいな心地よさで、私は幸せな夢を見た。
小一時間ほど経って、時雨に起こされた私は時計を見る。時刻は三時半を指していた。知らない土地を観光していると、時間の経過が驚くほど速い。
十一月の今はこの時間でも少し日が傾き始めていた。もうそろそろ丘を下って、船に戻ろうと時雨に言われ。茜色に染まり始めた空と風車に後ろ髪を引かれながら、時雨の後に続く。
丘を下る道すがら、様々な家が立ち並んでいて。学校から帰ってくる制服姿の少年。畑をたがやす老夫婦。ご近所さんと立ち話をしている主婦さんたち。どの人も皆、明らかに観光客らしき私たちに笑顔で会釈してくれた。
不思議な気持ちだった。知らない街には知らない街の「いつも」があった。私が知らなかっただけで、この世界にもまだ色んな場所があるのだ。
私が、誰も知らない場所。誰も、私を知らない場所。この世界にもそれは沢山あって。逃げればよかったのかもしれない。誰の言葉も批判も届かない場所へ。
「…あっ!」
ドン!と時雨の背中にぶつかる。「ごめん」と謝りつつ、突然立ち止まった時雨の視線の先を追った。
「…あ…」
来る時に降りたバス停の、反対向き路線の乗り場。そこは、白いアーチで囲まれた石造りの広場のような場所で。古代ローマを思わせるような白い彫刻、石畳に刻まれた文様…その中央に。
ピアノが、あった。茶色いアンティーク調のピアノだ。
その場所は、第五街区のノワールの神殿にも似ていたし、第三街区のルナと時雨が演奏していた広場にも似ていた。茶色いピアノは、藍珠さんの塔にあったものと似ている。
瞼の裏に、時雨のピアノに合わせて幸せそうに歌っていたルナの姿が蘇る。藍珠さんと三人で、色々話し合いながら作曲した夜のことも。
茶色いピアノの前で、二人が手招きしているような気がする。
「…時雨、」
静かに名前を呼ぶ。隣で時雨が小さく笑った。
「…いいよ。」
コツ、コツと靴音を立てて。時雨がピアノに近寄る。閉じ切っていたピアノの蓋を全開にして、一つ鍵盤をポーンと押した。ピアノはきちんと誰かに手入れされているらしく、ちゃんと正しい音が出た。
スッと、時雨が椅子に座る。ふわっと、鍵盤に手を置く。
私は、ピアノの窪みに立って。時雨を振り返り、頷いて。
時雨の手が奏でたその曲は勿論、「あまりある残像」。
『~♪朝露、木漏れ日を浴びて…惑う胸の内まで澄み渡るような空気を…』
歌い紡ぐ言葉の一つ一つに、あの世界での思い出が蘇る。
第一街区の森の美しさ、雪降る森で時雨と出逢ったこと、ルナの音楽が大好きだと語った輝く眸、藍珠さんの甘くて幸せなクッキーの味、寧々ちゃんの寂しそうな横顔、ノワールがくれた言葉の数々。
全部全部、この歌の中に。
『~♪それを幸せだと思いながら、旅した…知らない街を君と歩いたこの日々を…』
ピアノの音色が優しい。時雨のピアノは心地よく、私を支えてくれる。音楽の波に乗せて、そっと運んでくれる。
楽しい、美しい、幸せ。その感情だけが、零れる。
『~♪世界が歌う、私にはあまりある日々を~』
最後の一節が、終わって。歌声はピアノに乗って遠く、夕陽の沈む海へ、茜色の空へ、溶けていく。
時雨の手が、最後の一音を、弾き終えた。
パチパチパチ…
背後から聴こえた力強い拍手の音。驚いて振り返れば、中学生くらいの女の子一人と、庭仕事をしているらしき年配の老人が手を叩いていた。
「いやあ…まさかこの歳になってこんな演奏を間近で聴けるとは…」
先に声をかけてくれたのは、老人の方で。
「わたしゃ毎日ここの庭を手入れしててね。ピアノも管理を任されて、毎日雨除けのカバーを掛けたり、調律に立ち会ったりしているんだが…長いこと誰にも弾かれていない可哀そうなピアノでねえ。私ももうこれが弾かれる所なんて見られないと思っていたんだが…ありがとう、お嬢さんたち。いい歌だった…」
ニコニコ顔でお爺さんが去っていく。その後ろ姿を見送った後、今度は中学生の子がおずおずと近寄ってきた。
「…この島小さくて、何もなくて、つまらない日々が一生続くんだって、そう思ってたんです」
その子は、暗く淀んだ目をしていて。一瞬その眸に私は、かつての自分の面影を見た。けれど、パッと上げたその子の顔に、うっすら笑顔が浮かぶ。
「でも今日…聴けて良かった。今の曲、凄く好きでした。…ありがとうございます、私に違う日常をくれて。…救われた、気持ちです」
不器用に紡がれた言葉だけを置いて、その子はペコリと会釈して去っていく。その背中を見つめながら、どうしてか涙が出そうになって。私は俯いた。背中にそっと、時雨の手が触れたのを感じながら。
声も出さず静かに、手で顔を覆って。私は泣いた。
元来た道を辿り、バスに乗って船着き場まで戻ってきた。その頃にはもう西の空が真っ赤に燃えていて、時刻は四時半を指していた。次の船が出るのが五時だというので、チケットを先に買って待合室で待つ。
最初に声をかけてくれたチケット売り場のおばあさんと談笑しつつ、丁度船が着いてじゃあそろそろ乗ろうか…と立ち上がった時。
「あの…すみません…!」
後ろから焦った声がして、振り向く。見ると、エプロンを付けた女性が駆け寄ってきていた。丘の上のカフェの、店員さんだ。
「あ…あの、何か?」
「霜月さんに会う用事があるみたいだったから…これ渡してくれますか?」
女性がパッと開いた手の中にあったのは…星のピン止めだった。それを見た瞬間、時雨の顔に衝撃が走る。
「え、これは彼女の物ですか?」
「はい…いつも大事に付けてて…先週来てくれた時に更衣室に落ちてたの。探してたら困るから早めに返してあげたいなって…」
私はそのピン止めに見覚えがある気がした。時雨が真剣な表情でそれ受け取る。
「じゃあ、お願いします…!」
お辞儀をして、立ち去ろうとする女性を。時雨が「あの…!」と呼び止める。
「…霜月さんの顔が分かる物って持っていませんか?…大切な物を預かるのに、別人だったら困るので…」
「ああ!それもそうですよね…写真があります…!えーと…この子です!」
女性はスマホを取り出して、一枚の写真をこちらに見せる。
そこに映っていたのは、緑の髪をポニーテールにした赤い眸の女の子。二十代前半くらいだろうか。写真の中の彼女は、控えめに笑ってピースをしていた。大人っぽい黒のブラウスに、お洒落なブレスレットをして。
その顔が誰かに似てるな…と感じた瞬間。私は思い出した。
この星のピン。寧々ちゃんがしていたものと同じだ。そしてこの子の顔立ちは、寧々ちゃんにそっくりで。
気づいてしまった事実に動揺を隠せないまま。何も言わない時雨のシャツを、そっと握った。
◆◆◆【Side 璃々】
眼前に広がる、侘しい夜景を眺めながら。柵に両肘を乗せて、下を見る。
職場の屋上にはいつも人が居なかった。古いビルなので、危ないから閉鎖されているらしい。確かに柵は全体的に錆びていて、床も所々ひび割れている。
「…今日は星、見えないなあ…」
呟いて缶コーヒーを一口。昔は苦くて堪らなかったブラックコーヒーも、今では中毒のように一日何本も飲んでいる。
星が見える日は、寧々のことを思い出せる気がして好きだった。
私の大切で、大好きな、双子の妹。
寧々と私は、田舎町の小さなアパートで育った。
昔は父と母含め、家族四人で仲が良かったけど。大きくなるにつれて、父は仕事ばかりで家におらず、次第に母も何処かへ出かけることが多くなった。
私と寧々は、いつも二人きりだった。
でも寂しくはなくて。自分の分身みたいな妹が、ずっと一緒に居てくれる。それだけで十分だった。幸せだった。毎日二人で「戦いごっこ」や「家族ごっこ」をして遊んだ。寧々は私より大人しくて、危ないことをしようとする私をいつもオロオロしながら止めてくれた。
小学生になると、双子は同じクラスになれない…の法則で寧々とは別のクラスになった。私は持ち前の明るい性格で友達が沢山できたけど、寧々は内気で中々友達が出来ずいつも一人だった。だから私は毎日、寧々と一緒に登校して帰りも寧々と下校するために玄関で待っていた。他の友達が遊びに誘ってくれても断った。妹と一緒に居たいから…と。
『…りり、無理して一緒にいなくてもいいんだよ?』
『はあ?違うよ!りりが一緒に居たいから、一緒に居るの!』
『…でも、りりも友達いなくなっちゃうよ?』
『いいもん。ねねがいてくれたら、あたしそれだけでいいの』
心の底からの本心だった。控えめに笑う寧々の手をギュッと握って、私たちは毎日同じ道を歩いて帰った。
中学生になると、両親は家に居ない日ばかりになった。その頃にはもう親が不仲なのも何となく察していたけど、あまり興味は無かった。寧々が居ればそれでいい。その気持ちは揺るがなくて。
だけど中学二年生の冬。十四歳の時。父と母がとうとう離婚し、私は母に、寧々は父に連れていかれることになった。
父は仕事で成功して、大手企業の重役を任されることになったらしい。そのため、本社のある都会に引っ越すと言い出して。
『寧々の方が成績優秀だ。お前と違って口答えもしない』
『そんなことで決めたの!?ならあたしも父さんについていく!連れてってよ!』
『駄目だ。二人も面倒は見られない。お前は母さんとここに住め』
後に知ったことだが、母は浮気をしていたらしい。新しい恋人と再婚をしたいと、母から別れを切り出したそうだ。母は別段私に興味はなさそうで、でも揉めるのも面倒だから私を引き取る…その程度だった。
私と寧々は何度も、二人一緒に暮らすことを望んで直談判した。だけど、中学生の私たちに選ぶ権利はない。二人だけで暮らせるほどの財力も、知識もない。聞く耳を持たない両親のもとで、私たちは諦める以外の選択肢を持たなかった。
そして訪れた引っ越しの日。私は最後までごねて、寧々の手を離さなかった。絶対に行かせない、と大粒の涙を流した私の手を、母と父が無理やり引き剥がして。
『いい加減諦めなさい!往生際が悪いわよ!』
『くそっ…空港行きのバス一本逃したじゃないか…ほら、行くぞ、寧々。』
『…っ、お姉ちゃん…』
泣きながら寧々が私を呼ぶ。その瞬間、手が離れた。父が寧々の手を引っ張って無理やりバスに乗せる。もう寧々は抵抗しなかった。
『…っ、寧々っ!』
バスは定刻通り去っていく。母はそれを見送りもせず『ほら、帰るわよ』と踵を返した。
その一時間後。空港行きの高速バスが横転し、死者や重傷者が多数いる…というニュースがテレビの速報で流れた。
それは紛れもなく、寧々たちの乗ったバスだった。
寧々は、意識不明の重体で。あれから七年経っても、未だ目を覚まさない。
医師にはもう意識回復の見込みはないと散々言われた。それでも私は絶対に諦めるものか…と必死に縋った。父は何度も『もう無理だ。諦めよう』と言ってきたが、私はそれを絶対に受け入れなかった。
父は一人軽傷で済んだ罪悪感からか、或いは仕事がうまくいってお金に余裕があったからか、寧々の治療費は払い続けてくれていた。だが半年前、父がお世話になっていた会社は経営不振で倒産。寧々の治療費はもう払えないと言い出して。
私はどうにかして寧々を生き延びさせたかった。だって、私のせいだ。あの時私がごねて寧々たちの乗るバスを一本遅らせなかったら…寧々は今も元気だった。
私のせいだ、私の。だから私が寧々の命を、守らなくちゃいけない。
専門学校を卒業した私は、自分が出来る範囲で一番給料の高い会社に就職した。介護の仕事だ。夜勤続きのシフトでも構わなかった。シフトが休みの日は、島のカフェでバイトをした。
一方で自分は五帖の狭いボロアパートに住んで、スーパーの半額のお惣菜を買って生活した。母とは疾うに別居している。再婚相手と幸せに暮らしているんだろう。
何を犠牲にしたっていい。何を捨てたっていい。幸せな暮らしも、友達と遊ぶ時間も要らない。寧々さえ戻って来てくれるなら。
一時期ふと魔が差して、恋人を作ったことがあった。その人は多分、私のことなんて好きじゃなかったと思う。ただ都合の良いタイミングで現れて、程よく優しくしてくれて、拠り所になってくれそうだったから付き合った…その程度の。
彼は私の事情を知っても離れていかなかった。私の体を心配してくれた。大事だって言ってくれた。私が自分の犯した罪を後悔していることも、ちゃんと聞いて「璃々のせいじゃない」って言ってくれた。
でも結局は空しいだけ。他の誰が許しても、私は許さない。命より大事な妹の、未来を奪った自分を。百人が「貴方のせいじゃない」と言っても。
私が私を、絶対に許さない。
今年は八年ぶりに、ふたご座流星群が月明かりの影響なく綺麗に見える年だ。
それを知ったのは、週末に行ったカフェバイトで。店員の有馬さんに教えてもらった。見られるのは、あと一か月後の十二月十四日の夜。
「…また見られたら。お願いごとしたいな」
八年前。二人で一緒にアパートのベランダから見た時は。二人で一つ、一緒の願いごとをした。
「…でもあれ、よく考えたら叶わなかったな」
ヒュウウッと冷たい風が吹いた。寒い。薄着で出るんじゃなかった。建物内に戻ろうかな…と踵を返そうとして。
ふと、考えがよぎる。
ここから飛び降りたら、また寧々に会えたりしないだろうか。
もうとっくに天国にいった寧々の体を、私が引き留めているだけなんじゃないか。
寧々はもうずっと天国で、私が来るのを待っていてくれたりしないだろうか。
もう一度柵に近づいて、下を覗いた。ゴクリ、と喉が鳴る。
怖かった。高い所は苦手だ。でも、今ならどうだ。ちょっと柵を乗り越えるだけだ。幸いここの柵は低い。この時間なら、通行人もいない。ひょいっと越えて、パッと手を離せば…。
「…きょ、今日は寒いですね…」
ハッと息を呑む。傾いていた体勢を戻して、ゆっくり後ろを振りむく。
赤い服の女の子と白いシャツの…青年かまたはボーイッシュな女性か。
この時間に、こんな何もない古びた屋上に現れた奇妙な二人組は、やけに神妙な顔つきでそこに立っていた。
◆◆◆【Side 詠】
「…きょ、今日は寒いですね…」
その命を今にも放り出そうとしている人が目の前に居たとして。なんて声をかければいいのか。ついこの間自分も同じ立場であったはずなのに、出てきたのはしょうもない気候の話くらいで。無意味な世間話をし始めた私を、時雨が驚いたように見つめている。
一方、初めて見る寧々ちゃんの姉…璃々ちゃんは、一瞬面食らった表情を浮かべたもののすぐに作り物みたいな笑顔になって。
「…そうですね」
返された言葉からは、何も意図が読めない。
ここへ来る道中で、時雨は知る限りの寧々ちゃんと璃々ちゃんの話をしてくれた。仲のいい双子で、でも事故に遭って寧々ちゃんだけがあの世界に来てしまって。それから姉の璃々ちゃんは責任を感じてずっと引きずっていたこと。苦しみながら、寧々ちゃんの命を諦めずに戦ってきたこと。全部知ってしまった。
本当は話をしに来たつもりだったのに。地上から、ビルの屋上に佇む璃々ちゃんの姿を確認した時、察してしまった。
大切な人の死を引きずって、それでも生き続けてきた璃々ちゃんが。もう諦めてしまいたいと、思っていること。七年も必死に待って、それでも現状が変わらなかったのだ。絶望して当然だと思った。
「…星が見たいなって思っただけなので。大丈夫です。ありがとうございます」
璃々ちゃんがペコッと会釈する。必要以上に介入するな…という無言の圧を感じた。早く出て行って欲しい、独りにしてほしい。そんな本心が見える。
駄目だと思った。今一人にしたら、きっと璃々ちゃんは。
そっと、刺激しないように。ゆっくり璃々ちゃんに近づく。不審そうな目で私をにらみながら、璃々ちゃんが数歩後ずさった。私は右手に持ったそれを…星のピンを、差し出す。
「これ…忘れ物みたいで…」
「あっ…!」
璃々ちゃんの目が、大きく見開かれる。
「これ、どこで…」
「島のカフェの店員さんが、更衣室で拾ったそうです」
微かに震える手で受け取って、ピンを大切にギュっと握り直す璃々ちゃん。
「どうして貴方がこれを…?」
「だってお揃いのピンでしょう?早く届けてあげなきゃと思って…」
「…待って」
鋭い声。私は自分の失態に気づいた。このピンがお揃いだということは、寧々ちゃんに会っていなければ知りえない情報だ。案の定璃々ちゃんの顔には、衝撃の色が走っている。
「…どうしてこれが、お揃いのピンだって知ってるの…?」
「そ、それは…」
「このお揃いのピンのことは、私と…私と寧々しか知らないの!二人でこっそり買った、秘密のピンなの…なのに…」
寧々。その名前が出た時、不覚にも一瞬反応してしまった。それを見た瞬間、璃々ちゃんの目の色が変わる。ぶわっと彼女の心の中で何かが決壊したのを感じた。
「ねえ、知ってるなら教えて…?寧々のこと、ピンのこと、どうして知ってるの?」
「…そ、それは…」
どうしよう。実際に会った時に見た、なんて口が裂けても言えない。頭がおかしいと思われて、今度こそ会話の余地がなくなってしまう。でも、返す言葉を必死に探す私の後ろからあっさり時雨がその答えを口にして。
「…寧々が付けてたから。」
「え?」
「寧々が唯一手放さなかった物だから」
「…何、言ってるの?寧々はずっと前から意識不明なの!もう目を覚まさないの!私のせいで…私が、ワガママ言ったから…」
璃々ちゃんの声が震える。辛くて苦しくて、身が引き裂かれそうな声音だった。違う、璃々ちゃんのせいじゃない。そう言ってあげたいのに。その眸があまりにも悲痛で、私は俯いてしまう。
時雨だけが、冷静にまっすぐに璃々ちゃんを見つめていて。
「違うよ。寧々は君のせいだなんてこれっぽっちも思ってない」
「分かったような口きかないで!」
大声を出した拍子に、またガン!と背中が柵にぶつかる。腰の高さまでしかない柵が、グラグラと揺れる。心臓がドクンと跳ねる。柵を璃々ちゃんの手がガシッと掴む。咄嗟に体が動く。一歩前に出て、璃々ちゃんの手を掴もうとして。
「だめっ!」
「私には!」
私と璃々ちゃんが同時に叫んだ。私の手は、璃々ちゃんに触れられないギリギリの所で止まっている。赤色の眸が揺れている。その眸の向こうに、かつての…ベランダから飛び降りた私の、面影を見た。
「…私には、寧々しかいないの…。寧々だけなの…」
璃々ちゃんはゆっくりと体を反転させる。
「いやっ…!違う、ダメなのあなたはまだ…!」
何とかして止めなきゃ。こんなのは違う。こんなのは…間違ってる。
思い切り手を伸ばした、刹那。
『~♪君の名前も、思い出さえ。忘れてしまったとしても。
この約束が またいつか 僕らの行く先を 繋ぐから』
バッと手が届いた。璃々ちゃんの細い手首を掴む。だけどそれよりも。私と璃々ちゃんの視線は時雨に注がれていた。
今、時雨が歌ったのは…懐かしい歌。私の思い出の歌。
「…そんなっ…どうして…?」
口から零れたのは、私の言葉ではなく。璃々ちゃんまでなぜか、唖然とした表情で時雨を振り返っていて。
歌い終えた時雨が、何か言おうと口を開きかけた瞬間。
ガシャンッ
「…!?危ないっ…」
時雨が手を伸ばしている。柵が壊れた音。私と璃々ちゃんの体が傾く。
ふわっと気持ちの悪い浮遊感が漂う。さっきまで目の前にいた璃々ちゃんが、少し下に居て。私は自分たちが落ちているのだと悟った。
遥か視界の上の方で、時雨が必死の形相で手を伸ばしている。
…映画やドラマでは間に合うけど。現実ではやっぱり無理なんだなあ。
そんな冷めた感想を抱きながら。私はまた、堕ちてゆく。
暗闇の中に。
美しい、夜景の中に。
9 スターライトと星の海
少し前に遡る。ボクが、詠を現世に帰した後のこと。
ボクの所に時雨がやって来た。珍しく怒っていたけど、ボクはどうして時雨が怒るのか分からなくて。だって、詠が望んだことだ。苦しいまま生きるより、詠が幸せな道を選ばせてあげる方がいいのに。
そんな旨を伝えると、時雨は悲しそうな顔で走り去ってしまった。
ボクは何か、悪いことをしたのだろうか。
ボクはただ、一緒に居てくれる誰かが欲しかっただけなのに。
それから丸一日経った頃。時雨がライラという少女と入れ替わりで現世に行ったことも一部始終見ていて。ノワールとライラがそのすぐ後にここを訪ねてきた時も、驚かなかった。
ノワールはボクに一言だけ『ターミナルを使うね』と前置きして、刹那。そのままライラを連れて、第三街区に落ちていった。ターミナルを便利な瞬間移動装置みたいに使うのは、この世界でノワールだけだと思う。
またぼんやりと他の街を監視して過ごした。いつも通り、何もイレギュラーはない。三百六十五日、五年、十年とそうやって、何もない毎日を監視して過ごしてきた。この塔から一歩も出ずに、ただ画面だけを見つめて。たまに来るノワールや時雨と少しだけ話をして。
つまらなくて寂しくて、何の希望もない馬鹿みたいな時間。もう何年前からここに居るのかも、忘れてしまう程に。大切なものも全部、忘れてしまう程に。
画面を切り替える。ライラは第三街区で、ルナという女の子と楽しげに過ごしているみたいだ。
「…どうせ、あと一日くらいしか居られないのに」
呟いてから思った。大切な誰かと過ごす一日は、独りぼっちで過ごす十年よりずっと価値があるんじゃないだろうか。
ボクがそれを、一番よく知っている。
「…君もああなりたい?」
「…いつから、そこに居たの」
背後から聴こえた声。驚きはしたけれど、ヴァルの神出鬼没にはもう慣れた。二冊の本を脇に抱えたヴァルが、そこに立っていて。
「んー?ほんの数秒前さ」
「…どうやってここに来たの」
「勿論、第七街区から真っすぐ上がってきたんだよ?」
「…なんで?」
「えー?…君に、いいことを教えてあげるため」
ニヤッと笑って、ヴァルはボクの机に緑色と薄紫、二冊の本を置く。
「…さてと、どこから話そうか…まずは君に、思い出してもらうところからかな?」
「…思い出す?」
「うん。…現世の詠って子の様子を、見てごらんよ」
ヴァルはいつも意味深に笑っている。ボクはさして深く考えもせず、画面を操作して現世の詠を探した。
「…あ、いた…」
見つけた詠は、ここでボクと別れた姿のままで。必死にどこかの建物の階段を上っているみたいだ。そのすぐ後を、見慣れない格好の時雨が追いかけていて。二人とも何を急いでいるんだろう…とそのまま見守る。
ガチャ、と詠の手が鉛色の重たそうな扉を開く。
そこは、真っ暗な夜の中で。
「…え…?」
その奥に立っている人物を認識した時。ボクの心臓がドクン、と跳ねた。
緑色の髪。強気を絵にかいたような、切れ長の赤い眸。
「…あ…」
失くしていた最後の針が、廻る。
ボクの大切な片割れ。双子の姉、璃々。
いつも明るくて天真爛漫で、強気でかっこいいお姉ちゃんだった。ボクと生まれた時間がほんの少し違うだけなのに、性格も正反対で。いつもボクの手を引っ張って、色んな場所に連れて行ってくれる璃々が大好きだった。
引っ込み思案なボクは、学校で友達が一人も出来なかったけど。璃々がずっと一緒に居てくれて、ボクも璃々が居ればそれでいいと思っていた。
一方で璃々が友達と居られるはずの時間を奪っている気がして、申し訳なくて。それを璃々に言うといつも怒られるから、口にしないことにしたけれど。
『…そういえば、今日流星群なんだって』
狭くて薄暗い部屋の中で。ボクは隣に居る璃々に言う。確か十三歳の時だ。同じテーブルで宿題をしていた璃々は、きょとんと眸を丸くして。
『流星群?何それ?』
『流れ星が沢山降ってくる日。ふたご座流星群』
『えー!ふたご座!?私たちにピッタリじゃん!見ようよ!』
興奮して立ち上る璃々は、相変わらず子供みたいで。苦笑いしながらボクは言う。
『真夜中から明け方にかけてだよ。それに、ボクたちの家のベランダからじゃ見えるか分からないし…』
『きっと見えるよ!見えなかったら、他の所に移動しよ!』
『どうせ璃々は待ってる内に寝ちゃうよ…』
半ば諦めてそう言えば、璃々は少しムッとした顔で反論して。結局、意地でも起きていると決めた璃々はちゃんと深夜二時まで眠らず待っていた。
田舎町というのもあって、意外に家からでも夜中は星が綺麗に見えて。
真冬の寒空の下、ベランダで毛布に二人くるまって、何枚も上着を着こんで。空を見上げて、待ち続けた。その日の星空は本当に綺麗で。
『世界はこんなに綺麗だったんだねえ…』
『ふふっ、寧々は時々センチメンタルなこと言うよね』
『そ、そんなことないよ…』
照れ臭くて一瞬下を向く。流れ星は中々現れてくれなくて。つまらなくなったボクは、ふと何気なく馴染みの歌を口ずさむ。
『~♪君の名前も、思い出さえ。忘れてしまったとしても…』
『寧々はいっつも鼻歌歌うときその曲だね。寧々が歌うその曲、私好きだよ…それ、昔流行ってたアニメのやつでしょ?あの変身して戦うやつ』
『そう。好きなんだぁ、この曲。そのキャラクターが変身した後に歌うとね、傷が癒えたり、心を病んじゃった人が安らかな気持ちになる効果がある歌なんだよ』
『へえ~…現実でもそんな歌があったらいいのにね』
璃々はあんまり興味なさそうに相槌を打った。このアニメを見ていたのはボクだけで、璃々はその次の枠のナントカジャ―が好きだった記憶がある。
またボクは小さな声で曲の続きを歌いながら、流れ星を待った。すると数分後、璃々が『あっ!』と声を上げて立ち上がる。
『ねえ、今通った!通ったよ、寧々!』
『しー…大きい声出しちゃだめだよ璃々…』
『あっ、ごめん…』
慌てて口を押えた璃々が、また空を仰ぐ。ボクもつられて上を見た。途端にキラッと光の尾が流れて消える。
『あっ…!…いっちゃった…』
『ねえ、先に願い事決めようよ!次出てきたら、一緒に願い事唱えよう!』
『そうだね…璃々は何お願いするの?』
ボクも考えてはみたものの、思いつく願い事はたった一つで。璃々の願い事が気になるな…と尋ねてみる。すると璃々は一瞬も迷わず、言い切った。
『勿論、寧々とずっといられますように、だよ!』
お揃いの願い事は、流れ星に届いただろうか。
それが叶わなかったと知ったのは、それからまもなくで。十四歳の冬、ボクは父と乗ったバスで事故に遭った。
そして…あの世界に、落ちたんだ。
「…どうして、ボクは…こんな大事なこと…」
現世で、璃々と詠が何か話している。それも耳に入らないくらいボクは動揺していた。今の今までボクは、誰よりも大事だった璃々のことを忘れて。
思い出しも、しないで。
「それはね、君が君の手で、君自身の記憶を消したからさ」
「…消した?ボクが?」
ヴァルが薄紫色の人生録を、机の上に置いた。パラッと捲ったその一ページ目が、黒く焼け焦げている。全部が焼けているわけじゃないが、前半の部分がごっそり抜け落ちていた。
「君は時雨に拾われて、少しの間この世界を旅した。そして…」
ヴァルの三日月のように細い目が、ボクを射貫く。
ボクが落ちた場所は、第九街区の雨の街で。訳も分からずぼーっとしていたら、暫くして時雨が助けに来てくれた。
事故の記憶は曖昧で、でも自分が死にかけたという事実は覚えていて。摩訶不思議な場所に一人放り出されて戸惑っていたボクを、時雨が暫く一緒に連れて行ってくれた。詠の時と同じように。
ボクたちは第七街区、第八街区、第五街区…と順に回って。最終的に第四街区までたどり着いた。ボクは一目で第四街区を好きになった。だって、一年中星空だけを見られるなんて夢みたいだ。
『…璃々にも見せてあげたいなあ』
そう呟いたボクを、時雨が切なそうな目で見ていたことは覚えている。
ボクがあの世界に落ちて、十日ほど経った頃。ボクの薄紫色の人生録を確認した時雨が、何とも言えない表情で黙り込んで。
ボクは自分が、暫く現世に帰れない運命なのだと知った。
その日時雨は、少しだけ人に会いに行く…と朝早く出て行った。後から考えると、ノワールに会いに行ったんだと思う。まだ第四街区の塔に居る時で、ボクはひたすら星空を眺めて過ごしていた。何時間経ったか分からないが、コンコンと真鍮の扉をノックする音が聞こえて。時雨が帰ってきたのだと思ったボクは、扉を開けた。
『…おや、珍しい。君が例のイレギュラーなお客さんかい?』
『…だれ?』
シルクハットに、マント。手品師みたいな風貌の男が、ボクに語り掛ける。
『オレはヴァル。旅商人をしてる。…時雨は?』
『…今はいない』
『行き違いか。仕方ない、出直そうか』
『待って』
踵を返した背中を、呼び止める。ヴァルは胡散臭い笑みを消さずに、眉を上げて促すようなまなざしを向けた。
『…旅商人。時雨が言ってた、取引をする人?』
『へえ。時雨がオレの話をしたのかい?』
『うん。前に一緒に旅してた人の話の時に』
『ああ…セツナのことか』
納得して頷いたその人…ヴァルは、再び閉じた扉に背を預け腕を組む。
『で?オレに何か用かい?』
『…頼み事したら、何でも聞いてくれるって本当?』
『ああ、ただし代償は支払ってもらうよ?タダでの取引はしない主義だ』
ヴァルの目がギラリと光る。ボクは躊躇いなく、その願いを口にした。
『…ボクという存在を、消すことはできる?』
『…何故だい?』
予想外の頼みだったのか、初めてヴァルは驚いた表情を見せた。
『ボクは、暫くここにいなきゃいけない。だけどそれは、現世で誰かが眠ったままのボクの面倒を見たり、治療費を払い続けるってことでしょう』
『…まあ、そうなるね』
『それは嫌だ。璃々には、ボクのことなんか気にせず幸せになってほしい』
璃々に迷惑をかけて、お荷物になるのだけは絶対に嫌だ。きっと璃々のことだから、ボクが事故にあったことも自分のせいだって言うに違いない。
でもボクは。璃々と一緒に居られないのなら、璃々だけでも幸せになってくれた方が嬉しい。璃々がボクの為に身を削るより、百倍も。
ボクの頼みを聞いたヴァルは、真剣な面持ちのまま口を開く。
『…悪いけど、それだけはオレも出来ないんだ』
『どうして?』
『ここの決まりでね。人生録に加筆は出来ても、人間の存在を…命そのものをどうこうすることは出来ない。命は、例えどんな理由があっても本人にしか操れない』
『…だったら』
ボクは入り口のすぐ傍の壁に差し込まれた、一冊の本を手に取った。それは時雨が昨晩見ていた、ボクの人生録。ボクには読めない、薄紫色の人生録。
時雨が前に旅をしていた人との話をしていた時。人生録が燃えてしまったことで、自分の存在が危うく消える所だった…と言っていたのを思い出したのだ。人生録が燃えれば、ボクの存在も、ボクに関する記憶も全部消せるのではと思って。
バッとそれを抱えて駆け出した。目指したのは応接室、ピアノと暖炉のある部屋。後ろから足音が聞こえる。ヴァルが追っかけてきているみたいで。
バン!と応接室のドアを開けて、暖炉の前まで走ってそして。
一瞬躊躇ったけど、脳裏に璃々の笑顔が浮かんだ瞬間。ボクは自分の人生録を暖炉の火の中に投げた。
視界が真っ白になって…刹那。次に目を覚ました時、ボクは全ての記憶を失くしていた。赤色だった眸は、なぜか左右それぞれ違う色になっていた。
「オレはあの後、火の中から君の人生録を救出した。幸い燃え残った部分が多くて、君は消えずに済んだ。後からやってきた時雨とノワールに事の顛末を話した。時雨はオレに対しても怒っていたし、君に“人生録を燃やす”という方法を予期せず教えてしまったことも後悔してた。あれからずっと『あの子みたいにさせないため』って、迷い込んだ人間が居ればすぐ助けられるよう時雨とノワールは気を付けてた」
「…ボクにここの管理をさせたのは?」
「…それは、寧々がここに居る理由を作ってあげたかったから…」
いつの間にかもう一人。ヴァルの横に現れたノワールが、酷く申し訳なさそうに眉尻を下げていて。
「為すべきこともなく、やりたいこともなく…希望になるような記憶もないまま十年以上の時を過ごすなんて、あまりに酷だから。せめて何か理由をあげたかったの。」
「…そうなんだ」
じゃあボクがこの世界に十年以上いることは決まっていたのか。結局ボクのとった行動は無鉄砲なだけで、消えることも出来なくて。ボクだけが璃々を忘れて、生き続けて璃々に迷惑をかけた…その結果は同じだったんだ。
「…ボクは何のために十年もここにいたのかな…」
ポツリと呟いて。ノワールが何か言おうと口を開いた…その時。
「…あっ!」
画面の向こうで、璃々と詠が一緒に夜の中に落ちていくのが見えた。
「…璃々ッ、璃々ッ!」
「ヴァル、二人が落ちたのはどこ!?」
動けないボクの背後で、ノワールが悲鳴のような声を上げる。珍しくヴァルが真剣な表情で画面を操作して、ある一か所を映し出した画面を見つけて止まる。
「…ここだね」
ヴァルが指さしたそこは…。
◆◆◆【Side 璃々】
真っ暗闇の中で、沢山の記憶を見た。
これが走馬灯か…と半ば安らかな気持ちで、記憶を俯瞰する。どれも皆、寧々との思い出ばかりで。改めて私には、大切な物が寧々しかなかったことに気づく。
星空を見るたびに寧々を思い出して、泣いて。もう戻ってこないんだって、頭では分かっているのに我儘を言った。私だけが諦めずにずっと寧々を繋ぎとめようとして。父にも諦められて、私さえ寧々を諦めてしまいたいって思うようになって。
最後は不可抗力だったとはいえ、きっと私は落ちて死んでしまったんだろう。一緒に落ちた赤い服の女の子は大丈夫だったかな。どうかあの子だけでも、生き残ってほしい。
…それにしても、私は最低なお姉ちゃんだったなぁ。
自嘲気味に笑った所で、ゆっくりと意識が浮上する。
最初に目に入ったのは、鉛色の曇天。ポツ、と頬に何かが落ちた。雨かと思ったそれは、雪の結晶で。
静かに身を起こす。冷たい雪の上に、仰向けに倒れていたはずなのに寒くない。辺りをグルっと見渡せば、青々とした木々。季節が夏なのか冬なのか、よく分からない場所で。夜景も島も屋上も、どこにもない。
「…あの子、は…?」
一緒におちたはずの赤い服の女の子を探す。近くには見当たらなかった。やっぱりここは、私の夢の中か。はたまた私だけが死んで、ここに…天国に来てしまったのかもしれない。
「…バチが当たったのかなあ…」
寧々に執着して、そのせいで寧々をひどい目に遭わせて。なのに寧々を諦めようとして…自分勝手だった私の末路。
「…ふふっ、ここが天国なら寧々に会えたりしないかな…」
諦めの笑みを浮かべながらそう、呟いた時。
「…璃々っ!」
夢にまで見た、声がする。
振り向いた瞬間に、ガバッと胸に飛び込んできたその、懐かしい匂い。
信じられない。手がぶるぶる震える。勝手に涙が溢れ出す。
「ね、…寧々…?」
震える声で問えば、抱き着いていたその顔が上がって。涙にぬれた赤色の眸が、私を見上げていて。記憶のままの寧々がそこに居て。
「嘘…信じられない…夢…?」
「ううん、夢じゃないよ…璃々、あのね璃々のせいじゃないの。璃々は悪くないよ、ごめん。ごめんを言わなきゃいけないのは、ボクの方なのに…」
寧々の姿は、私が最後に見た時の…十四歳のままで。紫色のパーカーも、星のピンも全部。記憶の中に焼き付いている寧々の姿そのものだった。
「すぐに戻ってあげられなくてごめん。璃々を苦しめちゃってごめん」
「…そんなのっ…違う…私のせいで寧々はあんな目に…」
「違うよ、璃々。ボクがああなるのは、決まってたことだ。人生録に運命(さだめ)られてたことだったの。だから璃々は悪くない」
「…人生録?」
涙でびしょびしょのまま、問い返す。寧々は小さく頷いた。
「人の命にはね、運命られた期限があって。それは誰が何をしようと変えられないんだよ…ボクはこの十年、ずっとそれを見てきた」
寧々の眸には、昔お別れした時とは違う、別の強さがあって。何があったのかは分からない。私にはこの場所が現実に存在しているのかも、寧々にとってどんな場所なのかも分からないけれど。
真っ直ぐに私を見る寧々の目に、嘘は一つもなくて。
「でも璃々が諦めないでくれたから、ボクは生き続けられたんだよ。ボクの帰る場所を守っていてくれて、ありがとう」
「…寧々…寧々は、ど、どうなるの?私は?落ちて死んじゃったの…?」
「ううん。璃々はちゃんと生きてる…だよね?ヴァル」
いつの間にか、寧々の背後に二人の男女が立っていた。明らかに普通の人間とは違う服装とオーラを纏った二人組。シルクハットの男の方が、肩を竦めて笑う。
「うん。イレギュラーな時雨たちの介入のお陰でね」
「本当はね、璃々とボクは入れ違いになる運命だったの」
「入れ違い…?」
「そう。ボクが戻った時に璃々が死んじゃうっていう残酷な運命」
私の脳は既にキャパオーバーだった。だけど、一つだけわかる。
一つだけ、信じたいことがある。
「寧々が、戻った時?」
「うん。ボクは今日璃々と一緒に帰れる。また、二人で一緒に居られるんだよ…そうだよね?ノワール」
「…ええ、大丈夫。長い間お疲れ様、寧々。今までありがとう」
今度は黒いドレスの女性が微笑む。その目尻に涙が浮かんでいるのを見て。寧々は一瞬私の手を離すと、タタタッと女性の所に走り寄りその胸に飛び込んだ。ノワールと呼ばれたその女性が、愛おしそうに寧々を抱きしめて。そっとその手を離す。
「さて…じゃあターミナルに向かいましょう。私が二人を送り届けるわ」
「待って。…君はここに残ってよ」
「?どうして?」
女性が不思議そうに、シルクハットの男に問いかける。男は無言のまま意味深に笑って答えない。すると寧々が「大丈夫」と二人に小さく笑んだ。
「十何年も、色んな人を見送ってきたんだよ。ボク一人で出来る」
「でも…」
「大丈夫。最後の仕事だと思って、ボクにやらせてよ」
寧々の一言に、ドレスの女性はゆっくりと頷いた。
再び私の元へ戻ってきた寧々が、私の手をギュッと握る。夢なのか現実なのか、もう分からないけれど。二度とこの手は離さない。一緒に固く手を繋ぐ。
「…大丈夫、これからはずっと一緒だよ」
寧々が笑う。とめどなく零れる涙を拭いながら笑顔で頷いた。
「…じゃあ、ボクたち行くね。一つだけ…詠にごめんって伝えてほしい。それから時雨にありがとう、も。」
少し寧々の顔が曇る。すると男の方がふっと目線を上げて笑った。
「なら、そうすれば?」
「…え?」
「…っ寧々!」「寧々ちゃん!」
森の奥の方から声がして。寧々がハッと振り向く。息を切らせて走ってきたのは、私と一緒に落ちたはずの女の子と、堕ちる寸前に歌っていた青髪の人。寧々の顔がゆがむ。ぶわっと涙の膜が張る。
「しぐれ…詠…ごめん…色々、全部、ごめんなさい…っ」
さめざめと泣きだした寧々を見守る、二人の目は温かくて。
「ううん、いいの…寧々ちゃんのお陰でね、私も大事なことに気づけたし、また時雨と少しだけ旅が出来た。だから気にしないで」
「僕の方こそ…あの時、気づかなくてごめん。寂しい思いをさせてごめん」
「…二人とも、璃々を、助けてくれてありがとう」
三人がギュッと輪になって抱き合う。別れを惜しむような間が流れて。やがて、青髪の人がスッとその身を離したのを合図に、寧々が再び私の所へ戻ってくる。
「…じゃあね、詠、時雨。ノワール、ヴァル」
一歩ずつ後ずさっていく。並んだ四人が微笑んだまま、私たちが遠ざかるのを見守ってくれている。寧々が大きく手を振る。四人もそれぞれに手を振る。
やがて、雪に霞んでその姿が見えなくなった頃。ようやく寧々は振り向いて、前を見て歩き出した。繋いだままの手の温もりを感じながら、ふと最後に気になったことを寧々に問いかける。
「…ねえ、寧々」
「ん?」
「あの人たちは誰?どういう人たち…?」
寧々は少しだけ考えるような間をおいて。小さく笑んで答える。
「…ボクの…家族と、友達かな」
それから私たちは雪の森を、雨降る街を、一緒に歩き続けた。
いつも二人で手を繋いで歩いていた、帰り道のように。
美しい星空が輝くプラネタリウムのような部屋に着いて、光の粒に包まれて、その視界が真っ白に染まって。
この世界から、私たちの体が消える。その最後の瞬間まで。
⒑ 輪音‐Rinne‐
『~♪君の名前も、思い出さえ。忘れてしまったとしても。
この約束が またいつか 僕らの行く先を 繋ぐから』
小さい頃、ずっと歌っていた曲。憧れて憧れて、いつか自分もこんな風に歌で人を感動させられるようになりたい。誰かに幸せをあげられるようになりたいと願った、その原点。おばあちゃんの前で何度も歌った、思い出の曲。
その歌を、時雨の声で聴いた時。私の中で最後の扉の鍵が、開く音がした。
璃々ちゃんと共に落ちた後。夢を見た。時雨と旅した道筋を辿る夢。ルナや藍珠さんにもらった言葉を辿る夢。ノワールや寧々ちゃんと、もう一度出逢う夢を。
ルナとライラちゃんのことを想った。
理不尽な運命によって夢を叶えられなかったルナと、親友の死という苦しみを背負ったまま生き続けるライラちゃん。二人はこの約二日間、少しでも幸せな時間を過ごせただろうか。
璃々ちゃんと寧々ちゃんのことを想った。
大切な妹の未来を奪った自責の念に囚われていた璃々ちゃんと、大切な姉の為に自分の存在すら消してしまいたいと願った寧々ちゃん。引き裂かれたまま終わるはずだった二人の残酷な運命を、私たちは変えられただろうか。
藍珠さんとノワールのことを想った。
最後まで私のことを娘のように心配してくれた藍珠さん。世界の真理と大切な命のことを教えてくれたノワール。二人はこれから先もずっと、あの世界に居続けるのだろうか。
そして、時雨のことを想った。
私の為に、危険を冒してまで現世に来てくれた時雨。第二街区の森で、私を拾い上げて知らない世界を見せてくれた時雨。誰よりも音楽に誠実で、音楽の楽しさを私に思い出させてくれた時雨。
時雨はこれからもずっとあの世界で。旅を続けるのだろうか。
…それじゃあ、私は?
目を覚ますと、美しい雪景色が広がっていて。上からはらはらと落ちるぼたん雪が、頬にあたってじゅわっと溶ける。…デジャヴだった。
ゆっくり体を起こせば、そこは見覚えのある第二街区の森で。再び私は、あの世界に落ちてきたのだと悟る。
「…大丈夫?」
頭上に降り注いだ声。視線を上げればそこには、初めて出逢った時と同じように私に手を差し出す時雨の姿があった。もうライラちゃんの服装ではなく、元通りの白いマントに戻っている。
「…うん。大丈夫」
微笑んでその手を取る。時雨の手は冷たかった。ゆっくりと立ち上がり、スカートについた雪をパンパン、と払う。
少し先から誰かの話し声がした。聞き覚えのある声。私は時雨と顔を見合わせる。
「…行こうか」
穏やかにそう言って、時雨は声のした方向に歩き出す。
音の少ない、静かな懐かしい風景を、大好きな背中について、歩く。
少し開けた森の真ん中に、璃々ちゃんと寧々ちゃんの姿があった。二人とも泣きながら再会を喜んでいて、すぐ傍にノワールと、ヴァル…らしき男の人も影もあって。彼が一番最初に私たちに気づき、少し遅れて寧々ちゃんもこちらを見て。
涙を流して謝る寧々ちゃんを、抱きしめる。十何年もあの場所に一人で、転生していく人たちを見送り続けるのはどれだけ寂しかっただろう。幸せになってほしかった。苦しんできた璃々ちゃんと一緒に、もう二度と二人が離れないことを祈った。
お別れの挨拶を済ませて、四人で双子を見送る。胸の奥に、ポッと灯がともったような温かさを感じながら。二人の姿が、雪景色の奥に消えるまで。
「…さて…」
静寂が辺りを包む中、口火を切ったのは時雨で。真っすぐに私の目を見つめて、時雨は優しい笑みを浮かべている。
「…詠は、どうしたい?」
「私は…」
色んな人の顔が浮かんだ。現世で見た色んな景色がよぎった。時雨がくれた沢山の音楽が反芻した。言葉を探す。答えを、探す。
大きく息を吸う。
「…現世に戻った時。絶対にここに帰るって、時雨と永遠に旅をするんだってそう決めてた。未練を失くして、心置きなくここに来るつもりだった。だけど…おばあちゃんに会って、ほんの少し決意が揺らいだ自分に気づいて。まだ自分を想ってくれてる人がいるって、決意にヒビが入って。」
視線が下がる。時雨の足元に、はらはらと雪が積もっていく。
「見ないフリをしようとした。現世の…私が居なくなった後の世界のことは、私には関係ないって。でも…ここに来て私は、死んだ後も世界は続いてるって知った。娘を見守ってる藍珠さん、約束を守るために待ってるルナ…関係なくなんてない。全部私の人生録の続きになってる」
いつか時雨が第一街区で見せてくれた、茶色い表紙の…私の人生録を思い出す。
「そう気づいたら怖くなった。私のしようとしてること、本当に正しいのかなって」
命の責任は自分にしか取れない。感じたこと、苦しみも喜びも私だけのもので。
責任も捨てて、私だけの宝物も思い出も感情も全部捨てて。
本当に、それでいいのかって。
「…時雨が現世に来てくれて、嬉しかった。また一緒に旅を出来るのが嬉しかった。現世にもまだ、私の知らない場所があるって知った。見えてなかっただけで、知らなかっただけで。」
誰も、私を知らない場所。私も、誰も知らない場所が、まだあるんだって。そう思えるだけで、少し胸がスッとして息がしやすくなった気がしたのだ。
「一緒に現世で『あまりある残像』歌って、聴いてもらえて…救いだって言ってもらった。…涙が出る程嬉しかった。私が時雨の音楽に救われたように、私の音楽が誰かの生きる糧になれるんだって」
勝手に涙が頬を伝っていた。必死で、何を話しているのかも分からなくて。それでも今の思いの丈を精一杯伝えたくて。
「…思い出したんだ。時雨が…落ちる前に時雨が歌ってた曲ね。私が音楽を好きになったきっかけの曲なの」
「…え、そうなの?僕は寧々がよく口ずさんでて、思い出の曲だって言ってたから…咄嗟に気を引けるかと思って歌っただけなんだけど…」
「実はね、私にとっても大事な曲だったんだ。…不思議だよね、年齢も生まれも違う。生きてきた環境も違う。現世では出逢ったことも無いのに…同じだった。同じ音楽を知ってた」
驚いた顔の時雨に、涙に濡れたまま私は笑いかける。
「ノワールの言った通り、人間の生は繋がってる。失われたものは、消えるわけじゃない…だから、だからね」
真っ直ぐに、時雨の碧い眸を見て。
「私、帰る。私にしか作れない音楽で、誰かを幸せにしてみせる。あの曲が私を救ってくれたみたいに。そうやって生きて、生きて…全部終わった後、またここに来るから」
「…詠」
「たとえ時雨を忘れても。時雨が居なくても。私には音楽がある。時雨がもう一度好きにさせてくれた音楽がある…それに、命に焼き付いた記憶は、消えない。ルナの約束みたいに。きっと、私はあの曲を忘れない。だから…」
時雨の手を取る。冷たい手。私に曲を書いてくれた手。美しい音楽を生み出す手。
世界で一番の感謝を込めて、言葉を紡ぐ。
「ありがとう…また、必ず」
時雨の目が、見開かれて。ゆっくりと閉じる。その言葉を噛み締めるように。
「…うん、また必ず」
そっと手を離した。雪は相変わらず、私たちを見守るように静かに降り続く。
「…詠ちゃん、」
「ノワール…ごめんなさい。もう今度こそ、大丈夫だよ」
「ええ。…私が、詠ちゃんを送るわ」
うっすら滲んだ涙を拭いながら、ノワールが微笑む。それを「待って」と時雨が制した。不思議そうに、時雨を振り返るノワール。
「どうしたの?」
「…僕が送る。詠…一つだけ。一つだけね、僕から最後に頼みがあるんだ」
「…頼み?」
時雨が私に何かを頼むなんて初めてで。戸惑いながらも手招きする時雨に近づく。耳元で時雨が囁いて、そっと私のスカートのポケットに何かを入れて。身を離す。
意味を咀嚼できないまま、私は曖昧に時雨を見つめ返した。時雨は寂しそうな、それでいて酷く優しい笑みを浮かべて。
「…元気でね」
そう一言呟いて。すうっと息を吸った。
時雨の歌声が響く。雪降る森の中で、時雨の声だけが聴こえる。
不思議なことに、言葉の意味は分からない歌だった。
だけど心地よくて、優しくて、幸せな歌だった。
風が吹いた。雪が舞った。視界が白く染まる。
耳の奥に、最後まで。
時雨の歌だけが、残っている。
そして私は、この十日間の記憶を全て失くして。
現世へと、帰った。
「…さてと。お別れの時間だ。」
詠が帰っていった後。暫く沈黙が続いた森に、響くヴァルの声。ノワールだけが状況を呑み込めず、困惑した顔で僕とヴァルを見比べる。
「…どうやってやったの?ここに迷い込んだ人を帰せるのは、ターミナルからだけ…それも私か寧々だけだったのに…」
「時雨は彼女を帰したんじゃない。救ったんだよ」
「…意味が分からないわ」
説明を求めるように、ノワールの双眸が僕を射貫く。僕は答えられなかった。ノワールにだけは、自分から説明する勇気が無かった。
「じゃあオレが、答え合わせ役を買って出よう…鍵はセツナが時雨に譲り渡した楽譜にある」
片眉を上げて、肩を竦めて。変わらぬ飄々とした態度でヴァルが語り出す。
僕の人生録が燃えた、数百年前のあの日。
セツナは僕を助けるために、唯一残された手段を使った。
それは、あの世界で生まれたセツナが例の万年筆を使って、あの世界の言葉で書いた曲。失われかけた命を救う、特別な力がある曲。
セツナが奏でたその曲は、本来死ぬはずだった僕の命を繋ぎ止め、人生録を修復し、文字通り僕を蘇らせて見せた。但し、その効果には代償があって。
正確には救う力ではないのだ。
…命を、器を、人生録を譲り渡す力。
セツナは元々あの世界の人間だ。ノワールやヴァルと同じで、人生録を持たなければ転生もしない、現世へ行くことも出来ない。永遠にあの世界に留まるはずの存在だった。そのセツナが譲り渡した命は、僕にもあの世界に留まる力を与えた。
僕は転生もせず、現世に戻ることもせず、吟遊詩人として旅をし続ける力をもらったのだ。
セツナの存在と引き換えに。
楽譜の力を知らなかったノワールは、ヴァルが種明かしをしても呆然としていて。
「…まさか今のがその曲?でも、おかしいわ。だって詠ちゃんは死んでないのに…」
言いかけたノワールの言葉は、途中で止まった。綺麗な青い眸が、衝撃で見開かれる。動揺した彼女の視線が、僕に注がれて。
「…まさか…」
「そう。璃々が助かったのは、ヴァルが僕と詠を寄越したことで起きたイレギュラーだ。それによって璃々の運命は変えられたけど…代わりに、失われることになった命があったんだよ」
「…それが詠ちゃんだって言うの?」
「本来一緒に落ちる人はいなかったんだ。でも詠が璃々ちゃんを助けた。ノワールも分かっているはずだ。運命の天秤は残酷で、絶対に傾かない。誰か一人が生き延びる運命になれば、バランスを保つために誰か一つの命が奪われる」
絶句したノワールの唇が、言葉を失う。
「…そう。もう分かったかい?時雨はね、詠の命を救うためにさっきあの曲を歌った。時雨は自分の命を、詠に繋ぎ渡したんだ。だから…ああ。もうお別れが近いね」
冷静にまとめるヴァルの視線を感じて、僕は自分の両手をかざす。うっすらとその手が透けているのを見て、ノワールがハッと息を呑んだ。
「…本当だ。意外と早いんだね。…セツナは…僕の為に消えるその瞬間、何を思っていたんだろう」
「最後までいつも通りだったさ。消えかけてるのにオレに取引を持ち掛けてきて、君に楽譜を渡すように言ってきたり…」
「ははっ、あの人らしいねまったく」
『君が必要になったら使うといい』その言葉と共に託されたあの楽譜。詠の為に使ったことを僕は一つも後悔していない。元々、あの時失われるはずだった命だ。セツナが繋いでくれて、数百年も長く生きて。この世界を沢山旅して、沢山の音楽を作って、ノワールといろんな話をして。沢山の人に…詠に、出逢えた。
幸せな旅路だった。
「し、時雨…」
「…ふふっ、ノワールが泣くなんてレアだね。そんな顔しないでよ。『刻まれたものは、なくなるわけじゃない』そう言ったのは君だろう?」
もう消えかけの両手で、ノワールの手に触れた。微かに、まだ温かさを感じられる今のうちに。
「…寧々も詠も居なくなって、その上僕まで消える…酷いよね、本当にごめん。でも間違ったことをしたとは思ってないよ。…許してほしい」
「…許さないわ。何千年後まででも、絶対に覚えていてやるんだからっ…」
綺麗な泣き顔のまま、恨めしそうにノワールが僕を睨む。苦笑して、僕はそっとノワールの手を離した。
「うん。忘れないで…僕の音楽だけ、ずっと覚えていて」
そうすれば僕自身も、永遠になれるから。
今度はヴァルに向き直る。最後まで何を考えているか分からない彼は、うすら笑みを浮かべたままだ。
「…どこまでが君の仕込みだったの?」
「…さあね。でも君が居なくなるのは想定外だ」
「そう。じゃあ一泡吹かせられてよかったよ。…ノワールを、よろしくね」
「まったく無責任だねぇ。…まあ、またいつか会おう」
ヴァルのその言葉が聴こえた時、もう僕の体は半分くらい感覚がなくなっていた。でも苦しくはない。夢の中に落ちていく時みたいな、穏やかで優しい温かさがある。
涙がたまったノワールの碧い眸を、最後に見つめ返して。
「…ありがとう。さよなら…忘れないよ」
目に薄い膜が張って、一滴の雫が零れ落ちた時。
頭の奥で微かに、懐かしいピアノの音が聴こえた気がした。
Side.N ロストシルフィード
…お元気ですか?
私は最近、第五街区と第九街区を行ったり来たりしています。時雨と寧々がいっぺんにいなくなったせいで、私ばかり忙しくなって正直てんてこまいです。
ヴァルは全然手伝ってくれないし…
あの後。
ルナはきちんと、ライラちゃんとお別れができたみたいです。
「振り返っちゃだめだよ」とルナが言ったのを最後に。ちゃんとライラちゃんは現世に帰っていきました。ルナに「どうしたい?」と尋ねたら、「次に呼び出しが来たら…来世に行こうかな」と言われました。
ライラちゃんに言われたそうです。「いつまでも待たせていたら悪いから。先に来世に行ってていいよ。その代わりに自分は忘れないし、夢は必ず叶える。その上で、ルナを追いかけて来世でまた出会って、今度こそ約束を果たそうね」と。
…ライラちゃんは強くて、逞ましくて、真っすぐだよね。
ルナはルナで「私が一向に転生しなかったら、ライラは自分が約束で縛り付けた…って言いそうだから。ちゃんと来世でライラを待つし、約束を叶えられるように今度こそ頑張る!」と張り切っていました。
きっともうすぐ、ルナの順番が来ると思います。
藍珠は相変わらず、第四街区の塔を管理してくれています。
もう今の私には、頼りになる存在が藍珠しかいません…。
時雨や詠ちゃん、寧々の話は私から伝えました。藍珠は誰のことよりもまず、私のことを心配してくれてね。「一人じゃないからね、一人にしないから、私が居るよ」って言ってくれました。
時雨も少しは見習ってくれたらよかったのに。
璃々ちゃんと寧々は、現世ですべて忘れて幸せに生きているみたい。寧々は十四歳で記憶が止まったまま現世に戻ったので、今も凄く苦労はしているようだけど。璃々ちゃんが支えて、二人で頑張って暮らしているみたいよ。
この先もずっと、二人が一緒に居られることを願います。
…そういえば一つ、聞き忘れたけれど。
あの時。詠ちゃんに何を囁いていたの?
何かを手渡していたように見えた…。もう私には確かめようがないけれど、気になります。いつか、教えてね。
いつか…。
居なくなってから、よく時雨のことを考えるの。
あの時あなたは何を思ってこの曲を作ったんだろう、とか。
時雨が残した楽譜が沢山私の手元にあってね。一つ一つ、曲を聴くたびに思い出が溢れ出すの。玉手箱みたいに、閉じ込めていた記憶がいつでも蘇るの。
時雨に確かめたかった。
もっと話をすればよかったね。もっと沢山曲を聴かせてもらえばよかった。
それだけをずっと、思っています。
…そろそろ今日は、終わりにしようかしら。
今日の第五街区の空は、昼の月が見えてとても綺麗だから。
あなたもどこかで、見ていてくれたら嬉しいです。
それじゃあ、また。
Side.Y Paradis
よく見る夢があった。
いつも同じ景色で始まって、同じ人が出てきて、同じ音楽が流れていて、最後にその人が同じ台詞を言って…そこで目が覚める、夢。
夢のことを誰かに話したりはしない。私だけの宝物で、私だけが知っていればそれでいい…と、そう思っていた。
その夢は、最期の日にも現れた。
とても幸せな人生だったと思う。
大好きな音楽を続けて、大して名前が売れたわけではなかったけれど。仕事をしながら細々とやり続け、私の音楽を好きだと言ってくれる人たちに沢山出会えた。
人並みに年を重ねて、引っ越した先で数は少ないけれど友人も出来て。結婚はできなかったけれど、その友人家族が私と本物の家族のように接してくれた。
美味しいものを美味しいと感じながら食べて、年に一、二回自分の知らない街を旅しに行った。旅先で音楽を作ると、なぜかいつもよりもいい曲が書けたから。
たまにふと、真っ白い誰かの背中が脳裏に浮かぶ時があって。
昔旅先であった誰かだろうか…と頭を捻るけど。それらしい人は思い浮かばなくて。でも、その影を見るたびなぜか温かい気持ちになった。
そうやって、長くて短い人生を全うして。
私はきっと、今日。この世界から去る。
故郷の病院の一室で、目を覚ました。
真夜中だった。赤い月が、窓から見えて。
届くような気がして、手を伸ばす。かざした手の向こう側で、月はただ静かに輝くばかりで。
その瞬間、なぜか目尻から涙が零れた。どうして私は泣いているんだろう。
悲しい夢なんて一つも見ていないのに。
幸せな人生だったのに。
暫くベッドの上で、ぼんやり月を眺める。
…月。
『…詠。』
誰かが呼んでいる。耳元で囁かれた、その声が蘇る。
『この楽譜を君に託すから。君の人生録が終わる時に…君の言葉で、奏でて』
託された楽譜のメロディー。誰に貰ったかは覚えていないのに、ずっと大切に宝物の箱の中にしまってあった楽譜。
何度も何度も見返して、覚えてしまったその音楽は。
「…時雨、」
その名前を口にして。頭の中で、そのメロディーを、紡いだ言葉を口ずさむ。
目を閉じて。真っ白い光の中に、私は落ちていく。
雪が降っている。
目の前に落ちてきた雪の結晶を、掌に乗せた。
音もなく、結晶は崩れて水滴だけが残る。
その、手の平にそっと。
冷たい手が重なる。
碧い眸のその人が、優しく微笑みかける。
ずっと大切に持っていた楽譜を。私はその手にそっと返す。
「Paradis」
そう記された、楽譜を。
…白い雪が舞い落ちる、静かな森で。
Fine
酔シグレ2nd Full Album「吟遊詩人の人生録」を各種ストリーミング配信で視聴する↓
酔シグレ1st Full Album「吟遊詩人の置き手紙」を各種ストリーミング配信で視聴する↓
特別BOX盤及びCDを購入する↓
あとがきを読む↓
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
