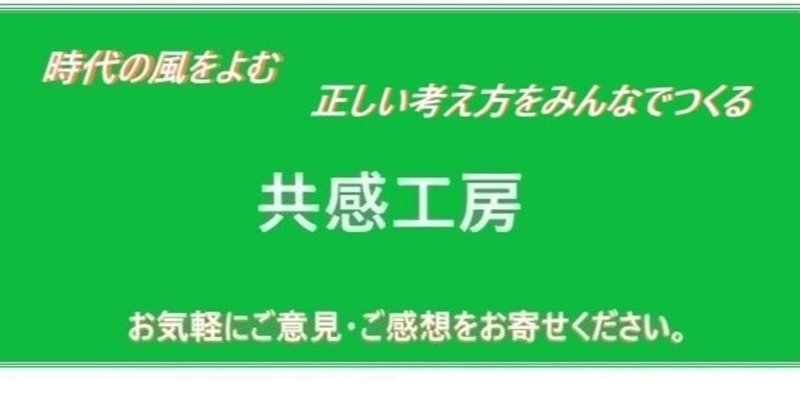
題... 春は新しい旅立ちの季節
◆ 今年は、2月4日が立春でした。
1月末で急に派遣切りになったりして気分的にバタバタしていたので、立春のことをすっかり忘れていました。
バタバタしていたというのは、何となく気分的にそう感じていただけ。現実には次の派遣先も決まっているので、焦っていたわけではありません。
逆に、ちょうど給食センターの仕事に飽きていたし、立春という新しい旅立ちの季節に別の職場で仕事ができるとは、“縁起がいい”のかも? 負け惜しみ? [ #縁起がいい ]
立春で思い出すのは、20年ほど前に亡くなった親父殿。親父殿は、“間質性肺炎”というやっかいな病気で死にました。
間質性肺炎という病気は、今は知りませんが、20年前は治療法もなく、不治の病でした。進行を遅くする類の薬はあるにはありましたが、治す薬はありませんでした。[ #不治の病 ]
親父殿の場合は、発病してから1か月ほどで死んだのですが、自宅での治療は難しいということで1週間ほどして入院しました。
◆ 立春というのは、別れや新しい旅立ちを暗示する“季語”らしい。
私の親父殿は“風流人(趣味人?)”で、特技は“小謡”や“囲碁”や“俳句”や“書道”などでした。どれも、素人としては上級者のレベル。
友人や親戚などに筆で書く年賀状には、毎年、新作の俳句が書いてあり、意外に人気もありました。ちなみに、私は、親父殿から年賀状をもらったことはありません。
その親父殿が入院している病院の集中治療室に私がひとりで付き添っていた時、“今日は何日か? 立春はまだか?”と聞いてきました。死ぬ1週間ほど前のこと。[ #立春 ]
そして、窓のカーテンを開けろと言って、“春立つ”云々と何度も口ごもっていました。[ #春立つ ]
私は何のことか理解できず、お袋殿が付き添いに戻った時、親父殿が“春立つ云々”と何度も言っていると伝えたら、俳句でも思いついたのだろうと言っていました。
俳句では、春の季語として“春立つ”ということばが多用されるのだとか。
◆ その翌々日に、親父殿は、一般病室(個室)に移されました。
実は、親父殿は、お袋殿に、“もう治療しても無駄だから、うちに帰りたい”と言っていたらしい。
お袋殿も困った挙句、自宅に帰るわけにもいかないから、不気味な機器が並んだ殺風景な集中治療室から、多少は落ち着ける個室の一般病室に移してもらったらしい。
結局、その1週間後くらいに息を引き取りました。
気管挿管型の人工呼吸器を使えばあと1週間や10日は延命できると医師から説明があったらしいのですが、親父殿の希望もあったので、お袋殿はそれは丁重に断りました。
親父殿の従弟に医者が数人いて、見舞いに来る。親父殿は間質性肺炎の治療法がないことをみんなから聞いていたので、自分の死期が近いことを悟っていたらしい。[ #悟る ]
私は親父殿の、“春立つ”云々がその後もずっと頭に残っていました。自分があの世に旅立つことを私に暗示したつもりだったのだろうと気づいたのは、数年後のこと。
風流人という人たちは、死ぬ時まで“謎かけ”をして、実に含蓄深いのです。
ここから先は
30字
¥ 100
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
