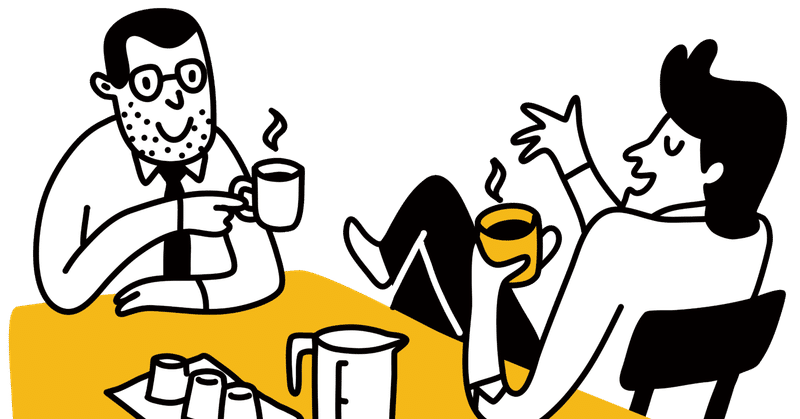
クリティカルシンキングを学んで気づいたコーチングとの共通点
2021年に受講して大きな影響を受けたクリティカルシンキング。資格を取ってから趣味的に続けているコーチングと重なる部分があるなと思ったので3つご紹介させてください。どちらかにご興味ある方に読んでいただけたら嬉しいです。
0.クリティカルシンキングとコーチングとは
まずこの2つの言葉からご紹介します。
とてもざっくり書くと、クリティカルシンキングは思考法、コーチングはコミュニケーションの手法です。

<クリティカルシンキング>
問題を見極め、答えを出し、周囲に伝えるための思考法。
新入社員のころに通信教育で受講したロジカルシンキングをがとても役立っていたが、クリティカルシンキングを学んだことで独りよがりだった自分に気づかされた。理想論が通用しない実務で、特に新しい領域に挑戦する人にとっては欠かせないスキルだと思います。
<コーチング>
対話によってクライアントが本当にありたい姿に向けて前進する背中を押すこと。
クライアントに対して真摯に寄り添いながら誰もが無意識に囚われている思考の枠を広げるきっかけを提供する技術です。
ひとりひとり行うものなので、一人当たりにかかる時間は増えてしまいます。それでも、行動変容を促すという意味では、暴力的な手段を除いて最も効果的なコミュニケーション手法だと、僕は思っています。
1.「問い」にこだわる
<クリティカルシンキング>
クリティカルシンキングと比較される思考法としてロジカルシンキングがあります。
論理的に考える、根拠をもとに判断する、という部分は共通しています。一番の違いは、「問い」自体に積極的に疑問をもつことです。なぜなら「問い」がその先の思考の範囲や方向性を規定する力を持っているから。「問い」が重要なことは当たり前のように思えます。でも、小学校の頃から与えられた問いに真面目に答え続けてきた大人にとっては、意識し続けることが難しいのです。
<コーチング>
コーチングでは、クライアントと1対1の対話をしますが、通常の話し合いとは違います。
コーチとクライアントの話す量の理想的な割合は7:3で、基本的にはクライアントに話してもらうために問いを投げかける役割をもっています。そしてその質問によって、思考の枠を広げてもらいます。

2.構造化のピラミッドを下から積み上げない
クリティカルシンキングでもコーチングでも、頭の整理整頓をします。その方法が構造化です。設定した問いに関する要素を洗い出して、それぞれの関係を整理します。一般的には下の図のようにピラミッド型で整理します。
<クリティカルシンキング>
ロジカルシンキングでは根拠を積み上げていく方法をとりますが、クリティカルシンキングその順番が違います。
クリティカルシンキングを受講する以前、僕は問い(課題)があったら取り敢えずデータを集めてそこから浮かび上がるものを探していました。つまり、とりあえずググっていました。そうすると時間がかかりすぎてしまったり、必要な論点を漏らしてしまうかもしれません。クリティカルシンキングの受講後には、課題に対してどのような論点で考えるべきか、手元にデータがなくても大体の全体像を捉えることを学びました。

<コーチング>
コーチングでは構造化はコーチの役割です。コーチングでは、構造化をコーチに完全に委ねたり、共同で行います。そうすることで、その瞬間瞬間の思考に集中でき、深く考えるきっかけになります。自分と違った切り口で整理をしてもらうことで新たな発見にもなります。
といっても、コーチが構造化のピラミッドを建設しやすくるために質問を投げかけるわけではありません。相手が話したいと思っている順番で話をしてもらいます。
3.相手の立場に立つ
僕はコーチングにもクリティカルシンキングにも、少し怖いイメージを持っていました。でも実は、どちらも相手の立場にたって伝える技術なんです。
<クリティカルシンキング>
クリティカルシンキングは漢字で書くと「批判的思考」ですから。もし「批判的人間」がいるとしたら、元気なときにしか会えないです。ちなみに、僕はクリティカルシンキングを受講することでカミソリのような人間になれると勘違いしていました。。だけど本当のクリティカルシンキングは想像と違って優しいものでした。
クリティカルシンキングの批判は攻撃ではありません。批判とは(主に自分の)思考の検証のことで、問い/論点/仮説/根拠 のすべてに「本当に?」「だから何?」と問いかけてチェックします。
そして、そこで組み立てたものを相手の立場に立って組み直すのです。
実はやさしい! クリティカルシンキングの言葉シリーズ
・×抽象 → ○具体
・×難しい言葉 → ○やさしい言葉
・×絶対の正解 → ○妥当性
・×論破 → ○理解

<コーチング>
「質問攻め」という言葉があるように、質問には攻撃力があります。
「なんで?」という質問は非難にもなるし、「これできる?」といえば命令にもなります。
質問される立場からするとちょっと怖いです。だから、自分が相手の立場になることが重要なんです。相手の味方になりたいと思っていないと尋問になってしまいます。
コーチというと目標を掲げて高いところで待っているイメージを持たれる方もいるかもしれません。そうではなくて、相手の横に立って、同じ目標をみているイメージなんです。
相手の立場に立っていますよということは「傾聴」と「承認」によって表現します。
・傾くくらい相手の話を聴く「傾聴」
・相手の存在自体を認めるメッセージとしての「承認」
言葉にして面と向かって相手に伝えるのですが、はじめは小っ恥ずかしいです。特に日本男児は訓練しないと難しいと実感してます。

人の悩みや置かれている状況は千差万別ですが、前項のように構造で捉えるとパターンが見えます。
人生経験が豊富な方ほど「あーこれはあのパターンか」と問題の真因から解決策まですぐに浮かんでしまうものです。そしてそれが当たってしまうことも多いと思います。しかし、クライアントにとっては複雑かつ重大な問題なので、その複雑性と重大性は事実として受け入れたいものです。
よくある話だ、って言われたくないよ
そのためのテクニック、それはオウム返しです。(!?)
僕はこれ苦手でした。ただ相手の言葉をそのまま返すよりも、何か気の利いたことを言ったほうがいいと感じてしまうのです。でも実は、気の利いたことを言いたいのは自分自身の欲だし、言い換えている時点で解釈が入ってしまいます。だから、センシティブな内容のときこそ、相手の言葉を復唱することで、その意味をそのまま受け取ることができるオオム返しがオススメです。
ここまで読んでいただいて、極端にスロー&マイルドな印象になってしまったかもしれません。「ていねいな暮らし」が出来ない方でも大丈夫です。むしろ、人とともに働き成果をだすために、結局は相手の立場に立つことが、一番の近道なのだと思います。
クリティカルシンキングとコーチング、僕はうまく意識ができず後からヘコむこともあります。しかし、活用できる場面ばかりで、奥が深いスキルなのでこれからも楽しんで実践していきます。今回はアドベントカレンダー企画に参加させていただきありがとうございました。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
