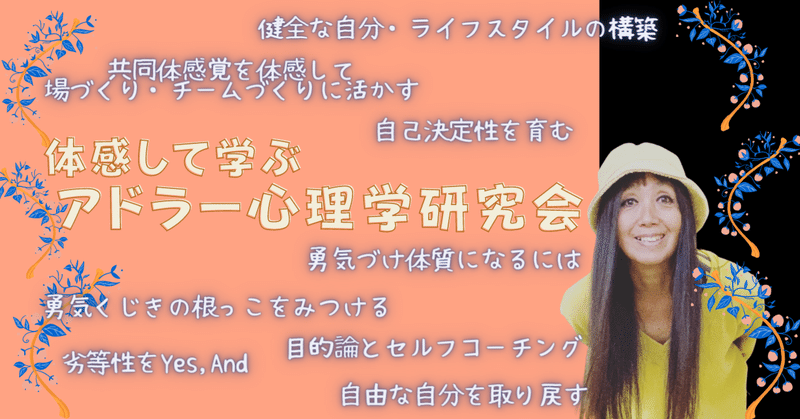
なぜ、体感が大事なのか・・【2】
みなさんは、「Knowledge Model(知識習得のモデル)」という言葉をきいたことがありますか?
学びの場をデザインするにあたっては、学習者が学びを習得するプロセス「Knowledge Model」を理解し、学びの場づくりを行っていくことです。
全体像を次のような図で示すことができます。
Knowledge Modelとは

●KK (I know that I know)
自ら理解していることを認知している状態
●KDK (I know that I didn’t know)
理解していなかったことを認知した状態
●DKK (I didn’t know that I’ve known)
理解していることを認知できていなかった状態
●DKDK (I didn’t know that I didn’t know)
理解していないことを認知できていない状態
KKに到達するために
上図のように、KKに到達するには二つの道があります。(実際は、二つ以上・・ DKDKからDKK(実践)を通して、KDK(知識注入)し、KKへ。 また、DKDKからKDK(知識注入)したうえで、DKK(実践)を踏まえて、KKへ。など)
その上で、体感をすることの重要性は、DKK(実践)することによって、学習者本人ができる・できないを実感し、そこで支援者(ファシリテーターやコーチ)が、本人ができるようになる(または、より上達を目指す)ための寄り添いを行うことで本人の行動の強化につなげることができます。
図のように、学習者自身の『AHA体験(実感)』があると、学習意欲がより向上し、主体的な行動に結びつくのです。
KKへの導くためのポイント
では、KKへ導くためには。
まず、ファシリテーターは、学習者がどのステージにいるかを観察することです。
ここで、重要なのは、ファシリテーター自身の在って欲しい姿を反映するのではなく、あくまでも学習者自身がどのような状態にありたいかを観察から洞察し、また対話をすることです。
そして、学習者のステージあわせてteaching(インストラクション、指示)とcoachingまたはfacilitationを効果的に使い分けることです。
つまり、teachingからfacilitationに変えましょう!ということではなく、学習者をよく観察して、必要に応じて、より有効な手段を瞬時(アジャイル)に選択し、臨機応変で柔軟に学びの場を創り上げていくことです。
社会のひとりひとりが自分らしくを楽しめる文化にしたいと一言でまとめきれないくらいのいろんな活動をしてます。 感謝と愛に溢れた社会づくり・人づくりにすこしでも貢献できたら、と、学びを楽しみに変える教育の改革活動をしています。 サポートいただけたら勇気になります!ありがとうございます
