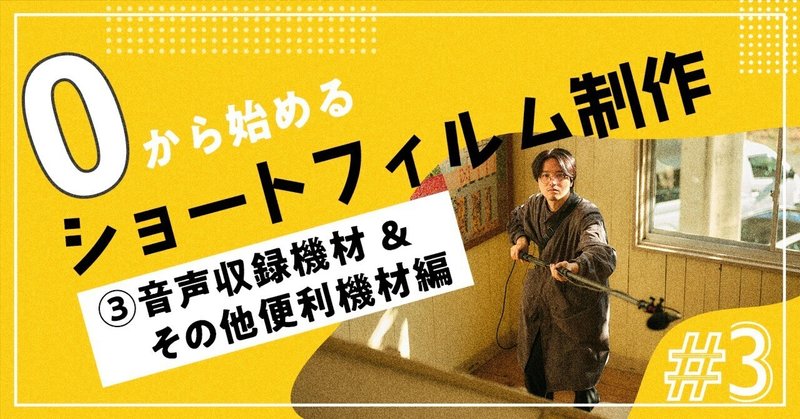
0から始めるショートフィルム制作③ YFLおすすめの音声収録機材 & その他便利機材編
こんにちは。ショートフィルム制作チーム「Yellow Film Labo」(以下YFL)発起人の稲垣です。今回は「0から始めるショートフィルム制作」シリーズの3本目、YFLの使っている音声収録機材と、その他便利機材についてご紹介したいと思います。
↓前回記事「おすすめの照明機材」
↓前前回記事「おすすめの映像撮影機材」
↓YFLとは…?という方向けの記事
映像撮影を始めたばかりだと、なんとなく優先順位が下がりがちな「音」。しかし、YFLで作品制作した後に出てくる反省点として、毎回必ず「音」に関する問題があります。

「毎回...??君たち学習せんのか~い!」と思われるかもしれません。たしかに。私もいまそう思いました。
そこでなぜそんなに毎回音に悩まされるのか少し考えてみたのですが、編集を経験しないと音の重要さが分かりづらいという事があるかもしれません。編集してみると、音一つでガラッと映像の雰囲気が変わることや、音によってシーンの繋がりが作られていることに気がつきます。ここに気がつかないと、現場でとりあえず音が録れてればいいかと思いがちになってしまうのかもしれません。YFLでも自作品の編集を経験した人から順番に「音が大事だ.........」と音の重要さに目覚めています。
また、ストーリーテリングの面でも音が人間の感情に与える影響はとても大きいです。ハラハラドキドキ、涙ポロポロ、ウキウキワクワク、映画の名シーンには必ず音が効果的に使われています。
スターウォーズを思い返してみてください。あの有名で壮大なテーマ曲で冒険へのワクワク感が醸成され、独特なライトセーバーやブラスター・ライフルの効果音で私たちを臨場感ある映画の中の世界に誘います。もし、あの音楽や効果音がチープなものだったら...もしかしたら名作とは呼ばれていなかったかもしれません。
もう一つ例をあげると、濱口 竜介監督の「ドライブ・マイ・カー」では、途中全くの無音になるシーンがありました。
通常映画は静かなシーンでも環境音などが流れており無音にはなりません。それが全くの無音になることで、逆に一気に映像の中に、登場人物の心の中に引き込まれるような感覚があり、とても新鮮で、心地良い映像体験でした。
音をどのように映画に使うかは、自由で、クリエイティブな作業です。初めのうちはなかなか上手くいかないと思いますが(私たちも苦戦しています)、だからこそ、経験を積むためにも最初から音にこだわって撮っていくことをお勧めします。
それではここからは、いつもの通り、私たちが実際に使っている機材と、そのおすすめ理由や扱い方をご紹介していきます。
YFL保有の音声収録機材
【メインマイク】ゼンハイザー ガンマイク MKE600
【マイク用防風】Micolive Blimp マイクウインドシールド
【マイクブーム】マイクブームポール
【レコーダー】ZOOM F3
【ピンマイク】TASCAM DR-10L Pro
【オンカメラガンマイク】SONY ECM-B10
【タイムコード生成】Timecode Systems Ultra Sync Blue
音声収録機材の選び方 & 扱い方
メインマイクとして使うガンマイク
YFLでは私が所有しているMKE 600をメインのマイクとして使っています。ガンマイクというのは指向性が高いマイクのことで、マイクが向いている方向に絞って音を拾うことができます。そのため、環境音などのノイズは小さく、演者の声などは大きく録音することが可能になります。
このマイクで録った音は編集の際にもメインで使う為、できるだけ高性能なマイクであることが求められます。私たちが使っているマイクであるMKE 600はガンマイクの上位製品というわけではありませんが、10万円以内で買えるマイクとしてはトップクラスの性能で、安心して使うことができます。
とはいえ、マイクは他の機材に比べて技術の進化による陳腐化がそこまでないため、奮発して良いマイクを買ってしまうのもありです。
同じゼンハイザーの MKH416は業界標準と言われるガンマイクで、これを持っておけば間違いはないと思います。
そしてガンマイクを使う際には、私たちは必ずマイクウインドシールドに入れるようにしています。特に外ロケで使う際にはこの効果は非常に高く、これなしでは良い音を録ることは困難です。
私たちはこちらのMicolive Blimpを使っています。良く使われているRode Blimpとほぼ同じ作りで価格が安いモデルというものですが、不満を感じたことがないためかなりお勧めです。

但し、少しサイズは大きいため普段持ち歩くにはちょっと大変かもしれません。外ロケが無く、完全に室内だけみたいな形であれば、デッドキャットと呼ばれるふわふわの風防シールドも軽量でそれなりに効果もあるためお勧めです。
このセットをマイクブームポールにつけて、カメラの画角外から音を狙っていきます。音はできるだけ近くで、音の出る方向にマイクを向けるということが大切です。以下のテレビ朝日映像撮影部さんの動画が見て分かりやすいと思いますので、参考にしていただければと思います。
マイクブームポールの持ち方はこちらの動画が分かりやすいです。
また、より詳しく録音の全体像を知りたいという方は以下の記事が現場目線で書かれている良記事だと思います。
レコーダーは32bitフロートが絶対おすすめ!
ガンマイクを繋げるレコーダー。これは今なら絶対に32bit float録音をおすすめします。こちらに関する詳細な解説は以下のTASCAMさんの記事を読んで頂ければと思いますが、簡単に言うと、音割れがなくなります。
従来のレコーダーですと録音レベルの設定に注意しなければいけなかったのですが、この32bit floatだと録音ボタンを押すだけでほとんどミスが起きません。
(音割れが本当に起きないのか不安な方もいるかと思います。以下の記事の方がとても丁寧に検証されています。)
このミスが起きないという事が、現場において本当に助かります。録音担当の習熟度が低くても扱えますので、特に入門者の方は必ずこちらの32bit float対応のものを選ばれるのが良いと思います。
32bit floatのレコーダーはZOOMやTASCOMなどからいくつか発売されています。私のおすすめは、持ち運びがしやすく、2ch使える(マイクが2つまで使えます。ステレオ録音も可能になります。)ZOOMのF3です。
このレコーダー自体はタイムコード生成(タイムコードについては後述します)ができないのですが、別売りのBTA-1をつけることでタイムコード受信機能が使えるようになります。
外部のタイムコードジェネレーターからタイムコードを受信することで、録音データにタイムコードのメタデータを付与することができます。これが編集時に非常に便利ですので、このタイムコード機能があるかないかという事もレコーダーを選定する際に重視するポイントです。
理想を言えば、レコーダー自体にタイムコード生成機能がついており、それを無線で送信等できればよいのですが、現状そのようなレコーダーや対応カメラ等は無いかと思います。
レコーダーにタイムコード生成機能がついているものはZOOM F6などがありますが、カメラのタイムコードと同期させるには有線になるため、私たちの運用には合わないかなと思い、後述するTimecode Systems Ultra Sync Blueをベースにしたミニマムな運用にしています。
ピンマイクのセッティング
ピンマイクで使っているのはこちらも32bit floatのDR-10L Proです。
ピンマイクを演者さんにつけた際に地味に大変なのが、録音開始・停止のスイッチを押すことです。こちらのピンマイクの場合、bloutoothで複数台を同時に遠隔操作できるため非常に便利…と思って買ったのですが、有効距離が思いのほか短く実はあまりうまく使えていません…
ただし、こちらもタイムコードを外部から受信することが可能(別売りのAK-BT1 Bluetooth アダプターは必要)です。そのため実際の運用方法としては、タイムコードを走らせて、あとはずっと録音を回しっぱなしという形を取っています。正直かなり邪道だと思いますが、録音開始・停止の漏れもなく、データ量・電池の持ちも1日程度なら回しっぱなしで足り、タイムコードによって編集時の音声同期もそこまで手間ではない、ということで現状はこの運用です。
尚、ピンマイクを使う際には演者さんに仕込むことになりますが、色々とテクニックがあります。良記事をいくつかピックアップしましたのでご参考にどうぞ。養生テープを両面にする方法は特に汎用性も高いので覚えておくと吉です。
地味に大切。タイムコード
さて、タイムコードが編集時に便利と書いていましたが、どのように便利なのかイメージしづらい方もいらっしゃるかと思います。
そもそも、良い音を録ろうとすると、オンカメラマイクだけでは足りず(カメラの位置にマイクが固定されるため、自由に音に近づくことができません)、ガンマイクやピンマイクなどを複数使うことになります。そうすると、通常のようにカメラで音と映像を一緒に録るケースと違い、映像と音がバラバラになります。これが編集時に非常に厄介で、映像と音を合わせるという作業が発生してしまいます。カット数が少なければ波形をベースに手動で、もしくは編集ソフトの音声自動同期機能を使ってコツコツ合わせても良いですが、カット数が多くなるとどの素材がいつ録ったものかの管理も大変で作業工数が膨大になっていきます。
そこで大切になってくるのがタイムコードです。タイムコードは撮影時に合わせておくことで、その映像・音をいつ録ったのかが全素材共通の時間軸で記録されます。例えば、12時から撮影をスタートして、12時のタイムコードが00:00:00:00(時間:分:秒:フレーム)であれば、12時35分20秒に撮った映像・音は全て00:35:20:00と記録されます。これは最小単位がフレームですので、全機材のタイムコードを正確に合わせれば、フレーム単位で一発で全素材の映像と音を合わせることができることを意味します。以下の近藤将人さんの動画にDavinciでのタイムコード同期の方法が紹介されていますが、非常に簡単です。
タイムコードの利便性は上記の説明で恐らくご理解いただけたかと思いますが(説明が下手でわからん!という方はごめんなさい…後にテレビ朝日撮影部さんの動画リンクや、分かりやすい記事も掲載していますので、そちらもご参照ください)、問題はそもそもタイムコードを全機材で同期させるのが大変!ということです。なんかいい感じにカメラのタイムコードが、他の機材にbluetoothとかwifiで同期される~~みたいな機能があればよいんですが、現状そんなに都合の良いものはなく、タイムコード同期用の機材がいくつか必要になります。現状私の知る範囲では、全ての機材のタイムコードを正確に合わせるためには、以下の記事・動画のように、UltraSync ONEとUltraSync BLUEを使う運用が良さそうです。
しかし、この運用、高い…(涙)
Ultra Sync Blueは4万弱、UltraSync Oneは7万弱(カメラ台数分必要)と、タイムコード作って同期するだけなのになんでこんな高いの…と失礼ながら思ってしまうぐらいのお値段です。
ということで、現状YFLではUltra Sync Blueのみを購入。録音機材(Zoom F3 , TASCOM DR-10L Pro)はUltra Sync Blueと同期、カメラはタイムコードをフリーランに設定し、目押しでUltra Sync Blueのタイムコードに(できるだけ)合わせるという脳筋運用をしています。カメラの映像と各レコーダーで録った音をフレーム単位で正確にあわせるには、編集ソフトで波形を揃える作業が発生はしてしまいますが、秒単位ではあっているため素材を探す作業が省略されます。この運用でも随分とタイムコードに助けられています。
ただ本当はやはり全機材タイムコードを同期させたい…しかし「Ultra Sync BlueがNikonの一部カメラにはBluetooth同期に対応しているから、いつかSonyのカメラも…」なんていう淡い希望を捨てきれず、追加投資に踏み切れていないこの頃です。タイムコード…もっとうまいこと各メーカーやってくれないかなぁ..…
YFLが愛用するその他便利機材
ここからは番外編。
その他YFLが愛用する機材をご紹介していきます。
SmokeGenie
コンパクトなスモークマシンです。
スモークマシンを使うと勿論空間に煙が舞うわけですが、これによって光の筋が見えるようになるというのが面白いところです。
ライトシャフト、ゴッドレイやボリュームライトとも呼ばれますが、これがあると非常にドラマチックな絵になります。空間に質感を足したいなというときに使えますので、一つ持っていると便利です。
(↓使っている製品は違いますが、こんな感じに使います。)
尚、ちょっとお高め…と思いつつ最近はめちゃくちゃ安いのが出ました…
私が購入した時にはなかったので辛い…以下がおすすめです…
Hollyland Solidcom C1
こちらもお高い!!ですが、非常におすすめです。現場での情報伝達などのコミュニケーションがとても円滑になります。
こちらを導入する前はDiscordのグループ通話でやってたりもしたのですが、マイクのオンオフ切り替えなどが案外手間だったり、小さな不便が重なってグループ通話で繋がっていても(イヤホン外していたりして)コミュニケーションができないという事が頻発し、あまりしっくりきませんでした。
このSolidcom C1の良いところは、片耳はフリーなため常にヘッドホンをつけた状態でいることができる点、マイク部分を上げ下げすることでオンオフが切り替わる機構がアナログでわかりやすい点です。これによってヘッドホンをつけておらず応答がなかったり、誰かのマイクが常にオンになっていてうるさい等の問題が起きずに、常にストレスフリーでリアルタイムにコミュニケーションをとることができます。

小規模な現場でも結構制作陣の距離が離れていることも多いので、どの現場にも持っていってます。YFLはみんなのお金で奮発して買いましたが、レンタルもできますので、まずはレンタルで試してこの便利さを体験してみてください。
着替えテント
着替え場所の確保は案外抜けがちですがとても大事です(超自戒)
外ロケでどうしても着替え場所が確保できない場合などは、こういうグッズを持っていきます。他には車を大きい黒幕で覆ってその中で着替えてもらったりした時もありました。大事なのは、事前に着替えをどうするのかを考えておくことです。演者さんファーストの精神を忘れずに!
ブルーシート
こちらも外ロケの際に荷物を置いたり、休み場所を確保するときに使います。撮影以外の時にどこにいてもらうかなどの想定も抜けがちですので、きちんと演者さんの待機スペース・休憩方法なども事前に考えて準備しましょう。また、夏には日傘・虫よけ・暑さ対策グッズ、冬には寒さ対策グッズなどを準備することも重要です。

iPad
最近新型が発表され「たけぇ~~~~~」と話題でしたね!高い!
YFLではiPadは監督用のモニターとして常用しています。
以下のようなipadに首からさげられるケースをつけて肌身離さず持っている感じです。
iPadは遠隔モニターとしてしか使わないので、最新版である必要はないですが、アプリとの相性もあるのでそこそこ新しい方が安定はするかと思います。ちなみに以前の記事で紹介しましたがYFLでは、Hollyland Mars M1 Enhancedを使っており、こちらのアプリ「Holly View」をiPadや各メンバー手持ちのiphoneに入れています。Log撮影でもLUTが入った状態で確認することもできますし、拡大表示や、アスペクト比を変えた表示、スコープ表示機能など揃っていますので便利です。
BTS用の小型カメラ
大人気韓国アイドルグループにより、すっかり検索しづらくなってしまったBTS(Behind The Scene)。さくっと撮っておくと振り返りや、チームの絆づくり、宣伝用にと様々な用途で活躍します。
どんなカメラでもいいんですが、私が使っているのはGR Ⅲ。ポケットに入れて置いて、撮りたくなったら片手でパシャリ。非常に便利です。
ただし、昨今人気爆発により手にいれづらくなってしまったのが辛いところ…iPhoneなどでもいいんですがiPhoneって案外カメラの起動に時間かかるし両手使うしで私は撮りづらいと感じてしまいます。
まぁ、撮れていればなんでも良いので、使いやすい小型カメラを持っておくと吉です!

おわりに
皆さんも経験があると思いますが、音が悪いと一気に作品自体を見る気がなくなってしまったりします。折角の作品、まず見てもらうためにも入門者の方も音を意識して作品作りをするのが良いと思います。
次回は恐らく本シリーズ最後になると思いますが編集編です。
長くお役に立てるような記事にしようと思いますのでこちらも宜しければお読みいただければ幸いです。
それでは最後までお読みいただきありがとうございました。また次回の記事でお会いしましょう!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
