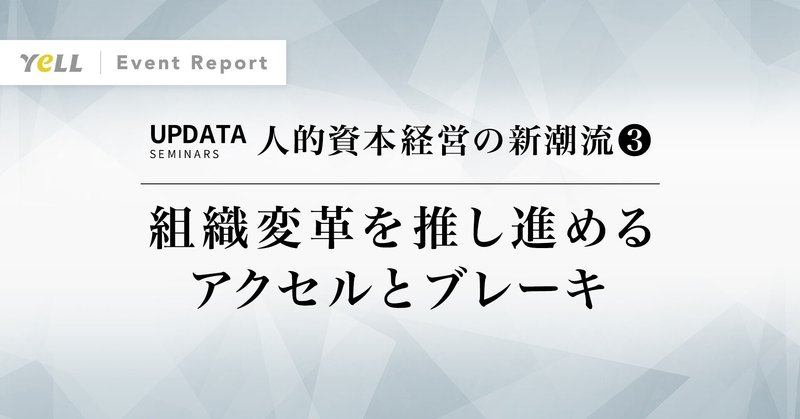
組織変革を推し進めるアクセルとブレーキ|聴き合う組織をつくる『YeLL』のnote
【UPDATA SEMINARS 全ての経営者に知ってほしい、「人的資本経営」の新潮流】から、イベントレポートをお届けする3回シリーズ。今回は、最終回となります。
前回は、「経営戦略が変われば、人材戦略も変わる」という実例を、エール株式会社篠田さんの個人的な体験から考えてみました。
経営戦略にともなって、職責が変わったり、専門職が置かれるようになったりと、さまざまな変化を受け入れざるを得ないケースは多々あるでしょう。ここで改めて意識しておきたいのが、「経営陣あるいは人事部が、人材戦略を新たに進めるときに陥りやすい”罠”があることだ」と篠田さんは語ります。一体、どういうことなのでしょうか。 【編集部 林】
変革できない現場の悪循環
「たとえば100名の従業員がいれば、100%の力が発揮できるはずです。しかし実際は、30%の力しか出せていない。200%、300%の力が出せるポテンシャルがあるのに、できていないわけです。トップがこのように変わって欲しいと現場へ方針を出し、組織内の人員配置や研修などを整えようと戦略を打つ。ここまではよくある話ですね。
しかし、しばらく経っても現場の動きは変わらず、結果も出ない。『変革前と何も変わっていないんじゃないか』と、トップの視点からは見えがちです。さらにトップから『そうか、わかっていないなら何度も言うしかない』と変革の方針が強く発信され、新たな施策が出て・・・こんなスパイラルに陥ってしまっている組織について、皆さんも聴き覚えがあるのではないでしょうか」(篠田さん)
確かに、「現場の意識と、上の意識がズレている」「もっとスピード感を持って変えられるはずなのに」との声は、日常生活でもよく耳にするかもしれません。その背景に、現場でかかってしまっている”ブレーキ”の存在があります。トップの視点からは、現場のブレーキは非常に見えにくいもの。そのため、変革進まない理由が分析できずにいるのです。
組織変革に対するブレーキとは?
「例えば、次の3点は代表的なポイントです」(篠田さん)
●当事者意識が弱い
「ウチの部署としては、やらざるを得ない。上からの指示だから」との意識が強く、やらされ感でいっぱいになっている。
●整合性を気にしすぎている
「過去にそういう事例はなかった」「一部の社員だけを優遇していることにならないだろうか」と、過去や周囲との整合性が取れないことを気にしすぎてしまう。
●意図せずに、周囲が邪魔をする
組織の中では各部門によって、、変革スピードの遅い・速いが分かれてしまうもの。その際にちょっとしたズレが生じてしまい、スピーディに事が進まなくなってしまう。「どうしてもハンコを押印してもらわないと、業務が進まない」といった、ちょっとした手順がネックになってしまうこともある。
次にあげる具体的な事例から、考えてみましょう。
人事が”変革を止めるブレーキ”になっていないか
「人事部門の苦労は、整合性をいかに取っていくかだと感じています。女性活躍の文脈で言うと『103万円の壁』って、ありますよね。年収103万円を超えると所得税が発生し、配偶者控除が適応されなくなるため、『夫はフルタイム、妻はパートで働き、妻の年収が103万円以下になるように調整する』現象です。会社側はもっと活躍して欲しいと願っていても、通用しない壁があります。
そうした社会問題について私も興味があり、勉強会に参加してみて、ビックリしました。税制や年金制度はかなり法改正が進み、扶養内と判断される年収額も変わっていました。にもかかわらず、多くの従業員が働き方をセーブしているのはなぜか?ある企業を調べてみると、家族手当の支給条件が『配偶者の年収103万円以下』となっていたとわかりました。それで『敵はこっちだったか!』と(笑)。
従業員のためを思って取り組んでいることが、実はブレーキになっている・・・組織の内部からは気がつきにくい部分です」(篠田さん)
良かれと思っているからこそ、目の前の現実を見落としてしまう。まさに、落とし穴にはまってしまったと言えるでしょう。
「組織変革を担う立場にあるトップの方々は、変革を推進する武器として『アクセルを踏もう』と思い、すでに行動されているでしょう。コンサルタントなど、社外リソースを活用されている方も多いと思います。しかし、組織変革にはもう1つの武器が必要です。それが、人材が持つ潜在能力を解放するために『ブレーキを緩める』という武器です」と篠田さん。
最後に、そのブレーキを緩めていける可能性について語りました。
もっと組織が聴き合えれば、変わっていける
「現場のブレーキを緩める必要があることすら、充分に認識されていないのが現状ではないでしょうか。経営戦略と人事戦略を並行して進めるためには、この『ブレーキを緩め、潜在力を解放する』ための施策も同時に取り組む必要があるんです。実はエールが提供している社外人材によるオンライン1on1は、『ブレーキを緩める』ことにもつながっています」(篠田さん)

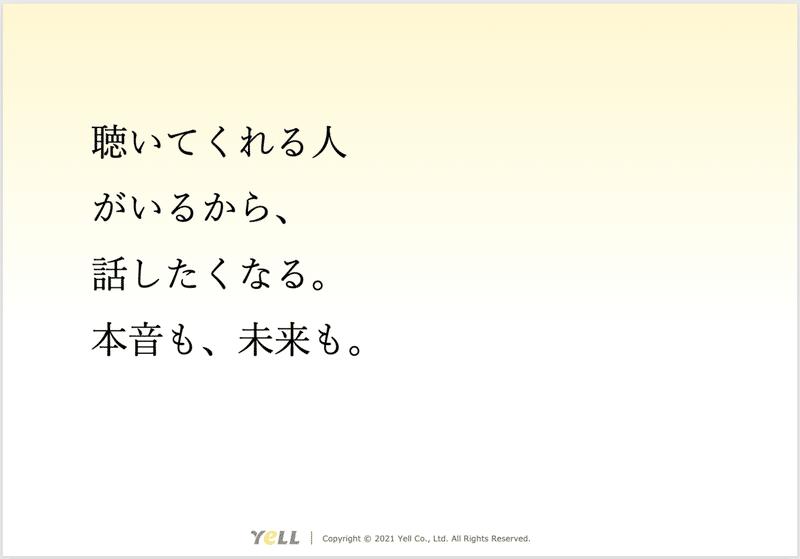
「モチベーションを高め、当事者意識を持ってブレーキを緩めてもらうためには、まずは自分の話をすることから始まります。そして、その本音を聴いてくれる人がいるから、新しい取り組みへの想いが言語化でき、変革が進んでいくはずです」(篠田さん)———最後は篠田さんの笑顔で、セミナーの幕が降りました。
社外人材による1on1サービス「YeLL」を導入している多くの企業は、業界における大きな変化に直面しています。今後もESG経営と正面から向き合い、経営戦略及び人材戦略の見直しを迫られる企業が増えていくはずです。ブレーキを緩めて大きくアクセルを踏み込み、成長曲線の上り坂を進むためには、3つのポイントがあるように感じました。
まず1人ひとりが仕事に対する自分の想いに気づき、当事者意識を養うこと。そして、対話によってそれぞれの意見を聴き合い、チームの意志を確認すること。さらに行動へ移した社員を応援し、チャレンジを止める要因を少なくすることが、大切なのではないでしょうか。
「人的資本は大切だ」との潮流に乗って、表面上の人事制度だけを変えるなら、誰でもすぐにできるでしょう。しかし、本当の意味での組織の変革とは、働く人の意識を根底から変えることなのではないでしょうか。
従業員一人ひとりが「自分たちが変えよう」と自ら走り出すには、まず経営者自身が変革を自分ごととして捉える必要があります。そのための仕組みづくりへ投資をしていくことも、経営戦略に含まれるのではないかと感じました。
※当日のイベント動画も公開されておりますので、合わせてご確認くださいませ。(https://www.wingarc.com/updata/seminar/index.html|過去セミナー紹介→Innovationよりご覧ください。)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?

