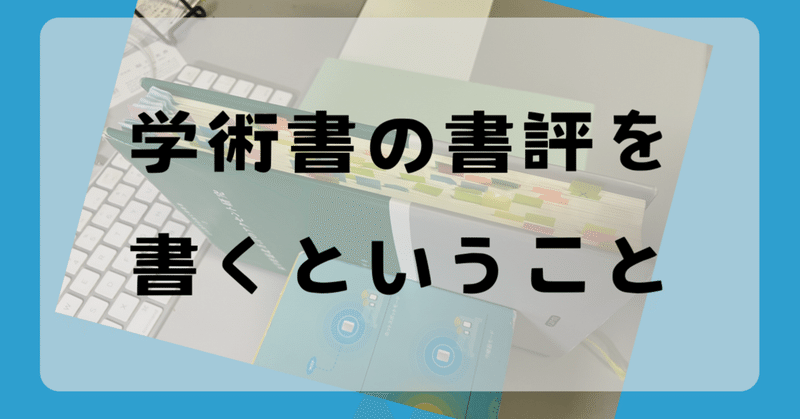
学術書の書評を書くということ
『日本語の研究』に出した書評が公刊されました。

オンラインに出るのは刊行の1年後なのでしばらくは紙媒体のみになります。
学術書の書評を書いたのは2度目になります。慣れたわけではありませんが,どうやって書評を書く仕事をしたのか少し記録を取っておきます。
依頼を頂いてから締切までは6か月でした。当たり前ですが、本を入手して通読します。読むときのスタイルは色々でしょうが、書評を書くことが決まっていたので、適宜付箋を貼り付け、鉛筆でメモを書き込みました。

今回の本は直接メモを書き込んでいましたが,前の書評では付箋を貼り付けて、notionに書き込んでいました。基本的に気になったら躊躇なく付箋を貼っていったのでそこそこの量になります。

ひと通り読み終わった後,notionでメモを作りました。アウトラインとも言えるもので,基本的にこれを書こう,これは伝えたい!というものを盛り込んでいます。ちなみにnotionだのようなクラウドメモアプリは喫茶店で読んだときなんかもスマホからメモできるのでとても効率的でしたね。

これはそういうものだと思いますが,最終原稿の構成はアウトラインから変わります。これは書いてみての感覚によるところもありました。
ただ以前書評には読者のために各章の概要を基本的には入れるべきとコメントいただいたので,それは別立てでメモを作りました。

これも全てを原稿に盛り込んだわけではありません。
そしてメモをもとに原稿を書きました。原稿は締切1週間前を目処に仕上げ(諦め),協力してくださる方にお送りしてコメントを頂きました。今回の場合,foの解釈など私の理解も足りないところがあり,ちょっと締切が厳しくなりました。あと,実は分量オーバーでどこを削るべきかなんて相談もしました。これは私が小節を作りすぎていたのでそこで対応しました。何人かからコメントを頂いたのでかなり改訂することに。ちなみに著者の漢字を間違えるという恥ずかしいミスも。危ない…!

こうして無事に提出原稿ができました。

わりと勢いで書いてしまうブログと違い,学術誌に書評を書くのはなかなか手間がかかりますが,その分こちらの勉強にもなるのは確かです。私は依頼でしたが,雑誌によっては自分で応募もできるのでそれを活用して読みたかった本を読んで投稿するのも良いかなと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
