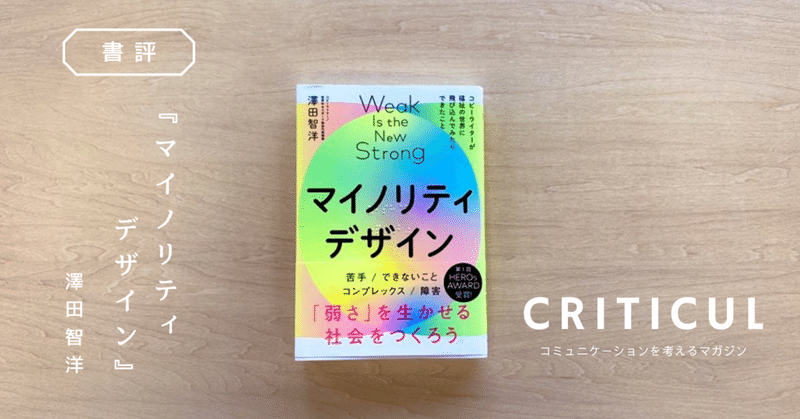
世界は、失敗作である。【書評】『マイノリティデザイン』(前篇)
(はじめに)コミュニケーションを考えるマガジンを始めてみます。
「CRITICUL(クリティカル)」という名前をつけてみました。
批評を意味する"Critical"に、文化を意味する"Culture"の"Cul"。
一方“Cul”はフランス語で「尻」を指す語だったりするので微妙かと思ったりもしたが、まぁ良しとしよう。
ここに書いてあることを読めば面白い企画が立てられる、とか、良いコピーが書ける、みたいな近道の話はここではあまりしない(できない)と思う。
効率や、有用性に尻をまくるマガジン。それが「CRITICUL」ということにしておこう。
ゆるっと続けてみたいと思います。
1. マイノリティデザインと超言葉術
阿部広太郎さんのツイートで知った、『マイノリティデザイン』の著者である澤田智洋さんとのトークイベント。
2015年のこと。
— 阿部広太郎|超言葉術 (@KotaroA) March 13, 2021
澤田智洋さん @sawadayuru とNHKに行った帰り道に 「今度僕がはじめる『企画でメシを食っていく』に登壇してもらえませんか?」と話したのを今でも覚えてるなあ…
「自分をクライアントにする方法」3/15夜 オンラインで青山ブックセンターさんにて、ぜひ☺️👏🏻https://t.co/gbDNr23sZ4 pic.twitter.com/q541KvglhQ
現在参加中の #アートとコピー という講座の課題も出ている中ですが、今回の相方デザイナーさんにも頼み込んで、一緒に受講してもらいました。
2. 「人間だれでもが身体障害者」
この本は、岡本太郎の過激な引用から始まる。
人間だれでもが身体障害者なのだ。
たとえ気どった恰好をしてみても、八頭身であろうが、それをもし見えない鏡に映してみたら、それぞれの絶望的な形でひんまがっている。
(岡本太郎『自分の中に毒を持て』)
そして、「弱さから、楽しい逆襲をはじめよう。」という、期待感に満ちた言葉が続いている。
第1章では、澤田さんがマイノリティデザインという概念を育む以前のコピーライター/プランナーとしての半生が語られる。
このとき初めて知ったのだが、かつてリクルート社が発行していたフリーペーパーの草分け『R25』で連載されていた短編マンガ『キメゾーの「決まり文句じゃキマらねえ。」』は、澤田さんの作品だった。社会人になりたての頃、帰宅の電車で楽しませてもらっていた(ファンでした。「キメゾーAR」とかもやったなぁ…)。

32歳の頃、視覚障害を持ったご子息が誕生したことで澤田さんの人生は一変することになるのだが、それ以前から澤田さんの企画には独特な視点がある。
トークイベントの中でも
死んだコピーってあると思うんです。
たとえばスポーツ関係者がインタビューに答える際に「感動」っていう言葉を頻繁に使うけど、これって言葉として「死んでいる」と思う。
という阿部さんとのやりとりがあった。
『キメゾー』自体「決まり文句じゃキマらねえ。」という題名の通り、毎回キメゾーが紋切り型の表現を疑い、一石を投じる(それがやりすぎたり、ズレていることに笑いが生じるのだが)構成になっている。
この「紋切り型の表現を疑い、そこから離れることで独自性があって興味を惹く表現を生み出す」ということこそコピーライティングの基本的な考え方でもあるのだが、澤田さんの作品にはキャリアの初期からその意識が強く見られるように思う。
自ら「アウトサイダーだった」と語る澤田さんには、すでにして「弱さ」を愛でるやさしい眼差しがあったのだった。
3. 〈ライター・ストロー・カーディガン〉
息子さんに視覚障害があることが判った後、「企画を立てることができなくなった」澤田さんは、仕事量を9割減らして200人以上もの障害当事者の方々に会いに行く中で、希望を感じるエピソードを知る。
ライターは「マッチで火をおこすには両手が必要だから、片腕の人でも火を起こせるようにしよう」というアイデアから、今の形になった。
ストローや、カーディガンも同様に、負傷者や身体障害者にも使えることを目指してデザインされた(諸説あり)。
澤田さんは「医学モデル」と「社会モデル」という2つの概念を引用する。
障害があったら、リハビリによってそれを直し、社会に再適応させるのが「医学モデル」。
反対に、障害を個性と捉え、社会の側に改善を促すことで適応可能にするのが「社会モデル」という考え方だ。
前者の「医学モデル」は、世界を変えない。一方、「社会モデル」にとって、障害は社会に変革を促すポジティブなきっかけになっている。
これが「障害=社会ののびしろ」と捉える、「マイノリティデザイン・シンキング」の根幹にある思想だと思う。
デザイン理論の名著、ヘンリー・ペトロスキーの『フォークの葉はなぜ四本になったか』にはこのように記されている。
実際、すべての人工物に共通する唯一の特徴とは(中略)いたるところに見受けられる不完全さにほかならない。そして、この特徴こそがまさにモノの進化を推し進める。
(第二章 形は失敗にしたがう)
「強さ」が世界を変えることはない。
「弱さ」こそが、世界の変革を推し進めるトリガーなのだ。
一方、すべての人間に居心地の良い社会など幻想にすぎず、この改善は繰り返されることになる。
広告・コミュニケーションは課題解決ビジネスと言われるが、澤田さんは「課題を掘る場所が違うんじゃないか?」と言う。
「大きすぎて見えない相手」あるいは「もうそこにはいない相手」に目掛けて、課題を発見しようとしているように見えます。
そこで、冒頭の岡本太郎の言葉のように、一人ひとりの人間を「誰もが固有の弱さを持ったマイノリティ」と捉えれば、たとえば「スポーツ弱者」「アルコール弱者」「ドライブ弱者」「朝弱者」「猫アレルギー弱者」(すべて僕自身のことです)…これら一つ一つが、「克服すべき課題」ではなく、社会のあり方を見直すヒントになっていく。そこはもう、課題の宝庫だ。
4. 「世界は、洋服のS・M・Lくらい乱暴に作られてる。」
トークイベントの澤田さんの言葉の中で、一番印象に残った言葉。
世界なんて、S・M・Lくらい乱暴に作られているじゃないですか。
そんな尺度に、ピッタリ合わない方が当たり前なんですよ。
そうなのだ。
既製服のサイズのように、自分の身の丈をそこに揃えようとばかりしてしまってるけど、本当は誰もがどこかしらに着心地の(居心地の)悪さを感じている。
だからこそ「第4章 自分をクライアントにする方法」で語られているように、自分にとっての「人生のコンセプト」を決め、自分宛の企画書で提案することを、澤田さんは薦めている。
5. ゲームから下りる、という勇気。
『マイノリティデザイン』は、そうして自分の「弱さ」に向き合う内に、自分が人生やキャリアで何を本当に重視しているかを考え直すことを促している。
それは、強さを競い合うという狭隘なゲームからいち早く下り、あたらしいルールを自分に課して生きていくことだ。
第4章以降は、自分への企画書づくりにはじまる「マイノリティデザイン」実践のメソッドに満ちている。本記事の後篇では、この実践に自分でも取り組んでみたいと思っている(更新時期は未定です、、、)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
