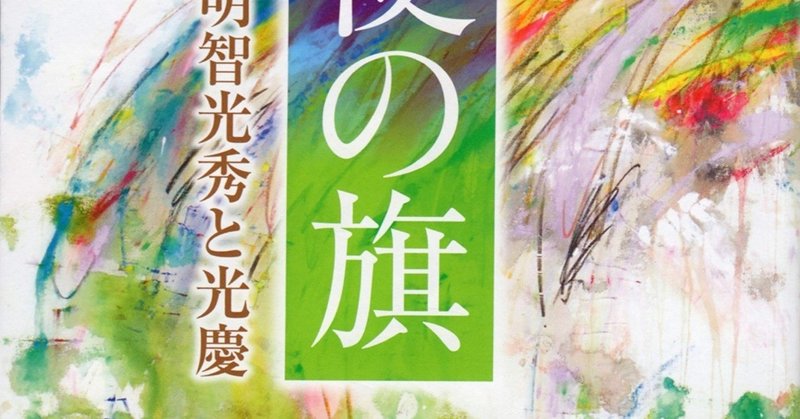
『桔梗の旗』(潮出版社)で谷津の唱えた”新説”について
【PR】
何気なく新刊『桔梗の旗』(潮出版社)で新説を唱えてしまったので、歴史のファクトに熱心な方々に叱られそうだなあ、とやや逃げ腰になっている小説家でございます、皆さんこんにちは。
とはいえ、実は「歴史小説家」と呼ばれる存在も一枚岩じゃないよ、という話が今回のお話です。
歴史小説家は
・歴史其儘派(史実・考証重視派)
・歴史離れ派(物語・小説重視派)
に大別できます。とはいえ、今では史実・考証を大事にしつつ、小説をおつくりになられている方もたくさんいらっしゃるのでこの大別にもあまり意味がなくなっているという実情も無きにしも非ずといったところですが、傾向としてこういうものがあるよ、くらいにイメージしてください。
実はこの違い、歴史的事実や学説に対するスタンスにも相当の違いが出てきます。
歴史其儘派の方は史実や学説を「信頼に足る」「蓋然的に見て事実なのだろう」と採用します。つまるところ、「一人の歴史学徒、歴史ファンとしてこの説を支持する」がゆえに作品で用いるのです。それに対し歴史離れ派の方は「そっちを採用した方が面白いから」諸説ある史実や学説から選んで採用します。えっ、歴史学に対して不誠実? いや、わたし自身歴史離れ派に属しているのでよくわかるのですが、小説家は大なり小なり物語、小説に奉仕している存在です。であるからには、「歴史か、それとも小説か」というぎりぎりの場面で小説を取る人がいるのもまた当然と言えましょう。
実を言うと、他業界から批判を食らいがちなのがこの「歴史離れ派」です。
(歴史学から見て)「正しさを追求しない」ように見えるからでしょう。
わたしはここに、正解を求めがちな現代の病巣を見てしまうのですがまあそれはさておき。
何が言いたいのかと言うと、わたしの小説『桔梗の旗』は、歴史離れ派であるわたしが書いている以上、そこで展開されているのはわたしが「面白い」と信じたロジックであって、これが歴史の真実だと言いたいわけじゃないよ、ということです。
(まあ、『桔梗の旗』をお読みの方ならお分かりいただけるとは思いますが、本作での本能寺を巡る解釈、「まあ、こういう解釈もできるんじゃねえの」程度のリアリティは確保しているつもりですのでその点はご安心いただけましたら)
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
