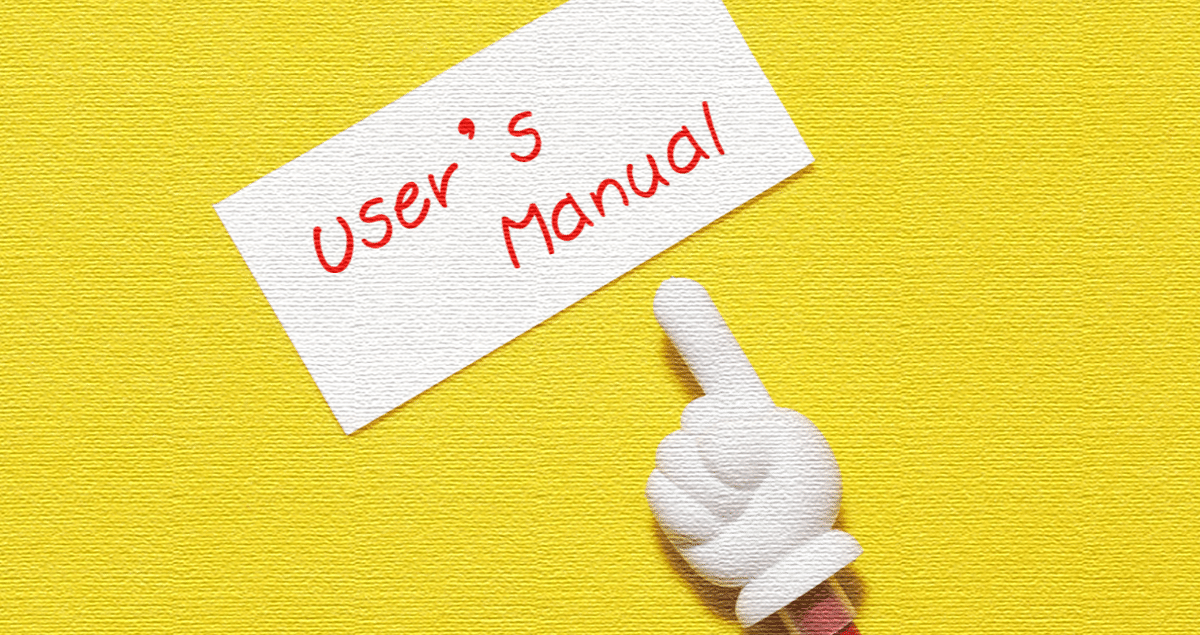
本の棚 #161 『マンガでやさしくわかる 業務マニュアル』
組織の規模が大きくなればなるほど
人によるバラつきは大きくなっていく。
やがては指導する側のマンパワーでは
立ち行かなくなり、サービスにバラつきが
目立ちはじめ…
「あれ、こんなはずでは…」となる。
そうならないために、というよりは
さらなる高みを目指すために
マニュアルというものはつくられている。
実は今まさにマニュアルなるものを
つくる仕事に取り組んでいる最中で
この本に出会った。
堅苦しい感じは嫌だからマンガで。
実際に見たことはないが
人をよく育てる企業は必ずと言っていいほど
マニュアルを大切にしているように思う。
マニュアルとは?どうやって運用する?
使われるマニュアルとは?
頭の中にある質問を著書にぶつける。
−−−−−−−−−−−−−−
「暗黙知」を「形式知」へ
マニュアルの機能は次の4つだ。
①業務を見えるようにする
②業務そのもの、業務上の判断の基準をつくる
③基準を守るようにするための行動がわかる
④ベストパフォーマーをつくる
まずは「見えるようにする」
普段見えているようで見えていない、
感覚的で、言葉にはできない。
そんな暗黙知をたくさん持っていないか。
組織の成長のためには、それを
隠し持っているだけではだめで
形式知とせねばならない。
いわば「型」を伝承していくことに近い。
優れたやり方があるならば
それを組織に開示して浸透させる。
それができることは立派な価値だと思う。
②③④の機能の土台として
①を正しく実行する。
マニュアル作成に適した担当者とは
①中立的な人
②マニュアル作成業務をある程度把握している人
③意思決定ができる人
④目的を理解している人
どんな人が適任か。
マニュアルを作成する際は
仕事の全体観がつかめていて、
ガシガシ進められる人がいいらしい。
また最初に決めた目的を掴んで離さないこと。
何度も目的を唱え続けて
話がそれたり、脱線した際には
振り返って修整できる人がいい。
あれもいい、これもいい、そっちもいい
なんて言ってたら全然前に進まない。
一発で100%を目指してはいけない。
まずつくってみて、磨き上げていく。
マニュアルは一度作成して終わりではない
「やったー!おわったー!」
と夏休みの宿題のようにやったら終わり
マニュアルはそんなものではない。
「随時更新」と「定期更新」を心得て
更に良いものをつくりあげていく。
要はブラッシュアップすることを前提に
制作するということだ。
また「だれがいつ更新するのか」
といった更新担当者の選定を忘れてはならない。
それを忘れると最初はうまく運用されていたのに
数年後には「古いもの」となってしまい
だれにも使用されない、なんてことになる。
つくってからがはじまりだ、くらいに
覚悟しておくことがマニュアルづくりの
最大のポイントなのかもしれない。
なんだか、えらい仕事に取り組んでいるなと
気づかされた次第ではあるが
良いサービスを提供し続けるためにも
重要な任務として取り組みたい。
−−−−−−−−−−−−−−
サポート頂いた分は全て書籍代として本屋さんに還元します!
