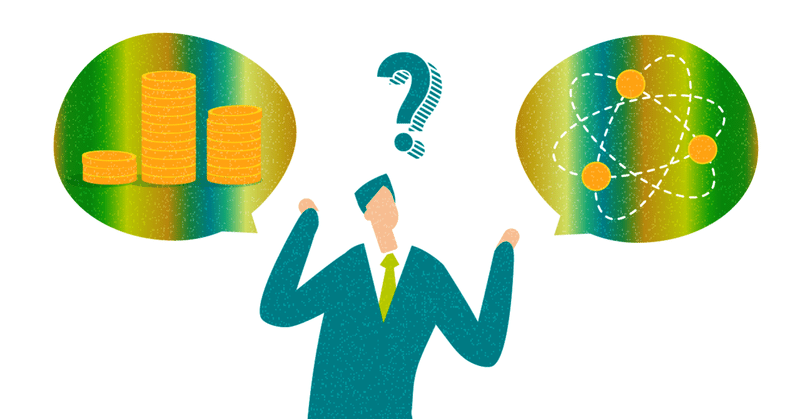
内外部から多くの”矢”が来る、公的基金
公的基金は運用に関して、常に公平や高い透明性が求められるもの。また基金内外部、両方からの監視がとても強いことが公的基金の経営・運営の難しさを露呈しているように感じる。
上記記事はシンガポールのGIC(シンガポール政府投資公社)や韓国のNPS(韓国国民年金運用)を例に挙げ、足元のような景気後退ー回復期には、アセットオーナー(政府なりその国の国民なり)から、企業救済などへの拠出を期待される一方で、景気回復-拡張期には高いリターンと運用業務を求められる。そのような政府など外部からの圧力・要望と同時に従来から予定していた年金受給者等の払出にも応じるために、超低利回りで高流動性の国債などを持ち、それに伴いポートフォリオ全体のリターン低下になるとともに、他の金融機関も投資している国債全体の利回りも押し下げる。基金運用側としては様々な方向から向けられる”矢”を適時捉えていく必要がある。
外部からの”矢”に加えて、基金の運用責任者や理事長など経営層は、内部からの”矢”にも応じないといけないのである。
上記2例(①2020年8月に起きたCALPERS-米カリフォルニア州公務員退職年金基金のCIO辞職と、②2019年10月に起きたGPIF-日本・年金積立金管理運用独立行政法人の理事長への処分)に関する詳細は直接記事を確認頂きたいが、記事の信憑性や当人の処分や辞任に至った経緯なども、私には分からない。でも少なくとも、基金内部の軋轢?が発端のよう、には見て取れる。
ちなみに取り上げた基金の大きさで行くと、下記の通りでどこも兆円単位の資金運用をしているのである。
・GPIF 164兆円程度(2020年6月末)
・NPS 62兆円程度(2019年末で$610Bnの模様)
・CALPERS 40兆円程度(2020年3月末で$389Bnの模様)
大きなお金が動く公的基金。その大きさ故に、外部からは様々な役割を担ってもらいたいと期待されながらも、一定程度の期待値を守りながら、空気を読みつつポートフォリオを動かしたり。同時に資産運用会社からの強いセールスなども上手くかわしながら、ステークホルダーの為に活動する。また内部はコスト抑制しながら、職員や関係者の軋轢を生まないように、同時に透明性高く運用していく意識を助長させなくてはならない。なんと難しいバランスだろうか。
公的基金でもちゃんと運用、経営層になりたいと進んで手を挙げる優秀な人材がもっと増えるように、役割の明確化や時間軸の目線など、現経営側のタスクも多いと感じる。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
