
楽譜のお勉強・番外編「集中講義・備忘録」
2022年12月に2日間の集中講義を愛知県立芸術大学で行いました。大学院の講義ということで、受講生は作曲家3人と少なく、ずっと僕が話すよりも囲みでディスカッション形式にした方が色々な視点が出てきて面白そうだと思いました。そこで当初の予定を少し変えて、受講生それぞれの作品への短いグループ・レッスンも取り入れつつ、より学習内容を自作に活かせる方法に変えました。講義はマルク・アンドレ(Mark Andre, b.1964)、カローラ・バウクホルト(Carola Bauckholt, b.1959)、ゲオルク・フリードリヒ・ハース(Georg Friedrich Haas, b.1953)、レベッカ・ソーンダース(Rebecca Saunders, b.1967)、ジェイ・シュヴァルツ(Jay Schwartz, b.1965)の作品を読んで、分析したり、表現内容を確認して記譜や演奏との関係を考察したりしていく内容でした。シュヴァルツ以外は「楽譜のお勉強」記事で取り上げたことのある作曲家たちですが、講義内で読んだ楽曲とは異なります。いずれも興味深い作曲家、面白い作品ですので、講義で取り上げた楽曲を簡単にご紹介します。
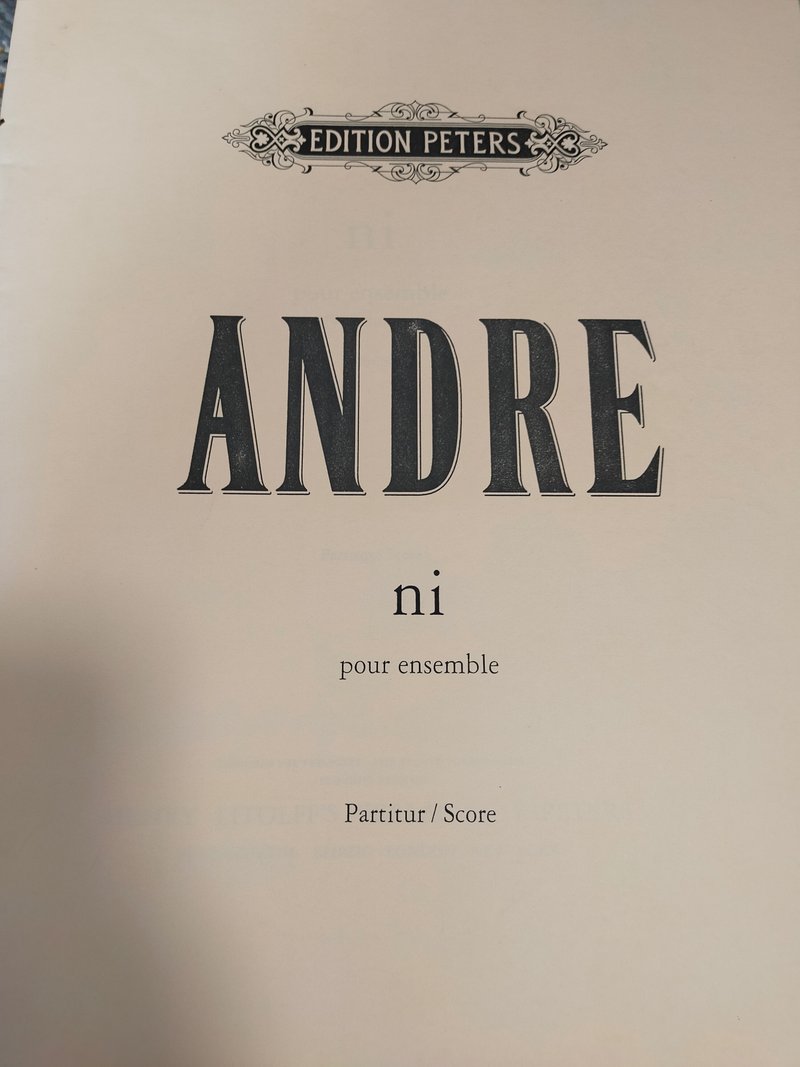
1)マルク・アンドレ『ni』(»ni« für Ensemble, 2006)
14人の奏者のためのアンサンブル曲です。アンドレの楽譜は説明書きページがたくさん付いていて、通常の楽譜では見かけない記号がたくさん出てくるのですが、それでも説明不十分なことがしばしばあります。作曲家本人から演奏方法や読み方を教わった演奏家たちが楽譜の読み方、演奏の方法を後輩演奏家たちに伝えていっていますが、日本のように欧州から離れた場所で楽譜だけ注文して勉強してみようとしても、何のことを表しているのか不明瞭なことがあり、勉強するハードルが高い作曲家と感じます。私自身もドイツ留学前に購入した楽譜を日本で持て余していました。タイトルの『ni』は「nach innen(内側へ)」の略語です。短い7つの楽章からなり、第2楽章で聞かれるノイズのカノンが魅力的です。また第4楽章では金管楽器の息音ノイズのイントネーションを色彩的に変化させるために、各管(指)を個別の段で書く極めて実験的な記譜が試みられています。これはアンドレの音楽でも珍しい記譜で、他の楽曲ではほとんど用いられません。
(第2楽章と第4楽章のリンクですが、他の楽章も作曲家本人のサウンドクラウド・ページでお聞きいただけます。)

2)カローラ・バウクホルト『球』(»Kugel« für drei Celli und Zuspielung, 2002/2003)
3本のチェロと録音された音源のための音楽です。特に興味深いのはユニゾンの扱いです。3人のチェリストが長い音価で極小の音程をグリッサンドするとき、どうしても時間配分のズレが起こり、不思議なディレイ効果のようなエフェクトがかかります。逆に早い時間に細かく揺れ動くユニゾンでは、動きに耳がいってしまって、ズレていてもユニゾンに聞こえたりします。認知の心理を巧みに利用した書法が個性的です。
(『球』の演奏動画・音源はオンラインで見つかりませんでした。CDの情報を上げておきます。)

3)カローラ・バウクホルト『チェロ三重奏曲』(»Cellotrio«, 2002)
バウクホルトのもう一つのチェロ三重奏曲も取り上げました。こちらは第2チェロがコルクを使ってG線とD線にプリパレーションを施し、鐘の音を模した音が使われることが特徴的です。また、現代音楽では弦楽器の駒の向こう側を弾き、軋んだような高音を出すことがありますが、バウクホルトはこの部分でもハーモニクス奏法を用い、通常の駒越え音とそのオクターブ上のハーモニクスの交替を巧みに用いて錆びた歯車が軋みながら回転するような表現を作り上げました。

4)ゲオルク・フリードリヒ・ハース『リミテッド・アプロークシメーションズ』(»Limited Approximations« Konzert für , sechs Klaviere im Zwölfteltonabstand und Orchester, 2010)
12分音間隔で調律された6台のピアノとオーケストラのための協奏曲という副題が付いています。タイトルは「制限付き概算値」とかそんな感じの意味ですが、これはピアノの制限について語っている言葉です。ピアノという楽器はその仕組み上、正しい意味でハモっている音程はオクターブしかありません。他の全ての音域は純正律に比べ、少しだけズレているのです。しかし、12分音間隔で6台のピアノを調律すれば、多くの倍音はほとんど正しい値まで近づきます。それでもごくごく微妙にズレていることには変わりないので、「制限のついた概算値」ということなのです。つまり、限りなく自然倍音に近い音響を得られるピアノを生み出したということです。その演奏効果はぜひ音源を聴いて確認してください。オーケストラの奏者は指定されたピアノからピッチを拾わなければなりません。大変な演奏になりますが、壮大なスケールで宇宙的な広がりを持つ響きを持つこの音楽は演奏家にも報いてくれることでしょう。
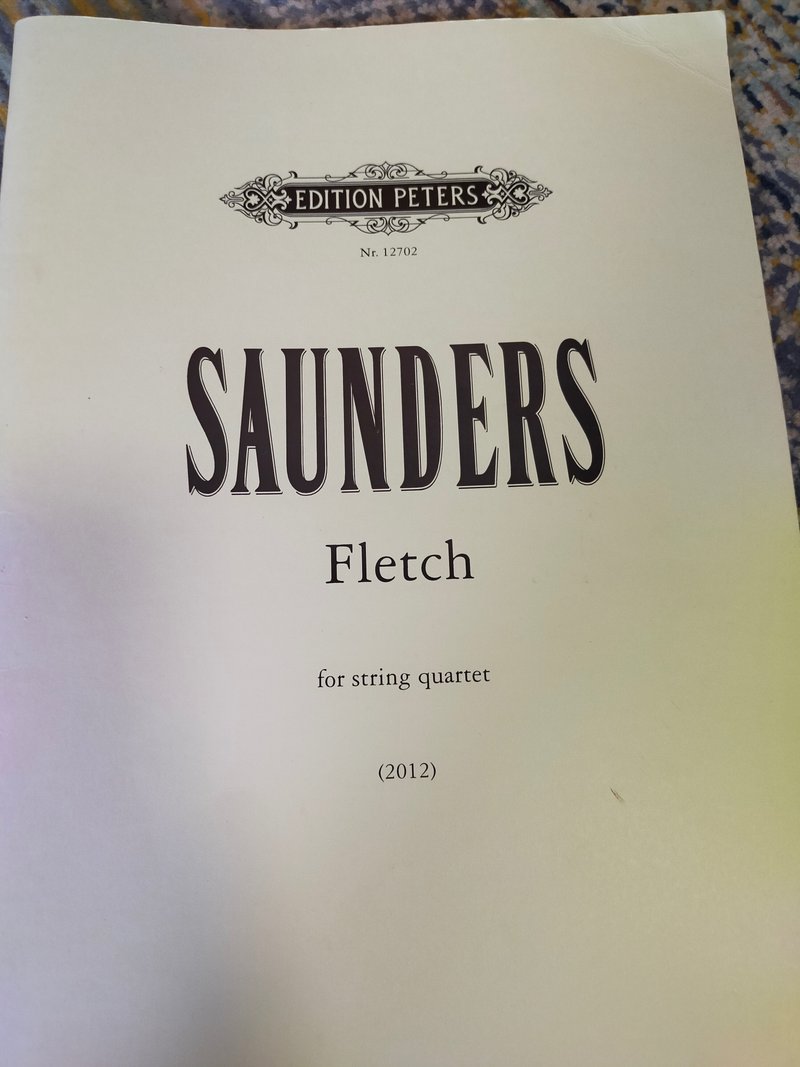
5)レベッカ・ソーンダース『矢羽根』(»Fletch« for string quartet, 2012)ソーンダースの曲の中でも動的な表現の多い曲です。重音のハーモニクスによるトレモロと素早い運弓の実験とも言える作品です。この二つの奏法に関して、作曲者はかなり細かく指示を書いています。重音のハーモニクスによるトレモロ記譜に関して、演奏の実現性に即した記譜法を開発しています。最初、激しいハーモニクスのうねりに動的な音楽かと思いますが、聴いているうちに内在するゆったりしたメロディーが耳にも届くようになってきて、実は抒情的な表情を持った曲であることに気付きます。実際に楽譜にも何度も「これはメロディーです!」と書いてあります。

6)レベッカ・ソーンダース『ささやき』(»murmurs«, 2009)
スコアのない曲です。パート譜だけで構成されていて、演奏会場のさまざまな場所に散らばった演奏家たちがストップウォッチでタイミングを計りながら演奏する音楽です。ソーンダースにはこのように空間を作曲した作品がいくつかあります。厳密なアンサンブルが難しくなりますから、自由度の高い記譜を採用していますが、楽曲を成立させる要素は厳密に規定されています。個々の演奏家が要求されている技術は特殊でなく、それほど難しいものでもないので、是非とも日本の教育機関等で演奏してほしい曲です。
(作曲者のホームページのリンクから演奏音源が聴けます。)

7)ジェイ・シュヴァルツ『オーケストラのための音楽』(»Music for Orchestra« for string orchestra, 2005)
この曲は当初取り上げる予定ではなかったのですが、急遽聞くことになりました。楽器本体を擦る摩擦音から徐々に高音が立ち上がり、少しずつグリッサンドで揺れながらクライマックスの調性的なコラールを目指します。静寂が成長していく様子は凄まじく、生演奏で聴くと途轍もない効果があります。ほとんど全編に渡って全音符が支配的な楽譜で、設計図の感覚が強いですが、細かいニュアンスも実はしっかり計算されて作曲されていて、情報の関わりを精査してみると興味は尽きません。

おまけ)マルク・アンドレ『üg』(»üg« für Ensemble, 2007-2008)
講義で取り上げる予定で、シュヴァルツと差し替えになって取り上げられなかった曲です。音源をここに上げておきます。他にアンドレの弦楽三重奏曲『…zu…』や、バウクホルトの『Schlammflocke』、ハースの『弦楽四重奏曲 第4番』などに関して、譜例を提示しながら言及していきました。
*「楽譜のお勉強」シリーズ記事では、著作権保護期間中の作品の楽譜の画像を載せていません。ご了承ください。
アンドレ、バウクホルト、ハース、ソーンダース作品を取り上げた過去記事はこちら。
作曲活動、執筆活動のサポートをしていただけると励みになります。よろしくお願いいたします。
