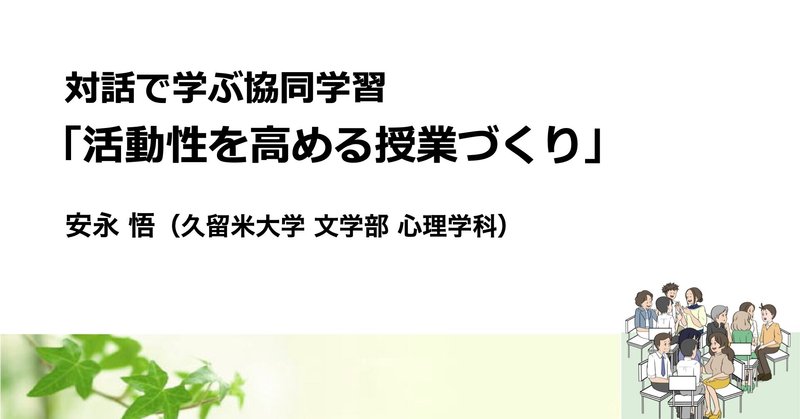
第2回 グループの編成と配置 (その5) 集団と個の関係に心を配る
今回は、第2回の返信(その4)に対する回答です。返信(その4)にある教師の思いを手がかりにグループ編成についてさらに理解を深めます。その後、返信(その4)の執筆にかかわられた千葉中央看護専門学校の先生方が実感した「学生を信じて任せる」という教育理念を吟味し、関連する質問にお答えします。
〇 バランスの取れたグループ編成
返信(その4)にはグループ編成に関して興味深い記述がありました。少し長くなりますが引用します。
「円滑なグループ活動のために、まずメンバーの中心となるリーダーシップの取れそうな学生、話し合いを活性化してくれそうな積極的な学生、確かな知識を持ち方向性がズレないようリードしてくれそうな学生などを軸に、成績の良し悪し、積極性の有無などバランスよくと考えメンバーを編成していました。しかしそれは、学生の能力を成績やコミュニケーション能力、積極性といった教員の視点のみで決めつけていたといえます。ここには、はじめから成熟したグループを編成するのが良い編成だという思い込みがあり、未熟なグループを育てるという意識が教員に不足していました。」
この引用の前半部分に書かれている「バランス」のとれたグループ編成の方法は間違いではありません。学生の認知面や態度面の違いを幅広く考慮したグループ編成は協同学習が推奨する異質なグループ編成の観点からしてもうなずける方法です。
また、教師の視点でグループを編成することも問題ではありません。とくに、入学直後など学生に関する情報が少ないばあい、外見的な性別や年齢、成績などを手がかりに教師の視点からグループを編成するしかありません。
一方で後半部分は少し気になりました。そこでは「バランス」のとれたグループ編成すなわち異質なグループ編成は、そのまま「はじめから成熟したグループ」になるという見解が述べられています。少なくとも文面からそのように読みとれます。しかし、どんな編成方法を用いたとしても「はじめから成熟したグループ」をつくることはできません。この点は留意が必要です。
どんなグループを編成しても編成直後のグループ活動は注意深く観察する必要があります。それは教師からみて有能と思われる学生だけを集めたグループにもいえることです。編成直後のグループはメンバー同士が互いを十分には知らないことが多く、程度の差はあれ、グループとしては未成熟な状態といえます。基本的な信頼関係が醸成されておらず、いわゆる支持的風土にはほど遠い状態です。
編成直後のグループでは、内部の人間関係を構築するために、短期間で多様な動きが活発に繰り広げられます。思いもよらない展開になることもあります。その変化過程を心細やかに捉え、より望ましい成熟したグループを育てるには教師としてどう対応すべきかをつねに考える必要があります。
〇 失敗を避けたい教師の思い
グループ編成に限らず授業づくりのさまざまな側面に教師の思い(教育理念)が強く影響します。この教師の思いの背後にある考え方は暗黙知であることが多く、一人では気づけないこともあります。それだけに、教師は授業づくりに対する自分の思いの背後にあるものを意識的に吟味する努力が求められます。
第2回(その4)に「教員はグループ活動がうまくいかないことを避けたかった」という教師の思いが述べられています。失敗を回避するために、学生に「何を学ぶのか、どう成長するのか押し付けていた」や「学生を信じることができていなかった」という振り返りが述べられています。このような振り返りこそ、教師の教育力を高める原動力になります。ぜひとも教師一人ひとりの気づきを同僚教師と共有して授業改善につなげてほしいものです。
〇失敗やつまずきの種を仕込んだグループ編成
失敗を避けたいという教師の思いはよく理解できます。そして、そのような思いが影響して、教師中心の指導に陥る過程も理解できます。
ただし充分ご理解いただいているように「グループ活動がうまくいく」とは学生が主体的に学び、変化成長することです。その途中で起こる失敗やつまずきは問題ではありません。むしろ、失敗やつまずきは変化成長の貴重な糧となります。
異質なグループ編成も、極論すれば、失敗やつまずきを誘発する仕掛けとさえいえます。背景の異なる多様な学生同士を集めることで、グループでの話し合いも一筋縄にはいきません。あちらにぶつかり、こちらにぶつかりしながら、グループとしての意思が形づくられていきます。そこには同質の学生を一緒にしたグループ以上に失敗やつまずきの種がたくさん潜んでいます。失敗やつまずきの可能性を事前に予測して回避したり、生じた失敗やつまずきを乗り越えていくことで、だれも想像できなかったグループとしての学びが展開します。この過程を通して学生一人ひとりの変化成長が実現します。
このようにグループ編成ひとつとっても、教育に対する教師の根本的な考え方が色濃く映し出されます。当然と思っている指示や指導も、ときには立ち止まり、振り返ってみることが大切になります。
〇学生を信じて育てる
返信(その4)には「学生を信じて任せる」という思いを見事なまでに実証した素敵な事例が紹介されていました。「グループ編成と配置」という第2回のテーマとは直接関係してはいませんが、ここで簡単に触れておくことにします。
学生を信じて任せることが教育の基本です。これは多くの先生方が気づかれていることでしょう。しかし「言うは易く行うは難し」です。なかなか実行できるものではありません。学生に任せてうまくいかなかった時のことを考えると、どうしても躊躇してしまいます。
それにもかかわらず、返信(その4)には、教師の都合に合わせた指導から、学生主体の学びへの見事な転換事例が紹介されていました。そこでは、教師の振り返りから始まり、学生を徹底的に信じてすべてを任せるという決断をおこない、実行しました。ここに、実践した先生方の素晴らしい変化成長を見て取ることができます。また、それに応えた学生の変化成長は先生方の予想をはるかに超えるものでした。先生方がいわれる「学生に伴走していく姿勢」の効果です。これからもこの基本姿勢を堅持してもらいたいと思います。
この「伴走」が基本姿勢として教師間で共有されている限り、伴走の仕方が教師間で少々異なっていても大きな問題にはならないと考えます。学生を信じて任せることは決して無計画ではありません。放任でもありません。その時々の学生の育ちを充分に把握し、その学生がさらに一歩前進できる範囲を考慮しながら任せることが必要になります。そこには緻密は観察と計画が前提となります。まさに「学生に伴走していく姿勢」と通底します。その結果、学生は自分たちでもやれるという自己効力感を獲得でき、変化成長し続ける力を獲得できます。同時に、教師も学生の大きな育ちに感動し、多くを教えられ、学ぶことができます。
*
第2回「グループ編成と配置」は今回で終わり、次回からは第3回「仲間づくり」に進みたいと思います。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
