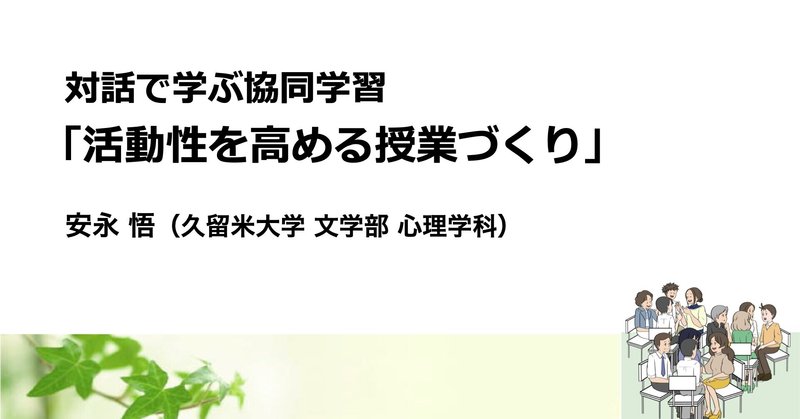
第1回 授業を始める (その4) 授業で残った「モヤモヤ」感
第1回「授業を始める」(その1〜3)に続く反応が参加者から届きましたので紹介します。この原稿に対する私のコメントは次回(その5)で掲載します。
*
今回の担当は、東京都立広尾看護専門学校の篠原千鶴子です。
第1回(その2)の中村先生の同僚です。教員歴は26年目になります。助産師ですので、母性看護学を中心に担当してきました。10年ほど前から学校管理の仕事をしています。
実習や授業で学生と接する機会は少なくなってしまいましたが、看護学生が入学して初めて「看護とは何か」を学ぶ「看護学概論」という授業を担当しています。抽象度の高い授業ですので、看護を初めて学ぶ学生が、なるべく具体的に考えられるような教材を用いるようにして、授業設計をしています。
学生の頭を働かせた授業にしたいと、以前からグループワークや演習を授業の中で取り入れてきました。しかし、発展的な意見交換や学習の深まりという手ごたえをあまり感じられない時もあり、毎年1年ずつ教員の経験は長くなっても、授業は難しいなあ、という思いは変わりません。今回、少しでも自分の授業改善に取り組めたら良いと思っています。
中村先生とは、安永先生のご著書とnoteで勉強しながら、「実践を交えて取り組もう!」を目標にしています。アドバイスで頂いた方法を授業で取り入れ、互いの授業を参観して、意見交換しながら進めたいと思っています。
○ラウンドロビンを取り入れてみました
「第1回(その3)」の安永先生の返信を受けて、早速、中村先生は授業でラウンドロビンを取り入れてみました。授業の概要について簡単にご説明します。
この授業は、看護師が多重課題に直面したとき、看護の優先順位をどう判断するか、というものです。もうすぐ朝6時になる状況で、次の3人の患者さんの援助の順序とその根拠を考えます。
Aさん:朝6時に術前処置(浣腸)のある患者さん
Bさん:朝6時に抗菌薬の点滴の処方がある患者さん
Cさん:トイレに行きたいとナースコールを押してきた患者さん
まず、学生は、個人で看護の優先順位を考えましたが、答えは実にさまざまでした。その後のグループの話し合いでは、それぞれの学生が、なぜそのように考えたのかを出し合い、お互いに意見を交換し、グループとしての看護の優先順位を決定しました。このグループで決定した優先順位もさまざまでした。
次に、グループ同士が、なぜそのように考えたのかを意見交換をしました。私たちはグループ間で活発に意見交換してくれることを期待しましたが、他のグループの発言に対して“拍手”で終わってしまい、活発な意見交換とまではいきませんでした。
○振り返っての2つのモヤモヤ
この授業が終了したあと、中村先生と授業に対する振り返りをしました。「見通しをつける」という発想でいえば、この授業では、学生が「優先順位の判断のためには、色々な要因を考えなければいけない」ということが理解できれば良く、正解を求めるものではありません。ですから、学生は授業の道筋を理解し、グループ内の意見交換で、自分では考えつかない要因についても考えることはできていましたし、ラウンドロビンを取り入れたことで、グループ内で活発な意見交換ができていたことで、評価はできます。もちろん寝ている学生は誰もいませんでした。
しかし、中村先生も私も何かモヤモヤした感じで終わったという印象がありました。モヤモヤの理由を考えてみたところ、2つの理由があげられました。
1つは、グループ同士の意見交換が活発にならなかったことです。私たちは、グループでの優先順位を決定した後、グループ同士の意見交換が活発にならなかったのはなぜか、その理由が今一つつかめませんでした。ラウンドロビンで、既にグループ内の話し合いが十分されていたため、グループ間の意見交換は授業設計上必要なかったのではないかと振り返りました。
もう1つは、教員が想定した優先順位の判断とは違うグループが最後まであったことです。経験を積んだ看護師である私たち教員が考える優先順位の1番は、Cのトイレに行きたい患者さんでした。複数の教員の意見を聞いたところ、AとBの優先順位は違っても、Cが1番に変わりはありませんでした。臨床経験の乏しい学生は、リアルな患者さんを想像するのは難しく、だからこそ、今回の授業の着地点は、「優先順位の判断のためには、色々な要因を考えなければいけない」ことがわかれば良しとしました。以降に続く授業で、今回学んだ優先順位の考えを活用したシミュレーション学習を重ね、優先順位の判断が少しずつできるような授業設計にしています。しかし、教員の心情としては、看護学生であれば、Cの患者さんの優先順位が高いことを判断して欲しいという思いが強かったのかもしれません。
安永先生には、この一連の取り組みと、その結果私たちが抱いたモヤモヤについて、ご意見がいただければありがたいです。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
