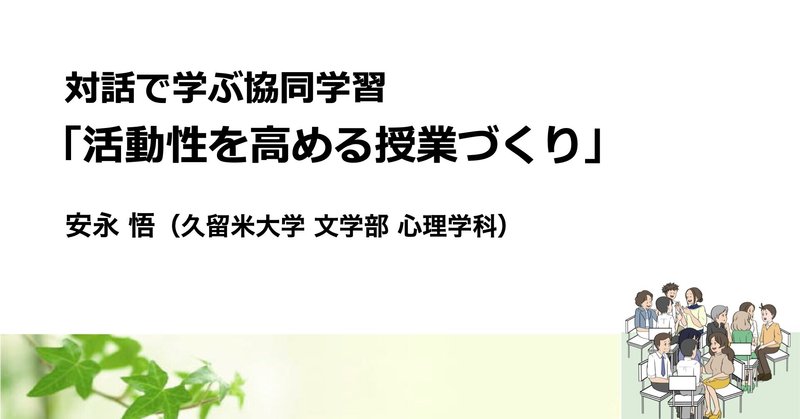
第1回 授業を始める (その5) 教師の感性が授業を育てる
今回は「第1回 授業を始める(その4)」に掲載した篠原千鶴子先生の原稿を手がかりに議論を深めます。
○教師の感性が授業を育てる
授業に対する教師の豊かな感性が主体的な授業改善のきっかけになる。篠原先生の原稿を読んで真っ先に確認できたことです。学びに対する学生の姿勢や授業展開に伴う学生の変化成長に寄り添いながら、教師として何を感じ、何を読みとることができるか。この教師の感性こそが授業改善の出発点にあるとつねづね思っていました。
授業のあと篠原先生は2つの「モヤモヤ」を感じました。1つがグループ間の対話に関する「モヤモヤ」であり、もう1つが学生の回答に対する「モヤモヤ」です。両者とも教師の期待と現実とのギャップが原因となっています。前者は教師が期待していたグループ間の活発な対話と学生がみせた不活発な対話とのギャップです。後者は教師が考える正答と学生が導き出した答えとのギャップが原因となっています。
この期待と現実とのギャップによる「モヤモヤ」感がきっかけとなり、なぜ学生は期待したように「反応しなかったのか」または「反応できなかったのか」という自問自答が始まります。より納得のいく解をもとめて書籍やネットで情報を集め、ときには仲間と議論し、機会があれば専門家に相談することもあるでしょう。そうして得られた答えらしきものを手がかりに次の授業を準備し実践します。そこでまた何かを感じます。この繰り返しで授業改善のサイクルが動き始めます。
そういう意味で、篠原先生が授業に「モヤモヤ」を感じられたということは授業改善の素晴らしいきっかけとなっています。この「モヤモヤ」感を不快なものとして消し去るのではなく、つねに心に留めておき、ことあるごとに問い続けることをお勧めします。本対話がその一助になればこれほど嬉しいことはありません。
○課題明示で見通しを共有する
本対話の「第1回(その1)」で強調したのが「見通し」の大切さでした。グループ活動を始める前に、活動の目標と目標にいたるまでの道筋(見通し)を学生と共有する課題明示が大切であることを説明しました。課題明示を通してグループ活動に対する教師の思いや期待も学生に伝わります。
この視点から、期待したグループ間対話が実現しなかった理由を検討してみましょう。残念ながら篠原先生の原稿にはグループ間対話に先立つ課題明示についての記述がありませんでした。したがってここでは具体的な検討はできませんが、どのような内容の課題明示をどれほど意識しておこない、どれほどの見通しを学生と共有できていたのかを検討するとよいでしょう。原稿を読む限りでは、グループ間対話に先立つグループ内対話(ラウンドロビン)の課題明示は一定程度うまくいっていたのではないかと思います。しかし、それに続くグループ間対話に関する課題明示は結果から判断して少々疑問が残ります。
たとえば「では、グループで出した答えをグループごとに発表してもらいます。質問や意見があったらお願いします」といった指示だったとします。この指示でグループ間対話をうまくできるクラスもあります。それは、①グループ間交流の目的や意味を理解しており、②グループ間交流をおこなう具体的なスキルが身についており、③グループ間交流に慣れており、④何を話しても認められるという「支持的風土」が醸成されたクラスだと思います。このような条件が満たされているのであれば、先の指示でもグループ間対話はうまくいくと思います。もしそこまでクラスが成長していなければ、その成長に応じた、より具体的で詳細な課題明示が必要となります。
○手本を示す:対話スキルの育成
前述のように多くの条件が整って始めて活発な対話が期待できます。ただし、すべての条件を一度に達成することは無理です。日々の実践での意識的な働きかけを通して必要な条件を少しずつ達成するという姿勢が教師には求められます。
ここでは活発な対話を促すことを目的に導入している「手本を示す」という方法を紹介します。手順は次の通りです。まず①クラス全員の前で、学生を相手に教師が対話を実演する。次に②学生2人を指名し、クラス全員の前で対話を促す。そして③学生の対話力が向上するにつれ教師の関与を減らす。
①について、対話をどのように進めればよいか、学生は具体的なイメージやスキルをもっていない可能性があります。そこで教師の発問を中心に学生と対話します。内容は何でも構いません。そして対話の進展にそって要所ごとに解説を加えます。学生がなぜそのような発言をしたのか、それに対して教師はどう考えて応答したのか。対話の背後にある教師と学生の心の動きを解説しながら対話を展開するポイントを説明します。
②について、①で具体的な対話についてのイメージを与えたのち、2人の学生を指名し、対話を求めます。対話がうまく展開すれば、その対話過程を教師が解説します。うまく対話が展開しなければ教師が両者の橋渡しをしながら対話を促します。そして①と同様、対話の展開過程と留意点やスキルをクラス全体に伝えます。
③について、上記の①と②を繰り返し体験することで、学生同士の対話がうまく展開するようになれば、教師の関与を減らしていきます。
授業中、学生と対話する機会があれば、この方法を意識して実践してみてください。少しずつですが学生の対話力向上に役立ちます。むろん「言うは易く行うは難し」です。一人ひとりの学生やクラス全体の変化成長、さらには、そのときどきのクラスの状態を考慮しながら、指導法を柔軟に変更することも必要です。
○「つまずき」を最大限に活用する
学生の「つまずき」こそ教育指導の絶好の機会です。このような機会は予期せず突然やってくるのが常です。どのような変化にも対応できるだけの研鑽を教師は常日頃から心がけておく必要があります。
篠原先生の原稿では「教員が想定した優先順位」と異なる判断をしたグループがありました。この「つまずき」を手がかりに、そのグループと徹底的に対話して欲しいと思います。対話を通して「つまずき」の原因を探究します。そこにクラス全体を巻き込みます。このクラス全体での探究活動を通して、仲間の「つまずき」といった具体的な事例を手がかりに、優先順位を決めるなど何かを決定する際には多様な視点を考慮することの大切さ伝えることができます。
同時に、異なる意見があったとき、どのような態度で、どのような側面に注意しながら、どのように話し合いを進めると、全員が納得できる理解に近づくことができるか。つまり望ましい対話の方法も体験を通して学ぶことができます。また、異質な意見を手がかりに対話を深めることにより、思いもよらない豊かで深い学びが実現することも学べます。
このように1つの「つまずき」を手がかりに、授業内容と対話方法を同時に学ぶことができることは協同学習の大きなメリットといえます。この点は「協同学習の効果」として改めて検討します。
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?
